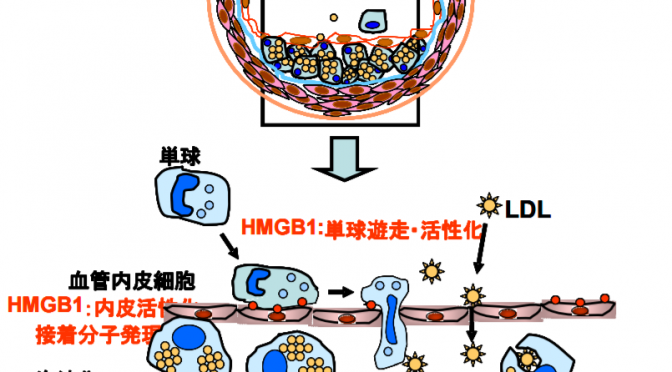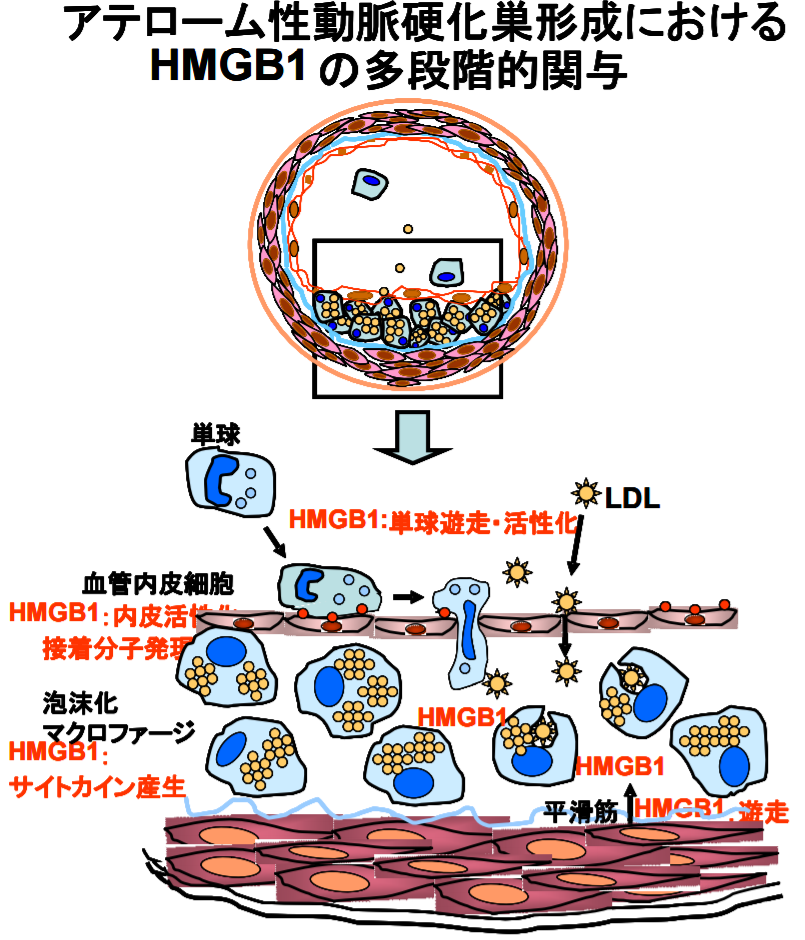by Alan Levine(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病の治療 > 進歩する糖尿病治療 インスリン分泌を保たせる
■進歩する糖尿病治療 インスリン分泌を保たせる
糖尿病 重症化を防げ!
(2009/11/22、中日新聞)
糖尿病に関連してインクレチンというホルモンが注目を集めている。
糖尿病治療の最前線 インクレチンに注目によれば、インクレチンは小腸などから分泌されるホルモンで、膵臓に働きかけることでインスリンの分泌を促し、血糖値を下げることから、インクレチンに着目した糖尿病治療薬が海外で作られています。
血糖値が高いときはインスリン分泌を促進する一方、血糖値が低いときはあまり作用しないという特徴を持つ。
このインクレチンの効果を持続させて糖尿病を治療しようという新しいタイプの糖尿病治療薬が承認され、近く登場する。
インクレチンは炭水化物や脂質を摂取した後に腸から分泌されるホルモンの総称。
代表的なインクレチンとしてGLP-1とGIPの二種類が知られている。
GLP-1は、主に小腸下部から分泌され、膵臓におけるインスリン分泌の促進と血糖値を上げるグルカゴン分泌の抑制をする作用を持っている。
GIPは小腸上部から分泌され、同じような作用を持つが、インスリン分泌作用はGLP-1の方が数倍強いとされている。
こうして注目されているインクレチンにも問題がありました。
それは、効果が長続きしないこと。
なぜ効果が長続きしないのでしょうか。
インクレチンは、体内で「DPP-4」という酵素によってすぐに分解されてしまうため、効果が長続きしなかった。
そこで登場したのが「DPP-4阻害薬」。
DPP-4の作用を阻害してインクレチンの効果を長続きさせる仕組みだ。
この薬が日本にも上陸します。
【関連記事】
米メルク社が開発した「ジャヌビア」(一般名、シタグリプチンリン酸塩水和物)は、DPP-4阻害薬として現在は世界八十五カ国以上で承認され、米国だけでも千六百万人以上の患者に処方されている。
日本では二〇〇三年から2型糖尿病患者を対象にした臨床試験を実施。
この十月に2型糖尿病治療薬として製造販売が承認された。
日ごろの血糖値レベルを表すヘモグロビンA1cの値を低下させる効果が確認されている。
治療薬には現在、インスリンのほかに(1)インスリン抵抗性改善薬(2)インスリン分泌促進薬(3)食後高血糖改善薬-などがある。
新しい作用機序を持っている経口糖尿病治療薬の登場によって「食後や空腹時の血糖値がコントロールしやすくなり、治療の選択肢が増える」と期待を集めている。
糖尿病患者の中には、ジャヌビアのような薬を待っている人もいるかもしれません。
しかし、まずは糖尿病になる前に、糖尿病予備軍の段階で食い止めることを考えましょう。
生活習慣を改善して、糖尿病を予防しましょう。
⇒ 糖尿病の症状 についてはこちら
 糖尿病関連ワード
糖尿病関連ワード
■薬局でもできる糖尿病の検査|検尿(尿糖検査)と採血による血糖検査