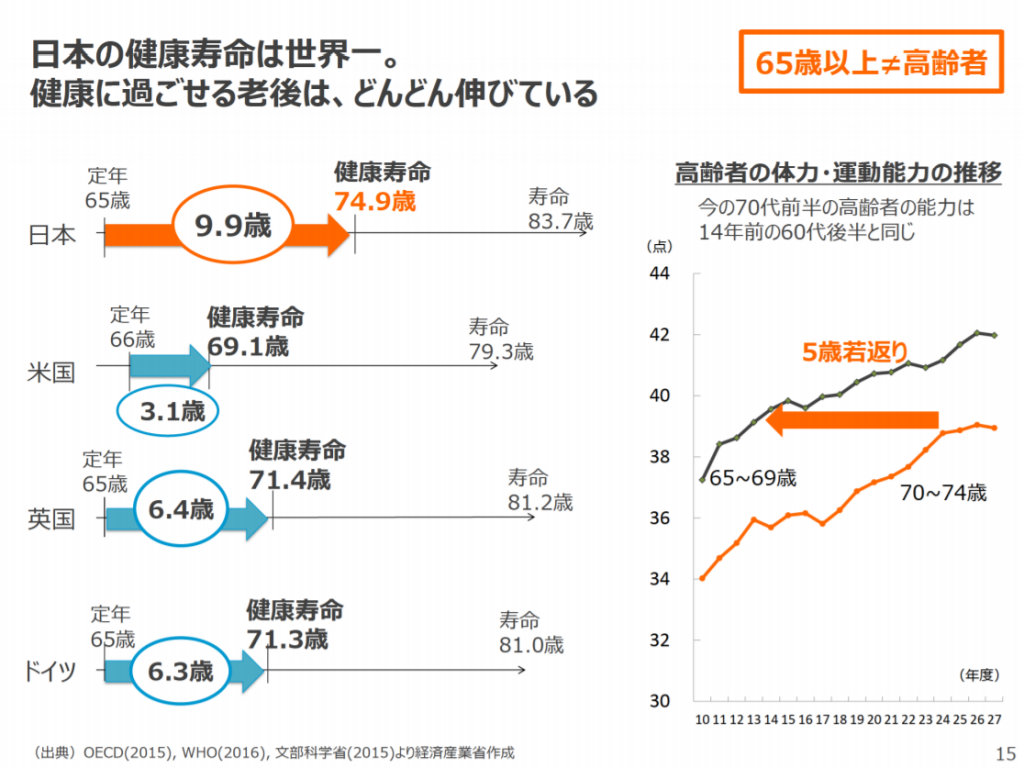スロトレで有名な東京大学教授の石井直方先生が解説する記事の中では、将来寝たきりになるNG習慣5つが紹介されています。
是非チェックしてみましょう。
【目次】
- 階段は使わずエスカレーター・エレベーターを使う
- 長時間立つのがイヤ
- 健康のためではなく、足が疲れるという理由でハイヒールを履かなくなった
- パンツを履くときにバランスを崩してしまう
- 落ちているものを、腰を落として拾う
1.階段は使わずエスカレーター・エレベーターを使う
(2012/11/26、美レンジャー)
日常生活に欠かせない主要な筋肉は、1年に1%ずつ減っていきます。日頃から、筋力を維持するように心がけていないと、10年後、20年後には、歩くこともままならい状態になってしまいます。とくに階段の登り降りは、心肺機能と足腰という大事な筋肉を鍛えます。
老化のスピードが速い大腿筋を鍛える方法によれば、階段を「降りる」動作は、大腿筋にとって比較的強い刺激になると同時に、前の筋肉がブレーキとして機能していることを認識できるそうで、階段を降りることが怖くなってきたら、筋量が落ち非常に危険な状態なのだそうです。
階段の登り降りは、体を鍛えられるだけでなく、自分の筋力のチェック方法としても使えそうです。
【関連記事】
2.長時間立つのがイヤ
by Fausto Hernandez(画像:Creative Commons)
直立姿勢を維持するには、背骨を伸ばす筋肉、骨盤と脊柱の姿勢を保つ筋肉、そしてふくらはぎの筋肉が必要です。そして、これらの筋肉は加齢の影響を受けやすいものです。
姿勢を維持する筋肉は加齢の影響をうけやすいそうです。
最近では、座り仕事であったり、スマホ・ケータイを見る動作で姿勢が崩れている人が多いようです。
【関連記事】
自身の姿勢が崩れていないか、ぜひチェックしてみてください。
【関連記事】
3.健康のためではなく、足が疲れるという理由でハイヒールを履かなくなった
ハイヒールを履くとかかとが上がります。もともと人間のカラダの重心は少し前にありますが、ハイヒールを履くとさらに重心が前に移動します。より前に倒れる危険性が高くなるので、直立姿勢を保つための筋肉を普段以上に使うことが必要になります。
さらに、ハイヒールを履く人は、膝を伸ばすことを意識しています。膝が曲がっていると貧相に見えるからです。これも、膝関節を支える筋肉に大きな負担をかけています。つまり、ハイヒールを履くと疲れるという人は、これらの筋肉が衰え始めたということなのです
ハイヒールは健康のことや体のことを考えると決していい靴ではないのですが、ハイヒールを履かなくなった理由が、足が疲れるからという場合は、注意が必要なようです。
【関連記事】
4.パンツを履くときにバランスを崩してしまう
お尻の筋肉が弱ってくると、パンツを履く時にバランスを崩してしまいます。
体のバランスを取る筋肉が弱っている証拠なのだそうです。
5.落ちているものを、腰を落として拾う
落ちているものを拾おうとして手が届かない。だから腰を落として拾っている。それは、すっかり腰の柔軟性がなくなってきたということです。腰が硬くなるのは、腰の関節を使っていないからです
腰の負担を考えると、落ちているものを腰を落として拾うというのは決して悪いことではないと思います。
ただ、できるけどしないのか、できないからやらないのとでは違います。
もしできないのであれば、腰の柔軟性がなくなってきていると言えそうです。
【まとめ】
どれくらいチェックポイントが当てはまりましたか?
当てはまった人は、ぜひ体を動かすようにしましょう!