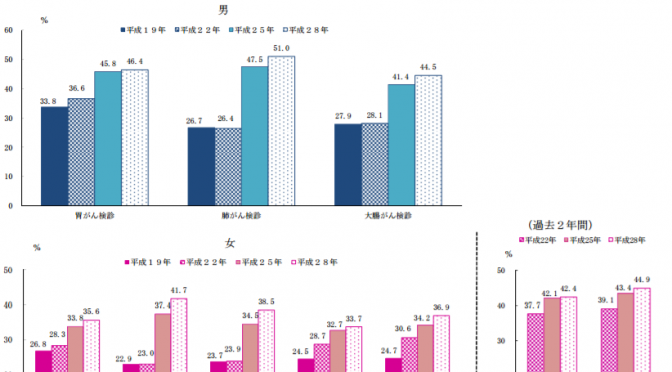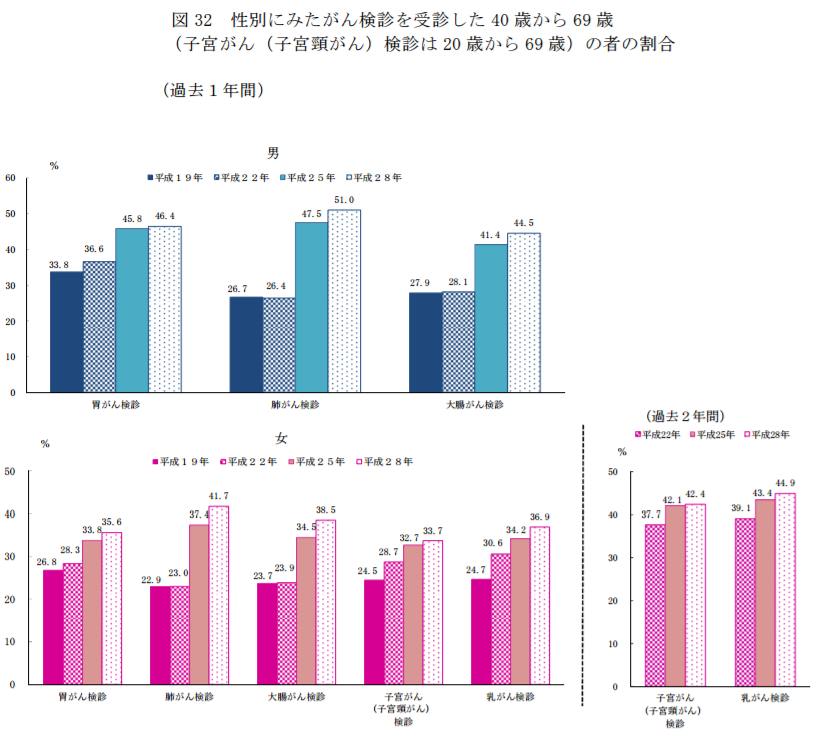ブルース・マーズ|unsplash
「ありのままの自分」「なりたい自分」を行き来する中で「推しに恥じない自分」は大事なコンセプトになる。
”「推しに恥じない体を目指す」というコンセプトは女性に強く響き、共感する声がたくさん聞かれた。”https://t.co/We4DwpfW0S https://t.co/R7EVh5vDFZ
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) July 11, 2021
【自分事がきっかけ】
”自分がアラサーになり、20代中盤から体重が増えても自分だけではなかなか痩せられなくなりました。”【基準】
”17年ほどコスプレをしているのですが、昔作った衣装が着れなくなった”【解決方法】
”パーソナルジムに通う”https://t.co/atjr2FyGWi— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) July 11, 2021
【悩み】
担当のトレーナーに、コスプレ衣装を着たいから痩せたい、腹筋を割って男装の見栄えを良くしたいという理由は、どう思われてしまうのかが怖かったため、なぜ痩せたいのか、なぜ腹筋を付けたいのかという目的をなかなか言い出せなかったhttps://t.co/atjr2FyGWi— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) July 11, 2021
【オタク共通の悩み】
✅身体を鍛えたいと思っているが行動に移せていないオタクが多い
✅ライブや舞台でいろいろな場所に遠征に行き、ライブに行く体力の悩み
✅こもりがちになり全身が凝り固まりやすい
✅細かい作業で身体が痛い
✅不健康な生活を送りがちhttps://t.co/We4DwpfW0S— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) July 11, 2021
「なりたい自分になる」&「あるがままの自分で生きられる居場所を作る」の両方を叶えてあげられるコンセプト!
”オタクがオタクであることを隠す必要がなく、堂々と話すことができ、オタクであるが故の悩みを共感し目標を共有する、そんな場所である必要がある”https://t.co/lMxBXDFetU
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) July 11, 2021
これまで個人は「なりたい自分になる」もしくは「あるがままの自分で生きられる居場所を作る」ことを求め、ブランドやコミュニティは「なりたい自分になる」ことを後押ししたり、「あるがままの自分で生きられる居場所」を提供するについて考えてきました。
でも、「なりたい自分になりたい」と思うと、「ありのままの自分」とは離れてしまうようで、なんだか居心地が悪い感じがありました。
例えば「なりたい自分になりたい」からダイエットをするというと、それじゃ太っているありのままの自分はダメなのかな?という発想が生まれてしまう感じです。
ただ、その時に心配になるのが、ただ一つ心配になるのは誰もがその体型でいていいんだよというメッセージを受け取ることにより、健康が悪化するのではないかという点です。
【関連記事】
「ありのままの自分」なんだから、どれだけ太っていたっていいじゃない!ということになってしまうと、健康への影響が出てしまったり、社会全体としては医療費の問題が出てきたりと、それはそれで大丈夫なのかなと思っていました。
しかし、今回の記事を見て、一つの答えが出ました。
それが「推しに恥じない自分になる」です。
「推しに恥じない自分になる」には、「なりたい自分」と「あるがままの自分」の両方が含まれています。
「推し」とは、応援する対象であると同時に、生きる活力を与えてくれるものであるもの。
例えば、病院の医師にいわれても運動習慣がつかなかった人が「フィットボクシング」で運動習慣がついた!行動変容を促すヒントがここにある!で紹介しましたが、病院の医師にいわれても運動習慣がつかなかった人が「フィットボクシング」で運動習慣がついた人がいました。
✅インストラクター(人気声優を起用)と楽しく本格エクササイズ
✅リズムゲーム感覚でフィットネス
✅「デュエットモード」「バーサスモード」
→ゲーム×エクササイズ×推し×協力&競争https://t.co/4gRTIsBgVm行動変容するには何が必要か?の答えの一つだね。https://t.co/1bH4nLJxon https://t.co/iLb5r2Cvwv
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) June 28, 2021
「習慣の力」(著:チャールズ・デュヒッグ)によれば、人間の心理には、2つの基本原則があるそうです。
1.シンプルでわかりやすいきっかけを見つけること
2.具体的な報酬を設定すること
新しい習慣作りには、「きっかけ」と「報酬」が重要です。
ゲームはまさに「きっかけ」と「報酬」が明確ですよね。
例えば、任天堂スイッチ&リングフィットが目の前にあることが「きっかけ」となり、人気声優を起用したインストラクター=「推し」との楽しいエクササイズが「報酬」となる感じです。
このように「推し」がダイエットの力になってくれたりもします。
”オタクがオタクであることを隠す必要がなく、堂々と話すことができ、オタクであるが故の悩みを共感し目標を共有する、そんな場所である必要がある”という言葉がありましたが、これはオタクだけに限らず、「ありのままの自分」を隠す必要がなく、「ありのままの自分」の悩みを共感し、目標を共有し、「推しに恥じない」「なりたい自分」になれる居場所(コミュニティ)は誰もが求めていることでしょう。
「推しに恥じない自分になる」こそがこれからの時代のキーワードになっていきますね!
P.S.
「推し」とは応援する対象であると同時に生きる活力を与えてくれるもの。「推し」への理解がある人というのは素敵なパートナーですね。
これからのダイエットは「推しに恥じない体になる」が大事なコンセプトになる!https://t.co/BhdyyUP5vX https://t.co/Ag9ggWEND0
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) May 28, 2022
境界線を跨ぐ人が強いんじゃないかな?と思っています。https://t.co/gn01mM8fKT
技術やルールは時代とともに変わっていく。技術者は趣味的に遊んでいたことでその分野のトップランナーになったり。https://t.co/GTgdiKbOcr
きちんとした強みを持って、軽やかに境界線を跨いでいく感じが理想。 https://t.co/kfJAvZY3hO— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) July 1, 2021