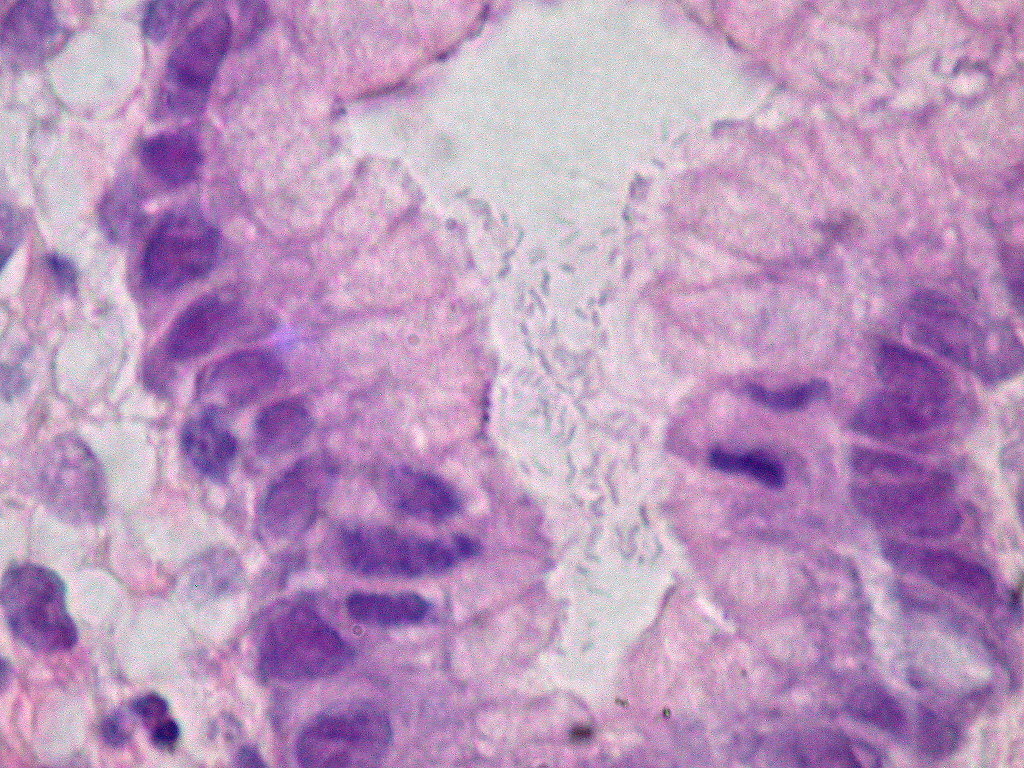by Joshua Rappeneker(画像:Creative Commons)
(2016/2/7、読売新聞)
原案では、飲み過ぎの人の割合を2020年度までに、成人男性13%(14年時点で15・8%)、成人女性6・4%(同8・8%)に引き下げるとした。飲み過ぎの基準は、日本酒換算で、男性なら毎日2合以上、女性なら毎日1合以上だ。
飲み過ぎにより高血圧、糖尿病やがんのリスクが高くなること、女性の方が短期間で依存症になりやすいなど、飲酒の危険性に関する知識の普及を目指す。
政府によるアルコール健康障害対策の原案がわかったそうです。
飲み過ぎの人の割合を2020年度までに、成人男性15・8%→13%、成人女性8・8%→6・4%に引き下げることを目標としています。
■アルコールと健康への影響
●動脈硬化とアルコール
動脈硬化の危険因子には、高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、肥満、喫煙、運動不足、偏った栄養バランスの食事、アルコール、加齢、ストレスの有無などがあります。
●がんとアルコール
大腸がん予防方法・大腸がんの危険度チェックによれば、最もリスクが高いのは飲酒。
飲酒による大腸がんのリスクは一日に日本酒を1合⇒1.4倍、2合⇒2.0倍、3合⇒2.2倍、4合⇒約3倍となっているそうです。
【関連記事】
- 中性脂肪が高くなる原因|炭水化物・アルコール・肥満による運動不足・タバコ
- 若い女性のアルコール依存症患者が増加傾向、厚労省研究班が報告
- 女性は男性より肝臓へのリスクなどアルコールの影響を受けやすい。
- 女性は飲酒量が男性と同じでも、肝臓は先に悪化する
■アルコールによる健康への影響を軽くする方法
- 休肝日の取り方(過ごし方)・ぺ―スの目安・休肝日は必要か?
- 運動量が多い人の脳は、アルコールによるダメージが小さい!?
- 肝臓に負担のかからないアルコールの取り方・食事の選び方
- 飲酒時にトマトを食べると、血中アルコール濃度が低下し、酔い覚めも早まる可能性
- 砂糖とアルコールを1ヶ月摂らなかったら体はどうなるのか?
- お酒と胃の関係|アルコールから胃を守るには?
 肝臓関連ワード
肝臓関連ワード
■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック
■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法
■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP