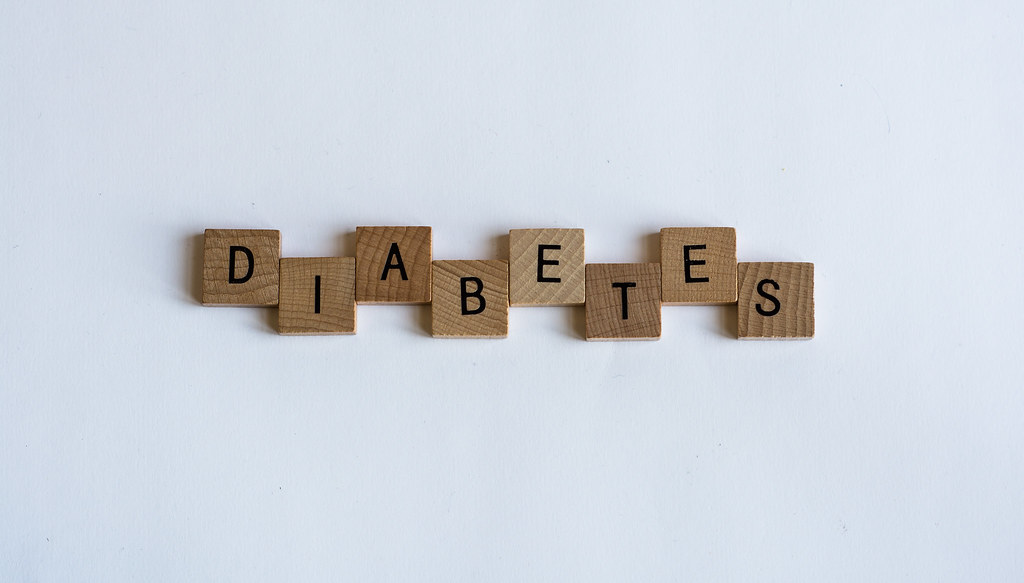by steve lodefink(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 目の病気 > 糖尿病網膜症 > 糖尿病網膜症(糖尿病の合併症の一つ)とは
■糖尿病の合併症の一つである「糖尿病網膜症」とはどんな病気!?
「糖尿病」診断されたら眼科検診を 合併症の一つ、網膜症に注意
(2008/10/29、MSN産経)
糖尿病網膜症は、糖尿病特有の三大合併症の一つ。網膜は、瞳から入った光の明暗や色を感知する組織で、細かい血管が密集している。そのため、高血糖状態が続くと血管の閉塞(へいそく)障害と血液凝固異常が起き、眼内の血管が徐々に詰まって、網膜に栄養や酸素が届かなくなる。
「そうなると、網膜に新しい血管が生まれ、酸素不足などを補おうとします。しかし、この新生血管はもろく、少しの刺激でも出血し、重篤化すると網膜剥離(はくり)を起こし、失明に至ります」
高血糖状態が続くと、血管が詰まって、網膜に栄養や酸素が届かなくなります。
すると、網膜に新しい血管(新生血管)が生まれ、酸素不足などを補おうとしますが、その血管はもろいため、少しの刺激でも出血し、場合によっては網膜剥離を起こし失明を起こすことがあります。
■糖尿病網膜症はどのようにしてなるか?
糖尿病(高血糖)
→血管の閉塞障害・血液凝固異常
→眼内の欠陥が詰まる
→網膜に栄養が届かなくなる。
→新生血管ができ、酸素不足を補おうとする。
→しかし、その新生血管は脆いため、少しの刺激で出血する恐れがある。
→場合によっては、網膜剥離を起こし、失明する恐れもある。
■糖尿病網膜症の進行度合い
糖尿病網膜症の進行度合いは、「単純網膜症」「増殖前網膜症」「増殖網膜症」の大きく3段階に分けられます。
1.単純網膜症
最初の変化は、点状出血や毛細血管瘤(りゅう)などの症状。この時点で血糖をコントロールできれば、失明には進まず、進行をとめることができる。ただ、自覚症状がないため、眼科での定期検診を受けていなければ気づかない。
2.増殖前網膜症
増殖前網膜症になると、血管閉塞が進み、静脈異常などの症状が現れる。この段階でも自覚症状はほとんどないが、眼科では網膜症の進行を防止するため、網膜レーザー光凝固術を行い、血管新生の発生を抑制する処置を取る。
3.増殖網膜症
第3段階の増殖網膜症まで進むと、網膜に接している硝子(しょうし)体の中にまで新生血管が伸び、硝子体出血や牽引(けんいん)性網膜剥離が起き、急激な視力低下や飛蚊(ひぶん)症が現れる。
糖尿病網膜症は、3つの段階を経て進行していくが、第1段階、第2段階の時点では自覚症状がなく、第三段階にまで進行しないと、自身の変調に気づかないそうです。
そこが、糖尿病網膜症の怖さなのでしょう。
■糖尿病網膜症の手術
眼科では、網膜に癒着した増殖組織をはがす硝子体手術を行い、失明の防止や視力の回復を目指すことになる。
糖尿病網膜症の治療では、硝子体手術を行なわれます。
■まとめ
糖尿病網膜症は、日本の中途失明原因の第2位で、年間約3000人がこの疾患で失明しているともいわれています。
糖尿病と診断された方は、ぜひ眼科の検診を定期的に受けるようにしてください。
→ 目の病気(目の病気・症状チェック) について詳しくはこちら
【糖尿病治療 関連記事】
【糖尿病網膜症 関連記事】
 糖尿病関連ワード
糖尿病関連ワード
■糖尿病の症状・初期症状|糖尿病とは
■糖尿病の診断基準(血糖値・HbA1c)
■糖尿病改善・予防する方法(食べ物・運動)
■糖尿病危険度チェック
■糖尿病の原因(生活習慣)|女性・男性
■糖尿病の検査|検尿(尿糖検査)と採血による血糖検査
■糖尿病の合併症|網膜症・腎症・神経障害
■糖尿病の食事(食事療法)|血糖値を抑える食べ方
■糖尿病の運動(運動療法)|筋トレ・有酸素運動
■血糖値(正常値・食後血糖値・空腹時血糖値)・血糖値を下げる食品