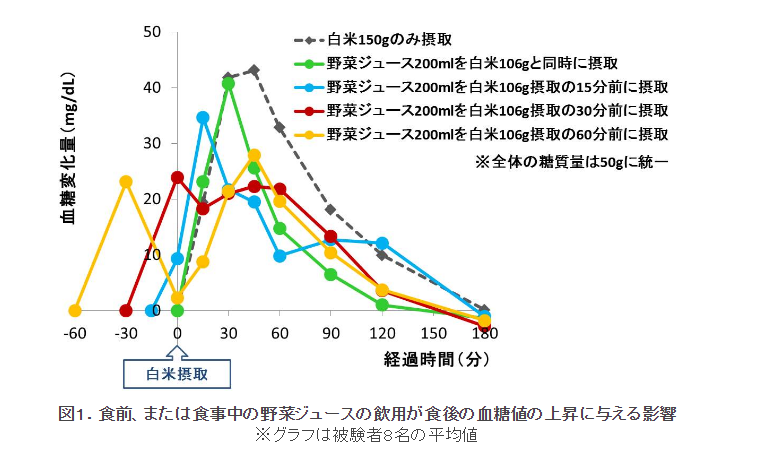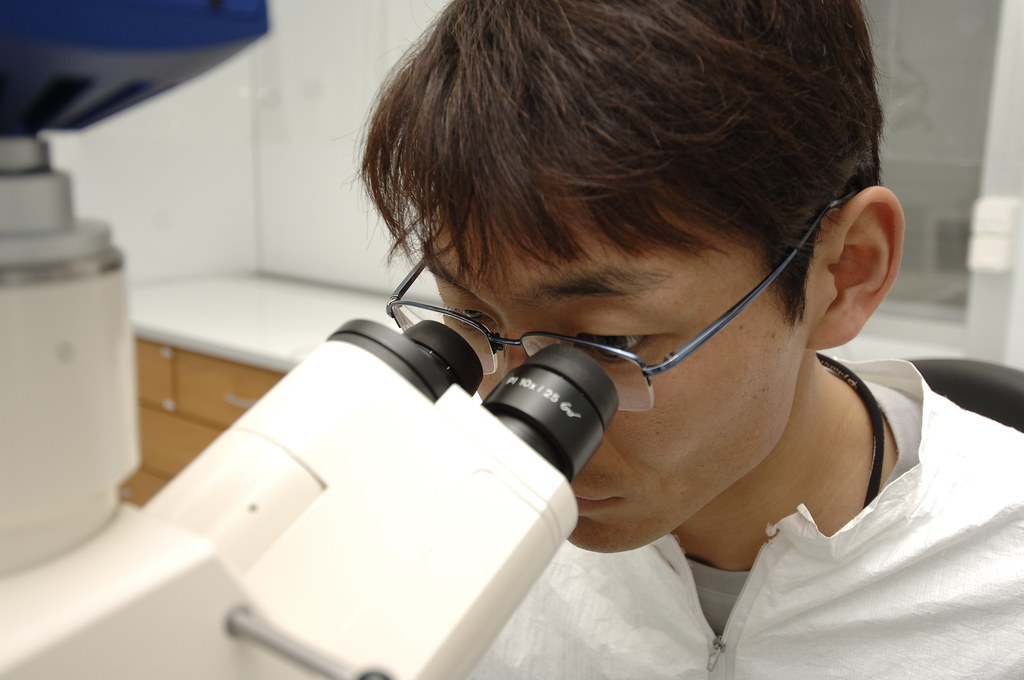> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病を予防する方法 > 大分の炭酸水素塩泉飲むと血糖状態が改善 糖尿病予防に期待
■大分の炭酸水素塩泉飲むと血糖状態が改善 糖尿病予防に期待
by Japanexperterna.se(画像:Creative Commons)
(2016/1/20、河北新報)
慶応大先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)などの研究グループは、特定の温泉水を飲むと血糖状態が改善するメカニズムの一端を、分子レベルで代謝物を調べるメタボローム解析などで初めて確認したと発表した。糖尿病予防への応用を期待する。
慶応大先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)などの研究グループの研究によれば、大分県竹田市の長湯温泉の炭酸水素塩泉の温泉水と市販の飲料水と1週間交互に1日0.5リットル、計4週間飲んでもらい、7日ごとに血液と便を調べたところ、血液検査の結果、温泉水の飲用後、一定期間の平均的な血糖値を反映する血中グリコアルブミン値(11~16%が基準値)が、19人中16人で下がったそうです。
メタボローム解析した結果、高いと糖尿病になりやすいとされる血中アミノ酸の一つチロシンの濃度が15人で低下した。腸内細菌の解析では、肥満防止効果がある細菌群を有していた13人のうち、10人で同細菌群が増えた。
今回の結果から考えられるポイントをまとめてみます。
- 大分県の温泉水を飲むと血中グリコアルブミン値が19人中16人で下がった
- 数値が高いと糖尿病になりやすいとされるチロシンの濃度が19人中15人で低下
- 肥満防止効果がある細菌群を持っていた13人のうち、10人で肥満防止効果がある細菌群が増えた
- 今回の実験は大分県の温泉水を飲んだが、その他の温泉水に同様の効果があるかはわからない
- 炭酸水素塩泉のどのような成分が糖尿病の予防・改善につながるかはわかっていない
■温泉水による糖尿病予防効果のメカニズムの仮説
温泉水飲用の効果をメタボローム解析および腸内フローラ解析で明らかに
(2016/4/1、慶応大先端生命科学研究所)
血液のメタボローム解析の結果、温泉水飲用期間では解糖系が亢進している可能性が示唆された。これは、グルコースを消費してエネルギーを生み出すはたらきが、温泉水の飲用によってより強くなることを示唆する結果である。その他にも、温泉水飲用後は血中のアミノ酸濃度が減少しており、これは生体内でのタンパク質分解が抑制された結果ではないかと考えられる。また、腸内フローラ解析の結果から、肥満防止効果があることがマウス実験で証明されているChristensenellaceae科の腸内細菌が飲泉後に増加することが明らかとなった。以上の結果から、今回実験に用いた長湯温泉の温泉水の飲用は、解糖系の亢進、タンパク質分解の抑制、肥満防止効果がある腸内細菌の増加などを介して血糖状態を改善し、糖尿病の予防や改善につながる可能性が示唆された。
炭酸水素塩泉を飲むことによって、1.生体内の代謝アップ、2.腸内環境の改善、という2つの効果によって、血糖状態の改善がみられ、一定期間の平均的な血糖値を反映する血中グリコアルブミン値が低下したと考えられます。
1.生体内の代謝アップ
●解糖系の亢進
グルコースを消費してエネルギーを生み出すはたらきが、温泉水の飲用によってより強くなることから
●タンパク質分解の抑制
温泉水飲用後は血中のアミノ酸濃度が減少したことから
2.腸内環境の改善
肥満防止効果があるといわれる腸内細菌が飲泉後に増加したことから
■まとめ
今回の研究は、大分の炭酸水素塩泉を飲むと血糖状態が改善したということはわかりましたが、具体的にどのような成分が血糖状態の改善に役立ったのかというのはわかっていません。
ただ、今後温泉水を健康に活用しようというところがますます増えていくのではないでしょうか。
→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら
→ 糖尿病を予防する方法 について詳しくはこちら
【糖尿病の症状】
続きを読む 大分の炭酸水素塩泉飲むと血糖状態が改善 糖尿病予防に期待