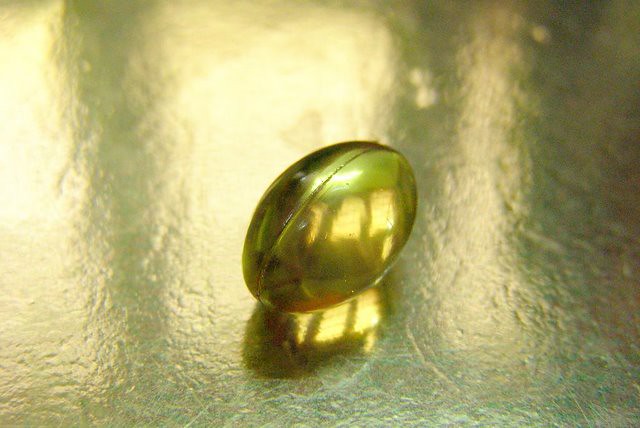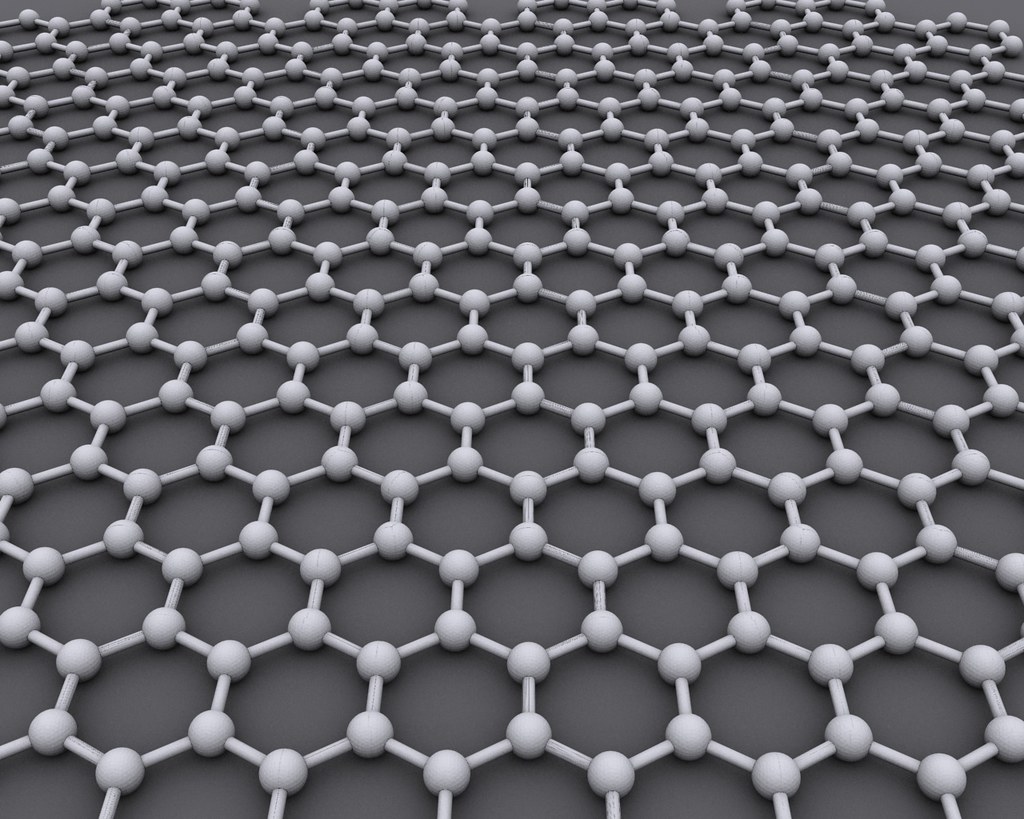by Dylan(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 睡眠 > 睡眠時無呼吸症候群 > 非肥満者でも首回りのサイズが睡眠時無呼吸の重症度に影響
非肥満者でも首回りのサイズが睡眠時無呼吸の重症度に影響
(2009/6/18、nikkei net)
肥満が閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の主要な危険因子(リスクファクター)となることは知られているが、肥満でない人でも多くの人にこの症状がみられることが、新しい研究で示された。
今回の研究では、ボディ・マス・インデックス(BMI、肥満指数として用いられる)が18.5~27の非肥満成人5,426人のうち54%にOSAがみられ、そのうち約半数は軽度であったが、残りの半数は中等度から重度のOSAであった。
特に、首回りの太い中高年の男性に中等度から重度のOSAがよくみられたという。
肥満だけでなく、首回りが太いほど閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)のリスクが高いそうです。
閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)は、様々な病気との関わり合いが高いとして注目を集めています。
過去の研究では、OSAが心疾患、肥満、糖尿病、高血圧、死亡リスクの増加などの重大な健康上の問題と関連することが示されている。
閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)には注意したいものです。
■睡眠時無呼吸症候群(SAS)に注意
「熟睡感がない」という方はもしかするとこんな症状がありませんか?
- 大きないびき(いびきがうるさいと言われる)
- 眠っている間に呼吸が止まる
- 日中の眠気
- 熟睡感がない(よく眠れた感じがしない)
- 起床時に頭痛やだるさを感じる
- 睡眠中に何度も目が覚める
こういう症状がある人は、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」かもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、簡単に言うと、眠っている間に呼吸が何度も止まってしまう病気のことを言います。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の方にはこのような治療が行われます。
 減量・ダイエット
減量・ダイエット
肥満が原因による睡眠時無呼吸症候群の治療・予防するためには、食生活の改善や運動不足の解消など生活習慣の改善が重要となります。
 睡眠前の深酒に注意
睡眠前の深酒に注意
アルコールは気道周辺の筋肉を弛緩させ、鼻づまりを引き起こしやすいので、いびきをかきやすくなります。
 横向きに寝る
横向きに寝る
軽度のいびきなら、舌が喉に落ち込んで気道を塞がないよう、横向きに寝るようにしましょう。
 腰枕
腰枕
ファスナーを開いて背中にボールを装着できる腰枕を使うことで、横向きの姿勢を保つことができます。
パジャマの背中に袋を縫い付けて、中にテニスボールなどを入れるお手製腰枕もおすすめです。
 ベッドの頭側を高くする
ベッドの頭側を高くする
体を少し起こした姿勢にしておけば舌が落ち込みにくくなります。
 マウスピース
マウスピース
中等症より軽いいびきには、舌や下あごを前に出させる特殊なマウスピースを使うと軽減することもあるそうです。
 CPAP療法
CPAP療法
中等症以上や重度のSAS患者の治療には、寝るときに呼吸用のマスクを付け、圧力をかけた空気を機械で持続的に送り込む「CPAP療法」が有効とされています。
睡眠時無呼吸症候群とメタボリックシンドロームによれば、「CPAP(Continuous Positive Airway Pressure=シーパップ)」は、睡眠中に装着した鼻マスクから圧力をかけた空気を送り込み、上気道を開いた状態に保って無呼吸をなくす方法です。
CPAP療法で治療すると無呼吸やいびき、日中の眠気が消失するだけでなく、高血圧や、メタボリックシンドロームのひとつの病態であるインスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性も改善します。
つまり、CPAP療法で睡眠時無呼吸症候群を治療すると、心筋梗塞などのリスクも低下します。
 ナステント
ナステント
「ナステント」とは、緊急救命時の気道確保の手法を応用し、鼻にソフトなシリコーン製の柔らかいチューブを挿入することで気道を確保するという発想で作られた治療器具です。
チューブ状の医療デバイスを、使用者自身で、鼻から口蓋垂(のどちんこ)まで挿入することで、空気の通り道をしっかり確保できます。
そのため、空気の通り道が狭くなることで起こる「いびき」や空気の通り道が閉塞してしまうことで起こる「無呼吸」を回避することで、呼吸をサポートできるのがナステントです。
→ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状・原因・検査・治療法 について詳しくはこちら
【いびき関連記事】
【関連記事】
- 睡眠時無呼吸症候群 高血圧、心疾患の原因にも
- 睡眠時無呼吸症候群の患者は緑内障になるリスクが高い|正常眼圧緑内障の原因は「低酸素状態」の可能性がある
- 出川哲朗さんの病気は高血圧や睡眠時無呼吸症候群|血圧の薬を飲んだり、生活習慣の改善をしている
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)はメタボリックシンドロームと関係がある!?
- 糖尿病治療と一緒に不眠治療を行うことで、糖尿病が改善し、血管障害を予防できる可能性がある!?