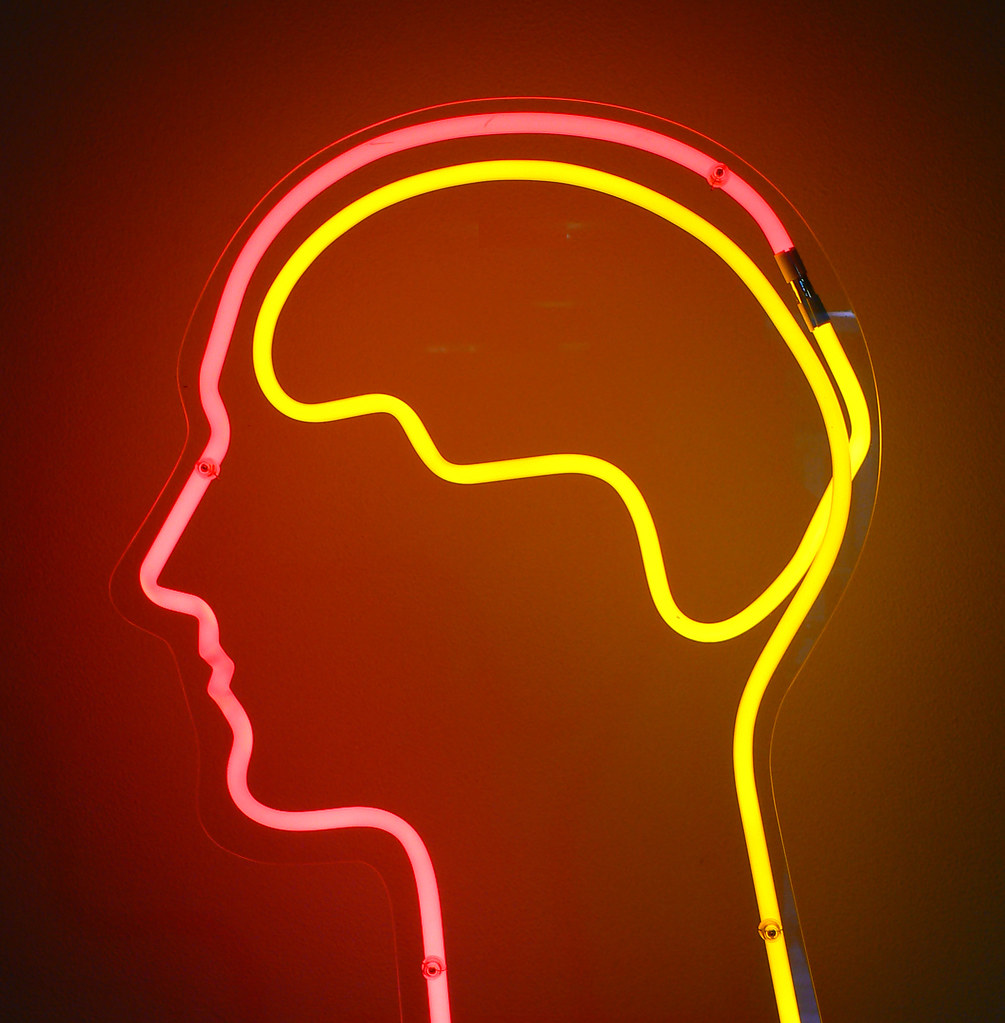by dierk schaefer(画像:Creative Commons)
ほぼ完全な人間の脳、実験室で培養成功 米大学研究
(2015/8/20、AFP)
米オハイオ州立大学(Ohio State University)の報告によると、小さな脳の培養に成功したのは、同大のルネ・アナンド(Rene Anand)教授。脳の成熟度は、妊娠5週の胎児に相当するという。
オハイオ州立大のルネ・アナンド教授が小さな脳の培養に成功したそうです。
今回の研究によって期待されるのは、脳や神経系の疾患に対する治療法を開発する上での実験に必要な脳モデルとしての役割です。
このことについては、「数学的相関法や統計的手法はそれ自体、因果関係を特定するには不十分だ。実験システム、つまり人間の脳が必要なのだ」と説明している。
自分の想像を超えるような発想を聞くと恐ろしいと感じてしまいますが、神経系疾患の治療に大きな進歩をもたらしてくれるということでしたら、すばらしいことですね。
【関連記事】