by 176th Wing Alaska Air National Guard(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 目の病気 > 近視 > 近視(近眼)の原因遺伝子を発見|眼球の成長をコントロールし、光が網膜で電気信号に変換されることを保障する3つの遺伝子の働きに影響
多くの人が悩まされている「近視(近眼)」を予防できる薬が登場か、原因遺伝子を特定
(2010/9/13、Gigazine)
Genetic code linked to short sight found | Technology | The Guardian
近視の兆候は、多くの場合子どものうちに現れます。
原因のうち生活習慣などの後天的因子と遺伝がどれほどを占めるかは人により異なりますが、特にひどい近視の人々では、80%が遺伝的要因によるものと言われています。
ネイチャー ジェネティクス誌に発表された2つの別々に行われた研究で、近視の人に多く見られるDNAのバリエーションが発見されました。
キングス・カレッジ・ロンドンのChris Hammond博士はChromosome 15(第15染色体)の中の1つのセクションが、近視の人に多く見られることを発見し、ロッテルダムのErasmus MC(エラスムス大学付属病院)のCaroline Klaver博士も、やはり第15染色体にある別のセクションが、近視と関連することを発見したそうです。
近視に関連する遺伝子・DNAのバリエーションが発見されたそうです。
この近視の人と近視でない人の間にあるDNAの違いは、眼球の成長をコントロールし目に入った光が網膜で電気信号に変換されることを保障する3つの遺伝子の働きに影響すると考えられます。
つまり、近視になりつつある子どもではこの3つの遺伝子がうまく働いていないため、眼球が「育ちすぎて」しまっているようなので、この段階で眼球の成長をコントロールできれば、近視の進行を防ぐことができます。
近視の人とそうでない人のDNAの違いは、眼球の成長をコントロールし、光が網膜で電気信号に変換されることを保障する3つの遺伝子の働きに影響されているそうです。
Hammond博士は「点眼薬や錠剤などでブロックすることができる経路を見つけ、脳の発達や身体のほかの過程をさまたげずに眼球の育ちすぎを止めることができれば、と期待しています」と語っていますが、眼球がすでに成長しきってしまっている大人の近視は、子どもと比べ治療することは難しいとのことです。
眼球が成長しきってしまうと治療が難しいとのことですが、眼球の成長をコントロールするということが本当に出来るのでしょうか。
不思議です。
特に強い近視は80%が遺伝的要因からくるとのことですが、近視の遺伝子を持つ子どもの全員が近視となるわけではありません。
2008年にシドニー大学の科学者が行った研究で、シンガポールとシドニーに住む中国人児童の近視率を調べたところ、シンガポールでは29%が近視だったのに対し、シドニーではわずか3%だったそうです。
これは遺伝では説明することができず、シドニーに暮らす子どもの方が外の自然光の中で過ごす時間が長く、遠くの物を見る機会が多いことで説明できるのではないかと示唆されています。
近視の80%は遺伝的要因ですが、その他の20%は環境要因ということでいいのでしょうか。
少しでも近視にならないためにも、自然の光のなかで、遠くのものを見る機会をもつといいと言えるかもしれませんね。
ただ、紫外線は目にはよくないといわれていますので、何だか難しい気もします。
【関連記事】
→ 近視 について詳しくはこちら
→カシス・ルテイン・ブルーベリーサプリ選びに悩むあなたに
→カシス・ルテイン・ブルーベリーサプリ通販専門店
今なら最大20%引きのお得な初回購入者価格・まとめ買いセール特価で購入できます!
→今ならサプリ無料お試しサンプルもあります。詳しくはこちら!

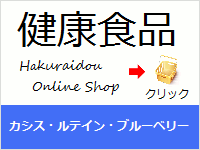


 肝臓関連ワード
肝臓関連ワード