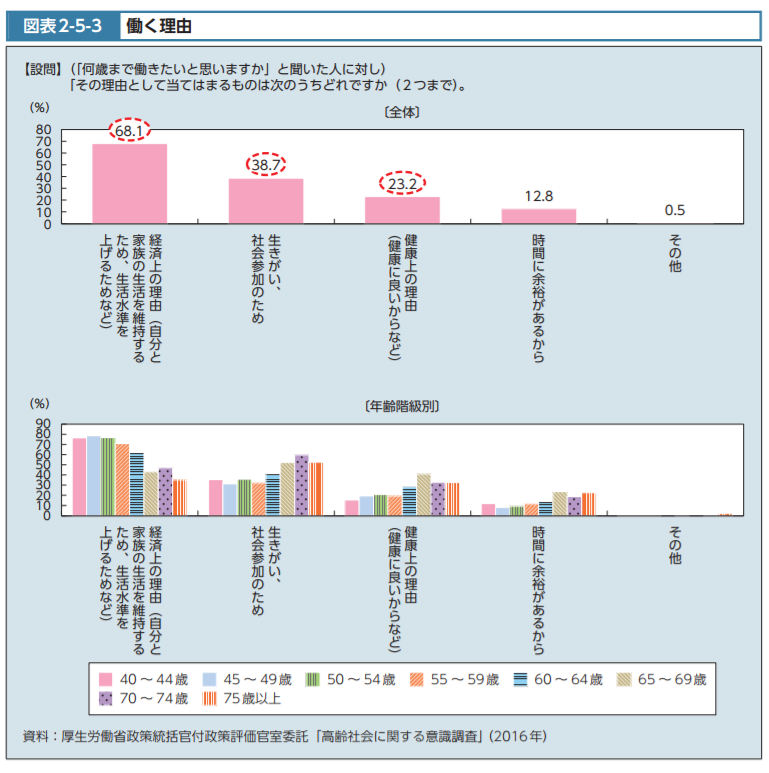■加齢性難聴は動脈硬化が原因で引き起こされる|#みんなの家庭の医学
by Ben Smith(画像:Creative Commons)
2010年8月17日放送のたけしの家庭の医学では、生活習慣と加齢性難聴について取り上げました。
■加齢性難聴と生活習慣
高齢化が進むと、高音から次第に聴力が低下し、加齢性難聴になります。
しかし、40代、50代の人にも加齢性難聴の症状が出ることがあるそうです。
その原因となるのが、食べ過ぎ・飲み過ぎといった生活習慣の乱れ。
生活習慣の乱れから動脈硬化になると、血管が硬くなり、血液の流れが悪くなります。
動脈硬化こそが加齢性難聴を進行させる大きな原因の一つなのだそうです。
最近様々な研究によって、動脈硬化と難聴との関連性が明らかになってきているそうです。
【論文・エビデンス】
- Laryngoscope. 2009 Mar;119(3):473-86. Audiometric Pattern as a Predictor of Cardiovascular Status: Development of a Model for Assessment of Risk|NCBI
動脈硬化によって血流が悪化→末端にある耳の毛細血管
音を感知する有毛細胞のある蝸牛には、たくさんの毛細血管があります。
有毛細胞はこの毛細血管から酸素や栄養素を摂取しています。
しかし、動脈硬化になると、有毛細胞は酸素不足に陥り、機能が低下し、難聴を引き起こすそうです。
高い音を感知する有毛細胞は、大量のエネルギーを必要とするため、少しでも血流が滞ると、すぐに機能が低下してしまうそうです。
加齢性難聴を進行させる危険因子として、
- 糖尿病
- 虚血性心疾患
- 腎疾患など
が疫学調査などからわかっているそうです。
【参考リンク】
- 「加齢および全身性基礎疾患の聴力障害に及ぼす影響」国立長寿医療センター内田育恵ら2004年研究より
また、一度壊れた有毛細胞は、元に戻ることはないそうです。
つまり、衰えた聴力が回復することはないということです。
加齢性難聴の進行を遅らせるためには、食生活など生活習慣に気をつけることが大事だということです。