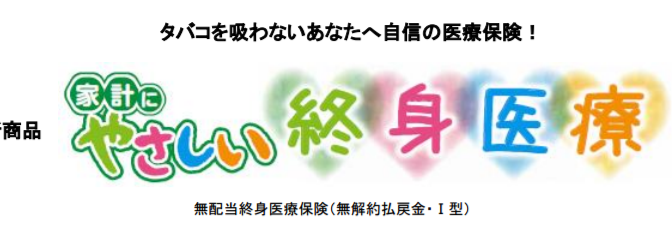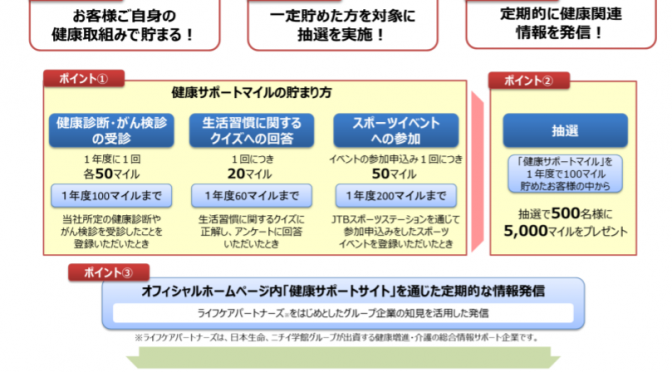■タバコを吸わない人の保険料を割り引きする医療保険を発売|T&Dフィナンシャル生命
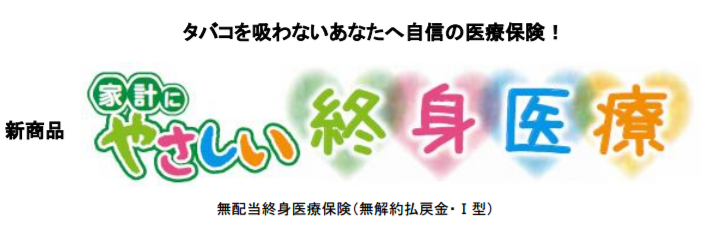
参考画像:タバコを吸わないあなたへ自信の医療保険! ~「家計にやさしい終身医療」』(2017/1/24、T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)|スクリーンショット
保険とIoTを融合した健康増進サービスの開発に注目!|ウェアラブルデバイスをつけて毎日運動する人は生命保険・医療保険の保険料が安くなる!?では、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社はFitbitを導入し、健康と運動データとの関係を分析する取り組みを行い、今後の新しい保険商品の開発を検討しているということを紹介しました。
例えば、ウェアラブルデバイスから得られるデータにより、運動をする機会が多い人が病気になるリスクが低いということがわかったとするならば、それに対応した新しい保険商品(例:ウェアラブルデバイスをつけて、毎日運動をしている人は保険料が安くなる)の開発が検討されるかもしれません。
健康な人ほど保険料が安くしていくということが傾向として表れているのでしょうか、T&Dフィナンシャル生命保険株式会社は、タバコを吸わない人が得をする医療保険の販売を開始するそうです。
タバコを吸わないあなたへ自信の医療保険! ~「家計にやさしい終身医療」』
(2017/1/24、T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)
「家計にやさしい終身医療」は、タバコを吸わない方の保険料を割り引き、日帰り入院・外来手術から保障するシンプルな医療保険となります。
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社が2017年2月2日より販売する「家計にやさしい終身医療」という医療保険の特徴は、「タバコを吸わない人の保険料を割り引く」というものです。
過去 1 年以内に喫煙歴がない場合、主契約の保険料を割り引きます。※
唾液検査を受けていただき、被保険者の喫煙状況等がT&Dフィナンシャル生命の定める基準を満たすことが必要となります。
同様のアイデアは第一生命の子会社のネオファースト生命でも保険商品として以前販売されています。
ネオファースト生命、過去1年間タバコを吸っていない方の保険料を割り引きをする非喫煙者割引特約を付けた終身医療保険を生保業界初めて適用したそうです。
【関連記事】
■喫煙率の高さと健康の関係
喫煙は、がん、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、動脈硬化などの病気に対するリスク要因であり、喫煙率の高さと健康には深い関係があります。
岩手県、脳卒中の死亡率が全国でワースト1!その原因とは!?によれば、岩手県は脳卒中の死亡率が全国でワースト1なのですが、その原因の一つに喫煙率の高さがあります。
なぜ、青森県が平均寿命最下位なのか?|青森県を長寿県にするための方法とは?によれば、たばこに関しては厚労省の25年の国民生活基礎調査によると、青森県民の喫煙率は男性が40・3%で全国1位、女性は14・3%で同2位と、喫煙率は男女とも高いという結果が出ています。
たばこを吸う人は非喫煙者に比べてがんの再発リスクは2.5倍|山形大によれば、がん経験者でたばこをやめなかった人は、たばこを吸わない人に比べて、がんの発症リスクが約2.5倍になるそうです。
世界一受けたい授業 5月2日|エクオール|健康な血管を作る為の3つの習慣|最新のがん予防法によれば、喫煙は肺がん・食道がん・胃がん・すい臓がん・子宮頸がんのがんの発症リスクを上げるそうです。
■まとめ
積極的に計画・実行する人はがん・脳卒中・心筋梗塞の死亡リスクが低い|国立がん研究センターで紹介した国立がん研究センターによれば、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の行動をとる人は、そうでない人に比べて、がんで死亡するリスクが15%低く、また、脳卒中リスクが15%低く、脳卒中や心筋梗塞などで死亡するリスクが26%低いという結果が出たそうです。
その理由としては、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の人は、がん検診や健康診断を受診するため、病気の早期発見につながり、病気による死亡リスクが低下して可能性があるようです。
タバコを吸わない人が得をする医療保険ができたように、これからは様々な予防医療に取り組んだ人には保険料が安くなるといった保険商品も考えられそうです。
また、可能性としては、PHYSIO HEALTH|従業員向けの健康コーチをするモバイルヘルスプラットフォームのような、雇用主の健康保険料に対するコストを減らし、健康奨励プログラムに励む従業員に報酬を与えるシステムを企業と保険会社が組み合わせるということもあるのではないでしょうか。
このように、健康とはこれまで縁がなかった銀行などの金融機関や保険会社が健康への関心を高めていくことによって、社会全体で健康な生活を後押ししていくような形になっていきそうです。
銀行が健康的な人には金利を上乗せする時代が来る!?健康が金利に反映されるアイデア|#ダボス会議2017 人生100年時代では、佐藤康博みずほフィナンシャルグループCEOが健康的な人には金利を上乗せするという健康を金利に反映するアイデアを提案されていたことを紹介しました。
人の信頼度を評価するシステムによって信頼自体がお金(通貨)のような価値をもつ時代になる!?では、信頼が通貨のような価値を持つ時代について紹介しましたが、長寿社会において健康であることは価値が高くなっており、行政機関や銀行、保険会社などの取り組みによって、健康であることが数字として表れることで、健康が通貨としての価値を持ち、本当の意味での資産になる日も近いかもしれません。