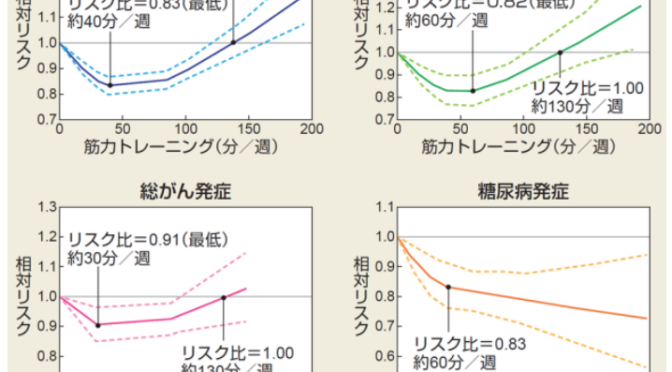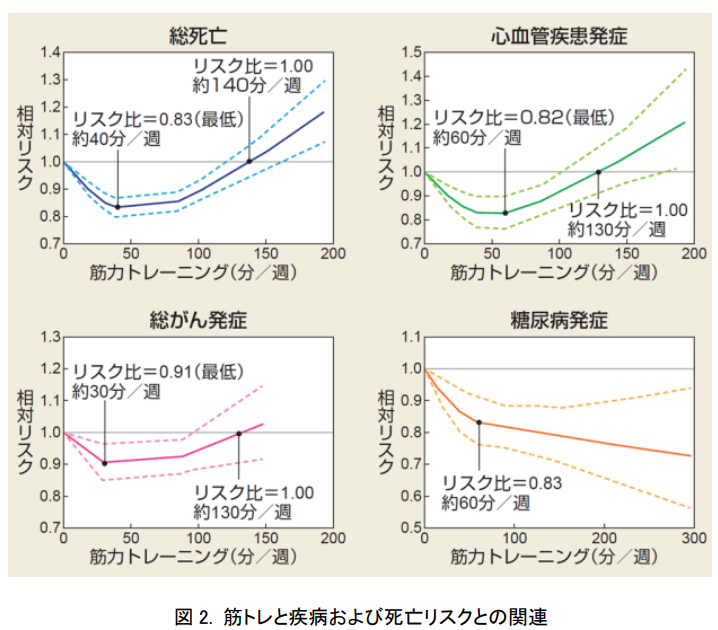> 健康・美容チェック > 内臓脂肪 > 【名医のTHE太鼓判】もち麦10日間生活&トイレぶらぶら体操で内臓脂肪を減らす!(FUJIWARA原西孝之さん、ニッチェ近藤さん、ナダルさん)|7月9日
■【名医のTHE太鼓判】もち麦10日間生活&トイレぶらぶら体操で内臓脂肪を減らす!(FUJIWARA原西孝之さん、ニッチェ近藤さん、ナダルさん)|7月9日
by Jessica Spengler(画像:Creative Commons)
2018年7月9日放送の「名医のTHE太鼓判」では「もち麦10日間生活&トイレぶらぶら体操で内臓脂肪を減らす!」を特集していました。
もち麦には食物繊維が豊富に含まれていて、管理栄養士の浅野まみこさんによれば100gあたり13gの食物繊維が含まれているそうです。
これはゴボウの2倍、白米と比べると26倍なのだそうです。
例:もち麦100g→ゴボウ1.5本
例:もち麦100g→レタス4個
もち麦は、昆布や納豆、にんにく、りんごなどの水に溶けやすい食物繊維とごぼうやサツマイモ、カボチャ、こんにゃくなどの水に溶けにくい食物繊維の両方を持つバランスの良い食材なのだそうです。
もち麦は水溶性食物繊維が豊富で、水溶性食物繊維「βグルカン」は水を加えるとゲル状になって、後から入ってくる糖分や脂質の吸収を邪魔するだけでなく、絡めて排泄する働きがあります。
→ 食物繊維の多い食品|水溶性食物繊維・不溶性食物繊維 について詳しくはこちら
【関連記事】
もち麦農家の方は、白米7:もち麦3の割合でもち麦ご飯として食べたり、もち麦団子やもち麦味噌汁、もち麦団子、もち麦五平餅、もち麦茶として食べているそうです。
もち麦は食物繊維が豊富なため便秘解消にも効果があります。
もち麦を食べる時のポイントは2つ。
1.朝食べると、余分な糖質を吸収する効果が昼まで続くので、毎朝食べること!
2.もち麦を食べる時は毎食中コップ一杯の水(200ml)を飲むことで満腹感が出て間食防止になる!
■トイレぶらぶら体操のポイント
トイレに行くときに、お腹に力を入れ、姿勢を正し、体をブラブラさせながら歩くだけ。
ベースとなる考え方はスロージョギングの考え方で、普通に歩くより3倍のカロリーを消費してくれるそうです。
一日平均6-8回トイレに行くため、運動量が飛躍的に上がるそうです。
FUJIWARA原西孝之さん、ニッチェ近藤さん、ナダルさんがもち麦10日間生活&トイレぶらぶら体操で内臓脂肪を減らすことに成功しました!
→ 内臓脂肪を減らすには|内臓脂肪の落とし方 について詳しくはこちら
「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」