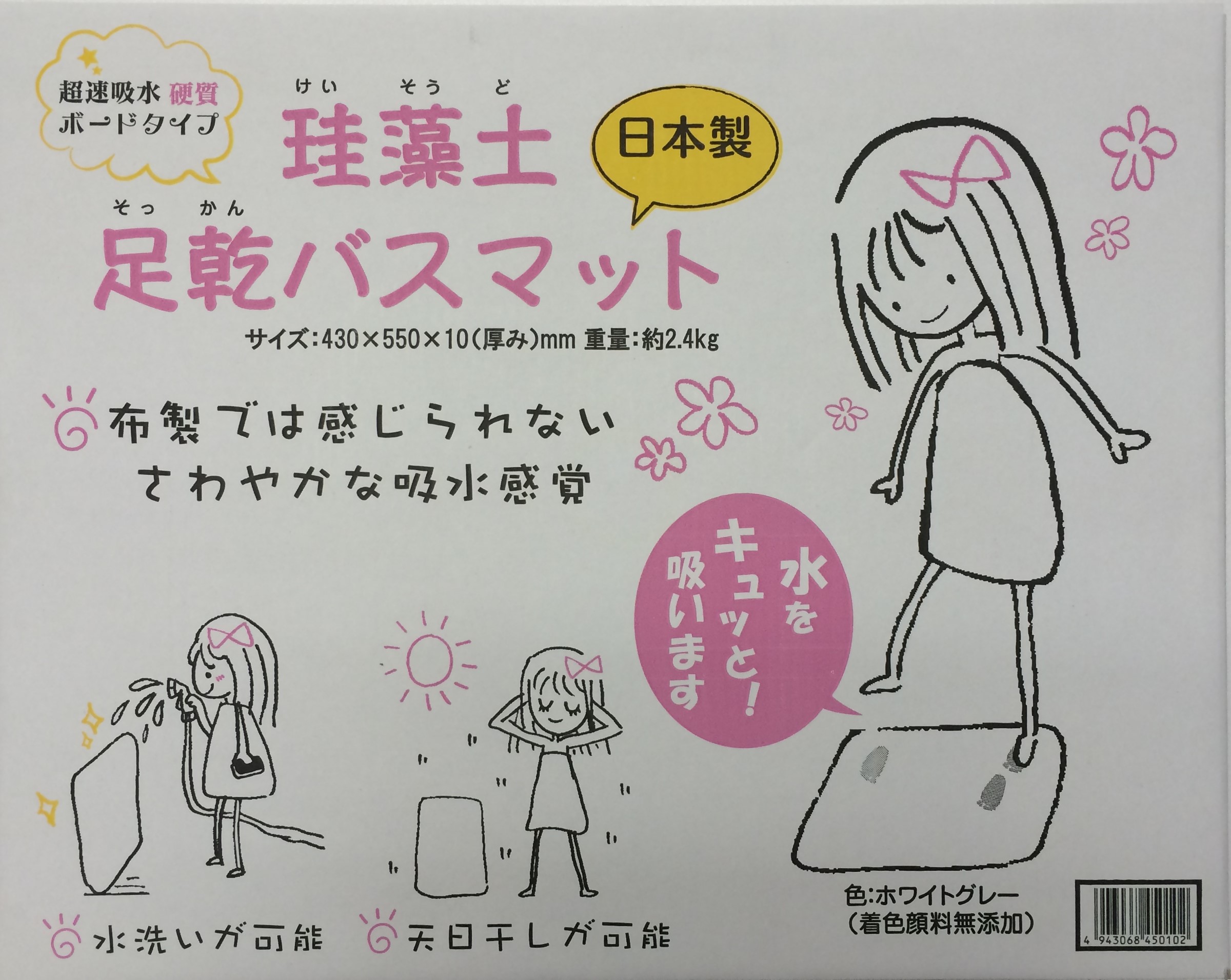by Alisha Vargas(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病が世界で急増、4億人に迫る 中国、インド、アフリカでも
世界で急増、糖尿病 10年で倍の4億人に 国際団体試算 中国、インド、アフリカでも
(2014/9/2、msn産経)
各国の糖尿病関連団体でつくる国際糖尿病連合(IDF)によると、2013年の世界の糖尿病人口(20~79歳)は3億8200万人で、1億9400万人だった03年から倍増。35年には5億9200万人に達する見込みだ。
世界の糖尿病人口は増加しており、10年で約2倍になっているそうです。
→糖尿病について詳しくはこちら
【関連記事】
IDFによると、糖尿病人口の約80%は中低所得国の人々。13年は1位が中国でインド、米国と続き、日本は10位だ。35年までに中国では約1・5倍、インドで約1・7倍に、サハラ砂漠以南のアフリカでも倍増する見通し。
経済成長にともなって、中国やインド、アフリカで糖尿病人口が増加しているようです。
【関連記事】
- インドの糖尿病患者、2030年までに1億人超え─IDF予想
- 〝糖尿病急増〟インド経済を脅かす 関連コストGDPの2%
- 中国、肥満や糖尿病が新たな課題に-医療保険改革は前途多難
- 中国は糖尿病の罹患率が10%、患者数でも世界最多―米紙
- アメリカで若年の糖尿病患者が大幅増
糖尿病が怖いのは、糖尿病をそのままにしておくと合併症(糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病神経障害など)を引き起こすことです。
→ 糖尿病の合併症 について詳しくはこちら
【関連記事】
さらに、糖尿病は医療費も大きな負担となってきます。
現在では、糖尿病による医療費負担が各国の財政を圧迫しており、例えば、米国の医療費を圧迫する肥満問題、ライフスタイルを変える必要あり(2009年の記事)によれば、たとえば11年前、糖尿病など肥満関連の病気に支出される医療費は総額約780億ドル(約7兆4000億円)だったが、2006年には約1470億ドル(約14兆円)に膨れあがっています。
もしかすると、糖尿病による様々な影響によって、国家を揺るがされるような国も出てくるかもしれません。
そういった事態を避けるヒントはこの部分になるのではないでしょうか。
IDFによると、糖尿病人口の約80%は中低所得国の人々。
中低所得の国の人々に糖尿病人口の80%が集中しているというのは、ひとつは経済成長にともなって急激に食生活が変化したことが関係していることが考えられ、もう1つは低所得者層ほど生活習慣に問題があることが考えられます。
低所得者ほど生活習慣に問題=野菜食べず、運動しないによれば、低所得者ほど野菜を食べる量が少なかったり、運動の習慣がなかったりと、生活習慣に問題がある傾向があることがわかったそうです。
【関連記事】
フードスタンプに頼っている人の割合が最も高い州はミシシッピ州で、20.7%です。
5人に一人が生活保護を受けているということ。
つまり、肥満と生活保護には相関関係があるのではと推測しています。
最も肥満率が高かったのは南部ミシシッピ(Mississippi)州で成人の32%以上、10-17歳では驚くべきことに44%が肥満だった。
同州は全米で最も経済的に貧しい州とされており、貧困と肥満の関連があらためて示された形だ。
ミシェル・オバマ大統領夫人が推奨する「ダイエット・プロジェクト」とは
ミシェル・オバマ夫人が、記者団に語るシカゴ時代の自分自身のエピソードにこんなものがあります。
「弁護士の仕事を持つ母親として、会議と子供たちのサッカーやバレー教室と駆け回った日の夜には、簡単で安いファーストフードのドライブスルーや、電子レンジで温めるだけの栄養バランスのとれていない食事を子供たちに出していた」--。
自分がそうだったからこそ、多くのアメリカ人が、栄養バランスのとれた食事の大切さは知ってはいるものの、新鮮な野菜や魚などを買うための支出と、手に入れた素材を調理する手間と時間を考えるとき、それよりも数百円で手に入れることができる完成したファーストフードの魅力が大きいと感じてしまう。
低所得者層で高い肥満率となっているようです。
なぜ、女の子の思春期に達する年齢が昔に比べて早くなっているのか?
研究によれば、BMI値が高ければ高いほど思春期を迎える年齢が早くなるそうです。
経済的に貧しい地域と肥満の地域に関連がある理由としては、栄養バランスのとれた食事の重要性を知らなかったり、どんな食品をとれば健康になれるのかということを知らないということが考えられます。
しかし、どんなに栄養バランスのとれた食事の大切さを知っていても、また新鮮な魚や野菜を買って、料理を作った方が良いということはわかっていても、仕事・家事をして疲れてしまうという生活をしていると、調理する時間や家計のことを考えてしまい、手軽で安いファストフード・冷凍食品に頼りがちの生活になってしまいがちです。
肥満問題については、個人のライフスタイルに影響を与えている、家計や知識、意識、社会の影響が大きいかと思います。
肥満問題を解決するためにも、個人の生活習慣の改善のために知識を提供し続ける必要があるだけでなく、貧困などの社会問題を解決していく必要があると思います。
 糖尿病関連ワード
糖尿病関連ワード
■薬局でもできる糖尿病の検査|検尿(尿糖検査)と採血による血糖検査