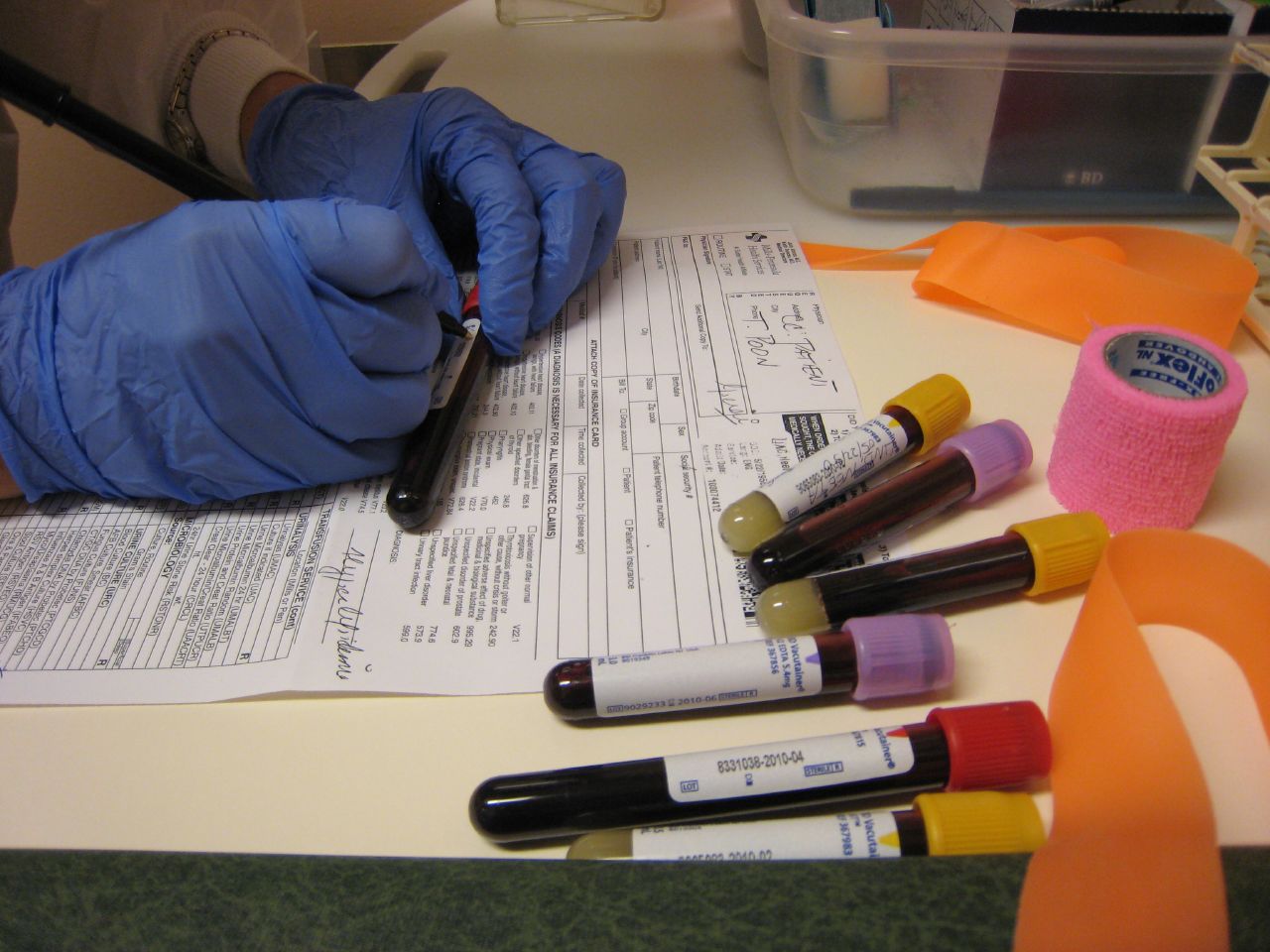by Rebecca Siegel(画像:Creative Commons)
(2014/5/7、WSJ)
「飽和脂肪酸は心臓疾患の原因にはならない」――。3月に発行された医学専門誌アナルズ・オブ・インターナル・メディシンに掲載された研究はこう結論づけている。
ここ最近の健康情報としては、飽和脂肪酸の摂り過ぎは体に良くないため、脂の多い肉やバター・チーズは避けたほうがいいと言われてきており、それを実践する人も多いですよね。
しかし、今回の記事で紹介された研究によれば、「飽和脂肪酸は心臓疾患の原因にはならない」そうです。
コレステロールの新常識(LH比・悪玉コレステロールを減らす食事・善玉コレステロールを増やす運動)|主治医が見つかる診療所 4月21日でも、飽和脂肪酸を多く含む食品をたくさん摂ると、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)値が上がりやすいとして紹介されていましたが、本当に飽和脂肪酸が体に悪いのでしょうか?
詳しい内容は記事を読んでもらうことにして、要点だけをまとめてみます。
●1950年代にミネソタ大学のアンセル・ベンジャミン・キーズ博士が飽和脂肪酸はコレステロール値を上げ、その結果、心臓疾患の原因になるという説を主張したのが飽和脂肪酸悪玉論の始まり
●ただ、研究を行う際に自説の正当性を裏付けるような国だけを意図的に選んだり、研究の対象者が数少ないなど、間違ったデータによる間違った考えで研究が行われており、本当に飽和脂肪酸が心臓疾患の原因になるかどうかはわからない。
●当初懐疑的だった米心臓協会(AHA)も1961年に飽和脂肪酸を悪者としたガイドラインを米国で初めて発行し、1980年には米農務省がこれに続く。
本来であれば間違ったデータによる間違った考えであるため、再度調査研究をすることが必要なのですが、この説を正しいという先入観をもとに、なぜかキーズ博士の説を証明する方向で労力も費用もつぎ込まれていったそうです。
行動経済学に「サンクコスト(先行投資額が巨大だと損失回避の傾向から、人は未来の予測をしばしば誤る)」という考え方がありますが、この研究においても、多くの人が労力も費用も注ぎこんでしまったがために、冷静に判断できず、正しいという先入観をもってしまったのかもしれません。
記事ではさらに飽和脂肪酸をあまり取らない食事方法に変わったことによる変化についても書かれています。
詳しい内容は記事を読んでいただきたいので、2つのポイントだけ。
1つは、炭水化物の摂取量が増えたこと。
飽和脂肪酸の摂取量が減ったものの、炭水化物の摂取量が増えているそうです。
飽和脂肪酸の摂取量が減ったから炭水化物の摂取量が増えたとは短絡的に言えないものの、炭水化物の摂り過ぎは、肥満や糖尿病の原因になり、さらには心臓疾患になる可能性も高まります。
問題は炭水化物がブドウ糖に分解され、インスリンが分泌されることだ。インスリンは効率良く脂肪を蓄積させるホルモンだ。果糖は肝臓が血液中に脂質や中性脂肪を分泌させる原因となる。炭水化物の摂りすぎは肥満の原因となるだけでなく、後天性の2型糖尿病の原因にもなる。さらには心臓疾患の可能性も高まる。
もう1つは、植物油の摂取が増えていること。
AHAが1961年に「健康な心臓」のために、飽和脂肪酸ではなく植物油を摂取するよう国民に勧めた後、米国民の食事は変わった。1900年にはほとんどゼロだった植物油の摂取量が現在は摂取カロリーの7~8%を占めるようになった。この1世紀の間にこれほど摂取量が増えた食品はない。
初期段階の臨床試験では、植物油の摂取量が多い人は、がんの発症率が高いだけでなく、胆石になる率も高いことが分かった。さらに驚くべきことに、暴力的な事件や自殺で死亡する可能性も高い。
植物油の摂取が増えたからといって体に悪影響があるというデータはないようなのですが、体の中の栄養バランスに何らかの影響を与えているかもしれません。
今回の「飽和脂肪酸悪玉論」の問題は、間違ったデータによる間違った考えであるということです。
もう一度先入観を取り払って、本当に飽和脂肪酸に問題があるのかを証明する必要があるのではないでしょうか。
そして、こういう健康に関する情報を紹介すると極端な方向に行きがちで、飽和脂肪酸が悪いというと、すべての飽和脂肪酸がいけないとなってしまいます。
大事なのは、何事もバランスです。
あまりに過剰に飽和脂肪酸を摂っていて健康に問題があるという方は、飽和脂肪酸を減らして、不飽和脂肪酸に変えて、バランスを調整してみるというアプローチをしてください。
【関連記事】