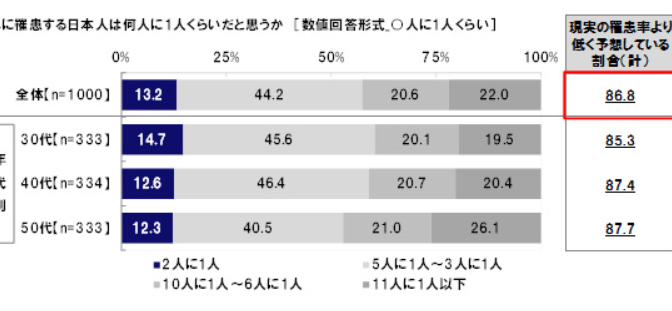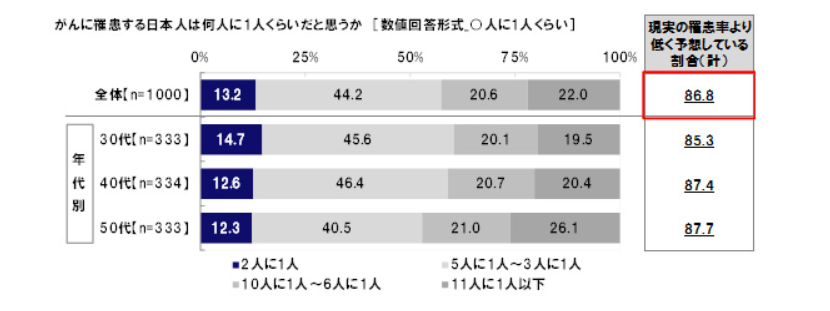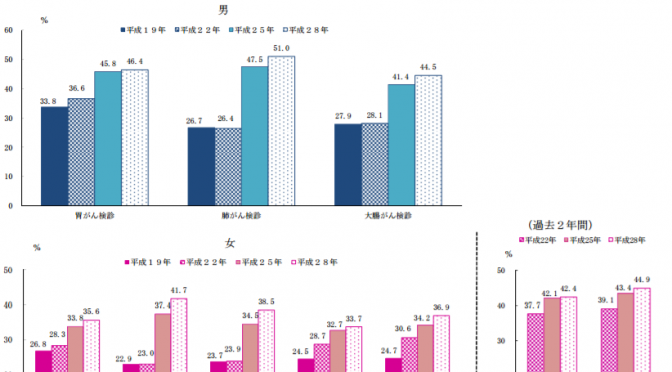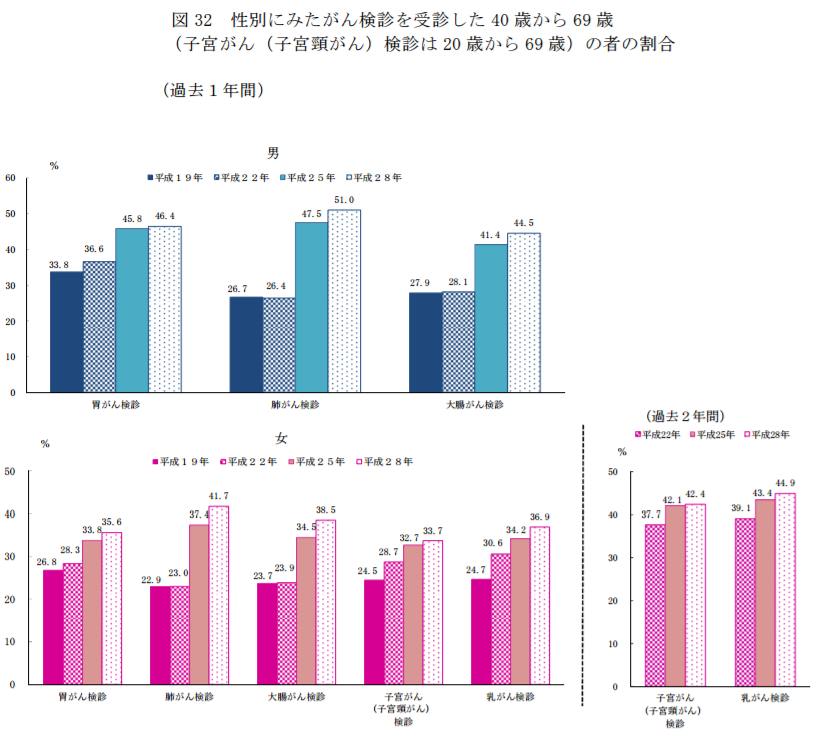ハクライドウがこれまで培ってきた約20年の健康情報をまとめた10箇条を紹介します。
あなたの健康的なライフスタイルにこの10箇条を取り入れていきましょう。
【目次】
■飲酒とがん・生活習慣病・認知症との関係
●がん
飲酒はがんの原因なのか?|肝臓がん・大腸がん・食道がん・乳癌(閉経後)・口腔がんのリスクが高くなるによれば、最近の国際的な評価では、アルコールが直接触れる消化管(口腔・咽頭・喉頭・食道)、アルコールを代謝する肝臓、そして女性ホルモンの影響が大きい乳房のがん、大腸がんのリスクが確実に高くなるとされています。
また、日本におけるアルコールによるがんのリスクは、2008年7月現在、肝臓、食道、大腸については「確実」と判定されています。
●中性脂肪
中性脂肪とアルコールの関係|なぜアルコールが中性脂肪値を高める原因になるの?によれば、中性脂肪は、糖質・脂質が多く含まれている食事の食べ過ぎやお酒の飲み過ぎで必要以上のエネルギーが体に入り、また運動不足でエネルギーが消費されないと、エネルギーが余り、その余ったエネルギーが中性脂肪となることで、中性脂肪の値が高くなります。
また、アルコールは、中性脂肪を分解する酵素の働きを低下させるため、中性脂肪値を高める原因となります。
肝臓にはアルコールの分解を行う機能がありますが、アルコールの量が多かったり、肝機能が低下していると、代謝がうまくいかなくなり、肝臓に中性脂肪がたまっていきます。
この状態をアルコール性肝障害の初期段階である「アルコール性脂肪肝」といいます。
→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 について詳しくはこちら
→ 脂肪肝を治す方法|脂肪肝の改善方法(食事・運動・サプリ) について詳しくはこちら
●認知症
お酒はがんや生活習慣病だけではなく、認知症のリスク要因でもあります。
慢性的な大量飲酒、全てのタイプの認知症、特に早期発症型認知症の発症の危険因子で紹介したThe LANCET Public Healthに掲載された論文によれば、アルコール摂取障害は、すべてのタイプの認知症、特に早期発症型認知症の発症の主要な危険因子であるそうです。
■休肝日を作る
お酒は健康にとってリスク要因になると考えられますが、「全て止めて禁酒しなさい!」とはいいません。
大事なことは、楽しいお酒にすること、そして休肝日を作ること。
楽しいお酒はいいものですが、孤独なお酒は病気のリスクを高めます。
<脳卒中>「孤独な酒」 リスク2倍|厚労省調査で紹介した厚生労働省研究班の調査によれば、親友がおらず、お酒好きな人が脳卒中になる危険性は飲まない人に比べて、約2倍高いことがわかったそうです。
頼れる人がいる時に適量に飲酒していると脳卒中が少なかったそうです。
国立がん研究センターの多目的コホート研究によれば、脳卒中のリスクに関して、社会的な支えが多い場合には、週にエタノール換算で1-299gの少量~中等量の飲酒のグループの場合はリスクが低いという結果が出たそうです。
ただし、週に300g以上になると、社会的な支えに関係なく、脳卒中のリスクが増加する傾向があることがわかったそうです。
適量で止められるかを楽しいお酒の一つの判断基準にするのもよいでしょう。
そして、もう一つ、休肝日だけは作ってください。
休肝日なしのグループは、飲酒量にかかわらず死亡リスクが最も高いことがわかっています。
お酒をよく飲む人が肝臓を休めるために休肝日をとることを勧められるイメージがありますが、最近では、非アルコール性の脂肪肝であるNAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)やNASH(非アルコール性脂肪肝炎)になる人が増えているため、アルコールを飲む人も飲まない人も、肝臓を意識した生活を心がけ、休肝日を設けるべき時代になってきています。
男性より若い女性の方が「肝臓を酷使」している!?によれば、女性の社会進出に伴いお酒を飲む機会が増えたことやストレス発散のためにお酒に頼るという人が増えているため、アルコール外来に来られる女性患者が増えているそうです。
女性は飲酒量が男性と同じでも、肝臓は先に悪化するによれば、女性のほうがアルコールによる影響を受けやすいのは、
●女性ホルモンにはアルコール分解を妨げる作用があるため、男性より依存症になる恐れがあること
●アルコールを分解する肝臓の大きさも男性より小さいため肝障害のリスクが高い。
ことが理由としてあげられるようです。
女性は男性より肝臓へのリスクなどアルコールの影響を受けやすい。によれば、女性は男性よりも体も肝臓も小さいことから、血中アルコール濃度は男性よりも女性のほうが高くなり、また、女性ホルモンにはアルコールの分解を抑える作用があるともいわれているため、女性は男性よりもアルコールの適量は少なくしたほうが良いようです。
特に女性はアルコールによる肝臓の負担が大きくなるため、しっかりと休肝日を作るように心がけてください。
→ 休肝日の取り方(過ごし方)・ペースの目安・休肝日は必要か? についてくわしくはこちら
*良い情報が入るたびに今後アップデートしていきます。
【おすすめの健康的ライフスタイル10箇条】
続きを読む 休肝日を作る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条