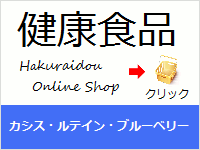> 健康・美容チェック > 低体温 > ヒートショックプロテイン・HSP入浴法で低体温改善|#世界一受けたい授業
2011年2月5日放送の世界一受けたい授業では「低体温」について取り上げました。
講師 伊藤要子(愛知医科大学准教授)
■ヒートショックプロテイン・HSP入浴法で低体温改善|世界一受けたい授業
by Stefan Powell(画像:Creative Commons)
■加温生活
正しく体を温めることは健康につながる。
■低体温
●低体温になると免疫力が低下し、インフルエンザウイルスやノロウイルス、風邪にもなりやすい。
●代謝が盛んな子供でさえも37度ある子は少ない。
●女性だけでなく男性にも低体温が多くなってきている。
■ヒートショックプロテイン
ヒートショックプロテインとは、熱による負荷で生まれるたんぱく質のこと。
ヒートショックプロテインは、傷ついた部分を直してくれる万能なたんぱく質と言われている。
体の中で起こる異常(ケガ・病気・筋肉痛)はたんぱく質の異常とも言えるが、体内のたんぱく質が外からの影響が受けないようにヒートショックプロテインが防いでいる。
ヒートショックプロテインが体に増えると疲労しにくい。そのため、運動能力がアップする。
■ヒートショックプロテインを増やすには?
ヒートショックプロテインは、熱による負荷を与えて増やすことができる。
ヒートショックプロテインは体温が上がったときに増える。
安全で簡単に効果的に増やすには入浴が良い。
■HSP(Heat Shock Protein)入浴法
42度のお湯に10分間入浴
※ふたを閉めると効果的。10分継続しなくても途中で休んでも良い。
※41度で15分。40度で20分でもOK。
※入浴後は保温が大切
ふとん・サウナスーツなどで15~20分保温すると効果的。
非常に汗が出るので水分補給もわすれない。
→体温が大体2度くらい上昇するそうです。
→ヒートショックプロテインが増えると考えられている。
入浴から2日後がピーク(ピーク時には個人差があるそうです)に1から4日くらいまでで、1週間後には元に戻るそうです。
HSP入浴法は週2回がベスト。
HSP入浴法以外の日はぬるめのお風呂でも良い。
4から5週間続けると慣れが出てきて、HSPが下がってくることもあるそうです。
⇒ 体温を上げる方法 についてはこちら。
⇒ 低体温|低体温の改善・原因・症状 についてはこちら。
⇒ 冷え性改善方法 についてはこちら。
【関連記事】
続きを読む 【#世界一受けたい授業】低体温改善!免疫力アップ!ヒートショックプロテインを増やす方法!HSP入浴法のやり方!