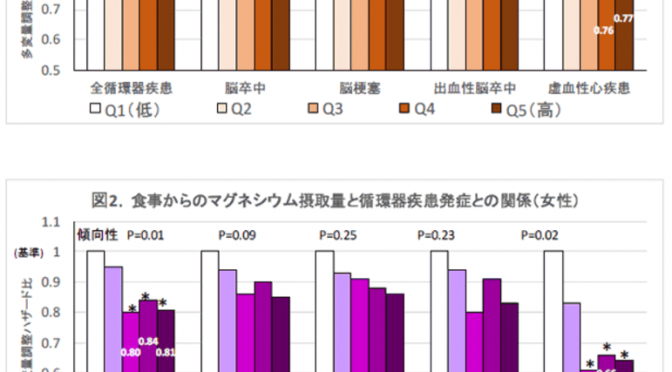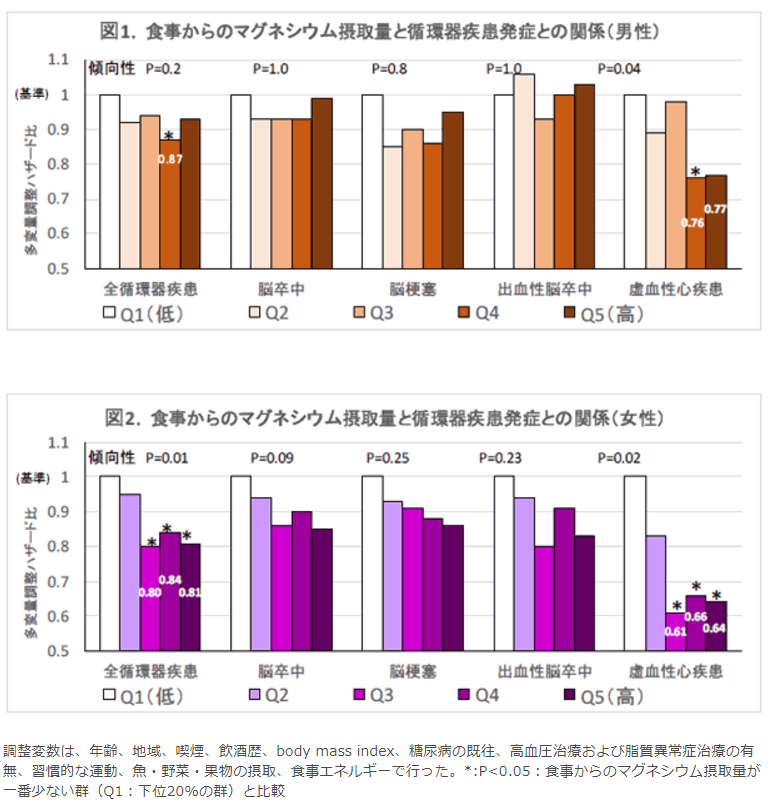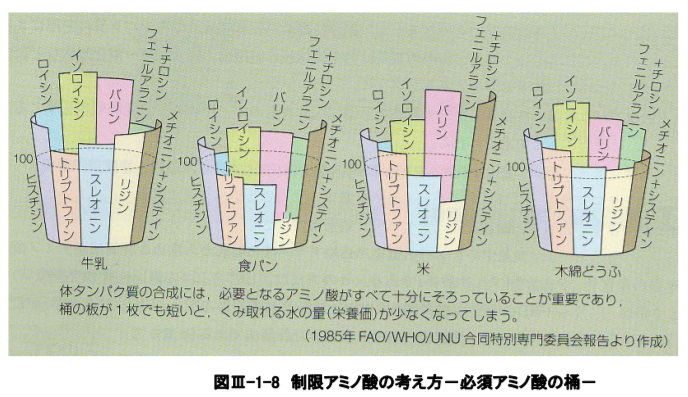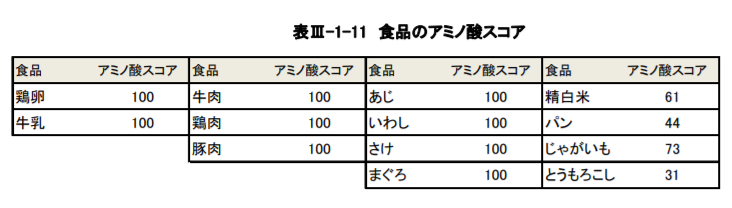Bereczki Domokos|unsplash
サンドウィッチマン伊達さんの病気は膀胱がん(ステージ1)でしたが、早期発見で手術を既に行ったそうです。https://t.co/ZSB18oT66u
✅痛みのない血尿は身体からの大きなサイン https://t.co/wBgfPtKuQV
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 26, 2021
サンドウィッチマン伊達みきおさんの病気は膀胱がん(ステージ1)ですでに手術で切除されたそうです。
膀胱がん早期発見のきっかけは「血尿」。
「#とくダネ!」キャスター #小倉智昭 さんの病気は「膀胱がん」でしたが、小倉さんも膀胱がんを発見するきっかけは、サンド伊達さんと同様に血尿を見つけたことでした。血尿が出たら、迷わず病院で診てもらいましょう!https://t.co/APordo1s9v
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 26, 2021
とくダネのメインキャスターだった小倉智昭さんの病気も「膀胱がん」でしたが、発見のきっかけはサンド伊達さんと同じ血尿を見つけたことでした。
【関連記事】
「血尿」が出たら、病院で診てもらってくださいね。
【追記(2024年12月14日)】
ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」で伊達みきおさんは小倉さんから3か月に一度定期健診に行くようにとアドバイスされたそうです。
伊達さんによれば、その検査は痛くて、血が出るし、恥ずかしく、つらい検査であり、小倉さんはその定期健診が嫌で行かなかったためがんが転移し膀胱を全摘することになったことを後悔していたからこそ、伊達さんにはそうならないようにメールしてくれたそうで、そのことに伊達さんは感謝しているそうです。
膀胱がんは再発率が高いことでも知られているものの、その検査がつらいために避けてしまいがちであるため、同じ後悔はしてほしくないと小倉さんは伊達さんのことを思ってメールされたんでしょうね。
同じようなエピソードとして、梅沢富美男さんをがんから救ったのは今井雅之さんのアドバイス 大腸検診で「ポリープ」発見によれば、梅沢富美男さんは、今井雅之さんから大腸検診に行くことを勧められ、ポリープが見つかったことを思い出しました。
定期健診や人間ドックを受けることの大切さがわかります。
【関連記事】
【人間ドック 関連記事】
- AKB48柏木由紀さん、「脊髄空洞症」を患っていることを公表!主治医が見つかる診療所の人間ドック企画で早期発見
- 狩野英孝さん、人間ドックの結果γ-GTPの数値が正常値を上回る「206」で脂肪肝の疑いあり!
- 高田純次さん、人間ドックで20個以上の大腸ポリープが見つかり、3度に及ぶ摘出手術を行なっていた!【徹子の部屋】
- 君島十和子さんが行なう3つの更年期対策|人間ドック・体を冷やさない・女性ホルモンを食事で補う
- 藤本美貴さん、人間ドックで悪玉コレステロール値が“D判定”
- 純烈 酒井一圭さん、人間ドックで脂肪肝が判明!血糖値スパイクの症状もあり、2型糖尿病になる危険性があると診断!【名医のTHE太鼓判】
- 【名医のTHE太鼓判】石田純一さんに人間ドック企画で肝機能異常が発覚!
- 【ヒルナンデス】和牛・水田さん、人間ドック企画で「脂肪肝」発覚!
- 【#主治医が見つかる診療所】芸能人人間ドックSP|岡田圭右さんと「lh比」・村本大輔さんと「高尿酸血症」・井上裕介さんと「アルコール性肝炎」
- 東てる美さん、「名医のTHE太鼓判!」の企画で人間ドックを受診し肺腺がんを発見!
- 【名医のTHE太鼓判】純烈 後上翔太さん、人間ドックで若年性肺気腫が判明!
- 【名医のTHE太鼓判】宮本亜門さん、人間ドックで前立腺がんが判明!
- 【名医のTHE太鼓判】クロちゃん、人間ドックで大腸ポリープが判明!
- 【生活習慣病】人間ドック受診者の9割が「異常あり」|最も異常の割合が多かったのは「高コレステロール」
- 世界的指揮者の #小澤征爾 さんは人間ドックを受けたことで食道がんの早期発見ができた|人間ドックのメリット|60歳過ぎたら年1回受診を
投稿日: 2021年3月26日 21:08