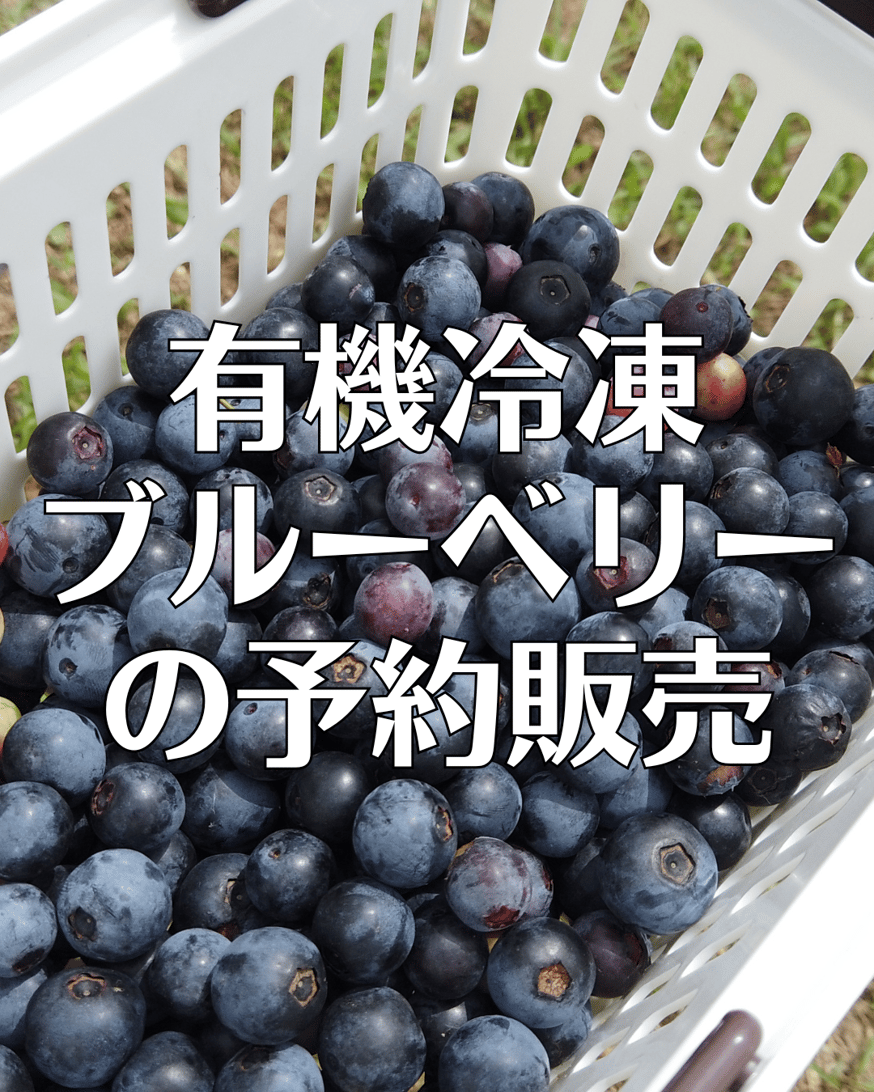ジャーナリングや日記を書くことが肉体的・精神的健康に与える影響について注目されているので、論文ベースで調べてみたいと思います。
「ジャーナル」と聞いて一番身近なのはiPhoneの「ジャーナル」アプリですね。
ジャーナルアプリでは日記を書くことで体験を思い出したり、振り返ったりすることを目的としています。
Apple、日々の瞬間や暮らしの中の特別な出来事を振り返るための新しいアプリ、ジャーナルの提供を開始によれば、ジャーナルは、心身の健康を改善するといわれている、ジャーナル記録を通じて、ユーザーが感謝の気持ちを振り返り、実践するのに役立つ新しいiPhoneアプリと紹介されています。
日記をオープン/クローズドにするかはその人の考え方によるけど、Appleがjournal appをわざわざ提供したのは「ジャーナル」≒日々の瞬間や暮らしの中の特別な出来事を振り返ることにより心身の健康を保つことにつながることを意識してるから。 https://t.co/Tawtg445EI pic.twitter.com/tMYiuTOj93
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) May 20, 2024
つまり、Appleもジャーナリングには心身の健康を改善することを期待して作ってるってことですよね。
1. 精神的健康への影響
ジャーナリングは、感情の処理、ストレス軽減、心理的ウェルビーイングの向上に寄与するとされています。
●ストレスと不安の軽減
Pennebaker & Beall (1986) の先駆的研究では、トラウマや感情的な出来事について書くことで、ストレスレベルが低下し、心理的安定が向上することが示されました。
被験者が4日間、15~20分間、感情的な出来事について書いたグループは、感情を抑制した場合に比べ、不安や抑うつ症状が有意に減少しました(Pennebaker, J. W., & Beall, S. K., 1986, Journal of Abnormal Psychology)。
メカニズム:感情を言語化することで、認知的な再構成が促進され、出来事に対する新たな視点が得られる(Pennebaker, 1997, Psychological Science)。
●抑うつ症状の改善
Krpan et al. (2013) のメタ分析では、エクスプレッシブ・ライティング(感情や経験を自由に記述する手法)が軽度から中等度の抑うつ症状を持つ人々の気分を改善する効果があると報告されています。
特に、定期的なジャーナリングは、感情の整理や自己理解を深めることで、抑うつ状態の緩和に寄与します(Krpan, K. M., et al., 2013, Journal of Affective Disorders)。
●自己認識と感情調整の向上
ジャーナリングは、自己反省を促し、感情の調整能力を高めます。Lieberman et al. (2007) のfMRI研究では、感情を言葉にすることで脳の扁桃体の活動が抑制され、感情的な反応が穏やかになることが示されました(Lieberman, M. D., et al., 2007, Social Cognitive and Affective Neuroscience)。
特に、マインドフルネスを意識したジャーナリング(例:感謝日記)は、ポジティブな感情を強化し、幸福感を高める効果がある(Emmons & McCullough, 2003, Journal of Personality and Social Psychology)。
2. 肉体的健康への影響
ジャーナリングは、ストレス関連の身体的症状や免疫機能にも良い影響を与えることが研究で示されています。
●免疫機能の向上
Pennebaker et al. (1988) の研究では、感情的な出来事について書いた被験者は、免疫系の指標(Tリンパ球の活性など)が向上し、風邪や感染症の発生率が低下しました(Pennebaker, J. W., et al., 1988, Journal of Consulting and Clinical Psychology)。
Smyth et al. (1999) の研究では、喘息や関節リウマチ患者がジャーナリングを行った結果、症状の重症度が軽減し、医療機関への受診頻度が減少したことが報告されています(Smyth, J. M., et al., 1999, JAMA)。
血圧と心血管健康
ジャーナリングによるストレス軽減は、血圧の低下や心血管系の健康改善にも関連しています。Davidson et al. (2002) の研究では、感情的なライティングを行ったグループは、対照群に比べ、血圧が低下し、心拍数の変動が改善したことが示されました(Davidson, K., et al., 2002, Health Psychology)。
●睡眠の質の向上
ジャーナリングは、就寝前の不安や反芻思考(ルミネーション)を軽減することで、睡眠の質を向上させます。
Harvey & Farrell (2003) の研究では、就寝前に感情やその日の出来事を書くことで、入眠までの時間が短縮され、睡眠の質が改善したと報告されています(Harvey, A. G., & Farrell, C., 2003, Behaviour Research and Therapy)。
3. 特定のジャーナリング手法とその効果
感謝ジャーナリング:Emmons & McCullough (2003) の研究では、毎日または週に数回、感謝していることを書くことで、ポジティブな感情が増加し、ストレスや抑うつが軽減されることが示されました。この手法は、特に精神的ウェルビーイングの向上に有効です。
トラウマライティング:Pennebakerの研究に基づくトラウマやストレスフルな出来事について書く手法は、感情の解放と認知の再構築を促し、PTSD症状の軽減にも効果的です(Sloan & Marx, 2004, Behaviour Research and Therapy)。
目標設定ジャーナリング:Morisano et al. (2010) の研究では、目標や価値観を明確にするライティングが、モチベーションや学業成績の向上に寄与することが示されています(Morisano, D., et al., 2010, Journal of Applied Psychology)。
4. 実践のポイント
研究に基づく効果的なジャーナリングのポイントは、週に1~3回、15~20分のライティングが効果的(Pennebaker, 1997)で、継続性が大事なのだそうです。
5. 限界と注意点
個人差:ジャーナリングの効果は、個人の性格(例:内省傾向)や書く内容によって異なる(Frattaroli, 2006, Psychological Bulletin)。
過剰な反芻:ネガティブな出来事に焦点を当てすぎると、逆にストレスが増加する可能性がある(Nolen-Hoeksema et al., 2008, Perspectives on Psychological Science)。
専門的支援の必要性:重度の精神疾患(例:重度のうつ病やPTSD)を持つ人は、ジャーナリング単体では不十分な場合があり、専門家の支援が必要。
■まとめ
Google NotebookLMの興味深い活用法。自身の日記をアップロードしてポッドキャスト化し、自分の人生を客観的に聴く人たちがいるのだそう。これがAIネイティブなのか! https://t.co/WbsgFJs3kK
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) May 20, 2025
ジャーナリングは、精神的健康(ストレス軽減、抑うつ症状の改善、感情調整)および肉体的健康(免疫機能向上、血圧低下、睡眠改善)に多くの利点をもたらすことが、多数の論文で裏付けられています。
エクスプレッシブ・ライティングや感謝ジャーナリングをやってみませんか?
【追記】
明石家さんま「手帳、こんな分厚いの持ってる」 日々やっていること告白「俺たちは言葉の商売やねん」(2025年6月4日、スポニチアネックス)によれば、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」で手書きの方が脳の活性化が進むというテーマに対して、明石家さんまさんは分厚い手帳に手書きで思いついたことや今日の出来事を書いているそうです。
その中から書いているときは面白いけど、言葉にすると面白くないものがあり、それを修正しているそうです。
実は明石家さんまさんもジャーナリングをしているんですね。
【参考文献】
- Pennebaker, J. W., & Beall, S. K. (1986). Confronting a traumatic event: Toward an understanding of inhibition and disease. Journal of Abnormal Psychology, 95(3), 274–281.
- Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8(3), 162–166. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00403.x
- Pennebaker JW, Kiecolt-Glaser JK, Glaser R. Disclosure of traumas and immune function: health implications for psychotherapy. J Consult Clin Psychol. 1988 Apr;56(2):239-45. doi: 10.1037//0022-006x.56.2.239. PMID: 3372832.
- Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389.
- Smyth, J. M., et al. (1999). Effects of writing about stressful experiences on symptom reduction in patients with asthma or rheumatoid arthritis. JAMA, 281(14), 1304–1309.
- Krpan, K. M., et al. (2013). An everyday activity as a treatment for depression: The benefits of expressive writing for people diagnosed with major depressive disorder. Journal of Affective Disorders, 150(3), 1148–1151.
- Frattaroli, J. (2006). Experimental disclosure and its moderators: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 132(6), 823–865.
- Nelson, D. L., & Simmons, B. L. (2003). Health psychology and work stress: A more positive approach. In J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health psychology (pp. 97–119). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10474-005
- Harvey AG, Farrell C. The efficacy of a Pennebaker-like writing intervention for poor sleepers. Behav Sleep Med. 2003;1(2):115-24. doi: 10.1207/S15402010BSM0102_4. PMID: 15600133.