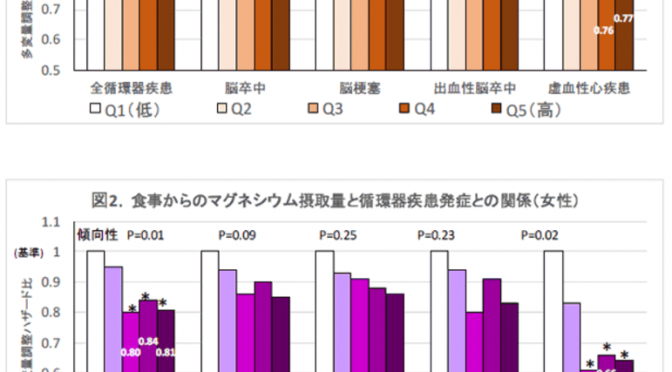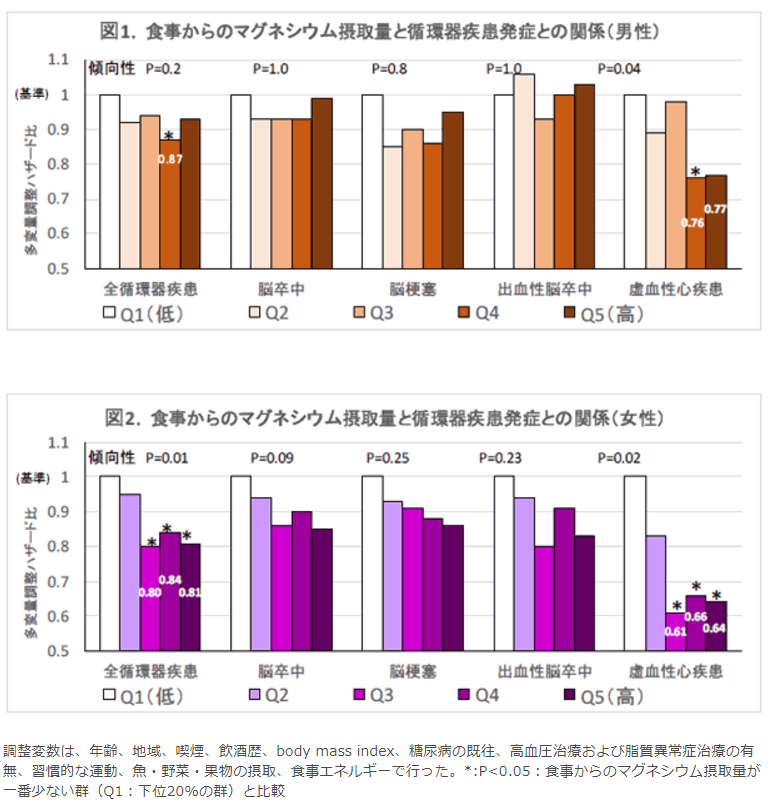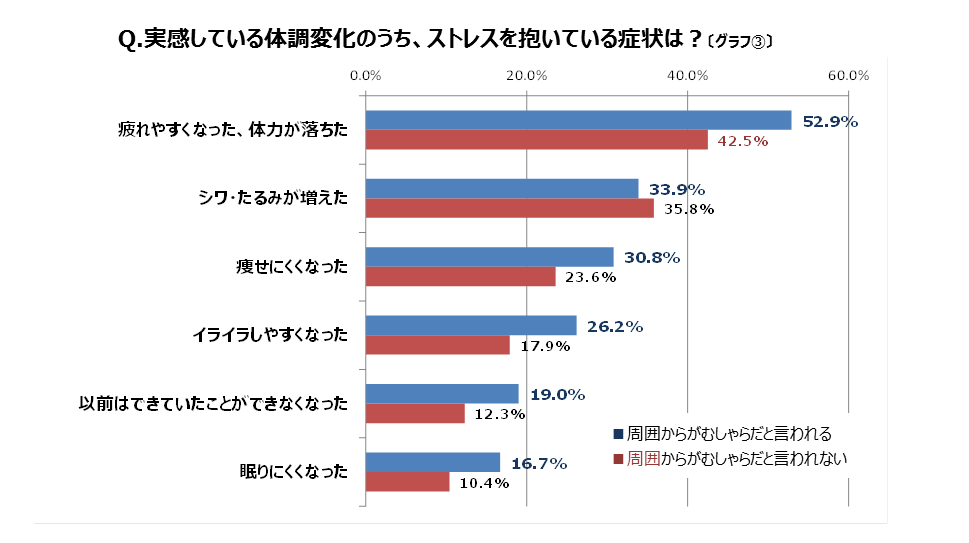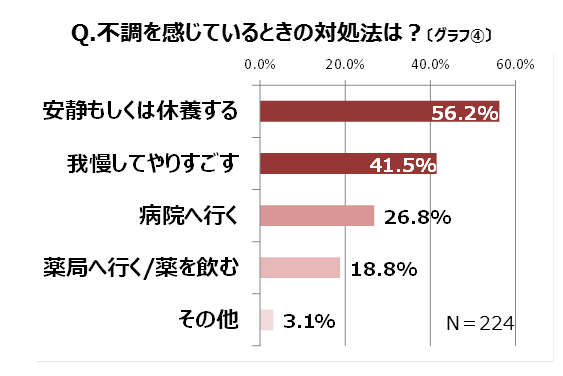コロナ感染で慢性疲労リスク4倍 米、後遺症頻度高く「予防策を」(2024/2/15、共同通信)で紹介された米CDCなどのチームによれば、新型コロナウイルスに感染した人はしなかった人に比べ、その後に疲労感の症状が現れるリスクが1.68倍に、慢性疲労に発展するリスクは4.32倍に上ったそうです。
これまで取り上げた記事の中でコロナ後遺症に関連したワードをまとめると、倦怠感、心不全、うつ病のような症状が現れています。
コロナ “後遺症 若い世代にも” 700人以上診療の医師訴えるhttps://t.co/EQUKMCdyYI
✅新型コロナの後遺症の症状(複数回答)
けん怠感 95%
気分の落ち込み 86%
思考力の低下 83%
息苦しさ 75%
髪の毛が抜ける脱毛 50%
味覚障害 30%✅“後遺症”とされる症状は若い世代にも多くみられる
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 4, 2021
国立国際医療研究センターによる日本人の新型コロナ後遺症に関する調査結果https://t.co/JdjyuGtOUy
✅女性ほど倦怠感、味覚・嗅覚障害、脱毛が出現しやすく、味覚障害が遷延しやすい
✅若年者、やせ型であるほど味覚・嗅覚障害が出現しやすい pic.twitter.com/zm1ks2er9T— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) October 12, 2021
✅コロナ後遺症により、最大400万人の米国人が働けていない
✅ブルッキングス研究所の報告書によると、米国人約1600万人が現在コロナ後遺症を患っている
✅コロナ後遺症の症状はブレインフォグ(集中力や思考力の低下)、不安、うつ、疲労、呼吸困難https://t.co/ImtWGR9tyv— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) August 29, 2022
”国立国際医療センターの大曲国際感染症センター長が公表した調査では、発症後、全体の76%に後遺症が出て、2カ月で48%、4カ月でも27%の患者に、何らかの後遺症があり、特に呼吸困難、倦怠(けんたい)感、嗅覚障害は4カ月たっても、およそ10%の患者で認められたという。”https://t.co/oGi2yxkqtL
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 4, 2021
これがどのようなメカニズムで症状が現れているのかわかりませんが、新型コロナウイルス感染をした後には疲労感が現れやすい体になってしまうという傾向にあり、例えば亜鉛不足と関連しているのではないか?ということが話題になったこともありました。
亜鉛不足でコロナ死亡リスク高まるとの研究 かきで摂取をhttps://t.co/HqPWMb1J4b
国際医療福祉大学病院内科学予防医学センター教授の一石英一郎さんによれば「亜鉛は細胞の修復に重要な物質であり、亜鉛が不足すると壊れた細胞がなかなか治らず、重症化したり死亡リスクが上がる可能性があります」
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) January 21, 2021
亜鉛不足でコロナ死亡リスク高まるとの研究 かきで摂取を(202012/9、NEWSポストセブン)によれば、スペインの研究チームは、「亜鉛」の不足が新型コロナで死亡するリスクを高めるという研究結果を10月に発表しているそうで、細胞の修復に必要な物質である亜鉛が不足すると壊れた細胞が治らず、重症化したり死亡リスクが上がる可能性があるそうです。
これは新型コロナウイルスの後遺症?それとも他の病気(うつ病・腎臓病・男性更年期障害)?
今後はなぜ新型コロナウイルス感染をすると、慢性疲労の症状が現れやすくなるのか、そのメカニズム、そしてその解決方法の研究が待たれます。
→ 亜鉛を含む食べ物・食品|亜鉛不足チェック・摂取量 についてくわしくはこちら
→ コロナ後遺症「クラッシュ」ってどんな症状?なぜ慢性疲労症候群になってしまうの? についてくわしくはこちら
【追記(2024年11月2日)】
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)とはによれば、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は、長い期間(半年以上)にわたって強い疲労感が続き、全身の脱力などによって、日常生活を送るのが困難になる原因不明の病気です。
コロナワクチン接種後にどこも悪いところはないにもかかわらず極度の倦怠感に襲われる「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」と診断された方がいました。
【関連記事】