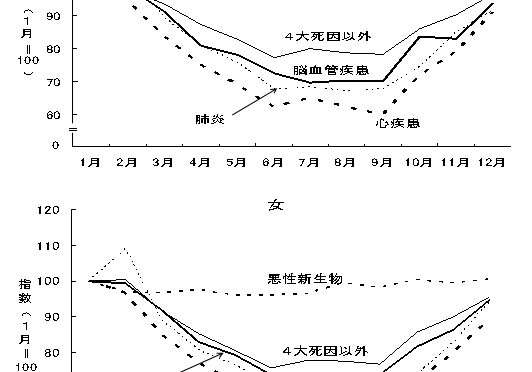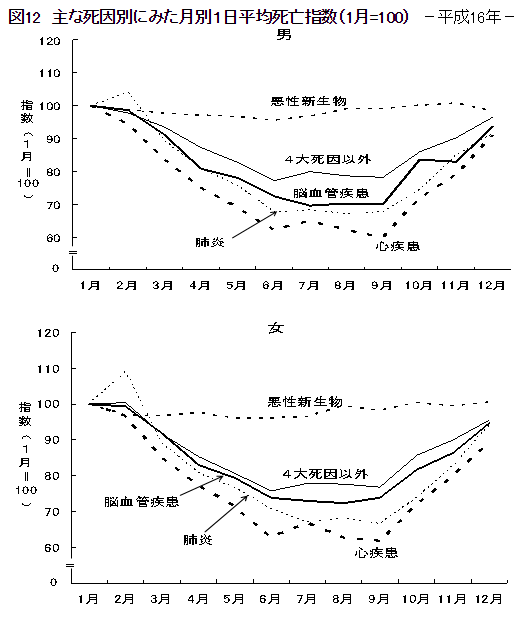■エクササイズ・プログラムに組み込むべき7つの動きとは?
by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet(画像:Creative Commons)
(2009/9/8、ライフハッカー)
「ちょっとした知識があればエクササイズ・プログラムは自分で組めるよ」ということが生活術サイト「Dumb Little Man」で紹介されていました。
まずはどのエクササイズを選ぶか?というのが問題なのですが、どんなエクササイズ・プログラムにも組み込むべき「基本の要素」 は、以下の7つだそうです。
- スクワット
- ランジ
- ベンド(屈曲)
- ツイスト
- プッシング(例:腕立て)
- プリング(例:懸垂)
- ウォーキング/ランニング
ランジという初めてのキーワードがありましたので、調べてみました。
【参考リンク】
- 「ランジ」老化防止に下半身強化 - 筋肉料理人の魚料理と自宅でできる簡単フィットネス
ランジとは、下半身を強化する運動で、真っ直ぐに立った姿勢から片足を前に一歩踏み出し、腰を沈めて前に出した足の太腿が、床と水平になるくらいまでしゃがみ込む、そして元の姿勢に戻ります。
この運動を交互に行うのがフォワードランジです。
このフォワードランジで鍛えられる筋肉はハムストリングス(太腿の裏側の筋肉)、大臀筋(おしり)、腸腰筋(足を持ち上げる筋肉、腰骨と足の付け根、背骨と足の付け根をつなぐ重要な筋肉、外から見えないのでインナーマッスルと言われます)、大腿四頭筋(太腿の筋肉)です。
足を前に踏み出すから太腿メインの運動と思われがちですが、後ろ側になった足に体重をかけることで、腸腰筋を鍛えることができます。
こうした7つの動きを取り入れると、良いエクササイズになるそうです。
以前このブログで考えたエクササイズメニューのサーキットスロートレーニング(サーキットスロトレ)はこの7つの動きの多くを取り入れたものになっているのではないでしょうか。
こうした記事を見て、さらに良いエクササイズメニューができるといいですね。
⇒ あなたにあった ダイエット方法の選び方 はこちら
⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら
ダイエット方法ランキングはこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【関連記事】
続きを読む エクササイズ・プログラムに組み込むべき7つの動きとは?|スクワット・ランジ・ベンド(屈曲)・ツイスト・プッシング(腕立て伏せ)・プリング(懸垂)・ウォーキング