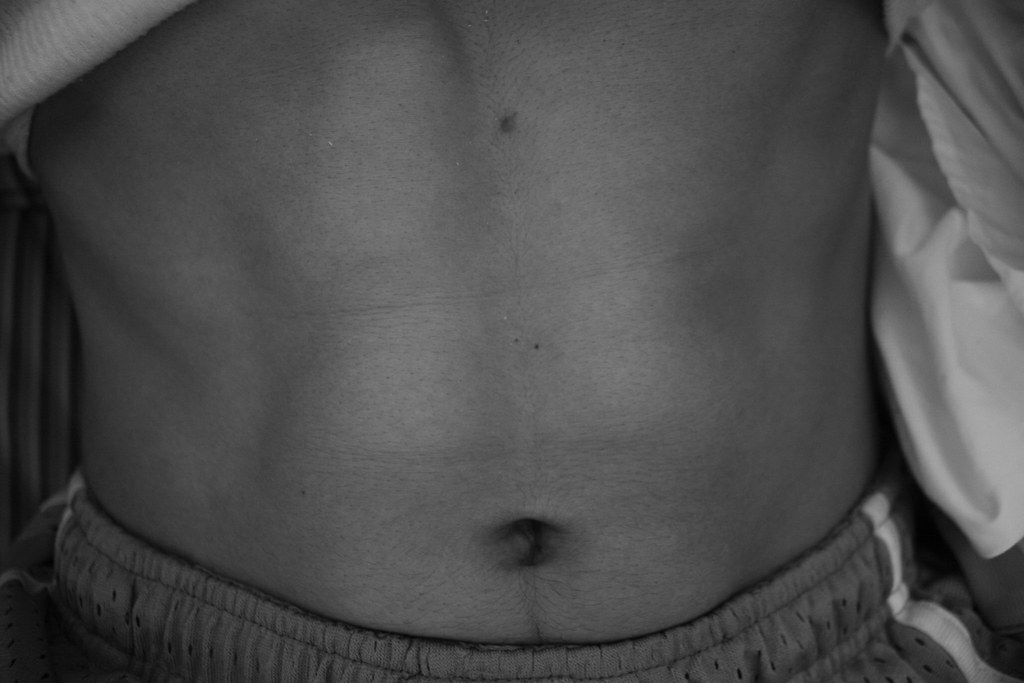> 健康・美容チェック > 便秘 > 頑固な便秘を治す方法 > 頑固な便秘を食べ物で解消!便秘に効く食べ物とは?
【目次】
■便秘解消には腸内細菌のバランスを整える
by Neil Conway(画像:Creative Commons)
頑固な便秘を治す方法によれば、気持ちの良いお通じは、腸内細菌が深く関係していることがわかっています。
腸内細菌の集まりのことを腸内フローラ(腸内細菌叢)といいますが、腸内細菌のバランスが崩れると、便秘になりやすくなったり、太りやすい原因となったり、免疫細胞が暴走し、アレルギー性疾患の可能性が高まると考えられています。
腸内細菌は、大きく分けると、善玉菌・悪玉菌・日和見菌に分けられます。
●善玉菌(ビフィズス菌・乳酸菌など)
エネルギー吸収を抑える
●悪玉菌
食べ物を腐敗させる
●日和見菌
その時の環境によって善玉菌にも悪玉菌にもなる
健康な人の腸内フローラは善玉菌が悪玉菌より多く、善玉菌が減少すると、エネルギー吸収が抑えられず、過剰に蓄積し、太りやすいカラダを作ると考えられています。
腸内細菌の理想のバランスは、善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7。
腸内細菌のバランスが崩れる理由とは、1.加齢、2.高脂肪食。
腸内細菌のバランスが崩れているサインは、「便が臭くなる」ことです。
■便秘に効く食べ物
1.善玉菌(ビフィズス菌)の餌になるもの
オリゴ糖(キシロオリゴ糖、大豆オリゴ糖など) ← 野菜、豆類、乳製品などに含まれる。
2.善玉菌(ビフィズス菌)の増殖を助けるもの
納豆菌、乳酸菌 ← 納豆、ヨーグルト、漬物などに含まれる。
3.善玉菌(ビフィズス菌)の育つ環境を作るもの
食物繊維 ← 野菜、穀類、海藻、豆類、果物などに含まれる。
→ 食物繊維の多い食品 について詳しくはこちら
■便秘を解消する食べ物のおすすめの組み合わせの例
便秘改善におすすめの組合せは、ヨーグルト+ハチミツ+大根。
・ヨーグルト(善玉菌であるビフィズス菌の増殖を助ける)
・はちみつ(ビフィズス菌の餌となるオリゴ糖)
・大根(水溶性食物繊維でビフィズス菌の育つ環境を作る)
→ 便秘とは|即効性のある便秘解消方法(ツボ・運動・マッサージ・食べ物)・便秘の原因 について詳しくはこちら
→ 便秘の症状で知る便秘の原因とは?|便(うんち)で体調チェック について詳しくはこちら
→ 頑固な便秘を治す方法|食べ物・ツボ・生活習慣 について詳しくはこちら
→ 腸内フローラとは|腸内フローラを改善する食べ物 について詳しくはこちら