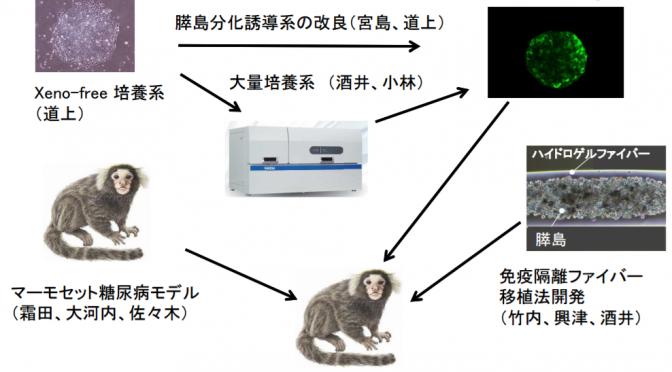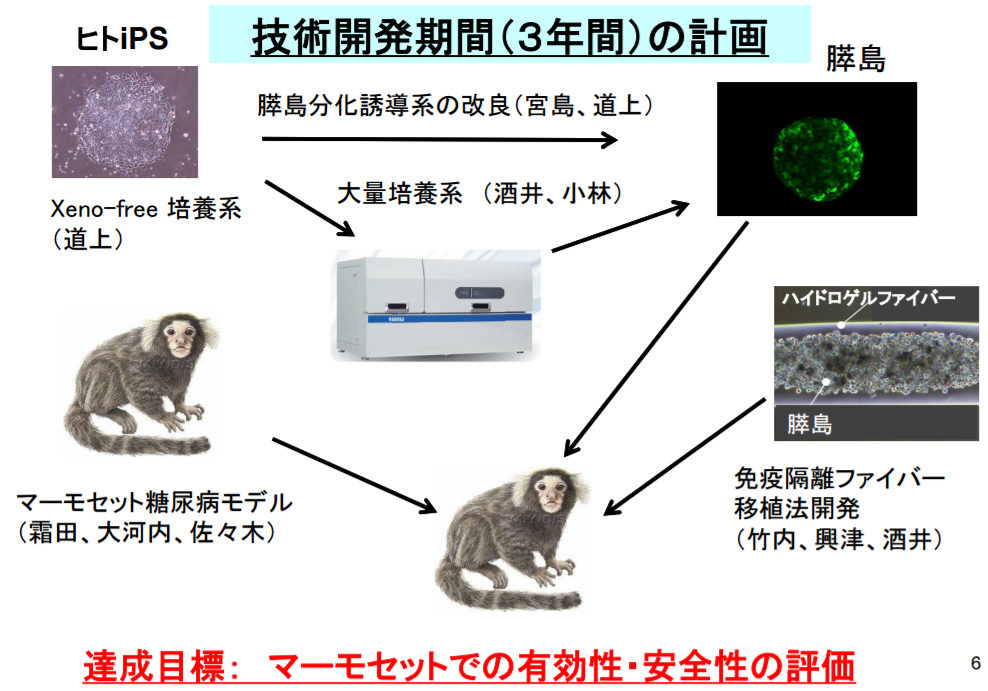by Alexis(画像:Creative Commons)
■ミランダ・カー(Miranda Kerr)

by discutivo(画像:Creative Commons)
どうやってナイスバディをキープしてるの!? スーパーモデル15人の食生活まとめ
(2011/12/27、pouch)
血液型ダイエットを実践。
主に低GI値のもの、高アルカリ食品、濾過された水、新鮮な野菜類を摂り、肉類はかなり控えめにしているそう。
血液型ダイエットを実践しているそうです。
【関連記事】
ミランダ・カー(MIRANDA KERR)がハマってる!?血液型ダイエットとは?|#スマスマ
スーパーモデル、ナタリアおすすめの“血液型別ダイエット”
海外で人気急上昇!血液型ダイエットとは?
エリカ・アンギャルさんおすすめ!ダイエット7つの食材|たけしの健康エンターテイメント!みんなの家庭の医学
雑穀米には食物繊維やビタミンが多く含まれている。
食物繊維には、便通の改善、コレステロールの低減に効果がある。
エリカ・アンギャルさんが、食物繊維を薦めるには、もうひとつ理由があります。
それが、GI値。
GI値(グリセリック・インデックス:血糖値の上がりやすさの指標)はエリカ・アンギャルさんのダイエット法の中核をなす考え方。
消化しやすい食品を食べると血糖値が急激に上がる。
⇒インスリンが大量に分泌され、残った糖を脂肪に変えてしまう。
つまり、血糖値を急激に上げないことが、太りにくい体を作ることにつながるということです。
GI値が低い繊維質の食べ物は血糖値が上がりにくい。
■カロリナ・クルコヴァ(Karolina Kurkova)
起き抜けに飲む野菜ジュースへ、プロテインの粉とグルタミンを少し混ぜるのだとか。
その2時間後に固ゆで卵を2つ食べる。
さらに2~3時間後にアーモンドなどのナッツ類を10粒摂取。
それから焼いた魚と野菜、サラダを食べ、また野菜ジュース……というふうにかなりシンプルな食べ方を心がけている。
野菜(野菜ジュース・サラダ)とたんぱく質(プロテイン・魚)、アーモンド(良質の油)という食事みたいですね。
【関連記事】
ミス・ユニバース・ジャパン ファイナリストのスタイルキープのための食事方法
エリカ・アンギャルさんとアーモンド
■ココ・ロシャ(Coco Rocha)
朝食はシリアル、その1時間後に2皿めのシリアル、昼食はサラダかサンドウィッチ、夕食は17時頃にがっつり食べ、21時頃に3皿目のシリアルを食べる。
シリアルが好き過ぎるよう。
記事の中では、「シリアルが好きすぎる」と書いていましたが、血糖値が上がらないようにしているのではないでしょうか?(血糖値の急上昇・急降下をすることが空腹感を感じる理由であるため)
【関連記事】
1日5食ダイエット|所さんの目がテン! 1月7日
血糖値の急上昇・急降下することが空腹感を感じる理由であり、血糖値を緩やかにすることが、太りにくい体づくりになるというわけです。
ただ、間違っていけないのは、1日5食普段の食事をしてしまってはカロリーオーバーになってしまうので、食事内容(摂取カロリー)には注意が必要です。
レディー・ガガも実践!1日5食ダイエット|ネプ&イモトの世界番付 1月31日
1.1日5食ルール
1日に5回食事をとるようにすれば、ひどい空腹感に悩まされることもなく、食べる量もコントロールすることが容易です。
また、新陳代謝を活性化し、空腹感を覚えることなく減量が可能になります。
血糖値をコントロールする方法ですね。
おなかが減らなくなる方法とは?|ためしてガッテン 1月5日で紹介していましたが、お腹がすぐ減ってしまうと感じるのは、血糖値が急降下しているからなのだそうで、一回の食事の量を減らすことで、血糖値の値の動きが緩やかになることで、空腹感を感じにくくなるそうです。
1日5回食事をしても一回の食事を減らすことで、食べる量をコントロールしていると考えられます。
6kgも痩せたブレイク・ライブリーのダイエット方法とは?
タンパク質を中心とした腹6分目の食事を一日5食食べるように指導
血糖値コントロールでダイエット|ためしてガッテン 1月5日
血糖値の急上昇・急降下をすることが空腹感を感じる理由なので、空腹感をできるだけ感じないようにするためにも、血糖値を緩やかにすることを考えていく必要があります。
■アレッサンドラ・アンブロジオ(Alessandra Ambrosio)
好きなときに好きなものを食べるが、量を少なめにして、色々な種類のものを食べることを心がけているのだとか。
また食事日記を詳細に付けているという、モデルならではのプロ意識も。
計るだけダイエット|ためしてガッテン 5月26日によれば、朝と晩、自分の体重を計ってグラフにつけるだけで、いつの間にかやる気が出てくるという超簡単なダイエット法です。
【関連記事】
■ナオミ・キャンベル(Naomi Campbell)
「ダイエットはしないし、煙草を吸うし、昔からずっとお酒も飲んでいる。ダイエットを意識してしたことはない」というモデルらしからぬ発言が気になる。
ただ1年に3回、レモネードと水分しか摂らない「マスター・クレンズ・ダイエット」をしているそう。
こちらは多くのセレブが成功したことで有名になったダイエット法。
【関連記事】
ニコール・リッチーが痩せた!3日で-3kgやせた「クレンズダイエット」とは
◆「クレンズダイエット」とは?
食事の代わりにデトックス効果の高い生ジュースを飲んで「プチ断食」を行うダイエット法。
ジュースはにんじん、レモン、キャベツ、セロリ、りんごなどのナチュラル素材に水と氷を加え、ミキサーにかけるだけという簡単レシピ。1日3食をクレンズジュースに置き換えることで体内にたまった老廃物が排出され、短期間でのダイエット効果が期待できる。
セレブに人気の「クレンズダイエット」の方法とは?
デミ・ムーア、Twitterでダイエットについてファンに反論
ビヨンセが10日で8キロやせたレモネードダイエット
■ハイディ・クルム(Heidi Klum)
炭水化物抜きにして、大量の野菜とサラダを食べるという、実にシンプルな方法を実践。
炭水化物抜きダイエットをしているそうです。
■リンダ・エヴァンジェリスタ(Linda Evangelista)
健康的な食事を意識しているそうで、朝食には卵白をスクランブルエッグにしたもの、七面鳥のミンチ、トマトを。
また緑茶、新鮮なハーブ、サーモンやツナや鶏肉、七面鳥などの蛋白質をたくさん摂るのだとか。
たんぱく質をたくさん摂ることを大事にしているそうです。
⇒ 芸能人・有名人・セレブのダイエット方法 について詳しくはコチラ。
⇒ あなたにあった ダイエット 方法の選び方 はこちら
⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら
ダイエット方法ランキングはこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ダイエット方法ランキング
【ハリウッドセレブ系関連記事】
続きを読む スーパーモデルはどんなダイエットをしているの?ナイスバディをキープする方法とは? →