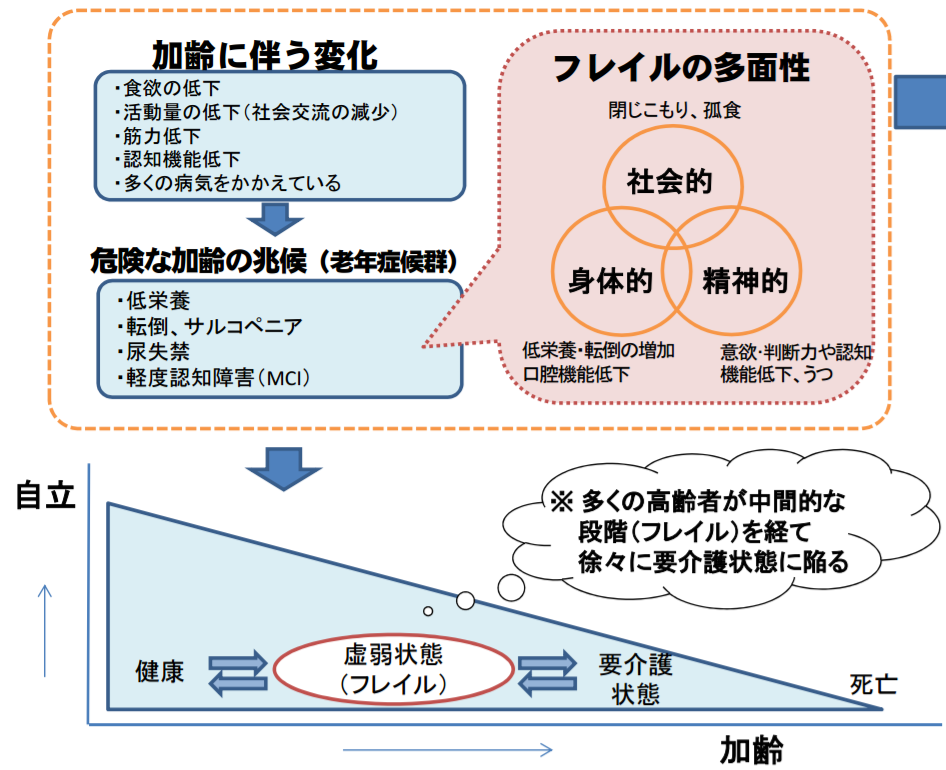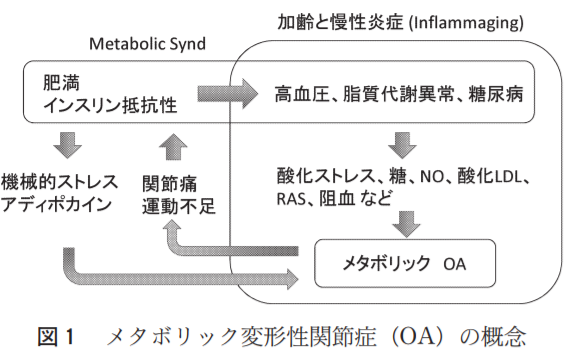> 健康・美容チェック > 認知症 > オメガ3 > えごま > オメガ3で健康に!認知症が予防できるエゴマ油|#主治医が見つかる診療所
■オメガ3で健康に!認知症が予防できるエゴマ油
by ayustety(画像:Creative Commons)
2014年12月15日放送の主治医が見つかる診療所で「認知症が予防できるエゴマ油」を取り上げていました。
認知症に効果があるのは、エゴマ油に含まれるオメガ3(不飽和脂肪酸)です。
→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効果・効能・食べ物(オイル)・ダイエット について詳しくはこちら
青魚に多く含まれるDHA・EPAもオメガ3に含まれます。
1日にオメガ3の必要摂取量を摂ろうとすると、イワシなら毎日2尾食べる必要がありますが、エゴマオイルは、そのほとんどがオメガ3でできていますので、スプーン1杯でオメガ3の1日の必要摂取量である2gを摂ることができます。
ただし、エゴマ油やアマニ油は熱に弱いため、加熱調理は避けましょう。
※αリノレン酸(えごま油・亜麻仁油)の注意するポイントは「加熱に弱い」という性質があるのは本当!?で紹介したサンマに含まれるEPA・DHAが調理方法によってどれだけ減少するかという大阪ガスが行った実験によれば、調理時のEPA保持率はフライ(200度)43%、グリル(350度)77%、フライパン91%であり、DHAではそれぞれ48%、75% 99%でした。
EPA・DHAが減少する理由は、脂の飛散と熱分解・酸化にありますが、フライでは脂の飛散と熱分解・酸化、グリルでは脂の飛散、フライパンでは加熱分解が減少メカニズムと考えられます。
つまり、熱に弱い性質があるといわれていますが、フライパンで加熱する程度ではほとんど影響がないことがわかります。
また、エゴマ (シソ) 油の加熱安定性と食品成分添加の影響によれば、180℃、70分までの加熱では、大豆油に比べてエゴマ油の劣化は若干進んでいたものの、α-リノレン酸の残存率も90%以上であり、栄養的に支障がなかったそうです。
熱に弱い性質があるからといって使わないよりも、積極的にαリノレン酸が豊富なえごまを料理に活用しましょう!
また、エゴマ油やアマニ油を保管するときには、常温保存ではなく、冷蔵庫での保存がおススメです。
→ えごま(エゴマ油)の健康効果 について詳しくはこちら

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)
長崎島原手延べえごまそば1kg|「麺(蕎麦)で食べるエゴマ」でオメガ3の栄養を手軽にとりいれよう!【ご自宅用・ギフトにも】
3,780円 → 3,402円(税込)
えごまそばには、話題の健康成分「αリノレン酸(オメガ3)」を含むえごまを練り込み、360年余りの伝統を誇る長崎県島原の手延製麺技術で仕上げました。
えごまそばは、発売以来、多くのお客様にご好評いただいている人気商品で、インターネット販売限定で10年以上のロングセラー商品です!
えごまそばは、インターネットではここでしか買えません!店頭では販売しておりません!
「麺で食べるえごま」は、蕎麦好きの方やご高齢の方、海外の方にも喜ばれています。