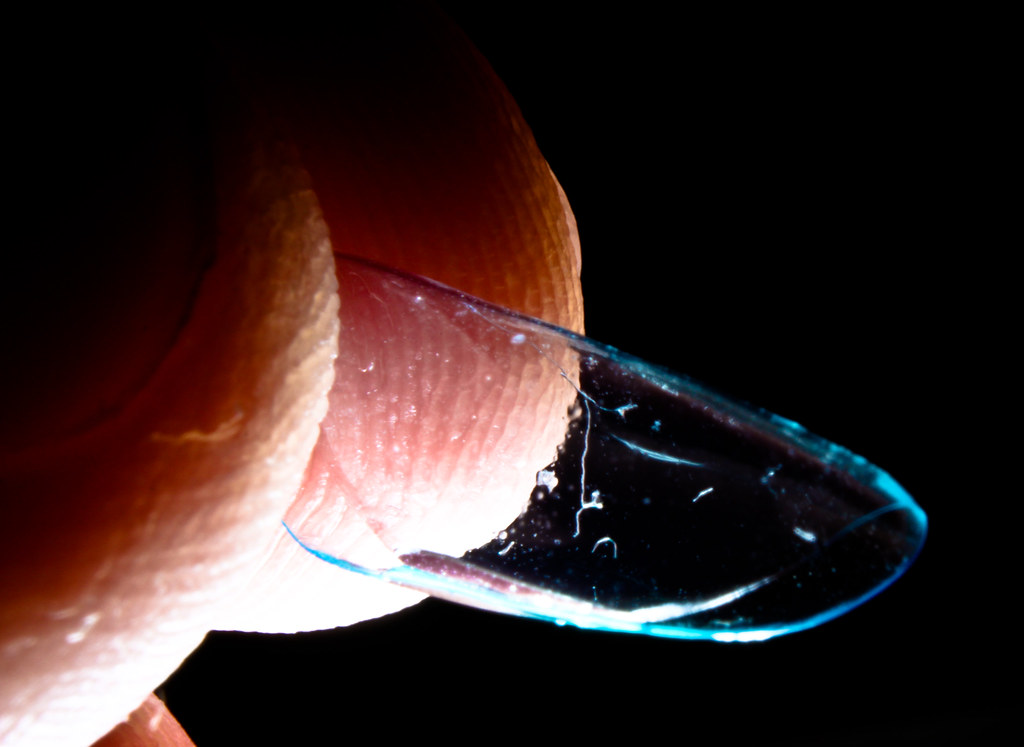by wumastawu(画像:Creative Commons)
(2010/4/20、日経ウーマンオンライン)
脂肪細胞には、1.蓄積モード(中性脂肪を貯める)、2.ダイエットモード(中性脂肪を吐き出す)、という2つのモードがあり、この2つを切り替えているそうです。
1.蓄積モード
「蓄積モード」に深くかかわるホルモンが、インスリン。
インスリンといえば、血糖値を下げる働きのあるホルモンだと記憶している人も多いだろうが、実は、血液中を流れる脂肪分を中性脂肪の形にして脂肪細胞にためるという役割も担っている。
血液中の脂肪分は、“運び屋”としてのたんぱく質がくっついた形で流れている。
この脂肪分には、食事でとった油分だけでなく、使われずに余った糖分やたんぱく質が肝臓で脂肪の形に作り変えられたものも含まれる。
食べた油が脂肪として流れているのはわかりやすい話だが、糖やたんぱく質までが脂肪になるのはなぜなのか。
「同じ重さで比べた場合に、脂肪はたんぱく質や糖に比べて2倍のカロリー密度を持つ。
エネルギー源として貯蔵するためには、脂肪の形にしておくのが最も省スペースですみ、効率がいい」と、東京農業大学の田中教授は説明する。
ちなみに、自律神経でいうと、蓄積モードになりやすいのは、副交感神経が働いてリラックスしているとき。
「だから、食べた直後に横になると太ると言われているんです。
その方が消化・吸収が進むので、胃腸に負担をかけないためにはいいんですけどね」(田中教授)。
■蓄積モードのまとめ
- 食事をして、使われずに余った分を肝臓で脂肪の形に分解され、中性脂肪として脂肪細胞に貯める。
- 蓄積モードに関連するホルモンが、インスリン。
- 蓄積モードに関連する自律神経が、副交感神経。
2.ダイエットモード
「ダイエットモード」では、脂肪細胞にたまっていた中性脂肪が分解され、「遊離脂肪酸」として血液中に放り出される。
最終的には、この遊離脂肪酸が、体の主な脂肪燃焼器官である筋肉や肝臓に届けられ、そこで代謝されて、活動エネルギーであるATP(アデノシン3リン酸)などが作られる。
ダイエットモードに傾くのは、交感神経が優位になったとき。
その際、中性脂肪を分解して遊離脂肪酸として取り出すのに大きな役割を果たすホルモンがアドレナリンだ。
アドレナリンは、体を動かしたり、大きなストレスを受けたときなどに分泌される。
「だからダイエットには運動が大事、というわけです」(田中教授)。
■ダイエットモードのまとめ
- 運動をすると、脂肪細胞にたまっていた中性脂肪が分解され、「遊離脂肪酸」として血液中に放り出され、脂肪燃焼器官で代謝されて、エネルギーが作られる。
- ダイエットモードに関連するホルモンが、アドレナリン。
- ダイエットモードに関連する自律神経が、交感神経。
■脂肪細胞のサイズダウンまでは1週間!
ただし、運動してもすぐにぜい肉が落ちるわけでも、体重が減るわけでもない。
これは、脂肪細胞の中の中性脂肪が外に出てから、実際に脂肪細胞のサイズが小さくなるまでにはタイムラグがあるためだという。
中性脂肪が出て中に空洞ができると、そこに、細胞の外から水が入りこんでくるため、細胞の大きさも重さもすぐには変わらない。
この水は、約1週間ほど細胞内にとどまる。
水が抜けると、ようやく細胞が引き締まり、サイズが落ちる、という流れだ。
「1週間たったらどーんと体重が減り始めるのだから、すぐに結果がでないといってあきらめないこと」と、京都市立病院の吉田俊秀部長はアドバイスする。
運動をしてもすぐに効果が出始めるわけではない理由とは、脂肪細胞のサイズが小さくなるまでには、タイムラグがあるということ。
このことをしっかりと理解しておけば、「結果が出ないので、運動やーめた!」ということにはならないですね。
また、脂肪細胞が小さくなるまでには3段階を経て縮小していくそうです。
■脂肪細胞は3段階で縮小する
1 脂肪酸が細胞内から分離
脂肪細胞にたまった中性脂肪から「脂肪酸」という成分が切り離され、「遊離脂肪酸」として細胞外へ。
2 空いた部分に水が入りこむ
(ぜい肉をつまむと軟らかい)中性脂肪が減って空いた部分に水が流れこむ。この時点では、脂肪細胞の大きさも重さも維持される。ただし、水が入る分、細胞が軟らかくなるため、ぜい肉をつまんだ感触が軟らかくなる。
3 水が抜けて細胞が縮む
(ぜい肉が減って硬くなる)中性脂肪が減って空いた部分に水が流れこむ。
この時点では、脂肪細胞の大きさも重さも維持される。
ただし、水が入る分、細胞が軟らかくなるため、ぜい肉をつまんだ感触が軟らかくなる。
■部分やせの方法とは
40℃のお湯に胸の下までつかりながら、二の腕やお腹など、気になる部分のぜい肉を10分間もむという方法だ。
部分ヤセの方法とは、40度のお湯につかりながら、気になるぜい肉を10分間もむという方法なのだそうです。
「もむことが刺激になってアドレナリンが出るため、もんだ部分の中性脂肪が遊離脂肪酸に分解されやすい」と吉田部長。
さらに、お風呂タイムは体が温まって血流がよくなるため、遊離脂肪酸が、脂肪燃焼器官である筋肉や肝臓に届きやすい。
しかも、この方法なら、全身がやせるわけではないので、バストなど、残したい部分の脂肪まで落ちる心配もない。
「実際、肥満外来で指導している女性の患者さんでも、この方法でメリハリのある体つきになった人は多い」と吉田部長は太鼓判を押す。
女性的なボディーラインになりやすい方法なのかもしれません。
【関連記事】
体脂肪の燃焼には、交感神経の活性化が欠かせないが、現代人女性は、交感神経の働きが弱っているそうです。
また、太っている人の場合、副交感神経も弱っているのだとか。
自律神経を鍛えるにはどのようにすればよいのでしょうか。
自律神経を鍛える方法として最も実行しやすいのは運動だ。
「運動している最中は交感神経が活性化され、運動後はその反動で副交感神経が活性化される」(中里さん)。
自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があり、「昼の神経」とも呼ばれる「交感神経」はよく動く昼間に活発になり、またリラックスを促す「副交感神経」は夜に活発になります。
しかし、昼過ぎまでだらだらと寝たり、あまり活動的に行動しないと、「交感神経」の働きが鈍り、脂肪の代謝がスムーズに行われず、結果やせにくい体になってしまうのだとか。
交感神経の働きが低下することで、代謝が起こりにくく、痩せにくいカラダになってしまうことを言うようです。
さつまいもダイエット|赤いプルトニウムダイエット|ビューティーコロシアム
・半身浴(60分)
出来ることなら朝晩!
朝は熱め、夜はぬるめがいいらしい。(交感神経と副交感神経)
・マッサージ
リンパマッサージ、お風呂でやる
3分57秒でわかる体脂肪|食べても太りにくい魔法の時間帯とは?
⇒ あなたにあった ダイエット方法の選び方 はこちら
⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら
ダイエット方法ランキングはこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓