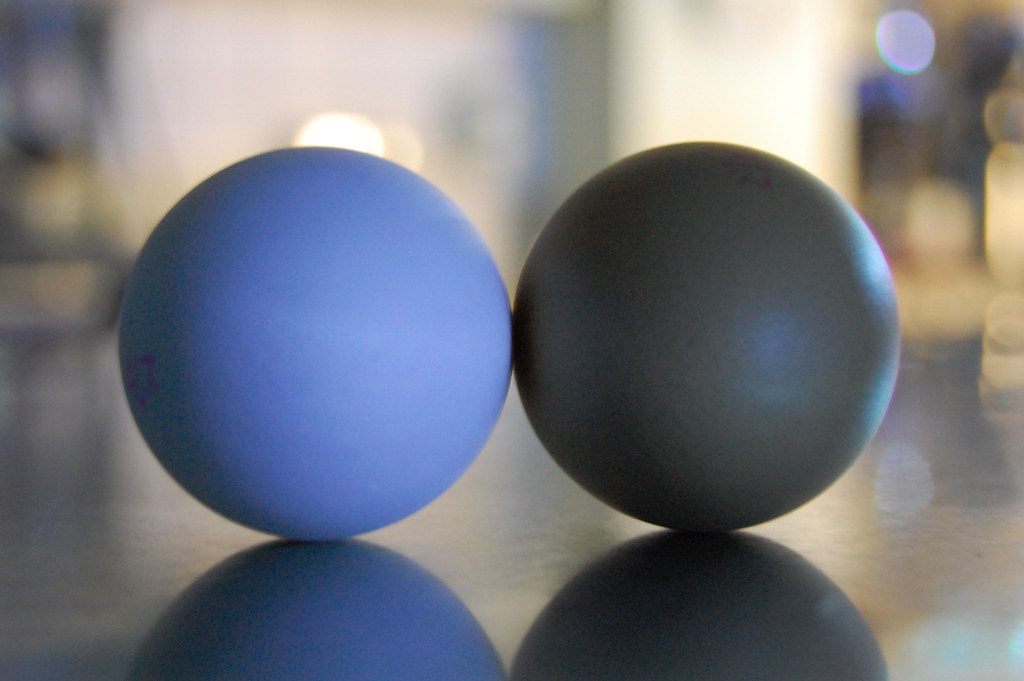> 健康・美容チェック > メタボリックシンドローム > トマトから脂肪肝、中性脂肪改善に有効な成分「13-oxo ODA」を発見|京大
■トマトから脂肪肝、中性脂肪改善に有効な成分を発見|京大
by Dave Crosby(画像:Creative Commons)
トマト、メタボ予防に効果=脂肪燃焼の新成分発見―京大
(2012/2/10、時事通信)
血液中の脂肪増加を抑える新成分がトマトに含まれていることを、京都大大学院の河田照雄教授らの研究グループが発見した。
<中略>
この物質を化学的に合成し、肥満マウスの餌に0.05%加えた結果、4週間で血液と肝臓の中性脂肪が約30%減少した。
脂肪燃焼に関わるたんぱく質の増加やエネルギー代謝の向上、血糖値の低下も見られた。
河田教授は「人間の場合、毎食コップ1杯(約200ミリリットル)のトマトジュースを飲むことで同様の効果が得られる」と話している。
(2012/2/10、日本経済新聞)
肥満・糖尿病モデルのマウスに高脂肪食とともにトマトに含まれる有効成分「13-oxo ODA」を与えたところ、4週間で血液中と肝臓中の中性脂肪が約30%減少したそうです。
トマトには、血液中の中性脂肪量を抑制する成分が含まれていることから、脂肪肝やメタボリックシンドロームの予防に効果が期待されるそうです。
→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 について詳しくはこちら
また、この物質は、血液と肝臓の中性脂肪の減少だけでなく、脂肪燃焼に関わるたんぱく質の増加、エネルギー代謝の向上、血糖値の低下などに役立ちそうです。
毎食コップ1杯のトマトジュースで同様の効果が得られるそうなので、トマト好きの方は試してみてはいかがでしょうか。
→ 中性脂肪とは・数値(正常値)・高い原因・下げる(減らす) について詳しくはこちら
→ 中性脂肪の減らし方(食事・運動・サプリメント) について詳しくはこちら
→ 中性脂肪が高い人の食事の特徴 について詳しくはこちら
【関連記事】
続きを読む トマトから脂肪肝、中性脂肪改善に有効な成分「13-oxo ODA」を発見|京大【論文・エビデンス】