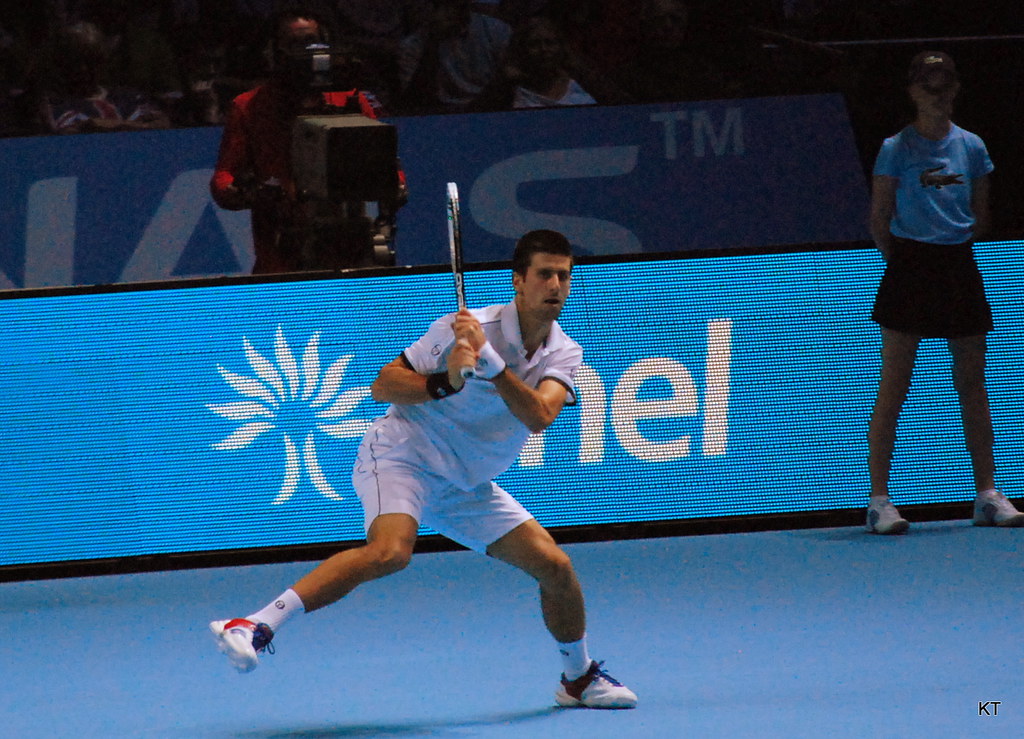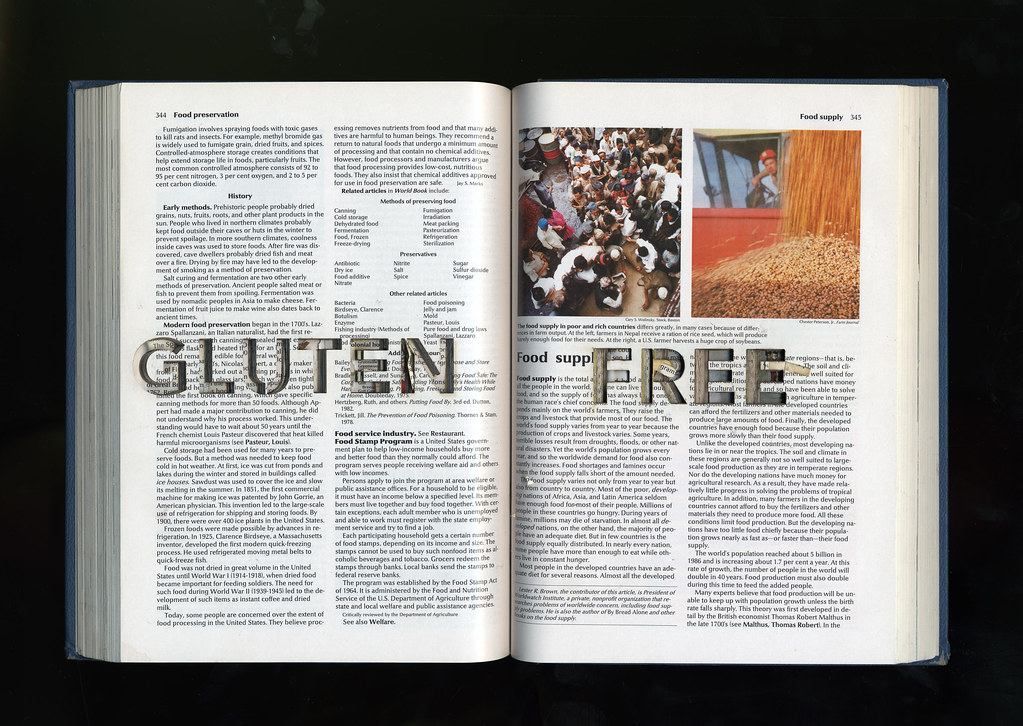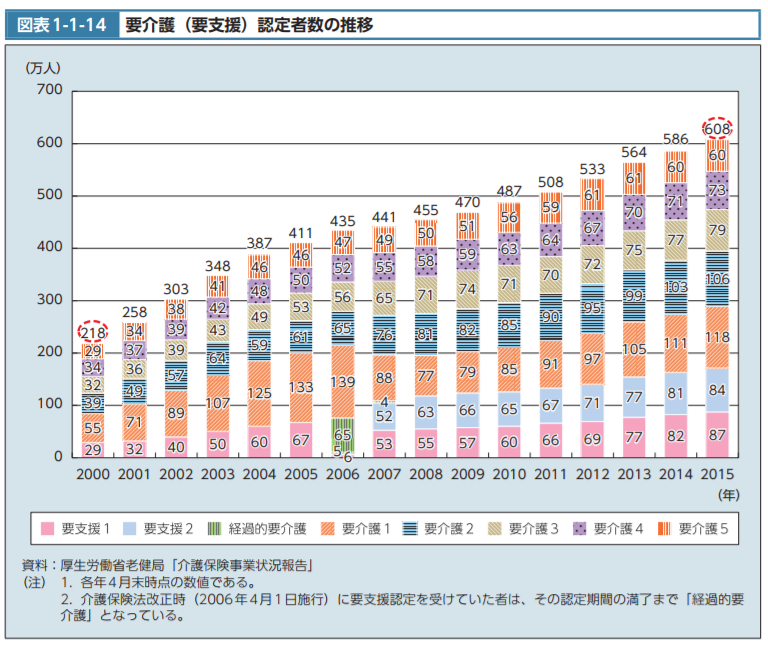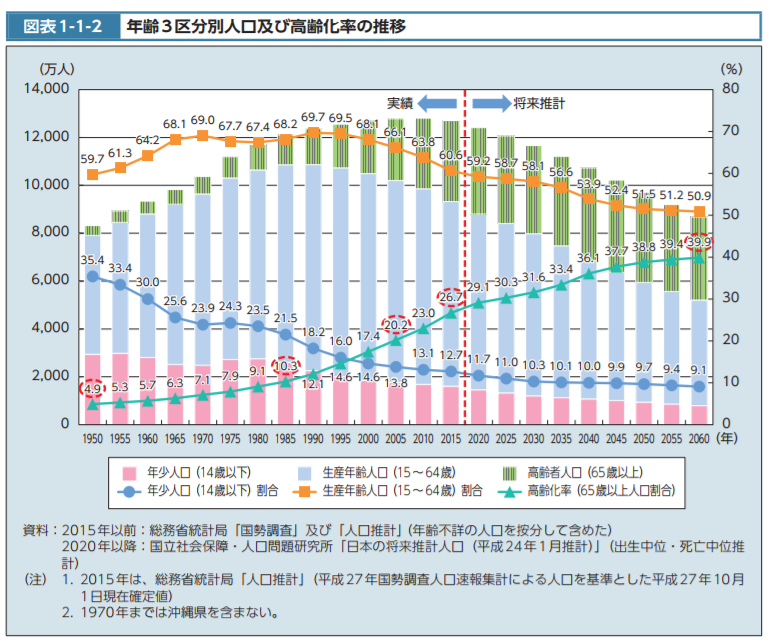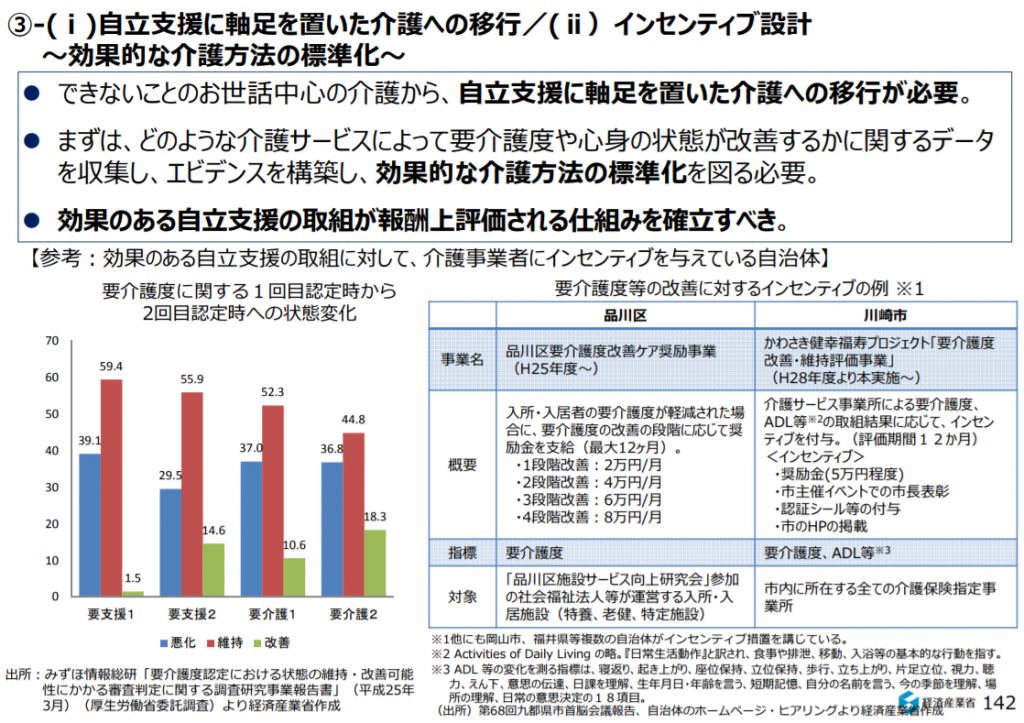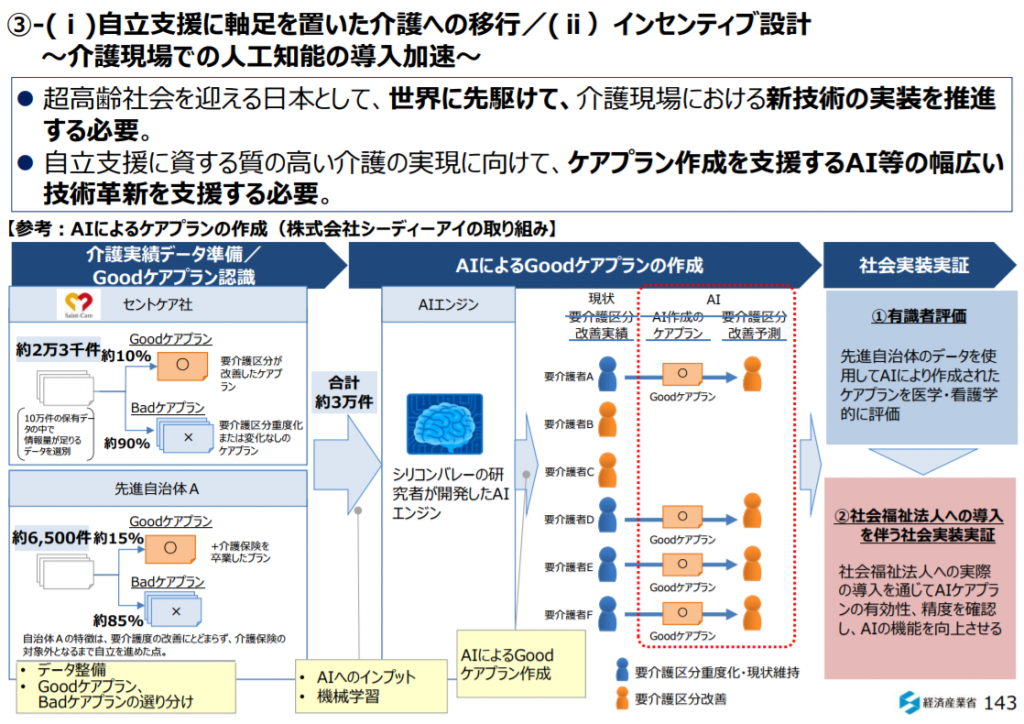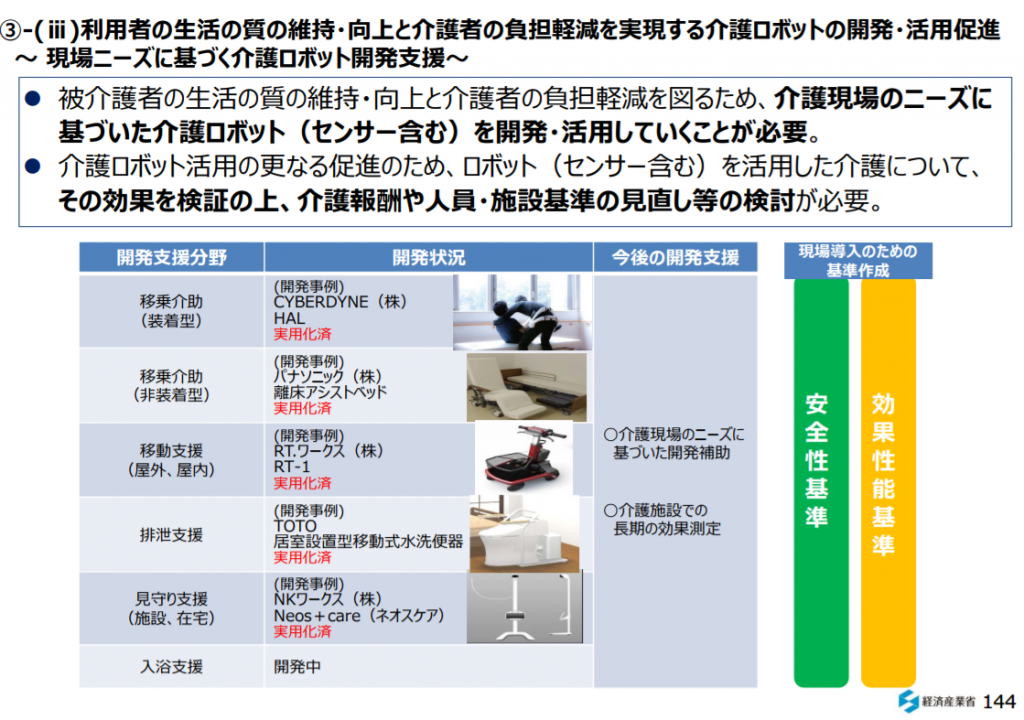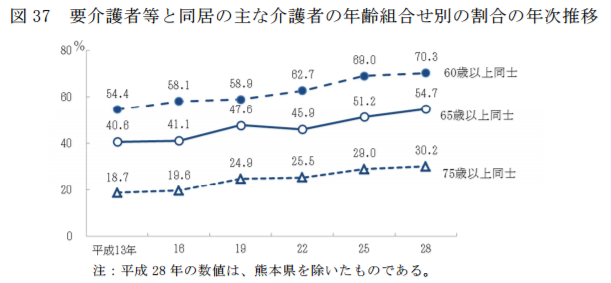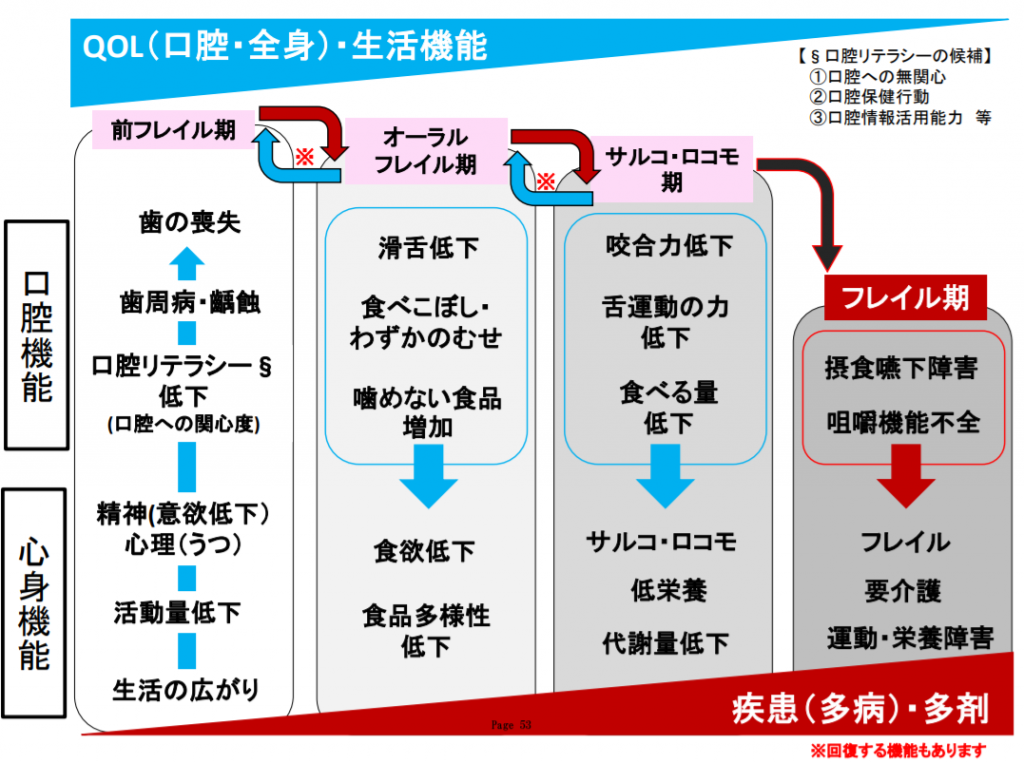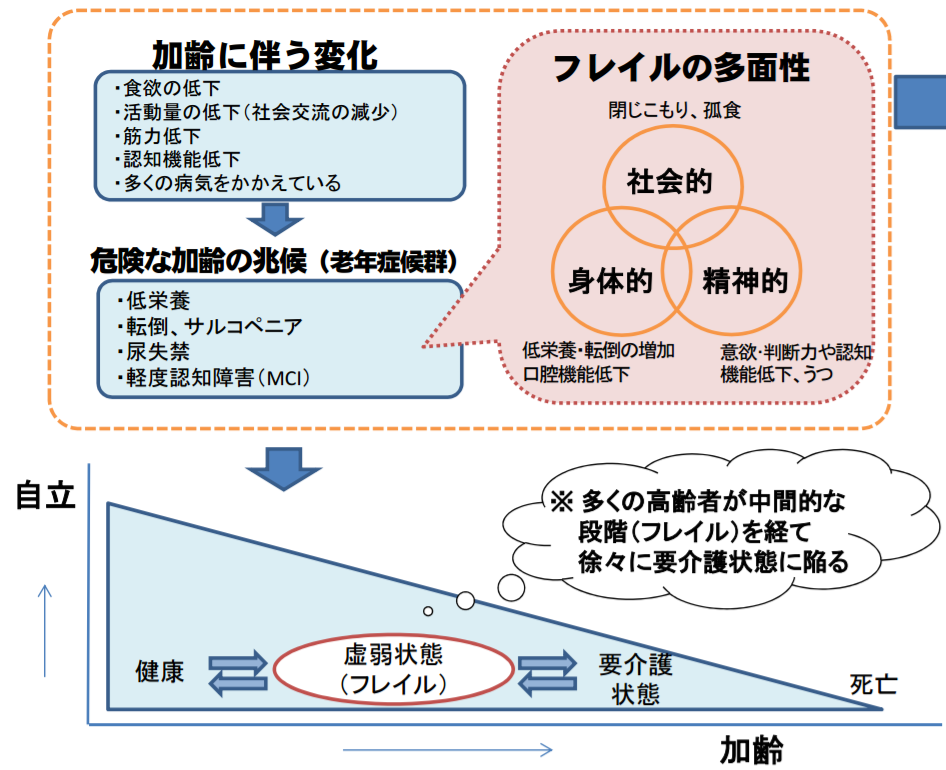■要介護(要支援)認定者数は2015年には約608万人
by Florian . (画像:Creative Commons)
要介護(要支援)認定者数の推移|平成28年版厚生白書 参考画像:要介護(要支援)認定者数の推移|平成28年版厚生白書 |スクリーンショット
平成28年版厚生白書によれば、要介護(要支援)認定者数は、2000年の約218万人から2015年には約608万人と増加しています。
その理由としては、生活習慣病(慢性疾患)中心への疾病構造の変化や高齢化の進展が挙げられています。
実際に高齢者人口は増加しており、高齢化率(65歳以上人口割合)は1950年4.9%→1985年10.3%→2005年20.2%と上昇し、2015年には26.7%と過去最高となっており、今後の予測としては、2025年30.3%となるなど、2060年まで高齢化率はずっと上昇していくことが見込まれているそうです。
年齢3区分別人口及び高齢化率の推移|平成28年版厚生白書 参考画像:年齢3区分別人口及び高齢化率の推移|平成28年版厚生白書 |スクリーンショット
つまり、この予測をもとにして、現状のままの仕組みで行くとすれば、要介護者の数は増加していくでしょう。
大事なことは、少子高齢化社会というトレンドは短期間では変わらないわけですから、介護度の改善などいかに要介護者の数を減らしていけるかがポイントになってくるわけです。
■「自立支援に軸足を置いた介護への移行」「人工知能や介護ロボット(センサーを含む)などテクノロジーを活用した新しい介護の仕組み」がキーワード 自立支援に軸足を置いた介護への移行|インセンティブ設計|新産業構造ビジョン|経済産業省 参考画像:新産業構造ビジョン (2017/5/30、経済産業省)
新産業構造ビジョン (2017/5/30、経済産業省)によれば、患者のQOLの最大化に向けて、高齢となっても自分らしく生きることの出来る「生涯現役社会」の実現に向けて、自立支援に向けた介護や質・生産性の⾼い介護の提供の実現が必要であるとして、できないことのお世話中心の介護から、自立支援に軸足を置いた介護への移行が必要であり、効果のある自立支援の取り組みが報酬上評価される仕組みを確立すべきとあります。
要介護度等の改善に対するインセンティブの例として、品川区や川崎市、岡山市や福井県など複数の自治体がインセンティブ措置を講じているそうです。
自立支援に軸足を置いた介護への移行|インセンティブ設計|介護現場での人工知能の導入加速 利用者の生活の質の維持・向上と介護者の負担軽減を実現する介護ロボットの開発・活用促進|現場ニーズに基づく介護ロボット開発支援 参考画像:新産業構造ビジョン (2017/5/30、経済産業省)
新産業構造ビジョン (2017/5/30、経済産業省)によれば、患者のQOLの最⼤化に向けて、⾼齢となっても⾃分らしく⽣きることの出来る「⽣涯現役社会」の実現に向けて、⾃⽴⽀援に向けた介護や質・⽣産性の⾼い介護の提供の実現が必要であるとして、ケアプラン作成を⽀援するAI(人工知能)や介護現場のニーズに基づいた介護ロボット(センサー含む)を開発・活⽤が必要になるとあります。
こうしたことを受けて、今後介護に関しては、「自立支援に軸足を置いた介護への移行」「人工知能や介護ロボット(センサーを含む)などテクノロジーを活用した新しい介護の仕組み」がキーワードとなっていくのではないでしょうか?
■重介護問題 「自立支援に軸足を置いた介護への移行」には重介護問題の解決にも役立つことが期待されます。
革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)「重介護ゼロ社会を実現する革新的サイバニックシステム」全体計画について |科学技術振興機構
「重介護」とは、全介助・部分介助・見守りが多数組み合わされ、介護される側・介護する側にとって身体的及び精神的に重く厳しい状態であり、継続的な介護が困難な状態である。排泄の例では、全介助ではなく部分介助状態となっている方であってもその介護生活が、介護される側・介護する側にとって重く厳しく継続的な介護が困難な状態の場合は重介護となる。一方、脳・神経・筋系の障害によって身体機能改善が見込めないとされていた要介護者について、機能改善が見込める革新技術によって、介護される側・介護する側にとっての重く厳しい介護生活が緩和され、生活の継続が困難な状態から改善される場合には、重介護が改善される一例となる。
少子高齢化に伴って、介護される側(要介護者・寝たきり高齢者・患者)・介護する側(家族・社会)への重く厳しい負担がかかることを「重介護問題」を解決を目指すことが求められています。
要介護者等と同居の主な介護者の年齢組み合わせ別の割合の年次推移平成28年国民生活基礎調査の概況|厚生労働省 参考画像:平成28年国民生活基礎調査の概況|厚生労働省 |スクリーンショット
75歳以上同士の「老老介護」初の30%超|65歳以上同士の「老老介護」は過去最高54%に|平成28年国民生活基礎調査 によれば、介護をする側と介護を受ける側の両方が高齢者の組み合わせである「老老介護」が話題になっていますが、平成28年国民生活基礎調査で発表された、同居の主な介護者と要介護者等の組合せを年齢階級別にみると、60歳以上同士70.3%、65歳以上同士54.7%、75歳以上同士30.2%となっており、また年次推移でみると、上昇傾向にあるのがわかります。
介護予防・生活支援サービス市場は2025年に1兆3000億円 によれば、今後高齢者人口と高齢者世帯の増加に伴いサービス市場は拡大し、介護予防・生活支援サービス市場は2025年に1兆3000億円に迫るそうですが、介護職員は2025年には約38万人不足するおそれがある そうです。
介護福祉士ピンチ!?介護福祉士を養成する大学や専門学校への定員に対する入学者の割合が約46% によれば、公益社団法人「日本介護福祉士養成施設協会」の調査によれば、2016年度の介護福祉士を養成する大学や専門学校への定員に対する入学者の割合が約46%だったそうです。
アメリカのプライム世代の女性の36%が「介護」を理由に仕事に就けない!?|働き盛り世代が無償の介護をしなければならない問題を解決するアイデア で紹介した米ブルッキングス研究所(Brookings Institution)のハミルトン・プロジェクト(The Hamilton Project)が発表した報告書によれば、アメリカでは2016年、成人の3分の1(37.2%)以上が仕事に就いておらず、そのうち「働き盛り世代」(25~54歳)に当たる人たちの5分の1近くが就業しておらず、女性の36%が介護を理由に仕事に就けないそうです。
「重介護問題」は遠い未来の問題ではなく、今目の前にある問題なのです。
そのためには、要介護者の自立度を高め、介護者の負担を軽減する取り組みが重要になってきます。
【関連記事】
■要介護者を減らす対策 要介護者の数を減らすには、どのようにしたらよいのでしょうか?
要介護者の数を減らす方法には大きく分けて2つあります。
1.介護度を改善すること、または介護度を悪化させないこと
2.テクノロジーを活用することによって、これまで要介護者にできなかったことをできることようにすること。
1.介護度を改善すること、または介護度を悪化させないこと 介護を必要とする期間をいかに短くするか、介護度を改善または悪化を防ぐという対策を行なう必要があると思います。
●食事(栄養管理)
要介護者等の状況|平成28年国民生活基礎調査の概況 |厚生労働省によれば、要介護度別にみた介護が必要となった主な原因として「高齢による衰弱」(16.2%)になっています。
「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう! で紹介した厚生労働省によれば、多くの高齢者が中間的な段階(フレイル)を経て、徐々に要介護状態に陥るそうです。
高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。
しかし、フレイルの段階で、適切な介入・支援を行なうことができれば、要介護状態に至らず、生活機能の維持・向上が期待できると考えられます。
それでは、具体的にどのように対処したらよいのでしょうか?
たんぱく質摂取と骨格筋|たんぱく質の関与|フレイルティ及びサルコペニアと栄養の関連|高齢者 |厚生労働省
地域在住の 70 歳代の高齢者を 3 年間観察したところ、3 年間の除脂肪体重の減少が、登録時の総エネルギー摂取量当たりのたんぱく質摂取量に依存し、五分位で最もエネルギー摂取量当たりのたんぱく質摂取量が多い群(平均91.0 g/日、1.2 g/kg体重/日)では、最も低い群(平均56.0 g/日、0.8 g/kg 体重/日)に比較し、交絡因子で調整後においても除脂肪体重の減少が 40% 抑制されていた 39)。
また、最近のコホート調査でも、たんぱく質摂取量が少ないことは 3 年後の筋力の低下と関連し 40)、さらに高齢女性の 3 年間の観察で、たんぱく質摂取量が少ないとフレイルティの出現のリスクが増加することが確認されている 41)。
日本人の高齢女性の横断研究でもフレイルティの存在とたんぱく質摂取量との関連が明らかにされている 42)。
39)Houston DK, Nicklas BJ, Ding J, et al. Health ABC Study. Dietary protein intake is associated with lean mass change in older, community-dwelling adults : the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. Am J Clin Nutr 2008; 87 : 150─5.Protein intake and muscle strength in older persons : does inflammation matter? J Am Geriatr Soc 2012 ; 60: 480─4.Protein intake and incident frailty in the Women’s Health Initiative observational study . J Am Geriatr Soc 2010 ; 58: 1063─71.High protein intake is associated with low prevalence of frailty among old Japanese women: a multicenter cross-sectional study. Nutr J 2013; 12: 164
これまでにも要介護者の中にはたんぱく質が不足する低栄養の人が多いということを紹介してきました。
適切な食物摂取ができず、栄養状態が悪化していることを「低栄養」と呼びます。
低栄養になると、免疫が低下したり、筋肉が減少したり、骨が弱くなったりすることで、感染症に掛かりやすくなったり、骨折するおそれが高くなるようです。
今回紹介した厚生労働省のまとめによれば、高齢者はたんぱく質の摂取量が少ないと、フレイルティの出現リスクが増加するそうです。
なぜ高齢者になるとタンパク質が不足しがちなのでしょうか?
肉料理が苦手だったり、以前は、家族のために栄養を考えて、肉や卵などを使って料理をしていた人が、一人暮らしになってから、自分が好きなものだけを食べることで食が偏るようになって、肉や卵を使った料理を食べなくなってしまったり、食事の量自体が減ってしまったり、中高年の頃からのメタボ対策のための粗食を継続してしまったりすることで、たんぱく質が不足してしまうということがあるようです。
つまりは、中高年(メタボ対策)から高齢者(フレイル対応)への食習慣の移行ができていないために低栄養になってしまっていると考えられます。
低栄養はタンパク質が不足したことで起こると考えられますが、●たんぱく質(アルブミン)不足を予防するには、肉を食べるとよいそうです。
アルブミンを上げる食事|肉を食べてアルブミンを上げたグループは死亡リスクが低い!? で紹介した熊谷修教授(人間総合科学大学人間科学部)によれば、肉をよく食べてアルブミンを上げたグループはほとんど食べないグループに比べて死亡リスクが低いそうです。
また、アルブミン値を上げるためには、鶏のささみよりも牛肉のほうが良いそうです。
それは、牛肉に含まれる「飽和脂肪酸(アルブミンを作り出すエネルギーとなる)」を一緒に摂ることができるからなのだそうです。
お肉を選ぶ場合には、脂身のある肉(豚肉やもも肉)のほうが良いそうです。
アルブミンを上げる食事|肉を食べてアルブミンを上げたグループは死亡リスクが低い!? によれば、「15の食生活指針」に沿った食生活を実践してもらったところ、アルブミンは増加し、血色素の低下も見られなり、つまり、栄養改善の効果があらわれたそうです。
3食のバランスをよくとり、食事を抜かずにきちんと食べましょう。
油脂類の摂取が不足しないようにしましょう。 肉、魚、乳製品、卵などの動物性たんぱく質を十分に食べましょう。 肉と魚の摂取は1:1の割合にしましょう。 いろいろな種類の肉を食べましょう。 牛乳は毎日200ml以上飲むようにしましょう。 野菜は緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草など)や根菜(大根、ごぼう、いもなど)など、いろいろな種類を毎日食べるようにしましょう。
食欲がないときは、おかずを先に食べ、ご飯の量を減らしましょう。
いろいろな調理のしかたや、食品の正しい保存法を覚えましょう。
酢、香辛料、香り野菜(ねぎ、にんにくなど)を十分に取り入れましょう。
調味料を上手に使い、おいしく食べましょう。
和風、中華風、洋風といろいろな料理を食べましょう。
家族や友人との会食の機会をたくさんつくりましょう。
噛む力を維持するために、義歯は定期的に点検をしましょう。
「元気」のための健康情報をすすんで取り入れましょう。
※2から6までの5項目が、低栄養を防ぐための動物性食品や油脂類の摂り方に関する項目です。
お肉はタンパク質が豊富で、実はバランス栄養食品です。
野菜よりも鉄分 が豊富で、かつ肉は野菜より鉄分の吸収率が5から10倍高い。
またビタミンも豊富で、特にビタミンB1は豚ヒレ肉100gでレモンの17倍含んでいるそうです。
さらにミネラルも豊富なのだそうです。
ただ、あなたやあなたの家族の食事をどのようにチェックしたらよいかわからない人もいると思います。
そこで、最近取り上げられているのが、「10食品群チェックシート」です。
「10食品群チェックシート」は、様々な種類の食材が摂れているかをチェックするシートです。
肉
卵
牛乳(チーズなど乳製品)
油
魚
大豆
緑黄色野菜
芋
果物
海藻
10食品群チェックシート |PDF(NHKチョイス@病気になった時)
http://www.nhk.or.jp/kenko/choice/pdf/160430.pdf
10品目チェックシート |PDF(NHKためしてガッテン)
http://www9.nhk.or.jp/gatten/pdf/10hinmoku.pdf
【関連記事】
●口腔ケア・食事(食べ方)
●オーラルフレイル
オーラルフレイルを知って健康寿命を延ばそう|自分の歯が多く保たれている人は、健康寿命が長く、要介護期間が短い|東北大学 によれば、東北大学の松山祐輔歯科医師が行なった研究によれば、自分の歯が多く保たれている人は、寿命が長いだけではなく、健康寿命(日常生活に制限のない期間)が長く、要介護でいる期間が短いことがわかったそうです。
食べこぼしやわずかなむせ、噛めない食品の増加というのは一つ一つを見るとささいなことですが、こうした症状が合わさって起こるということは口腔機能の低下のサインであり、オーラルフレイルという口腔機能低下を含む身体の衰えの一つです。
オーラルフレイルについて調べていたところ、「オーラルフレイル仮説」という考え方があることを見つけました。
オーラルフレイル仮説(前フレイル期・オーラルフレイル期・サルコ・ロコモ期・フレイル期) 参考画像:食(栄養)および口腔機能に着目した加齢症候群の概念の確立と介護予防(虚弱化予防)から要介護状態に至る口腔機能支援等の包括的対策の構築および検証を目的とした調査研究 (2015年3月、東京大学 高齢社会総合研究機構)|スクリーンショット
食(栄養)および口腔機能に着目した加齢症候群の概念の確立と介護予防(虚弱化予防)から要介護状態に至る口腔機能支援等の包括的対策の構築および検証を目的とした調査研究 (2015年3月、東京大学 高齢社会総合研究機構)によれば、オーラルフレイル仮説とは「前フレイル期」「オーラル・フレイル期」「サルコ・ロコモ期」「フレイル期」と4つのフェーズ(段階)に分かれていて、フェーズが移行するに伴い、QOLの低下・日常生活機能の低下、病気にかかりやすくなる、服薬する薬の種類が増えていくという考え方です。
ポイントとなるのは、第1期の「前フレイル期」と第2期の「オーラル・フレイル期」の段階で、歯磨きをしっかり行う、歯科医院に定期的に通ってチェックしてもらうなどいかに対策を行なっていくかということです。
この考え方が浸透すれば、定期的な歯科医院でのチェックで、サルコペニアやロコモティブシンドローム、フレイルに移行する前に、何らかの対策が必要であることを促すという流れができることにより、要介護状態になることを防ぐことができるようになるかもしれません。
●嚥下障害
要介護者の約6割に咀嚼や嚥下に問題がある|嚥下障害チェックテスト・嚥下障害対策(健口体操・嚥下体操) で紹介した日清オイリオグループが60歳以上の要介護者(要介護度1~3)を在宅で介護しており、介護食を作っている100名を対象に実施した「低栄養に関する実態調査」によれば、要介護者の約6割に咀嚼(そしゃく。かむこと)や嚥下(えんげ。飲み込むこと)に問題があるそうです。
高齢者は注意したい!誤嚥性肺炎の気づきにくい症状のサインとは? によれば、厚生労働省の人口動態統計の死因別統計によれば、「肺炎」で亡くなる人が年間12万人を超え、肺炎は「がん」「心臓病」に次ぐ第3位となっています。
高齢者にとって肺炎は怖い病気であり、肺炎を引き起こす原因としては、「嚥下障害(えんげしょうがい)」によって起こる「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」が挙げられます。
誤嚥性肺炎の原因は、食べ物や飲み物、唾液に含まれた細菌が気管から入り込むことですが、眠っている間に細菌を含む唾液を少しずつ誤嚥することがあるため、気づきにくいです。
寝たきりや脳血管障害、認知症の患者の場合は、嚥下反射やせき反射が低下し、細菌が気道を通じて肺に入り込みやすくなるため、誤嚥性肺炎のリスクが高くなるそうです。
誤嚥性肺炎の予防は、細菌を含む食べ物や唾液の誤嚥を防ぐことが重要となります。
そのため、口の中を清潔に保つ口腔ケアと誤嚥を防ぐ対策が必要になります。
1.口腔ケア 口の中の細菌を繁殖させないようにするために、歯磨き(入れ歯の人は入れ歯の洗浄)で口の中を清潔に保ちましょう。
また、唾液の分泌が減ると、口が乾きやすくなり、雑菌だらけの唾液が肺に入ることで、誤嚥性肺炎を引き起こすおそれがあるので、唾液の分泌をうながすようにしましょう。
●唾液がよく出る健口体操
童謡の「むすんでひらいて」に合わせて口を動かす
「むすんで ひらいて ベロを出して むすんで
またひらいて ベロ出して そのベロを鼻に
ベロを右に ベロを左 ベロをぐるぐる回します」
【関連記事】
また、ドライマウス にも気を付けましょう。
【関連記事】
2.誤嚥を防ぐ対策(嚥下反射を改善する嚥下障害対策) ●胃液の逆流を防ぐ
嚥下障害と誤嚥性肺炎
ゲップや胸焼けなどがある場合は、胃液の逆流が起こりえます。その場合、食後2時間ほど座って身体を起こしていることで、逆流を防止できます。
誤嚥予防のために、食後すぐに横にならずに、2時間程度座った姿勢を保つことで、胃液の逆流を防ぎましょう。
→ 逆流性食道炎の症状・原因・治し方・食事 について詳しくはこちら
【関連記事】
●嚥下体操
嚥下反射を改善させるために、嚥下体操を行ないましょう。
(1)腹式呼吸
鼻から息を吸って、口からゆっくり吐きます。
吸うのを4回、吐くのを8回。
(2)首の体操
前に後ろに動かします。
右に左に動かします。
首筋を伸ばします。
(3)肩の体操・腕の体操
肩をゆっくり上げてそのままにして、ストンと落とす。
片方の腕を上げて、もう片方の手で引っ張ります。
(4)発音練習
唇を使って、「ぱっ・ぱっ・ぱっ」「まっ・まっ・まっ」と発音し、舌を使って「たっ・たっ・たっ」「らっ・らっ・らっ」と発音します。
【参考リンク】
●運動
ロコモティブシンドロームになると要介護のリスクが高くなる?ロコモの原因・予防のためのトレーニング方法 によれば、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、運動器の障害のために要介護となる危険の高い状態のことをいいます。
加齢による筋力やバランス能力の低下によって、ロコモティブシンドロームになっているそうです。
ロコモティブシンドロームを予防するには、どうしたらよいのでしょうか。
ロコモティブシンドロームの考え方は、痛みに対する治療だけでは不十分で、筋力強化なども併せて運動の状態を向上させ、QOL(生活の質)を保つことを目指す。
それが、介護予防にもつながる。
痛みに対する治療だけでなく、日頃から筋力を強化することで運動の状態を維持していくことが、大事なようです。
毎日運動している人としていない人との間には体力に大きな差がある!?|2014年度体力・運動能力調査 で紹介したスポーツ庁の2014年度体力・運動能力調査によれば、高齢者(65~79歳)で、ほとんど毎日運動している人と運動をしない人では、体力に大きな差があることがわかりました。
記事の中には、ロコモティブシンドロームの予防に取り組む目安の五項目が紹介されています。
『要介護』招く運動器症候群 ロコモティブシンドローム
(2009/8/14、東京新聞)
日本整形外科学会は、予防に取り組む目安として五項目を紹介している。
片脚立ちで靴下がはけない
この5項目のうち、一つでも当てはまる人は、ロコモティブシンドロームを予防するロコモーショントレーニングを薦めているそうです。
『要介護』招く運動器症候群 ロコモティブシンドローム
(2009/8/14、東京新聞)
効率よく筋力強化ができるのが目を開けての「片脚立ち」。
松井医長によると、片脚立ちは両脚立ちに比べ二・七五倍の負荷がかかり、一日三回、左右一分間の片脚立ちは、約五十三分間の歩行に相当するという。
支えが必要なら、机に手をついて行ってもよい。
「スクワット」はお尻を低く下ろせばより筋力が鍛えられるが、継続するには浅い角度の方が安全だ。
脚はかかとから三〇度くらい外側に開き、体重が脚の裏の中央にかかるように意識する。
現在の筋肉を維持しようという人がウォーキングだけをしても、筋肉は衰えていってしまいます。
筋肉を衰えさせないためにも、筋トレが必要。
ロコモティブシンドロームを予防するトレーニングとして紹介されているのは、「片脚立ち」と「スクワット」です。
片手だけまたは手を使わずに床に座ったり立ったりできる人は長生きできる? によれば、中高年で床に座ったり立ったりが片手だけで、または手を使わずにできる人は筋骨格がしっかりしており、それができない人に比べて長い寿命が期待できるそうです。
また、おすすめなのが「スロトレ」。
スロトレは、軽い負荷でありながらも、、すべての動作を“ゆっくり、止めずに、連続して行う”ことで筋肉が力を発揮している時間を引き延ばし休ませないため、筋肉量が増えるのに効果的なトレーニング方法です。
2.テクノロジーを活用することによって、これまで要介護者にできなかったことをできることようにすること。 メディアアーティスト・落合陽一、「介護市場を開放したい」
(2017/9/12、ニュースイッチ)
身体の不自由な人を抱きかかえて入浴するには腕力がいるし、車いすで移動する時には絶えず周囲に注意が必要。コミュニケーションで高齢者の気持ちを明るくし、生活を活発化することなど、技術の活躍する場は多い。
介護作業を支援するロボットや介助者がいなくても使える車いす、コミュニケーションロボットなど介護の現場で役立ちそうなアイデアが紹介されています。
VIDEO
Telewheelchair at Laval Virtual Awards
そこで筑波大の落合研究室では、既存の電動車いすに介助者の目の代わりとしてリコーの全天球カメラ『シータ』を組み合わせた「Telewheelchair(テレウィールチェアー)」の研究を進めている。特別ではないハードウエアの組み合わせを、ソフトウエアで結合して機能を追加したのが特徴だ。映像を転送して遠隔操作したり、障害物を検知して自動で停止する。
例えば、Digital Nature Groupでは、「Telewheelchair」というアイシン精機の電動車いすとRICOHの360°すべてを撮影する全天球カメラ『THETA』を組み合わせて、ソフトウェアで結合し、VRでリモートコントロールしたり、障害物を検知して自動で停止するという車いすを開発しているそうで、この車いすであれば、介助者の負担を軽減することになることが期待されます。
また、排泄に関してなど、人によっては人間(身近な家族や介助者)よりもロボットのほうが恥ずかしくないので良いという分野もあるのではないでしょうか。
VIDEO
The Future of Hotel Delivery Service
VIDEO
ResidenceInnLAXCaseStudy (Japanese Subtitles)
人間用エレベーターも乗りこなす「荷物お届けロボット」、品川プリンスホテルに現る
(2017/9/14、ITmediaニュース)
Relayは、レーザーセンサーと3Dカメラを使って屋内の環境や現在位置を特定する技術「SLAM」(Simultaneous Localization and Mapping)を利用しているという。
ロボットベンチャー企業の「Savioke 」が開発したのは、部屋へ荷物を届けることに特化した自律走行型ロボット「Relay(リレイ)」です。
Relayは客から荷物の運搬を依頼されたホテルのスタッフの指示を受け、自分でエレベーターに乗り降りして、部屋の前に到着すると電話をかけて、ドアが開き、荷物をお客さんが取り出すと、自動で戻るという仕組みです。
こうしたアイデアこそ介護者の負担、介護される側の心理的負担を軽減してくれるのではないでしょうか?
■まとめ 介護については、どれか一つの対策をとるのではなく、さまざまな対策を組み合わせて行なっていかないと解決しない問題だと思います。
しかし、少子高齢化や要介護者の問題ははネガティブな側面だけではなく、ポジティブにとらえると一つのチャンスになる可能性があり、「少子高齢化による高齢化社会は日本にとってのビジネスチャンス(医療・介護など)になる!」と発想を転換してみない? でも紹介しましたが、日本は高齢化社会の新しいイメージを伝えるモデルケースとして、高齢化社会を引っ張るリーダーとなる可能性もあります。
例えば、大人用紙オムツの売上が子供用オムツの売上を追い抜いた!?|日本の紙おむつが国際規格化|高齢化社会がビジネスチャンスに変わる!? によれば、大人用紙おむつの評価方法に関する規格「ISO15621尿吸収用具―評価に関する一般的指針」が改訂し、欧米の「テープ止め型(体にテープで固定するタイプ)」ではなく、日本が提案する装着車の症状や生活環境に合わせたきめ細かい高齢者介護学科脳になるパンツ型やテープ止め型のおむつに吸着パッドを挿入するタイプなどを規格化されました。
つまり、世界に先行して高齢化社会に突入している日本は、医療費削減のアイデアやよりよい介護の方法を実行できる立場にあり、それらのやり方をスタンダードにすることができるというビジネスチャンスがあるのではないでしょうか?
また、こうした考え方を発展させれば、人間と機械(人工知能・ロボット)と一体化して、人間の能力を強化・拡張していくことによって、未来の社会基盤を構築していくことにもつながると思います。
この考え方は、ヒューマンオーグメンテーション(Human Augmentation)という暦本純一さんが提唱するコンセプトで、人間とテクノロジー・人工知能が一体化することで、知覚、認知、身体、存在感の4つの分野で人間の能力を強化・拡張していくIoA(Internet of Abilities:能力のインターネット)という未来社会基盤の構築を視野に入れた、最先端の研究を体系化していく学問領域です。
【関連記事】
https://twitter.com/ochyai/status/863280246140698624 で落合陽一さんはAIやロボットなど自動化技術によって、高齢化社会で成長する方法を提案しています。
高齢化社会をベースにすると発想を転換すると、それに合わせたテクノロジーが生まれることによって、もしかすると、若者にとっても過ごしやすい社会になるかもしれませんし、すでにそうした兆しも見えています。
ぜひこれをチャンスに変えてほしいですね。
【ロコモティブシンドローム関連記事】続きを読む 要介護(要支援)認定者数は2015年には約608万人|要介護者にならない段階(フレイル)で食い止める対策が重要 →

![]()