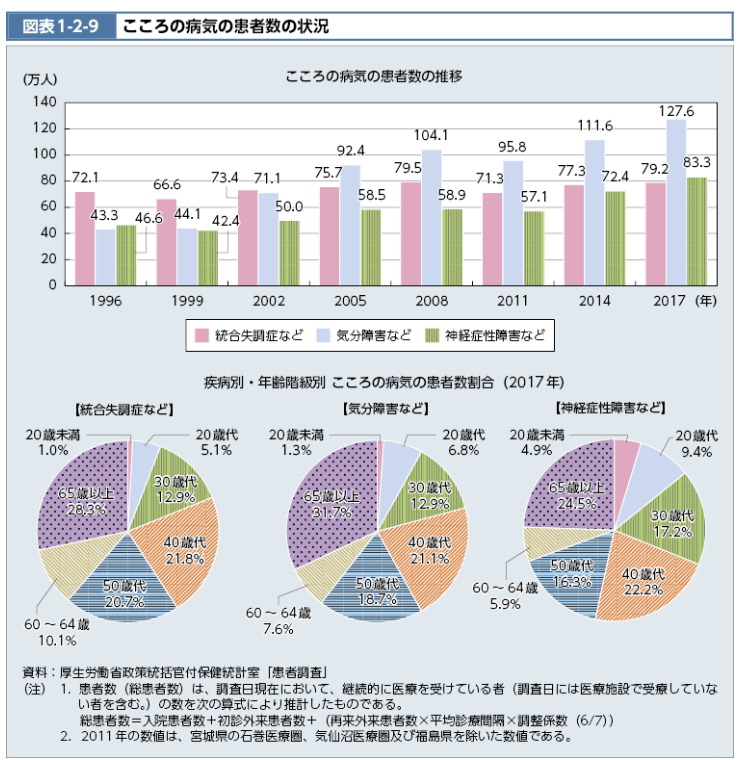マウスを使ったある研究によれば、運動をすると体ががんのエサを奪い取ってがんの成長を遅らせること、また「どれだけ体力がついているか」を測ることで、がん治療の効果を予測・最適化する可能性があることがわかりました。
■背景
●がん細胞は、ブドウ糖(血糖)をたくさん食べて急速に増殖する。
●運動はガンの予防・治療に役立つと知られていますが、なぜ運動ががんに効くのかはわかっていない。
■結果
実験の結果わかったことは、次の5つ。
1)運動するマウスは腫瘍の成長が遅くなったこと
2)運動前の体力が高いほど腫瘍の成長抑制に対して効果的だったこと
3)運動することによって、筋肉(骨格筋・心筋)と心臓へのブドウ糖の取り込み・酸化(エネルギーに変える過程)が増加し、腫瘍へのブドウ糖の取り込み・酸化が減少したことから、体がブドウ糖をがんから遠ざけていること
4)肥満マウスでも運動によって筋肉のブドウ糖利用がアップし、腫瘍の利用がダウンしたことから、腫瘍の進行が遅れたこと
5)運動群の腫瘍で、mTORシグナル(がんの成長スイッチ)が低下したことから、ブドウ糖が腫瘍に届きにくくなるメカニズムが示唆されたこと
■結論
1)運動をすることはガンの予防・治療につながる
運動をすると、体ががんのエサとなるブドウ糖を奪い取ることにより、がんの成長を遅らせることがわかりました。
2)「どれだけ体力がついているか」ががん治療の効果・最適化のカギ
■まとめ
運動はただの運動法ではなく、体とガンとの競争に打ち勝つ武器だということなんですね。
そして日ごろから運動をして体力をつけておくことがその勝負をさらに優位に進める方法だということも。
つまり、若いうちからしっかり運動をして体力をつけてがんを予防しましょう!
【参考リンク】
- B.P. Leitner, A.E. Fosam, W.D. Lee, K. Zilinger, S.C.B.R. Nakandakari, X. Zhang, R.C. Gaspar, W. Zhu, C.J. Perry, J.D. Rabinowitz, & R.J. Perry, Precancer exercise capacity and metabolism during tumor development coordinate the skeletal muscle–tumor metabolic competition, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (49) e2508707122, https://doi.org/10.1073/pnas.2508707122 (2025).
運動するとがんのエサを奪える!2025年最新研究が証明した衝撃のメカニズム
「がんになりたくない…でも運動は面倒…」
そんなあなたにとって大事なニュースが飛び込んできました!
2025年12月1日、イェール大学が発表した最新研究(MIT監修・PNAS掲載)で、「運動すると体が自動的にがんのエサ(ブドウ糖)を横取りして、がんを兵糧攻めにする」という驚くべき事実がマウス実験で完全に証明されました。
しかも重要なのは、「運動したかどうか」より「どれだけ体力がついているか」が、がんの成長を抑える決め手になるということ!
■がん細胞の弱点は「甘いもの大好き」
がん細胞は普通の細胞の10倍以上もブドウ糖を欲しがります。
ブドウ糖=がんのガソリン。
これをたくさん食べさせると、がんはドカドカ増殖します。
■運動すると何が起こるのか?衝撃の5大発見
●運動したマウスの腫瘍は成長速度が最大60%も遅くなった
●体力が高いマウス(1日10km以上走る子)ほど、腫瘍が劇的に小さくなった
●筋肉と心臓がブドウ糖をガンガン奪い取り、腫瘍に届くブドウ糖が激減!
→ 体が「がんにエサやるな!」と自動的に切り替わる
●肥満マウスでも同じ効果!運動で筋肉がブドウ糖を独占し、がんは飢餓状態に
●腫瘍の中の「成長スイッチ(mTOR)」がOFFに!がんがエネルギー不足で弱る
これ、すでに人間でも証明されつつあります。
●定期的に運動する乳がん患者さんは再発リスクが30~40%低下(世界中のデータ)
●体力(VO2max)が高い人ほど、がんになったときの生存率が圧倒的に高い
●米国がん学会も「運動は抗がん剤と同等の効果がある可能性」と公式見解を変更中
つまり、今から運動を始めれば、あなたの体も「がんを兵糧攻めモード」に切り替わるということです!
今日からできる「がん撃 撃退運動メニュー」週3回、30分でOK!
・早歩き(話せるけど歌えないくらいのペース)
・ジョギング
・水泳・自転車なんでもOK 1ヶ月続ければ体力は確実に上がります=がんに勝てる体に近づきます!
■最後に
がんに勝つのは抗がん剤だけじゃない。
あなたの足と肺が、最強の抗がん剤になってくれる時代がもう来ています。今日、5分でもいい。
外に出て歩いてみませんか?その一歩が、未来のがんを兵糧攻めにする第一歩になります。
シェアして、大切な人をがんで失わない未来を一緒に作りましょう!
「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」
この街を初めて訪れた方へ
この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。
この街には、生活・料理・健康についての記事が、
同じ考え方のもとで並んでいます。
ここまで書いてきた内容は、
単発の健康情報やレシピの話ではありません。
この街では、
「何を食べるか」よりも
「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。
もし、
なぜこういう考え方になるのか
他の記事はどんな視点で書かれているのか
この話が、全体の中でどこに位置づくのか
が少しでも気になったら、
この街の歩き方をまとめたページがあります。
▶ はじめての方は
👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。
▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)
※ 無理に読まなくて大丈夫です。
気になったときに、いつでも戻ってきてください。
この考え方の全体像(意味のハブ)
この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。
▶ 料理から見る健康
この街の考え方について
この記事は、
「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」
という この街の憲法 に基づいて書かれています。
▶ この街の中心に置いている憲法を読む