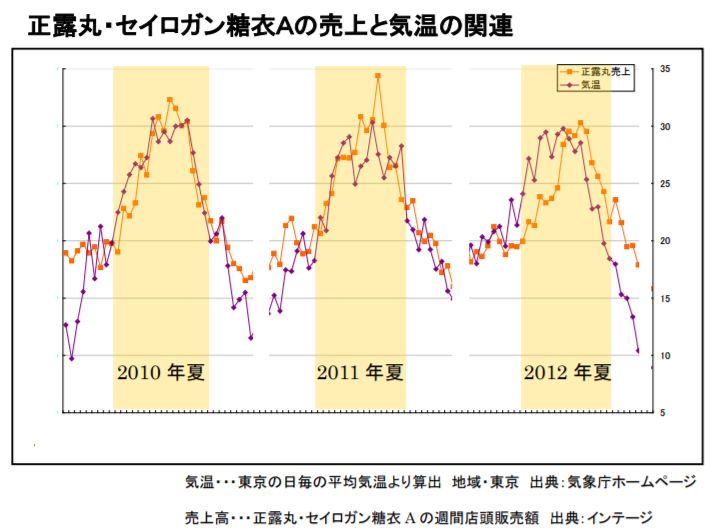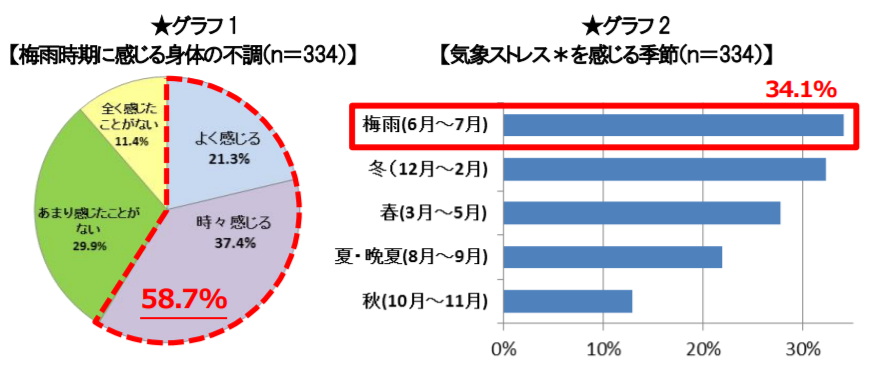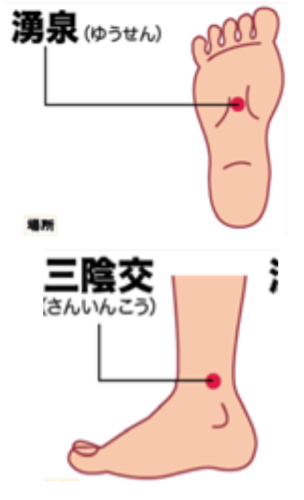> 健康・美容チェック > 熱中症 > 「マスク熱中症」に注意!新型コロナ対策と熱中症対策両方を一緒にやる必要がある!
■「マスク熱中症」に注意!新型コロナ対策と熱中症対策両方を一緒にやる必要がある!

“マスク熱中症”にご注意!熱こもり思わぬ体温上昇https://t.co/6XhSaWcdJU
”帝京大学医学部付属病院救命救急センター・三宅康史センター長:「コロナ対策と同時期に熱中症対策両方を一緒にやる必要があります。」”
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) May 12, 2020
“マスク熱中症”にご注意!熱こもり思わぬ体温上昇(2020/5/11)によれば、マスクをつけることによる体温上昇が心配されています。
熱中症で死亡した人の9割が屋内|65歳以上の高齢者やエアコン不使用のケースが多い!によれば、エアコンがない人やエアコンがあるのに発見時には使っていなかった人に熱中症でなくなったケースが多いようです。
熱中症は自宅での発症が最も多い!熱中症になったらどう対処したらよいか?で紹介した独立行政法人・国立環境研究所によれば、熱中症で緊急搬送された人のうち、自宅での発症が最も多かったそうです。
また、室内での死亡例を見ると、エアコンが作動していなかったケースが目立つため、室温28度、湿度70%を超えたらエアコンを使ったほうがいいようです。
真夏の暑い時期にコロナ対策と熱中症対策両方をやることはできるのかどうか。例えばエアコン。エアコンは部屋の中の空気と外の空気を入れ換えていないため、快適な温度で過ごすことと室内の空気を入れ替えることをバランスよく行う対策が必要になってきます。
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) May 12, 2020
ただ、今回はコロナ対策と熱中症対策を同時にやる必要があります。
熱中症対策でエアコンをつけることが推奨されていますが、ほとんどのエアコンでは換気ができないため、新型コロナ対策のため屋内・室内の換気をするためには何らかの対策を行なう必要があります。
1⃣24時間換気システムを正しく使う
2時間で室内の空気を入れ替える2⃣窓を開けて空気の通り道を作る
2時間で1回10分の換気をするよりも、1時間に5分の換気を2回する方が換気の効果は高い。
空気の通り道を作るには2つの窓(対角線上)を開ける3⃣台所の換気扇を活用https://t.co/DAPu3XI8nO pic.twitter.com/OQ0PkOXUg2
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) May 12, 2020
厚労省によれば、高温多湿の中でのマスク着用は体に負担になるので、屋外で他の人と2メートル以上の距離が取れる場合はマスクを外し、着用する時には負荷のかかる作業や運動を避けることを勧めています。熱中症と新型コロナ対策の両立をしましょう!https://t.co/aNr7HU300J
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) May 27, 2020
家やマンションについている24時間換気システム(換気口)を正しく使ったり、対角線上にある2つの窓を開けることで空気の通り道を作り、また1時間に5分の換気を2回する、屋外で距離がとれる場合はマスクを外すなどをして熱中症対策と新型コロナ対策を同時に行っていきましょう!
日本小児科学会曰く、2歳未満の子供の場合マスクは不要。
✅乳児の呼吸器の空気の通り道は狭いので、呼吸をしにくくさせ呼吸や心臓への負担に
✅窒息リスクが高まる
✅マスクによって熱がこもり熱中症のリスクUP
✅顔色や口唇色、表情の変化など、体調異変への気づきが遅れるhttps://t.co/zQ5eqIjfzM— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) June 10, 2020
😷マスク内の口元の温度 ない場合より3度高く
😷横堀將司教授(日本医科大学大学院)「マスクを着けると呼吸がしにくくなり、心拍数や呼吸数が1割ほど増えるというデータ」
→熱中症を防ぐためにも、屋外では基本マスクを外して、人と接近する場合のみ着用に変更してほしいhttps://t.co/IULIhokN06
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) June 11, 2020
→ 熱中症の症状・対策・予防 について詳しくはこちら
→ 熱中症にかかりにくくなる「暑熱順化」とは|暑熱順化で身体はどう変わるか? について詳しくはこちら
理化学研究所はスーパーコンピューター「富岳」によってせきなどの飛沫がどう広がるのかを予測した動画を公開pic.twitter.com/y5pwJQisgg
室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測とその対策|理研https://t.co/M4t6onUr9x
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) June 5, 2020
新型コロナ エアコンの「風」で飛沫流れ感染 CDCが事例報告https://t.co/0nrx0vNhsE
COVID-19、エアコン気流でクラスター形成かhttps://t.co/GLMC7AthGp
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) June 5, 2020
理化学研究所によるせきなどの飛沫がどう広がるのかを予測した研究とCDCによるエアコンの気流で飛沫が流れて感染したのではないかという事例(飛まつが風下に流れて、隣のテーブルの家族に感染し、さらに、強い空気の流れで壁に反射して最も風上のテーブルの家族にも感染が広がったとみられると結論)をみると、エアコンによる室内の冷却と同時に換気も行わないと、熱中対策と新型コロナウイルス対策の両立は難しいように感じます。
また、理化学研究所の研究では、机をはさんで人が対面している場合では、頭の高さより高い仕切りであれば飛まつがせき止められることや時速80キロの電車が窓を開けて走行した場合でも満員電車の状態であれば、頭上での空気は動いても、足元の空気の流れが止まってしまうため、十分な換気ができないこともわかりました。
車内が混雑していると、立っている乗客の足下ではあまり空気が流れず、座っている乗客の口元のあたりでは換気が十分に進まない恐れがあるそうです。サーキュレーターのようなモノで空気を循環させる、空気循環ができる人数だけが乗れるように乗車制限をする対策が必要。pic.twitter.com/y5pwJQisgg https://t.co/2HlMPEHety
— 40代・50代のためのライフスタイル(健康・美容・お金) (@4050health) June 6, 2020
このことから、マスクをせずに対面で座る場合には頭の高さより高い仕切りが必要ですし、電車内には換気が十分にできる空間が必要なため、乗車制限が必要なのではないでしょうか?
【関連記事】
- 新型コロナウイルスについて考えたこと|症状・予防法・重症化を防ぐには?
- 新型コロナウイルスに負けない!『入浴』『睡眠』『食事』自宅で簡単に免疫力アップする方法!
- 「新しい生活様式(ニューノーマル)」の実践例とは?|新型コロナ専門家会議
- 新型コロナウイルスが血栓を招き、脳梗塞や心筋梗塞を起こす可能性がある!?
- 「コロナ太り」の検索数が急上昇!自宅でできるコロナ太りを解消する方法とは?
- 新型コロナウイルス対策をしながら、フレイル対策も行うことが大事!
- 『世界が元に戻ったらしたいことまとめ(コロナが終息したら、みんなは何したい?)』が人気!「新しい生活様式」を「オープンエア」の発想で楽しもう!
- GOOGLEが発表した新型コロナ以降検索数が急増したワードから予想される未来とは?