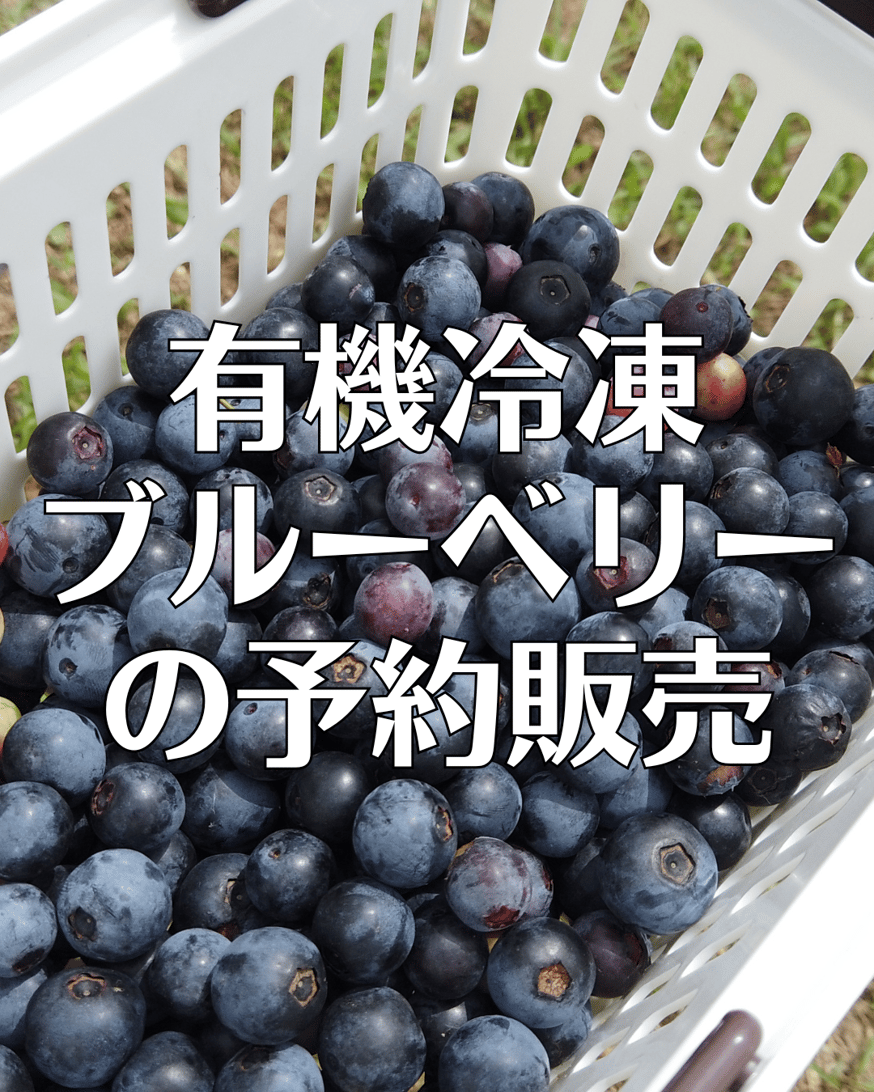Nature誌に掲載された研究によれば、筋肉から分泌されるホルモン「マイオカイン」の中でも「CLCF1」というマイオカインが加齢による筋肉や骨の衰えを抑える可能性があることがわかりました。
【参考リンク】
■概要
この論文は、加齢によって筋肉や骨が衰える仕組みと、運動がそれにどう影響するかを調べた研究です。
特に、筋肉から分泌される「マイオカイン」という物質に注目し、その中でも「CLCF1」というマイオカインが加齢による筋肉と骨の衰えを抑える可能性があることを発見しました。
■マイオカインとは?
マイオカインCLCF1は、運動によって骨格筋から分泌される物質で、加齢による筋肉や骨の衰えを改善する可能性のある「若返りスイッチ」のような働きをすることが研究で示されています。特に、高齢者ではCLCF1の分泌が低下する傾向があるため、運動や補充療法が重要であるとされています。
■CLCF1とは?
CLCF1 (Cardiotrophin-like cytokine factor 1) は、筋肉から分泌されるマイオカインの一種で、運動によって骨格筋から分泌される生理活性物質です。
マイオカインは、筋肉が収縮する際に分泌され、様々な生理機能に影響を与えると考えられています。
若い人やマウスでは運動後にCLCF1の血中濃度が上がりますが、加齢とともにその量が減少し、運動しても増えにくいことがわかりました。
CLCF1の効果筋肉への効果:高齢のマウスにCLCF1を投与すると、握力や走る能力が向上し、筋肉の繊維のサイズも大きくなりました。
CLCF1は、筋肉のエネルギー代謝(特に糖の取り込みや代謝)を改善し、ミトコンドリアの働きを高めることで、筋肉の機能を強化します。
骨への効果:CLCF1は、骨を壊す「破骨細胞」の働きを抑え、骨を作る「骨芽細胞」の働きを促進します。これにより、骨の量が増え、骨折のリスクが減ります。
これらの効果は、運動が筋肉や骨に与える良い影響と似ています。
■背景:なぜこの研究が重要か?
人は歳をとると、筋肉や骨が弱くなり、動きづらくなったり骨折しやすくなったりします。
これを「サルコペニア」(筋肉の減少)や「骨粗しょう症」(骨の弱化)と呼びます。
この研究では、運動がこれらの問題を改善する理由を調べ、特に筋肉から分泌される「マイオカイン」というタンパク質がどのように関わっているかを探っています。
マイオカインは筋肉と骨の健康を保つために重要な役割を果たすと考えられています。
■実験の方法
人間での研究:若い人と高齢者の運動前後の血液を調べ、CLCF1の量を測定しました。
運動(特にレジスタンス運動や高強度インターバル運動)でCLCF1が増えることが確認されました。
マウスでの研究:高齢のマウスにCLCF1を注射して、筋力や骨の状態を調べました。
CLCF1を過剰に作り出す遺伝子組み換えマウスを作り、筋肉や骨の健康がどうなるかを観察。
逆に、CLCF1をブロックする物質(eCNTFR)を使って、運動の効果がどう変わるかを確認しました。
細胞実験:筋肉細胞や骨細胞にCLCF1を加えて、その影響を詳しく調べました。
■CLCF1をブロックするとどうなる?
CLCF1の働きを抑えると、運動による筋力や骨の強化効果がほとんどなくなりました。
これは、CLCF1が運動の良い影響を伝える重要な役割を持っていることを示しています。
■まとめ
〇加齢で筋肉や骨が弱くなるのは、CLCF1というマイオカインが減ることも原因の一つ。
〇運動をするとCLCF1が増え、筋肉の力や骨の強さを保つ助けになる。
〇CLCF1を増やすと、高齢マウスの筋力や骨の密度が改善し、糖の代謝も良くなる。
〇CLCF1をブロックすると、運動の良い効果がなくなる。
CLCF1が筋肉と骨の健康を保つために重要であることは、これまであまり知られていませんでしたが、今回の研究によって、運動がCLCF1を増やし、それが筋肉や骨を強くすることを示したことで、定期的な運動の大切さがわかりました。
将来的には運動が難しい高齢者の筋肉や骨の健康サポートのために、CLCF1を薬やサプリメントとして使うことも考えられますね。
【関連記事】