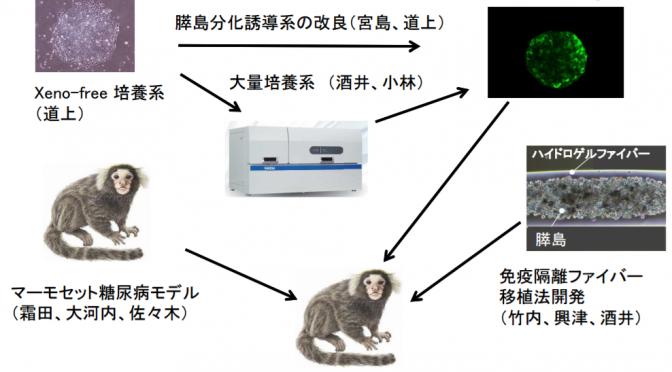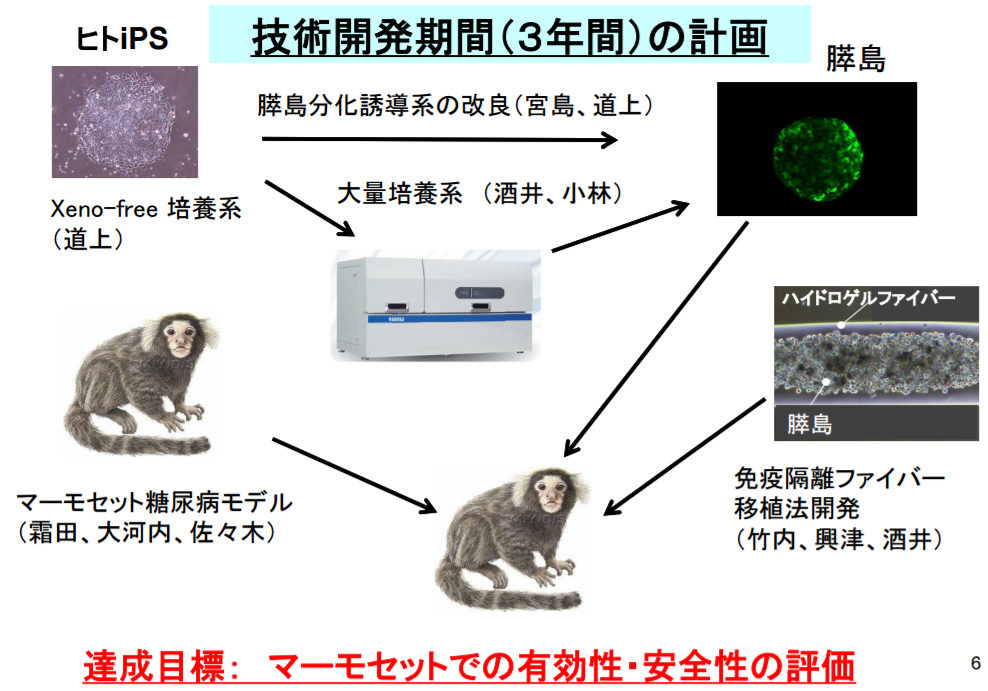■遅い夕食などで食事の時間が乱れると、体内時計が混乱し太ってしまう|早稲田大学
by Torsten Mangner(画像:Creative Commons)
遅い夕食やっぱり太る…体内時計混乱、早大実験
(2012/10/7、読売新聞)
夕食の時間が遅いなど食事の間隔が乱れていると、体内時計がずれることを、早稲田大学の柴田重信教授(薬理学)らの研究チームがマウスを使った実験で明らかにした。
早稲田大学の柴田重信教授らの研究チームによるマウスの実験によれば、夕食の時間が遅くなるなど食事の時間が乱れると、体内時計が乱れるそうです。
体内時計が乱れることにより、肥満や糖尿病になりやすくなります。
生物の体内時計は細胞中の時計遺伝子で制御されている。
1日は24時間だが、体内時計の周期は少しずれているため、光や食事によって補正し、1日のリズムを作っている。
柴田さんらはマウスに1日3回の食事を与え、腎臓と肝臓の時計遺伝子の働きを計測し、体内時計のリズムを調べた。
その結果、人間の朝7時、正午、夜7時に相当する時間に食事を与えた場合は、1日で最も長い絶食時間の後にとる朝食で体内時計がリセットされることが分かった。この朝食の時間が1日の活動リズムを規定する重要な役割を果たしている。
体内時計をリセットする方法は、朝食をとることだと紹介されています。
以前テレビ番組で紹介された方法としては、脳と体(内臓)とは体内時計のリセット方法は違うようです。
- 脳:朝日がリセット方法
- 内臓:朝食がリセット方法(内臓の時計遺伝子をリセットするには、たんぱく質が必要。)
朝から朝日を浴び、朝食(たんぱく質を必ず)をとることで、体内時計がリセットされ、太りにくくなると考えられるようです。
【関連記事】
夜食を取ると、肝臓の「時計遺伝子」が乱れ、代謝異常になり、太りやすくなる?
日本人のエネルギー摂取量の推移(厚生労働省 国民健康・栄養調査結果の概要)によれば、餓死者も出た昭和21年1903kcalに比べて平成20年1867kcalの方が低い。
しかし、日本人男性の肥満率は増加している。
このエネルギー摂取量が減少しているにも関わらず、肥満者数(男性)が増加しているという謎を解く鍵こそ「体内時計」にあるそうです。
時間栄養学とは、体内時計を利用し、食事の摂り方や摂る時間等を実践する最新科学。
■低カロリーなのにコレステロール値を悪化させた本当の原因とは?
栄養クリニックが改善したのは2点。
1 食事の内容
2 食事の時間
■体内時計とは
体内時計とは、体の中にある24時間時計というべきもので、睡眠・血圧・体温のリズムを司っている。
■時間遺伝子とは
体内時計の正体は、遺伝子に組み込まれている。
時計遺伝子とは、体内の様々な臓器の細胞に存在している遺伝子のことで、時間を刻んでいる遺伝子です。
時計遺伝子には、1日24時間を計る仕組みがある。
まず時計遺伝子は細胞内にたんぱく質を分泌させる指令を出す。
このたんぱく質が砂時計でいう砂であり、細胞にたんぱく質がいっぱいになるまでに約12時間かかる。
次に、時計遺伝子は、細胞内にたんぱく質を減らす指令を出す。
再び、たんぱく質が細胞からなくなるまでにおよそ12時間かかる。
このように1周が約24時間となり、その人の生活習慣に合わせて、様々なリズムをコントロールしている。
そして、この時計遺伝子によって、理想的な食事時間も決まっている。
朝食の時間と夕食の時間は起床時間で決まる。
理想的な1日のリズムは、7時起床の場合は、起床から2時間以内に朝食、起床から10時から12時間の間に夕食を摂るのが理想。
起床時間がずれれば、食事時間もずれる。
時計遺伝子が一日ごとにリセットされ、また新たに時計の針を動かしている。
体の場所によってリセット方法が違う。
脳:朝日がリセット方法
朝日を浴びることで脳のリズムがスタート
内臓:朝食がリセット方法
※内臓の時計遺伝子をリセットするには、たんぱく質が必要。
朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かす。
すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまる。
そのため、タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、内臓の機能も低下したままになります。
すると、すでに活性化している脳が、栄養分が入っていないことを感知し、体が飢餓状態にあると判断します。
そのような状態で昼食をとると、飢餓状態に対応するため、体内に脂肪をため込む機能がスタート。
脂肪がエネルギーとして消費されず、コレステロール量が増加してしまう。
■夕食の時間
BMAL1(ビーマルワン)と呼ばれるタンパク質の一種には、体内に脂肪分を取り込む働きがある。
起床後14時から18時間後BMAL1の数が最大に達する。
■食習慣と体内時計が合わないとどうなるのか?
人間は、食事で摂ったカロリーの中から一定量を脂肪としてため込むメカニズムが備わっている。
体内時計と食習慣が合わないと、余計にカロリーを脂肪としてため込んでしまう。
余計にため込むカロリー
朝食抜きの場合、男性100kcal、女性80kcal。
夕食が時間がずれてしまった場合、男性50kcal、女性40kcal。
※香川靖雄先生の研究によると、7200kcalで脂肪1kg相当をため込むことになる。
【関連記事】
- 朝食を抜く食生活をしている人は、動脈硬化を発症するリスクが高くなる
- 時間栄養学と体内時計とダイエット
- 体内時計制御する遺伝子、太った人は働き異常 減量で正常化
- 体内時計活用術|たけしの本当は怖い家庭の医学