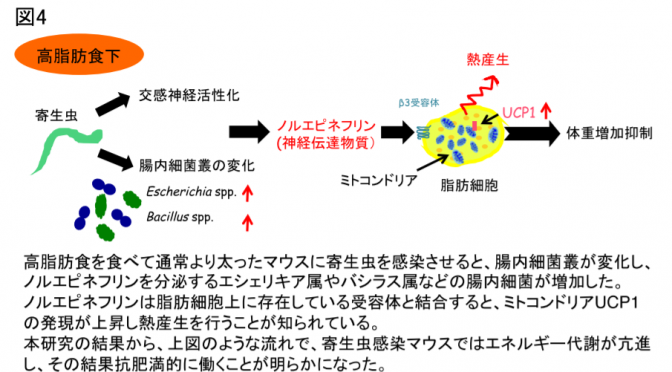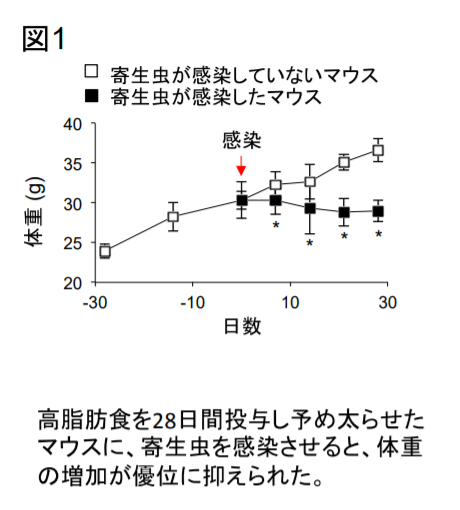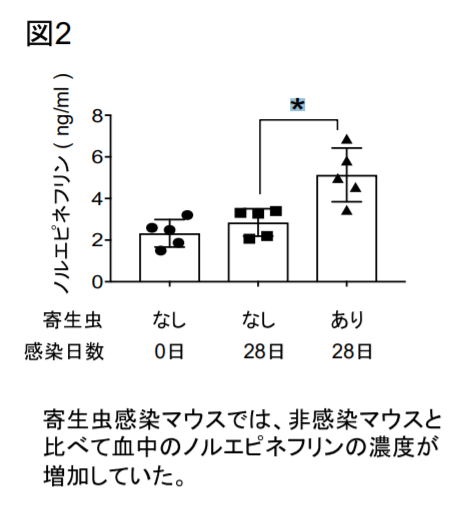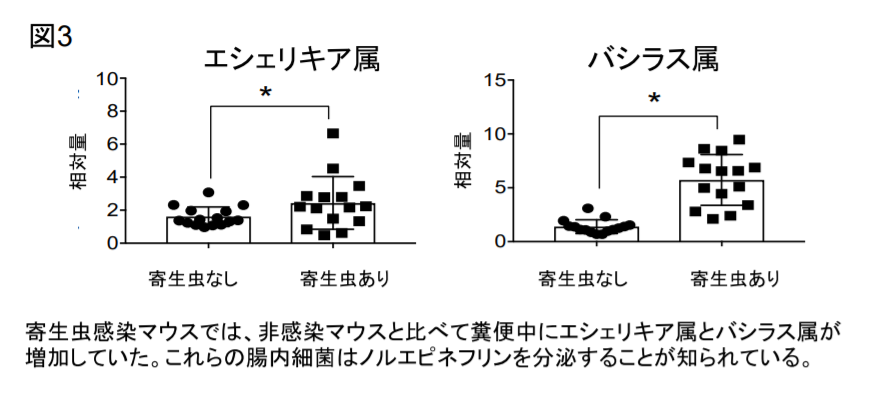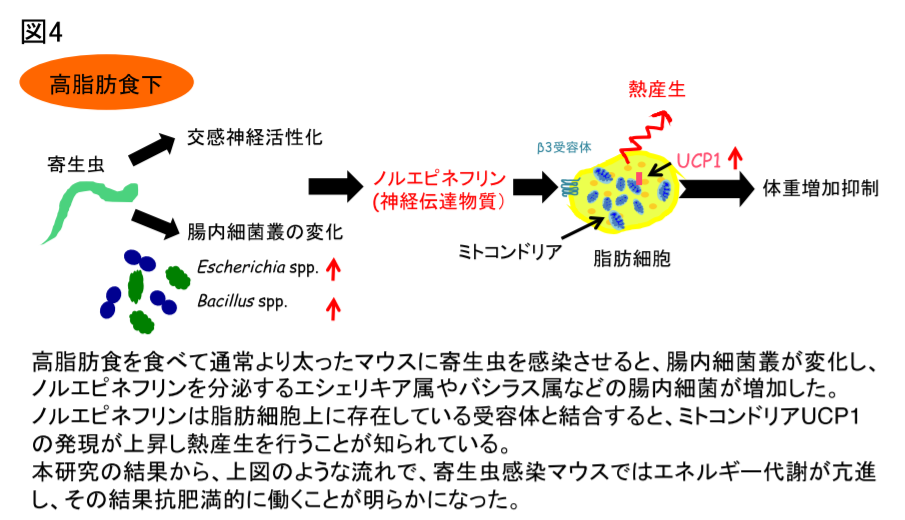学術誌「Nature Microbiology」で発表された研究によれば、食べ物によって腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう;マイクロバイオーム)が変わり、そしてそれが健康に直結していることがわかります。
【参考リンク】
- Fackelmann, G., Manghi, P., Carlino, N. et al. Gut microbiome signatures of vegan, vegetarian and omnivore diets and associated health outcomes across 21,561 individuals. Nat Microbiol 10, 41–52 (2025). https://doi.org/10.1038/s41564-024-01870-z
今回紹介する論文は「普段の食事がおなかの中の細菌である腸内細菌叢(gut microbiota)にどう影響するか」を大規模に調べた研究で、具体的には、雑食(肉・乳製品・野菜なんでも食べる)、ベジタリアン(肉は食べない)、ビーガン(肉も乳製品も食べない)の3つのグループを比べて、腸内細菌がどう違うかを5つの多国籍コホート(合計21,561人)のデータを用いて分析しています。
■【補足】腸内細菌叢って何?
腸内細菌叢は、腸に住む何兆もの微生物のコミュニティで、消化や免疫、心臓代謝の健康に深く関わっており、食べ物の種類によって細菌の種類や働きが大きく左右するため、食習慣が健康や病気リスクにどうつながるかを理解する鍵になります。
■研究の方法
研究では、イギリス、アメリカ、イタリアから集めたデータを統合し、雑食(19,817人)、ベジタリアン(1,088人)、ビーガン(656人)の便を調べて、細菌のDNAを解析し、「どんな食事を普段してますか?」というアンケートをもとに3つのタイプに分類しました。
雑食:肉、乳製品、野菜なんでも食べる。
ベジタリアン:肉はNGだけど、乳製品や野菜はOK。
ビーガン:肉も乳製品も一切食べず、植物性のものだけ。
■わかったこと
●食事で細菌が変わる!
雑食:牛肉などの赤肉と関連が強い細菌(Ruminococcus torques、Bilophila wadsworthiaなど)が優勢で、これらは心臓代謝マーカー(血圧やコレステロール)と負の相関(マイナスの影響)で、健康リスクと関連。
ビーガン:野菜や果物を食べると増える、植物繊維を分解する細菌(Lachnospiraceae、Roseburia hominisなど)が多く、心臓代謝マーカー(心臓とエネルギー代謝)に良い影響。短鎖脂肪酸(SCFA)の産生が活発で、炎症抑制や腸バリア強化に寄与。
ベジタリアン:中間的な特徴で、乳製品由来の細菌(Streptococcus thermophilusなど)が目立つ。
●肉 vs 植物:細菌の機能が対照的
肉をたくさん食べる雑食の人は、細菌が肉を分解するのに慣れていて、雑食の細菌は、肉のたんぱく質を分解して(タンパク質発酵)、トリメチルアミン(TMA)を生成し、これがTMAO(心血管疾患リスク因子)に変換される。
ビーガンの細菌は、植物多糖を分解して「短鎖脂肪酸(SCFA)」という健康にいい物質を作り、健康的な腸環境をサポート。ポリフェノール代謝も活発で、抗炎症作用、腸を強くする効果が期待できる。
●食べ物から細菌が入ってくる
乳製品を食べる雑食やベジタリアンでは、ヨーグルトやチーズの細菌(S. thermophilusなど)が腸に定着。
ビーガンでは、野菜についた土壌細菌(Enterobacter hormaecheiなど)が多く、野菜経由で移行してる可能性。
●健康への影響
雑食の細菌は、心臓や血管の病気リスクと少し関連がありそうで、ビーガンの細菌は、心臓代謝のマーカーが良くて、病気予防に役立つ可能性が高い。
■まとめ
今回の研究のポイントは、食事で細菌をコントロールできる、例えば肉多めだと心臓リスクが上がる細菌が増え、植物多めだと健康的な細菌が育つということです。
腸内細菌を「細菌の町」だとたとえてみると、雑食の人は「肉屋」が多くて、ビーガンは「八百屋」が多く、ベジタリアンはその中間で「乳製品屋」もあるイメージ。町の住人(細菌)は、どんなお店が多いかで決まる。
腸内細菌を「生態系」と捉えてみると、雑食は「肉食動物が支配する森」、ビーガンは「植物が豊かな草原」、ベジタリアンは「乳製品の牧場もある中間地帯」で、どんな食事をするかでどんな生態系を作るか、そして健康になるかが決まる。
【補足】
腸を健康に保つ秘訣、意外と簡単な食事のポイントとは、最新研究から専門家がアドバイス(2025年3月18日、ナショナルジオグラフィック)では今回の研究に関連して3つ気になることが書かれていました。
1)同じ野菜ではなくいろんな野菜を食べることで体に良い影響がある
もし毎日ケールのサラダばかり食べているとしたら、ケールを好む細菌だけが餌をもらっていることになる。キャベツを好む細菌もいれば、メキャベツを好む細菌、キヌアを好む細菌もいる。さまざまな微生物に餌を与えることで、さまざまな短鎖脂肪酸が作られ、体にさまざまな良い影響をもたらす。
研究の中では野菜をとることが腸内細菌叢にとってよいことだということでしたが、同じ野菜ばかりを食べていてはその野菜を好む細菌だけが餌をもらっていることになるため、腸内細菌叢をよくするためにはいろんな野菜を食べたほうがいいということですね。
2)フィトケミカル(ファイトケミカル)
また、カラフルな植物はファイトニュートリエント(植物栄養素、ポリフェノールやカロテノイドなど)の宝庫でもある。例えばその一つであるさまざまな抗酸化物質は、炎症を防ぐ細菌の増殖を促すなどして、慢性疾患から体を守る働きをする。
がんリスクを下げる抗ガン食材とはどんな食べ物なの?で紹介した野菜の色の成分「フィトケミカル(ファイトケミカル)」とは、植物性食品に含まれる物質の総称のこと。
植物性食品には、ビタミンやミネラルなどの栄養素、食物繊維などが含まれていますが、フィトケミカルとは、「色」「香り」「苦味」といった今まで栄養素とは考えられていなかった成分のことをいいます。
食物の5大栄養素は、炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルであり、近年、食物繊維が第6の栄養素として注目を集めました。
そして、今まで食物繊維同様、栄養素と考えられていなかった「色」「香り」「苦味」等の植物性食品の成分のフィトケミカルが第7の栄養素として取り上げられるようになりました。
「色」「香り」「苦味」が実は栄養素であり、同じ野菜ばかりを食べるのではなく、いろんな色の、香りの、苦みの野菜を食べることが健康に良いのではないでしょうか?
【関連記事】
3)ヴィーガンの腸内にはプロバイオティクスがない
セガタ氏らはさらに、ビーガンの腸内にはチーズ、ヨーグルトなどの発酵乳製品に含まれる有益なプロバイオティクス(腸内微生物叢の多様性を高める生きた微生物)がないと指摘している。
発酵乳製品をとらない食生活と摂る食生活で腸内細菌叢が変わるのは間違いがなく、それがどのような影響を与えるのかが気になるところです。
【関連記事】
- プロバイオティクス飲料の継続摂取が日本人2型糖尿病患者の腸内フローラを変化させ、慢性炎症の原因となる腸内細菌の血液中への移行を抑制|腸管バリア機能強化による慢性炎症抑制の可能性|順天堂大学
- 乳酸菌(ガセリ菌)が「脳腸相関」を介してストレス性の不調・腹痛(便秘・下痢症)・不眠の改善効果を実証|#カルピス #徳島大
- 花粉症を抑えるには、乳酸菌で腸内環境を整えるといい!?|乳酸菌ヨーグルトの摂取量・選び方のポイント
- 腸内細菌を元気にすると糖尿病になりにくくなる!?|血糖値が下がりやすい体質にする方法
- 肥満やメタボの第3の要因に腸内フローラ(腸内細菌叢)が関係している?和食を食べて予防しよう!
「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」
この街を初めて訪れた方へ
この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。
この街には、生活・料理・健康についての記事が、
同じ考え方のもとで並んでいます。
ここまで書いてきた内容は、
単発の健康情報やレシピの話ではありません。
この街では、
「何を食べるか」よりも
「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。
もし、
なぜこういう考え方になるのか
他の記事はどんな視点で書かれているのか
この話が、全体の中でどこに位置づくのか
が少しでも気になったら、
この街の歩き方をまとめたページがあります。
▶ はじめての方は
👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。
▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)
※ 無理に読まなくて大丈夫です。
気になったときに、いつでも戻ってきてください。
この考え方の全体像(意味のハブ)
この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。
▶ 料理から見る健康
この街の考え方について
この記事は、
「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」
という この街の憲法 に基づいて書かれています。
▶ この街の中心に置いている憲法を読む