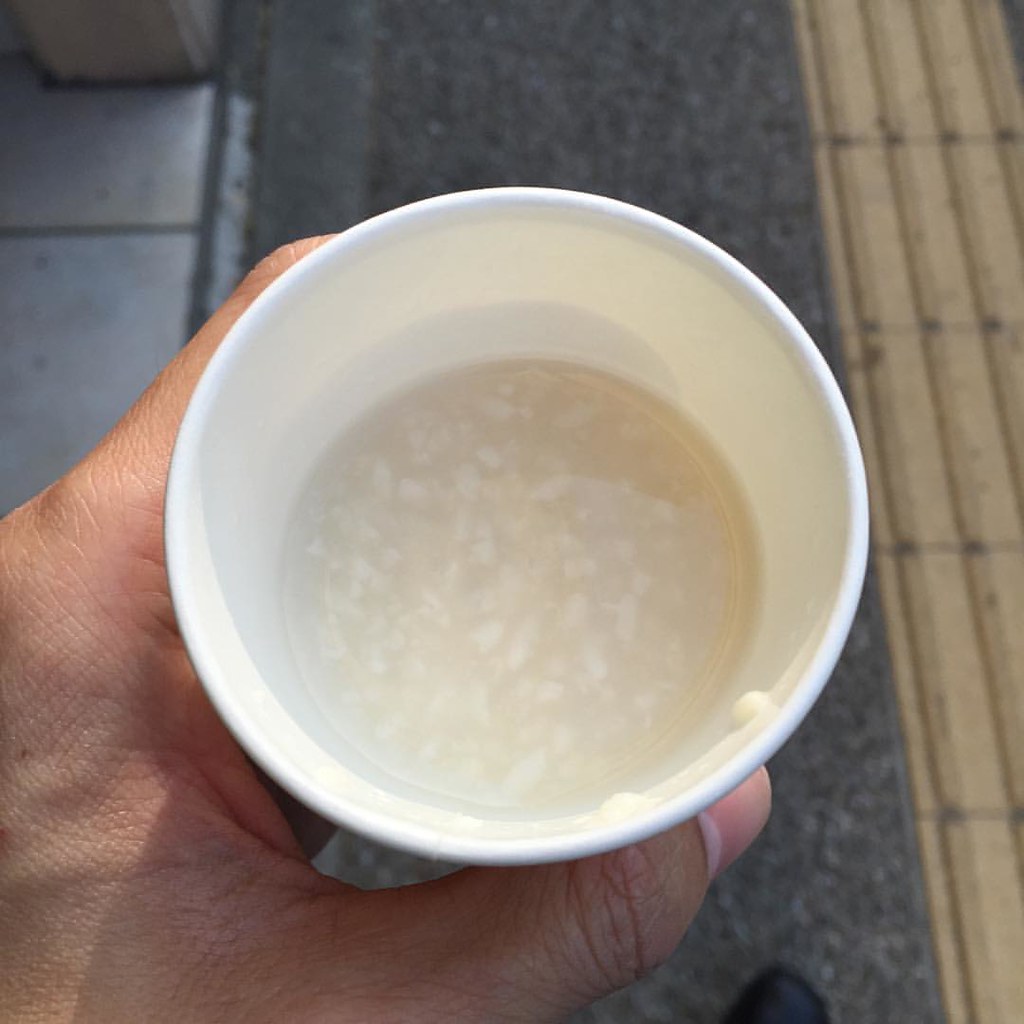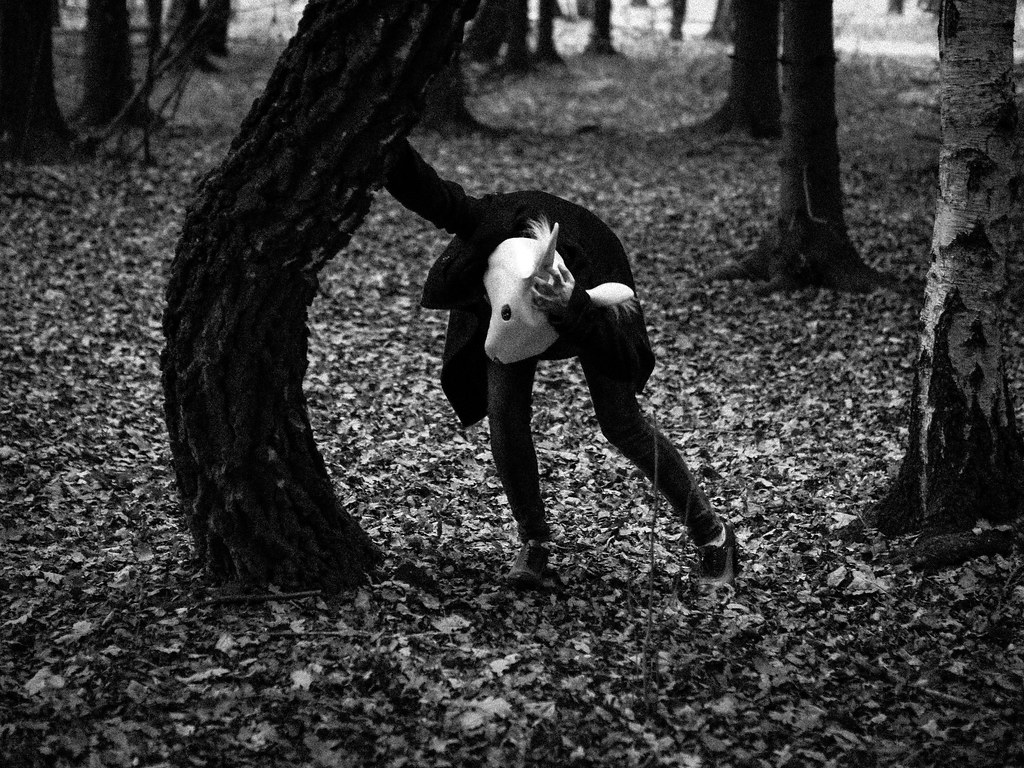2010年10月19日放送のたけしの家庭の医学では「PEM(たんぱく質・エネルギー欠乏症)」を取り上げました。
【目次】
- PEM(たんぱく質・エネルギー欠乏症)とは
- PEMの原因とは
- なぜアルブミンとヘモグロビンが不足したのか?
- なぜ栄養失調が増えているの?
- なぜ栄養失調が増えているの?
- たんぱく質が不足するとどうなるの?
- なぜたんぱく質が不足してしまうの?
■PEM(たんぱく質・エネルギー欠乏症)とは
by Osamu Kaneko(画像:Creative Commons)
たんぱく質とエネルギーが足りていない、栄養不足の状態。
なんと飽食とよばれる現代で、65歳以上の4人に1人がこの状態だといわれている。
そして、そのまま放っておくと、身体を動かす筋肉量が減少。
さらに風邪などから身体を守る抵抗力が弱まるなど、様々な身体機能の低下がおこる。
近年、お年寄りの寝たきりや死亡原因の一つとして、早期発見の重要性が叫ばれている。
PEM(protein-energy malnutrition)とは、たんぱく質・エネルギーが欠乏している、新しい栄養失調(低栄養)の状態ともいえます。
この状態がそのまま続くと、筋肉量の減少や抵抗力の低下などが起こり、寝たきりの原因ともなるそうです。
■PEMの原因とは
主な原因は、血中にある「健康配達成分」と呼ばれる重要な成分が不足すること。
その成分とは、アルブミンとヘモグロビン。
そもそもアルブミンとヘモグロビンとは「たんぱく質」から作られる成分のこと。
血中で様々な栄養素やホルモン、酸素を運び、身体中の細胞を活性化させるという、重要な働きがあります。
年を重ねてからアルブミンとヘモグロビンが不足すると、身体中に栄養と酸素が行き届かず、細胞が脆くなり、その結果、脳卒中や心筋梗塞といった血管の病を引き起こしやすくなるのです。
PEMの原因とは、アルブミンとヘモグロビンが不足していること。
アルブミンとヘモグロビンが不足することにより、体に栄養と酸素が行き渡らず、身体機能の低下が起こるようです。
■なぜ、アルブミンとヘモグロビンが不足したのか?
今回番組で取り上げたケースでは、60代になってから食事のメニューを肉料理から魚料理中心のメニューに変えたことが原因でした。
タンパク質の量は厚生労働省が推奨している数値を満たしていたのですが、カロリーは必要とするカロリーよりも低かったのです。
たんぱく質は十分なのに、カロリーが不足している食事。
そこにこそ、アルブミン、ヘモグロビン不足の原因があったのです。
実は、カロリーが不足すると、体内ではたんぱく質の使われ方にある変化が。
足りないカロリーを補うため、なんとたんぱく質が「糖分」に変えられてしまうのです。
このアルブミンとヘモグロビンが減少してしまった血液こそ、長生きできないといわれているヘロヘロ血の状態。
だからこそ、ヘルシーでカロリーレスな食事にする時は、より多くのたんぱく質を摂る必要があるのです。
■お肉はバランス栄養食品
お肉はタンパク質が豊富でバランス栄養食品です。
野菜よりも鉄分が豊富で、かつ肉は野菜より鉄分の吸収率が5から10倍高い。
またビタミンも豊富で、特にビタミンB1は豚ヒレ肉100gでレモンの17倍含んでいるそうです。
さらにミネラルも豊富なのだそうです。
【感想】
日本人が長寿になったのは、日本食+欧米食になったことで、今までの植物性食品に加えて、動物性食品・油脂を摂取するようになったからだとも言われています。
最近の健康志向により、低カロリーのものを選んで食べていらっしゃる方も多いと思います。
ただ、年を重ねるにつれて、食事が細くなり、十分な栄養を取れないことも多いようです。
それぞれの食品・栄養素が持つ役割を知った上で、その年代に合わせた食事をしていきたいですね。
■なぜ栄養失調が増えているのでしょうか?
この栄養失調は、血液中の「ある物質」が不足することによってなるそうです。
この物質が足りないと、血管や免疫細胞、筋肉などの組織がスムーズに作られなくなり、体にさまざまなトラブルが起こってしまうそうです。
このある物質とは、「アルブミン」。
アルブミンとはタンパク質の一種で、血液を流れている血清タンパク質のおよそ6割を占めています。
つまり低栄養とは「タンパク質不足」のことなのです。
■たんぱく質が不足するとどうなるのでしょうか?
赤血球の材料が少ない→「貧血」
血管を作る材料が少ない→「脳出血」
免疫細胞を作る材料が少ない→「肺炎」「結核」
筋肉を作る材料が少ない→「転倒」→「骨折」
■なぜたんぱく質が不足してしまうのでしょうか。
低栄養になった人の食事を見てみると、食に偏りがありました。
以前は、家族のために栄養を考えて、肉や卵などを使って料理をしていたのですが、一人暮らしになってから、自分が好きなものだけを食べるようになり、肉や卵を使った料理を食べなくなってしまい、たんぱく質が不足してしまったようです。
高齢者の孤食が「低栄養」になるリスクを高めてしまうようです。
3 お肉を食べよう
動物性食品や油脂類を摂ることにより、コレステロール値が上昇すると心配する人が多いようですが、血清コレステロール(血液中のコレステロールの濃度)は加齢に伴って自然と減少するため、高齢者が動物性たんぱく質や油脂をあまり摂らずにいると、栄養状態は悪くなってしまいます。
高齢者における総死亡(全死因)の危険率と血清コレステロールの関係をみると、75歳以上の女性では、コレステロール値の低い群ほど総死亡危険率が高く、男性ではコレステロール値と総死亡危険率は無関係でした。
高齢期でも、コレステロールを摂取することがとても大切です。
若い女性の中には、ダイエットのために、動物性食品や油脂類を摂取することを過剰に避けたりする人もおり、また高齢者になると自然と動物性たんぱく質や油脂をとらない食事をしてしまい、低栄養になってしまう人がいるようです。
簡単にまとめてみます。
日本人の平均寿命が伸びてきた理由の一つに、これまで日本人が続けてきた食事が変化したことが挙げられます。
※もちろん、衛生環境の改善、医療の進歩もその要因の一つです。
2 「寿命の延び」と「食生活」の関係
昭和40年以降、魚に加えて、牛乳・乳製品、肉類、卵類の動物性食品と、油脂類をとる量が増えていることが分かります。
日本食+欧米食になったことで、今までの植物性食品に加えて、動物性食品・油脂を摂取するようになったことが寿命が延びている理由と考えられるようです。
こうした食生活の変化により、血管をしなやかで丈夫に保つために必要な栄養素(質の良い動物性のたんぱく質やコレステロールなど)が摂取でき、血管が弱っておこる脳卒中(脳出血・脳梗塞)が減少しました。
戦後の日本人の平均寿命の延びには、このような食生活の変化による脳卒中の死亡率の減少が、大きく影響しています。
つまり、適度に欧米化した食生活により、栄養状態が改善されて、日本人の平均寿命は大きな延びを示したのです。
適度に欧米化された食生活により、質の良い動物性たんぱく質やコレステロールを摂取することになったことで、日本人の平均寿命は大きく延びたということですね。
5 老化予防はいまからでも遅くない
老化の原因を探るため、秋田県南外村に住む高齢者約1,000人を対象に健康調査を行いました。
食生活についてとくに改善の指導を行わないでいると、年齢とともに肉類や油脂類をとる量が減り、それに伴い血清アルブミン(※1)や血色素(※2)の値も低くなってしまいます。
ところが、下記「食生活指針」そった食生活を実践してもらったところ、アルブミンは増加し、血色素の低下も見られなくなりました。栄養改善の効果があらわれたのです。
この調査から、年をとってからでも、正しい食生活のあり方を伝えれば、十分実践でき、そして、健康状態が改善できるといこうとが分かりました。
<中略>
※1 血清アルブミンとは、肝臓で合成され、血液中を流れるたんぱく質の一種です。
※2 血色素(ヘモグロビン)は、血液中の赤血球に含まれる色素で、酸素を全身に運ぶ働きがあります。減少すると貧血をまねき、生活機能が低下しやすくなります。
高齢者の食生活は、年齢とともに肉類や油脂類を摂る量が減ってしまい、血清アルブミンや血色素の値が低くなっているようです。
これが貧血を招く原因のようです。
食生活指針とは一体どのようなものなのでしょうか。
6 元気で長生きのための「15の食生活指針」
① 3食のバランスをよくとり、食事を抜かずにきちんと食べましょう。
② 油脂類の摂取が不足しないようにしましょう。
③ 肉、魚、乳製品、卵などの動物性たんぱく質を十分に食べましょう。
④ 肉と魚の摂取は1:1の割合にしましょう。
⑤ いろいろな種類の肉を食べましょう。
⑥ 牛乳は毎日200ml以上飲むようにしましょう。
⑦ 野菜は緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草など)や根菜(大根、ごぼう、いもなど)など、いろいろな種類を毎日食べるようにしましょう。
⑧ 食欲がないときは、おかずを先に食べ、ご飯の量を減らしましょう。
⑨ いろいろな調理のしかたや、食品の正しい保存法を覚えましょう。
⑩ 酢、香辛料、香り野菜(ねぎ、にんにくなど)を十分に取り入れましょう。
⑪ 調味料を上手に使い、おいしく食べましょう。
⑫ 和風、中華風、洋風といろいろな料理を食べましょう。
⑬ 家族や友人との会食の機会をたくさんつくりましょう。
⑭ 噛む力を維持するために、義歯は定期的に点検をしましょう。
⑮ 「元気」のための健康情報をすすんで取り入れましょう。
2から6までの5項目が、低栄養を防ぐための動物性食品や油脂類の摂り方に関する項目なのだそうです。
ぜひご自身の食生活と比べて、参考にしてみてくださいね。
【感想】
糖尿病や高血圧などの生活習慣病を予防する食事をすることが、高齢者の食事として必ずしも良いというわけではないのですね。
簡単にバランス良い食事をすることが大事といってしまいがちですが、それぞれの食品・栄養素が持つ役割を知った上で、その年代に合わせた食事をしていきたいですね。
→ アルブミンを上げる食事|肉を食べてアルブミンを上げたグループは死亡リスクが低い!? について詳しくはこちら
【関連記事】
続きを読む アルブミン・ヘモグロビン不足で低栄養/PEM(たんぱく質・エネルギー欠乏症)|高齢者の寝たきりの原因の一つ!?|#たけしの家庭の医学