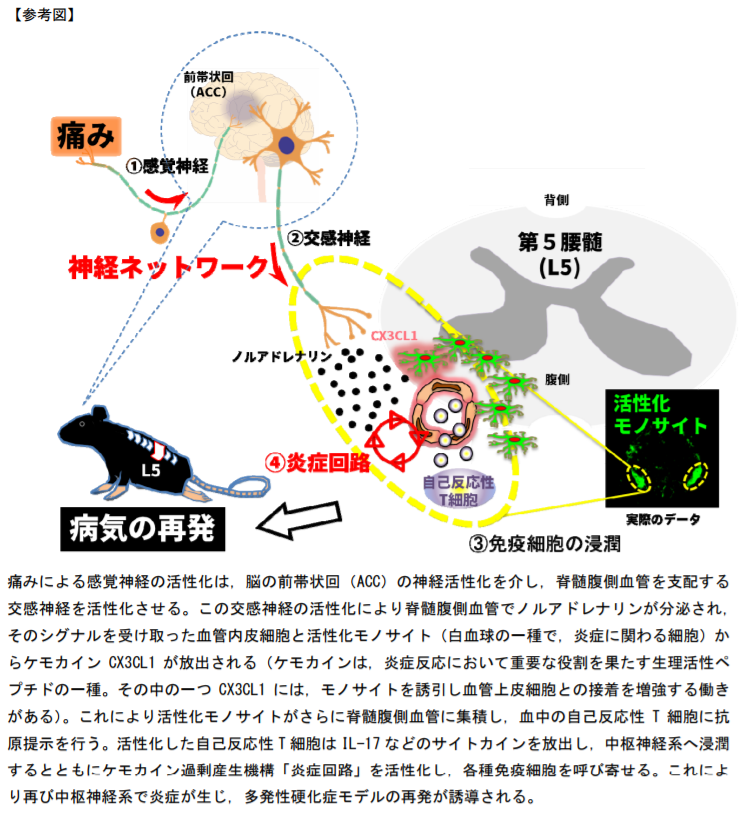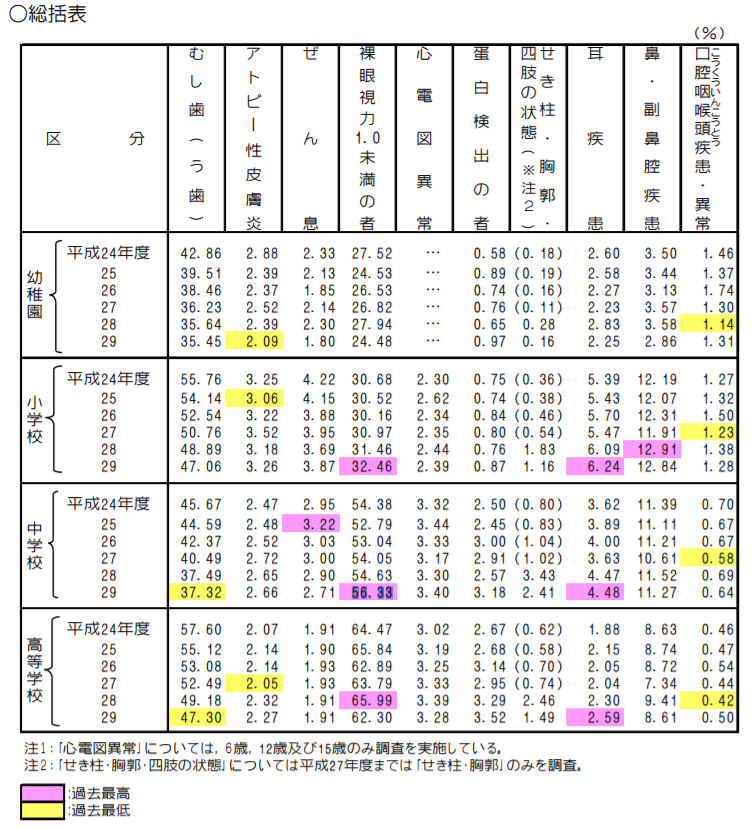> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 白米を多く食べるアジア人、糖尿病リスク55%増|米ハーバード大研究
■白米を多く食べるアジア人、糖尿病リスク55%増|米ハーバード大研究
白米を多く食べるアジア人、糖尿病リスク55%増 米研究
(2012/3/16、AFPBB)
白米を多く食べると2型糖尿病の発症リスクが高まる恐れがあるとの研究を、米ハーバード大の研究者らが15日の英医学誌「ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル(British Medical Journal、BMJ)」に発表した。2型糖尿病は一部の国で患者数が急増している。
米ハーバード大の研究者らによれば、白米を多く食べると2型糖尿病の発症リスクが高まるおそれがあるそうです。
→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら
孫氏の研究チームは、日本、中国、米国、オーストラリアで過去に行われた研究結果を再分析。のべ35万人以上の4~25年間にわたる追跡調査で、1万3000人以上が2型糖尿病を発病していることを確認した。
分析によれば、日中で実施された過去の調査では1人あたり1日平均3~4杯の米を食べていたが、米を多く食べた人では2型糖尿病リスクが55%高まった。一方、1週間に平均1~2杯と米の消費量が圧倒的に少ない米豪では、リスク上昇率は12%にとどまった。
米を多く食べた人は2型糖尿病の発症リスクが55%高まったそうです。
孫氏はこの分析について、調査対象者の食生活について米以外の詳細な情報がないこと、4つの異なった調査をメタ分析したものであることを指摘。
結果に100%の確証は得られないとしつつ「調査内容には一貫性があり、白米と糖尿病が関連しているという生物学的妥当性も見いだせる」と結論付けている。
その上で、より詳細な調査の必要と、糖分や脂肪分を多く含む食品への引き続きの注意を呼びかけている。
白米は世界で最もよく食べられている米の形態で、もみ米を脱穀・精米して作られ、成分のほとんどがでんぷんになる。
精白前の玄米は繊維やマグネシウム、ビタミンを多く含み、血糖値の上昇しやすさを示す「グリセミック指数(GI値)」も白米と比べて低い。
今回の研究では、白米と糖尿病が関連しているというものでしたが、これまで見てきた様々な記事を見るかぎり、日本人を含むアジア人は糖尿病になりやすいのではないかと思われます。
もちろん白米は血糖値が上昇しやすい(GI値の高い)食品であることは間違いないですが、糖尿病“やせ”の人こそ要注意|日本人の2型糖尿病の半数以上は標準体重以下かやせ形によれば、アジア人は欧米人に比べて体質的に血糖値を下げるインスリン分泌能力が低いため、太っていなくても糖尿病になりやすいため、たとえやせていたとしても糖尿病になる可能性があるということでした。
糖尿病“やせ”の人こそ要注意|日本人の2型糖尿病の半数以上は標準体重以下かやせ形
肉中心の食事では多量のインスリンを必要とするため、欧米人はインスリンを多く作れる体質になった。一方、穀物中心のアジア人の体はインスリンの分泌が少量でよかったのです」
ところが、日本人の食生活がほんの50年余りの間に激変。
インスリンの分泌が少ない体に必要以上の欧米化した高脂肪・高カロリー食が流し込まれるようになった。
加藤院長は、「少し体重が増えただけでもインスリン不足になり、肥満になる前に糖尿病になってしまう」と説明する。
「日本人は糖尿病になりやすい」認知度は4割未満
以前の記事(「やせ形で糖尿病」リスク遺伝子発見-東大)によれば、遺伝子変異により、KCNJ15と呼ばれる遺伝子の働きが過剰に高まり、インスリンの分泌が不足するため、痩せ型でも糖尿病を発症する危険性が高まるのだそうです。
欧州の糖尿病患者には肥満が多いのに対して、日本を含むアジア各国では、肥満でない人の発症が多いそうです。
日本人は太っていなくても糖尿病になりやすい体質を持っているため、「自分は太っていないから糖尿病は大丈夫」と思うのではなく、生活習慣を見直し・改善するようにしてください。
■玄米と糖尿病の関係
●玄米に含まれる「ガンマオリザノール」に糖尿病の改善・予防効果|琉大など研究グループ
●玄米のΓオリザノールが脳に働きかけ高脂肪食への誘惑を軽減する?
●<糖尿病>ごはんで女性の発症リスク増
●ブラウンフードダイエットとは?|低GIの食べ物を選んでダイエット
●糖尿病の予防には白米などの精白した穀物より玄米などの全粒穀物を食べる人のほうがよい|米ハーバード大
同チームでは、日常的に摂取する白米の3分の1を玄米に置き換えることにより、2型糖尿病の発症リスクが16%下げられると推定。
また、日常的に摂取する白米すべてを玄米などの全粒穀物に置き換えれば、同リスクは最大36%下がると見積もっている。
エリカ・アンギャルさんおすすめ!ダイエット7つの食材|たけしの健康エンターテイメント!みんなの家庭の医学
雑穀米には食物繊維やビタミンが多く含まれている。
食物繊維には、便通の改善、コレステロールの低減に効果がある。
エリカ・アンギャルさんが、食物繊維を薦めるには、もうひとつ理由があります。
それが、GI値。
GI値(グリセリック・インデックス:血糖値の上がりやすさの指標)はエリカ・アンギャルさんのダイエット法の中核をなす考え方。
消化しやすい食品を食べると血糖値が急激に上がる。
⇒インスリンが大量に分泌され、残った糖を脂肪に変えてしまう。
つまり、血糖値を急激に上げないことが、太りにくい体を作ることにつながるということです。
GI値が低い繊維質の食べ物は血糖値が上がりにくい。
■まとめ
米ハーバード大の研究者らによれば、白米を多く食べると2型糖尿病の発症リスクが高まるおそれがあるそうです。
ただ、これまでのニュースをまとめると、ポイントは白米の食べ過ぎというよりも、インスリンの分泌量に問題があるのであって、白米だけではなく、玄米・雑穀米をとり入れることが糖尿病の予防・対策になるのではないでしょうか。
→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら
→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら
 糖尿病関連ワード
糖尿病関連ワード
続きを読む 白米を多く食べるアジア人、糖尿病リスク55%増|米ハーバード大研究 →