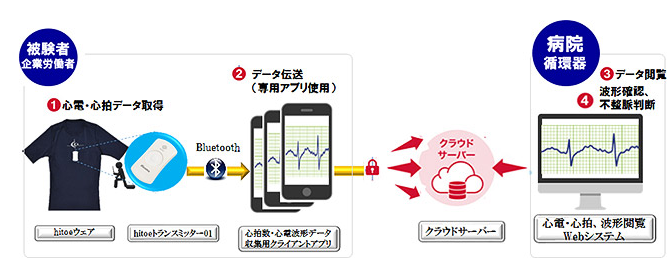by Jon Bunting(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 肺の病気 > COPD > 「肺の生活習慣病=COPD」の疑いがある人の受診率は1割未満
■「肺の生活習慣病=COPD」の疑いがある人の受診率は1割未満
(2009/12/21、キャリアブレイン)
喫煙習慣が主な原因で、今回の新型インフルエンザではワクチン優先接種の対象疾患にもなっているCOPD(慢性閉塞性肺疾患)。
その疑いがある人のうち医療機関を受診したことがあるのは1割にも満たないことが、日本ベーリンガーインゲルハイムとファイザーの調査で明らかになった。
ファイザーでは、「肺の機能は年齢とともに衰えるが、COPDになるとその衰え方が激しくなる。
COPDの原因の大半がたばこであり、喫煙習慣を見直すことで、急激な肺機能の悪化を抑えることができる」などと指摘し、今後も疾患の啓発に努めたいとしている。
COPDの疑いがある人のうち、医療機関を受診したことがある人は1割未満だったそうです。
COPDの主な原因がタバコであるので、喫煙習慣を見直し、できれば禁煙をして、肺機能の悪化を食い止めましょう。
→ COPDの症状・原因・チェック・予防 について詳しくはこちら
【COPD関連記事】
- COPDチェック|たけしの本当は怖い家庭の医学
- 藤田まこと、病気(COPD:慢性閉塞性肺疾患)のためドラマ『JIN -仁-』を降板
- せきとたんが止まらない時の原因とは?病気を見分ける方法・ポイント
- たんが出る|痰の色(黄色・緑)や原因でどんな病気かがわかる!?
- 咳の音から診断して、肺炎や喘息、気管支炎などを診断するアプリ
- 【林修の今でしょ講座】正しい呼吸法にするためのストレッチ方法で肺機能若返り|3月1日
- 「WING」|ぜんそくやCOPDなどの肺機能の低下を早期発見する肺の健康のための「体温計」
- #土屋太鳳 さんの肺活量は成人女性の2倍近い5210㏄|肺年齢を呼吸機能をチェックし肺の病気を予防しよう!
公開日時: 2010年1月19日 @ 06:51