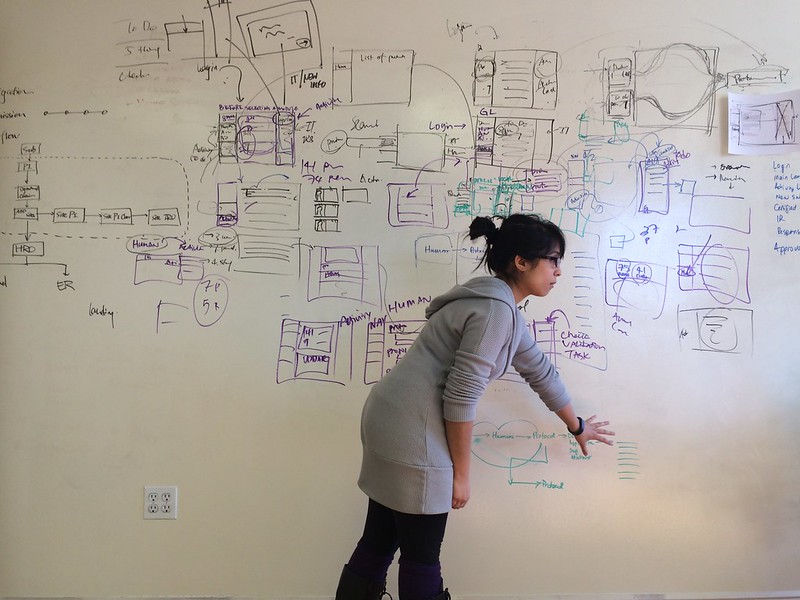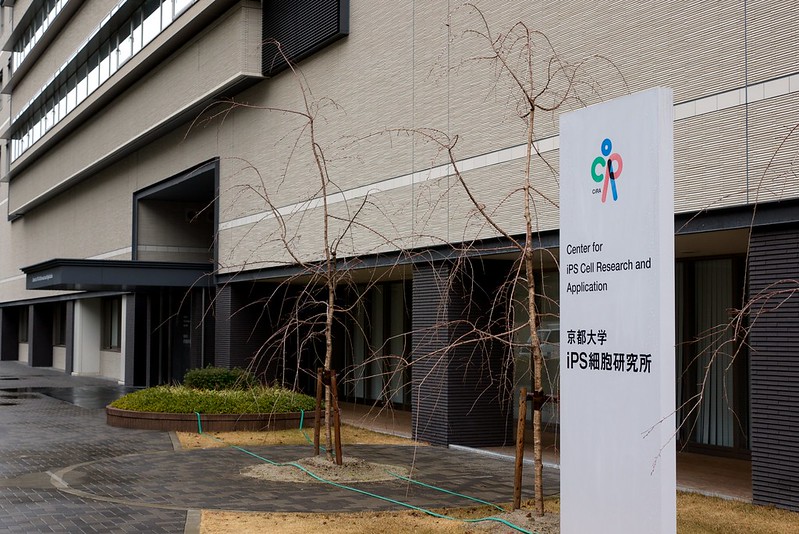by U.S. Department of Agriculture(画像:Creative Commons)
2015年3月22日放送の駆け込みドクターのテーマは「超人間ドックスペシャル」です。
番組予告によれば、次のことを取り上げるようです。
●心血管が石灰化?「動脈硬化性プラーク」とは?
コレステロール(悪玉コレステロールを下げる・善玉コレステロールを増やす)|世界一受けたい授業 2月28日によれば、コレステロールの数値が基準値内の範囲であっても、悪玉コレステロール値が善玉コレステロール値の2倍以上あると、コレステロールが血管内にプラークとして残ってしまい、動脈硬化になる恐れがあります
→ 動脈硬化の症状・予防・原因・改善 について詳しくはこちら
→ 悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を下げる方法 について詳しくはこちら
→ 善玉コレステロールを増やす方法 について詳しくはこちら
動脈硬化性プラークで、血管にカルシウムが沈着、石灰化している場合は、非常に危険なのだそうです。
原因はカルシウム不足。
カルシウムを含む食品を摂るようにしましょう。
【関連記事】
●コレステロールの過剰摂取が原因?「胆石症」とは?
胆石とは、肝臓から送り出された脂質の消化吸収を助け、老廃物を流す胆汁に含まれる成分(コレステロールやビリルビンなど)が胆嚢(たんのう)の中で石として固まったものです。
番組では、胆石症の予防として、食物繊維を摂ることやタウリンを含む食品をとることをおススメしていました。
→ 胆石症の症状・原因・予防 について詳しくはこちら
●夜間頻尿
●ピロリ菌による「萎縮性胃炎」
「慢性胃炎」とは、胃の粘膜に白血球が集まって、常にじわじわとした慢性的な炎症を起こしている状態を言います。炎症が長い間続き胃粘膜の障害が進むと、胃酸を出す胃腺というものがひどく縮小して、胃の粘膜がうすくぺらぺらになってしまいます。すなわち、慢性胃炎が長く続いた結果として、胃の粘膜が萎縮した状態を「萎縮性胃炎」というわけです。す
みぞおちの痛み、食欲不振、食後の膨満感、胸やけ、げっぷ、悪心、嘔吐などの症状がある状態を慢性胃炎といいます。
慢性的な炎症が長い間続き胃粘膜の障害が進み、胃酸を出す胃腺が縮小して、胃の粘膜が萎縮した状態を「萎縮性胃炎」と呼ぶそうです。
→ 胃炎|慢性胃炎・急性胃炎の症状・原因・対策 について詳しくはこちら
【関連記事】
●胃がん
胃がんの原因としては、最近の研究によって、ヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)が大きく関わっているのではないかと考えられています。
→ 胃がん|胃がんの症状・原因 について詳しくはこちら
●大腸がん
胃ポリープができやすい体質であると腸ポリープもできやすく、腸ポリープは放っておくとがん化する(=大腸がん)場合があるそうです。
→ 大腸がんの症状 について詳しくはこちら
●急性すい炎
急性すい炎はすい臓にある酵素がすい臓自体を自己消化してしまう病気。
膵炎の原因としては、胆石症やアルコールの飲み過ぎがほとんどの原因と言われています。
→ 膵炎|急性すい炎の症状・原因・食事 について詳しくはこちら
●すい臓がん
すい臓がんの症状として共通しているのが、胃のあたりや背中が重苦しい、お腹の調子がよくない、食欲不振やだるさ、体重の減少などがありますが、いずれもすい臓がん特有の症状ではなく、胃腸の調子が悪い程度のもので見過ごしてしまいがちです。
→ すい臓がんの症状・原因・治療 について詳しくはこちら
●高尿酸血症(痛風予備軍)
この結晶を異物として排除しようと体が闘い始めるために、足の親指の付け根やかかと、くるぶしなど足の関節を中心に、激しい痛みの発作が起こります。
→ 痛風とは|痛風の症状・原因・食事 について詳しくはこちら
→ プリン体の多い食品一覧・プリン体の少ない食品一覧 について詳しくはこちら
心筋梗塞や脳梗塞になる危険性もある。
●糖尿病
1) 空腹時血糖126(mg/dl)以上
2) 75グラムのブドウ糖を飲み2時間後の血糖200以上
3)随時血糖200以上
4) ヘモグロビンA1c6.5%以上
肝機能障害とは、肝臓が何らかの異常によって障害を受けることにより、正常に機能しなくなることをいいます。
ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTPといった肝機能の数値で肝機能障害がどの程度の状態であるかを判断します。
脂質異常症とは、血液中に含まれる脂質(コレステロールや中性脂肪)が多すぎる、もしくは不足している状態を指します。
●スクワットをしたら○○無料!?
●あんなものに税金が!?国を挙げて対策している、「世界のメタボ対策」の実態もご紹介!
世界初の「肥満税」がデンマークで施行によれば、デンマークでは世界で初めて「肥満税」(別のメディアでは「脂肪税」というところもありました。)が導入されました。
ハンガリーで「ポテチ税」施行、脱メタボと税収アップに期待によれば、ハンガリーでは、塩分や糖分の高い食品に課税する、通称「ポテトチップス税」が施行されたそうです。
目的は、食習慣の改善・肥満対策とのことですが、税収アップにも期待しているようです。
税収アップと国民の健康悪化(肥満や糖尿病など)に伴う医療費の増加を減らすために、世界的にこうした動きが見られますね
【関連記事】