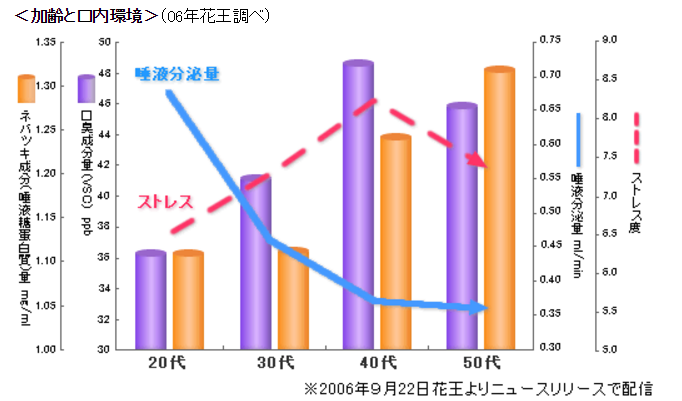by Debby ☂ (画像:Creative Commons)
参考画像:桐谷美玲、ほっそり美脚で“絶対領域”披露「神々しい」の声|モデルプレス
(2016/6/27、モデルプレス)
ファンからは「美玲ちゃん相変わらず細い…!」「可愛すぎます」「美しい…というか神々しい…」「絶世の美女!」「可愛くてかっこいい美玲ちゃんに憧れます」など桐谷のスタイルを羨む声が多数寄せられている。
桐谷美玲の太ももに「細い!」、ファンからは痩せすぎを心配する声も。
(2016/6/27、narinari.com)
これにファンからは「足が細いなぁ」「ほそー!」「足やばいもうちょっと体重増やしていいと思います!」「ほっそいぃい!!!!!」「あしほそーーー」「脚細すぎです!汗 体調とか大丈夫なんですか?」などの声がで出ているようだ。
桐谷美玲さんがInstagramで写真撮影のオフショットを投稿した写真が話題になっているそうです。
※2016/6/17 15:42現在写真は見つかりませんでしたので、削除されたのかもしれません。
細い体への憧れの声がある一方、やせすぎ・太ももの細さを心配する声も挙がっています。
先日も佐野ひなこさんがInstagramにアップした自身の体重計の写真に対して、やせ過ぎを心配する声が挙がっていました。
ただ、こうした心配をする場合に、本当にどんなにたくさんのご飯を食べても太らない体質だとしたら、かえってそうした体質の方を傷つけている恐れがありますので、注意が必要ですね。
【関連記事】
■女性のやせすぎ問題
日本人女性がやせる理由は「優越感や日本人男性が好むから」?によれば、日本人女性がやせる理由として、「ほかの女性から受ける批判的な視線による社会的な圧力」や「日本人男性が小柄な女性を好むため」、「ファッショナブルな服がやせた女性をターゲットにデザインされていること」、「ほかの女性と比較し優越感を得ることにある」としています。
10代少女の9割、「やせ」へのプレッシャーを自覚=米調査によれば、米国のティーンエージャーの少女の10人中9人近くが、ファッション業界やメディアが作り出した非現実的な美のイメージの影響で、非常にやせた体形になるようプレッシャーを感じているそうです。
【1】 女性は「人から見られている」ことを強く意識しているから
【2】 メディアにおける「やせに対する価値」の影響を受けているから
【3】 友人の影響を受けているから
女性の見た目に関する意識が高いことやメディアより「やせていることがよい」「ダイエットが良い」という価値観への影響を受けていること、自分自身の見た目に対する関心が高く、またメディアからの影響を受けた周りの人からの影響を受けることが、女性がさらに体重を気にする背景となっているようです。
また、日本ではダイエットの低年齢化が問題になっているそうです。
日本ではダイエットの低年齢化も問題になっており、以前、医師への取材で「私、太っているから」とダイエットをする小学生が増えているそうです。
ダイエットの新常識|ホンマでっか!?TV(2月1日)でも取り上げられていましたが、10代女性の過激なダイエットはホルモンバランスが崩れやすくなるため、老化を早めるそうです。
そこで、最近では、女性たちがモデルに憧れて摂食障害に陥っているという問題から、ブランド・ファッション誌側が女性のやせ過ぎ問題に取り組んでいるようです。
現在では、ブランド側もプラスサイズモデルを採用したり、ファッション誌がケイト・アプトンのような健康的な身体のモデルを採用し始めたことからもわかるように、時代は健康的な身体の女性へとシフトしている、もしくはシフトさせようとしているのがわかります。
■まとめ
以前であれば細身の体に対する憧れだけがあったのでしょうが、少しずつ美しさに対する価値観が変わってきているのではないでしょうか?
⇒ 芸能人・有名人・セレブのダイエット方法 について詳しくはコチラ。
⇒ あなたにあった ダイエット 方法の選び方 はこちら
⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら
ダイエット方法ランキングはこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【関連記事】
- 【クローズアップ現代】女性のやせすぎ問題|痩せ過ぎと低体重児・モデルのヤセ過ぎ問題|10月5日
- 拒食症対策のため「痩せ過ぎモデル」に罰則を与える新規制―仏議会
- 広告基準協議会、やせすぎモデルは「不健康」なためファッション誌広告NG-英
【関連記事】
- 「AERIE(エアリー)」はモデルの写真修正(デジタル加工)をやめたことで売り上げがアップしている!
- H&M 水着PRにプラスサイズモデル起用
- VOGUE、モデルのやせすぎ問題に対策を発表
- ラルフ・ローレンのモデルの写真修正が話題に、やせすぎへの警鐘も
- AERIE、丸みのある自然な身体の女性を広告に起用。女性の摂食障害が社会問題になっていることが背景に。
- お尻が大きすぎて解雇されたモデルが訴訟に勝利
- ケイト・アプトンの登場により、カーヴィー・健康的なボディの時代がくる?
- 大御所モデルが「ケイト・アプトンは太っている」と批判
- 憧れボディのトレンドは“健康的でメリハリのあるカラダ”
【有名人とダイエット 関連記事】
- 北川景子さんのダイエット方法まとめ(2010年~2015年)
- 水原希子さんのスタイルキープの秘訣(食事・運動)とは?
- 柴咲コウさんの美の秘訣(食事・運動)とは?
- 菜々緒さんの美脚を作る方法とは?|「腰・お尻・脚のバランスが良いことが美しいフォルムを作る」
- 道端ジェシカさんのパーフェクトボディを維持する方法(食事・運動)とは?
- ローラさんの美腹筋が話題|ローラさんのスタイルを維持するダイエット方法とは?
- ローラさんのダイエットの考え方|食事を抜かず、食事のバランスや運動をしてモデルとしての体型を維持
- 67キロから43キロへダイエットしたダレノガレ明美さんのダイエット方法とは?
- 榮倉奈々さんの美脚になる方法(ふくらはぎマッサージ)・トレーニング方法とは?
- 加藤あいさん、ダイエットの目標は体重を減らすことではないと気づく
- 三吉彩花さんの美容法|美脚・美肌・美髪になる方法まとめ
- 松井愛莉さんの美容法|スピルリナ・スロージュース(スロージューサー)|メレンゲの気持ち 5月9日
- 三吉彩花さんが行なっている腹筋トレーニングとは?|しゃべくり007 11月23日
- 中条あやみさんの美容の秘訣|美肌・ヘアケア・ニキビ・食事
- パーフェクトボディ!「non・no」モデル馬場ふみかさんのスタイルキープの秘訣(食事・運動)とは?
- 【#きみが心に棲みついた】水着グラビアが話題の #吉岡里帆 さんのナイスバディを保つダイエット方法とは?
- 「奇跡の9等身」「10等身弱」モデル朝比奈彩さんのスタイルキープの秘訣は「運動」
- MORE専属モデル内田理央さんのダイエット・バストアップ・ウエストを細くする・肌ケア方法とは?
- 20代のための効果的に体重を減らす方法(食事・運動)・ダイエットのやり方
【桐谷美玲さん 関連記事】