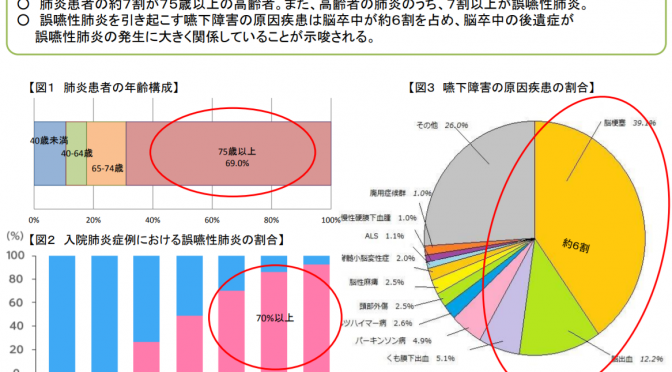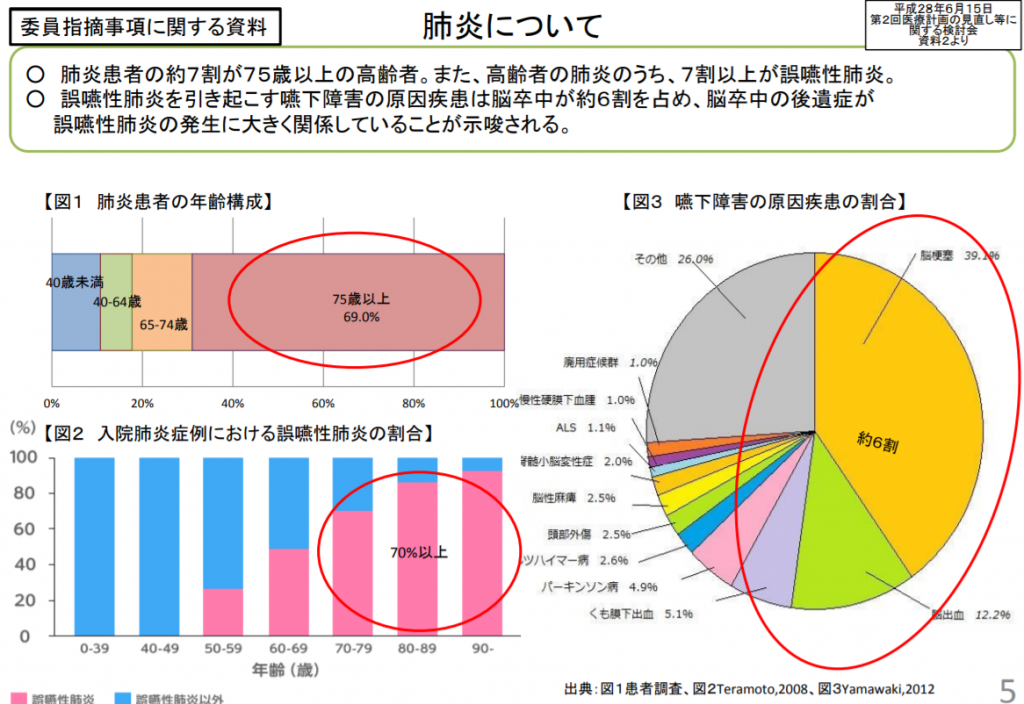2025年9月6日放送のNHK『知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?』でタモリさんが『人の名前は出てこない、やったことは忘れている。冷蔵庫を開けたら、何しに開けたんだろう』というような認知症の兆候と言われる症状は『全部ある』と発言したことが話題になっています。
→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら
日本人の死因第1位は「認知症」/平均寿命は延びたが都道府県格差が広がるによれば、慶應義塾大学や米ワシントン大学の研究グループが日本人の過去30年の健康状態を解析した結果、’15~’21年で最も多い死因が「アルツハイマー病およびその他の認知症」だとする研究成果を国際医学誌『THE LANCET Public Health』に発表しました。
2021年の日本人の死亡原因上位5つは、1)アルツハイマー病およびその他の認知症、2)脳卒中、3)虚血性心疾患、4)肺がん、5)下気道感染で、アルツハイマー病およびその他の認知症は、1990年から2021年の間に6位から1位に上昇しています。
つまり、アルツハイマー型認知症は日本人にとって珍しいものではなくなってきています。
認知症の新たな2つのリスク要因(視力低下とLDLコレステロール値の高さ)が追加!認知症の45%は遅らせたり軽減できる可能性/ランセットによれば、45%の症例は遅らせたり、軽減したりできる可能性があると提言していますので、認知症対策に取り組んでいきましょう!
【子供・青年期】
1)子供たちに初等・中等教育を提供する 5%
【中年期】
2)難聴への対策(補聴器など) 7%
3)外傷性脳損傷を防ぐ(頭部のけがを防ぐ) 3%
4)高血圧対策 2%
5)過度のアルコール摂取を避ける 1%
6)肥満対策 1%
【晩年期】
7)禁煙 2%
8)うつ病予防 3%
9)社会的交流・社会的接触を増やして社会的孤立を防ぐ 5%
10)大気汚染を減らす 3%
11)運動不足を解消する 2%
12)糖尿病予防 2%
【新たに追加された2つの要因】
13)視力低下 2%
14)LDLコレステロール値の高さ 7%
→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら
■ちなみに
●認知的予備力
若い時によく勉強した人はアルツハイマー型認知症になりにくい?認知機能の予備力を鍛えて認知症が予防できる?で紹介したジョンズ・ホプキンス医科大学の研究によれば、高齢になっても認知機能にまったく問題がない修道女は、脳にアルツハイマー型認知症と同じ変化が確認されているにも関わらず、病気の症状が表れにくいことが分かったそうです。
そのポイントは、10代の頃に高い言語技能を習得していること。
フレイルは「予備力の低下」が主要因として起こりやすい!?によれば、緊急事態や危機的状況で、普段は意識的にコントロールしている力を超えて、潜在的なパワーを発揮する「火事場の馬鹿力」や脳には筋肉や骨に過度な負担がかかるのを防ぐため、普段は100%の力を発揮しないようにする安全装置(リミッター)が備わっているといわれますが、これが予備力なのだと思います。
つまり、フレイルとは加齢に伴い身体や認知機能の予備力が低下して食欲の低下や活動量の低下、筋力低下、認知機能低下、多くの病気を抱えるといった状態と言い換えることができます。
若い時によく勉強した人はアルツハイマー型認知症になりにくいというのは、若い頃に勉強していたことによって、認知機能の予備力が鍛えられていたからだとは考えられなしでしょうか?
認知症の予防につながる9つのリスク要因|中年期の聴力低下・中等教育の未修了・喫煙・うつ・運動不足・社会的孤立・高血圧・肥満・2型糖尿病や認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、うつ傾向がある人で紹介した国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、学校教育の年数が9年以下の人のリスクは、9年を超える人の2倍だったそうです。
中等教育を修了しないのは大きなリスクで、論文の著者たちは、大人になっても学び続ければ脳の「予備力」を増やせる可能性が高いと述べている。
中等教育の未修了だからといって即、認知症になりやすいというのではなく、大人になって学習意欲がある人は「認知的予備力」(人生の過程で頭を使うことによって蓄えられる)を増やせる可能性が高いそうです。
→ デジタル認知症はウソ?テクノロジーで認知症リスク42%減!認知的予備力理論にテクノロジーが役立つ について詳しくはこちら
●鼻をほじるとアルツハイマー型認知症になるリスクが高まるって本当?で紹介した近年の研究でアルツハイマー病における神経炎症プロセスが外部から侵入する病原体が関与している可能性があり、鼻をほじると病原菌を押し込むリスクが高まる、鼻毛を抜くとバリア機能が低下するというように感染リスクが増加することから鼻をほじる行為による細菌感染と認知症仮説は研究するに値するものと言えそうです。