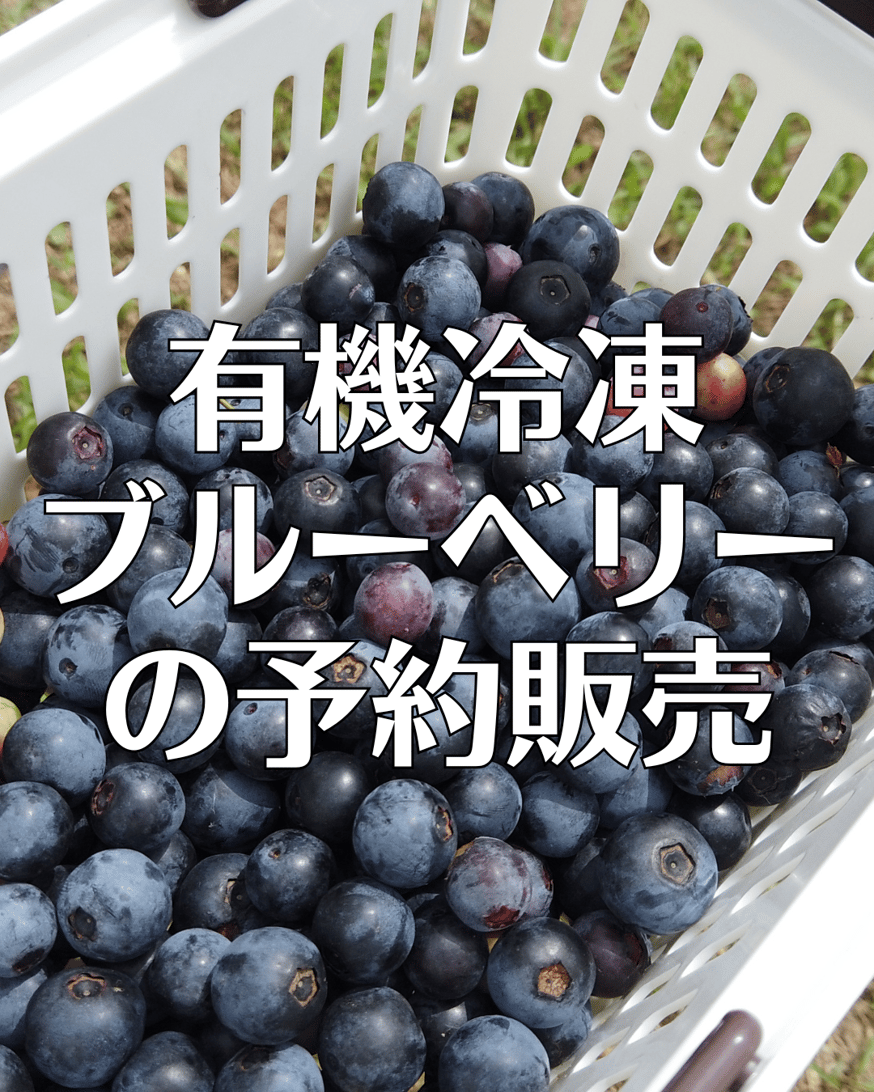Xの投稿で「飛蚊症(ひぶんしょう)」にパイナップルが良いという話題が広まっています。
飛蚊症は、視界にチラチラ浮かぶ黒い点や糸みたいなものを見える目の病気のことなのですが、飛蚊症がパイナップルで改善するかもしれないって話、確かに気になりますよね。
そこで、今回は、関連する研究を基にわかりやすくまとめました!
→ 飛蚊症とは|飛蚊症の原因・症状・治し方・見え方 について詳しくはこちら
1. パイナップルと飛蚊症の関係は?
台湾で行われた2019年の研究によると、パイナップルに含まれる「ブロメライン」という酵素が、飛蚊症の原因となるコラーゲン(目のゼリー状部分にたまるタンパク質)を分解する可能性があるそうです。
388人の参加者に3か月間毎日パイナップルを食べてもらう実験で、約70%の人が飛蚊症が減ったと報告したそうです。
さらに2022年の研究では、ブロメラインを含むサプリメントを高用量で摂取したグループで、飛蚊症が大幅に減ったという結果も出ています。
【参考リンク】
- Ma JW, Hung JL, Takeuchi M, Shieh PC, Horng CT. A New Pharmacological Vitreolysis through the Supplement of Mixed Fruit Enzymes for Patients with Ocular Floaters or Vitreous Hemorrhage-Induced Floaters. J Clin Med. 2022 Nov 13;11(22):6710. doi: 10.3390/jcm11226710. PMID: 36431188; PMCID: PMC9695351.
2. どんな仕組み?
ブロメラインは、タンパク質を分解する力がある酵素で、目の奥にあるコラーゲンを少しずつ溶かしてくれる可能性があるそうです。
これが飛蚊症の「チラチラ」を減らす仕組みと考えられています。
ただこの研究には、1)比較対象となるパイナップルを食べないグループ)がなかったから、偶然改善したのか、パイナップルの効果なのかがはっきりしないこと、2)パイナップルには糖分が多いため、血糖値が上がるリスクがあり、糖尿病の人には注意が必要なこと、血液サラサラする薬と反応する可能性があるから注意が必要なこと、4)もっと大規模な研究が必要なことなど、といった課題もあります。
■まとめ
将来的にはパイナップルに含まれる成分から飛蚊症の治療薬が生まれる可能性が期待されます。
ただ飛蚊症が気になる人はちゃんと眼科で診てもらってくださいね。
→ 飛蚊症とは|飛蚊症の原因・症状・治し方・見え方 について詳しくはこちら
【補足】
1. 研究の目的
この研究では、飛蚊症(目の前にチラチラ見える黒い点や糸)を減らす新しい方法として、フルーツ由来の酵素(特にパイナップルのブロメライン)をサプリメントで摂取する効果を調べました。対象は、普通の飛蚊症(自発性)と、硝子体出血(目の内部の出血)による飛蚊症の2つのグループです。
2. 実験の方法
参加者: 30~60歳の224人(男性126人、女性98人)が参加。2017年9月~12月に台湾の高雄武装総病院で募集されました。
サプリメント: 1カプセルにブロメライン190mg、パパイン95mg、フィシン95mgを含む混合フルーツ酵素(MFE)を用意。参加者は以下の4グループに分かれました:
グループ1: プラセボ(ビタミンC 10mg/日、効果なしのダミー)。
グループ2: 1日1カプセル(低用量)。
グループ3: 1日2カプセル(中用量)。
グループ4: 1日3カプセル(高用量)。
期間: 3か月間サプリを毎日摂取し、1、2、3か月後に飛蚊症の数をチェック。
測定: 超音波や写真で飛蚊症を確認し、視力(CDVA)の変化も調べました。
3. 結果は?
自発性飛蚊症(実験1): 1カプセル: 55%の人が飛蚊症が減った。
2カプセル: 62.5%が減った。
3カプセル: 70%が減った(用量が多いほど効果アップ!)。
硝子体出血による飛蚊症(実験2): 1カプセル: 18%が減った。
2カプセル: 25%が減った。
3カプセル: 56%が減った。
視力も0.63LogMAR(かなり見えにくい)から0.19LogMAR(かなり改善)に上がった。
プラセボ群: ビタミンCだけだとほとんど効果なし(95%が飛蚊症が残った)。
4. 仕組みは?
ブロメラインなどの酵素が、目のゼリー状部分(硝子体)のコラーゲンを分解し、飛蚊症の原因となる「混濁」を減らすと考えられています。
抗酸化作用(体内の酸化ストレスを抑える力)も確認され、これが効果を後押ししている可能性があります。
5. 注意点と限界
限界: すべての飛蚊症が消えたわけではなく、一部のコラーゲンは分解しきれなかった。もっと詳しい仕組みの研究が必要。
リスク: 3か月間試しても副作用(網膜損傷など)は出なかったけど、個人差があるかもしれない。
「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」