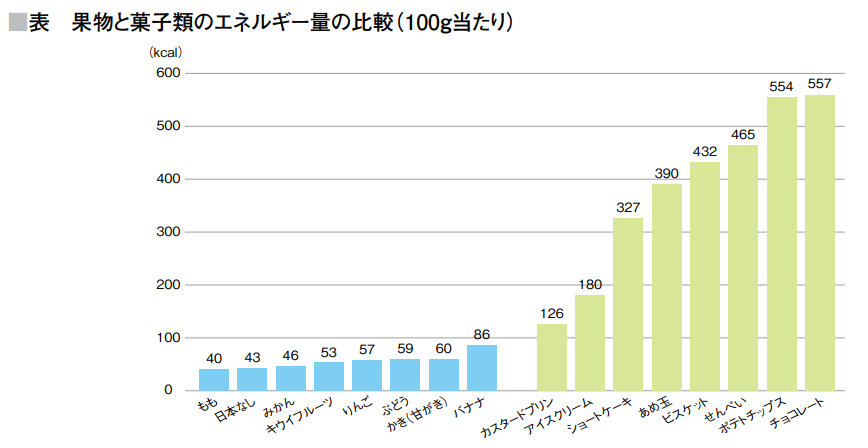「足がつる」と一口にいっても、「左足がつる」「右足がつる」「両足がつる」であったり、アキレス腱やふくらはぎというように部分が気になったり、貧血やめまいを伴っていて検索するケースもあるようです。
【目次】
■足がつるメカニズム
by Kryziz Bonny(画像:Creative Commons)
2012年4月25日放送のためしてガッテン(NHK)では、「痛ッ!“足がつる”に隠れた危険な病とは?」を取り上げました。
人間の足は、ふくらはぎの筋肉が縮むとアキレス腱が伸びる構造になっていて、筋肉が縮む時に、アキレス腱にある腱紡錘(けんぼうすい)という器官が働き、腱の伸びすぎを防ぐため、筋肉に「それ以上縮むな!」と指令を出しています
ポイントは、アキレス腱だったんですね。
冷え・運動・脱水3つともアキレス腱にある「腱紡錘(けんぼうすい)」の働きを弱めます。
そこで、何かをきっかけで筋肉が異常に収縮を続けてしまうと足がつってしまうのですが、寝ている時もふくらはぎの筋肉が少し収縮していることが多く、しかも腱紡錘が低下しているため、睡眠中は足がつりやすいのです。
夜寝ているときによく足がつる人とつらない人の差|この差って何ですか?によれば、足がつる原因には、加齢や筋肉疲労などがありますが、「汗を多くかいたか、かいていないか」、つまり「脱水」が足のつりやすさを決めているそうです。
足を動かす時には、脳からふくらはぎに指令が送られ、ふくらはぎの筋肉が収縮することで、足を曲げています。
この動きに重要な働きを果たしているのが電解質のマグネシウムイオンなのだそうですが、マグネシウムイオンは汗をかいたときに一緒に排出されてしまいます。
なぜ熱中症になると、「熱けいれん(筋肉痛・手足がつる・こむら返り・筋肉の痙攣・大量の汗)」という症状を起こしてしまうのか?によれば、電解質とは、体内の水分に含まれるナトリウムやカリウムなどのイオンのことで、体液に溶けこんでいて、全身の細胞の浸透圧を調節したり、筋肉の収縮、神経の伝達などを支えており、電解質は体機能の維持に重要なため、汗とともにたくさん失うと、「筋肉痛」「手足がつる」「こむら返り」「筋肉の痙攣」という症状を起こします。
汗をかいたことでマグネシウムイオンが不足すると、脳からふくらはぎへの指令が鈍ってしまい、筋肉が必要以上に縮んでしまい、足がつってしまうのです。
また、睡眠中に足をつってしまうもう一つの理由は、寝ているときの姿勢は足先が下の方を向いている状態にあることで、筋肉が縮んだ状態にあるためなのだそうです。
寝ている時に足がつることを予防するためには、寝る前に水分補給(特にマグネシウムイオンが含まれているもの)をするとよいそうです。
足がつってしまった時には、急に伸ばすと痛みが出るので、足のつま先をもって、ゆっくりと体に引き寄せるようにしましょう。
注意したいのは、夜寝る前にしっかりと水分補給をしているにもかかわらず、よく足がつる人なのだそうです。
その場合には、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病などの病気の可能性があるので、病院で検査してもらうことをおすすめします。
■危険なこむら返りの見分け方
閉塞性動脈硬化症が原因の場合も、こむら返りが起こりやすいそうです。
両足を上げて足首を曲げたり伸ばしたりして、片方の足だけが白く変わると疑いがあるそうです。
閉塞性動脈硬化症は、足の血管が動脈硬化を起こして詰まってしまい血流が悪くなる病気です。
閉塞性動脈硬化症の治療法としては、「1分歩いて3分休む」を10回セット繰り返し、1週間にこれを3回行い、3週間ほどで新しい血管ができて症状が改善し始めた患者さんもいるそうです。
こむら返りが頻繁に起きるようであれば、早めに病院にいくことをおすすめしています。
【関連記事】
■足がよくつる人は肝臓の病気の可能性がある?
足がつる人は肝臓病の可能性|ホンマでっかTVによれば、足がよくつる人は、肝臓の代謝機能が低いため、肝臓の病気の危険性があるそうです。
【関連記事】
■足がつらないための3つの予防策
足がつらないための3つの予防策としては、
- ミネラルが含まれるスポーツドリンクでミネラル補給
- こまめな着替えで、急激な体温上昇を抑える
- 肝臓を弱らせないように、暴飲暴食を控える
ことが重要なようです。

 肝臓関連ワード
肝臓関連ワード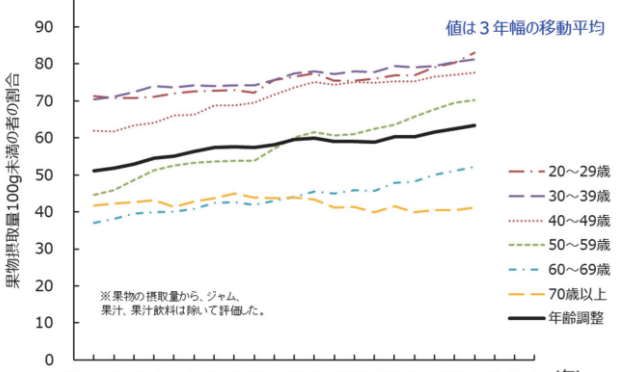
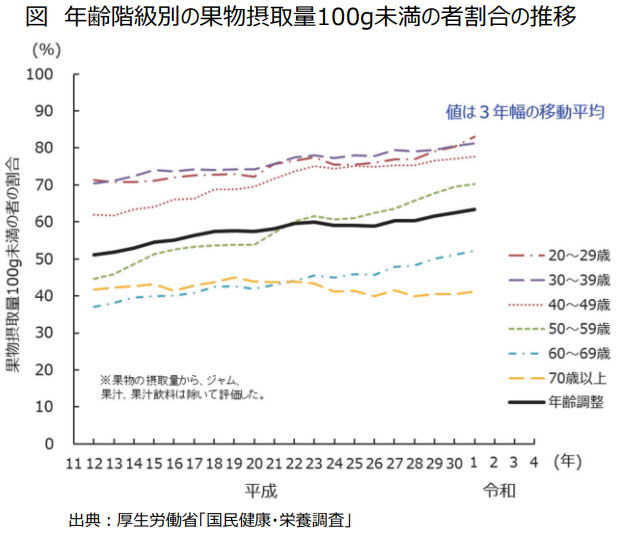
.png)