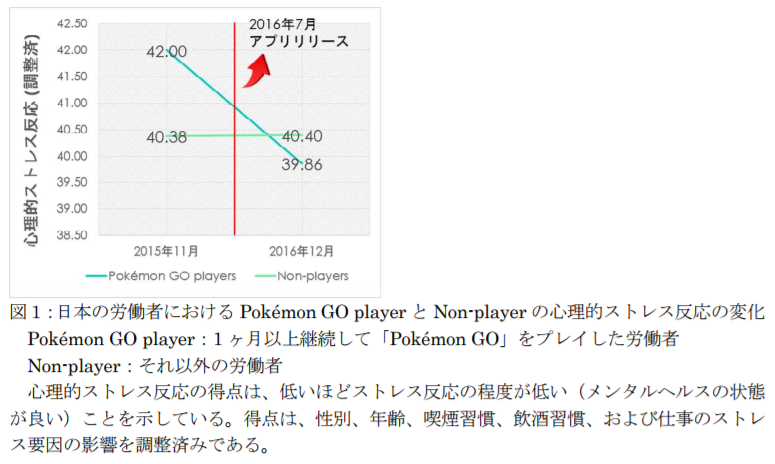> 健康・美容チェック > 認知症 > 認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、学校教育が9年以下の人、うつ傾向がある人、難聴の人
2015年9月1日放送のたけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学のテーマは「腸内フローラ」と「新型認知症」です。
「腸内フローラ」「新型認知症」|たけしのみんなの家庭の医学 9月1日
■新型認知症
by Gabriel Rocha(画像:Creative Commons)
解説 朝田隆 先生
認知症予防|たけしのみんなの家庭の医学 3月10日では、「白質病変」について取り上げましたが、今回は、新型認知症。
新型認知症の特徴は、物忘れ以外には、5つ。
※物忘れ以外に2つ以上当てはまった人は要注意です。
新型認知症とは、「うつ病性仮性認知症」。
うつ病性仮性認知症は、高齢者うつ病から認知症のような物忘れ症状などを発症する病気です。
うつ病性仮性認知症は、前頭葉の血流が下がっていることが原因。
前頭葉の血流を増やすためには、有酸素運動(散歩など)+知的刺激(川柳など)。
(2015/8/23、日本経済新聞)
運動プログラムとして同センターが推奨しているのが、単に体を動かすだけでなく、頭を使いながら有酸素運動をするというやり方だ。暗算やクイズなどの課題を解きながら速足で歩いたりする。「コグニション」(認知)と「エクササイズ」(運動)を組み合わせ「コグニサイズ」と呼んでいる。
国立長寿医療研究センターでは、頭を使いながら有酸素運動すること、例えば、暗算やクイズなどを解きながら速足で歩いたりすることを勧めているそうです。
このことを「コグニション」(認知)と「エクササイズ」(運動)を組み合わせ「コグニサイズ」と呼んでいるそうです。
週1回90分の運動プログラムを10か月間参加したグループでは、認知機能や言語機能が維持されており、また脳の特定部位の萎縮傾向がなかったそうです。
認知症予防運動プログラム「コグニサイズ」|国立長寿医療研究センター
1. 運動は全身を使った中強度程度の負荷(軽く息がはずむ程度)がかかるものであり、脈拍数が上昇する(身体負荷のかかる運動)
2. 運動と同時に実施する認知課題によって、運動の方法や認知課題自体をたまに間違えてしまう程度の負荷がかかっている(難易度の高い認知課題)
コグニサイズの目的は、運動で体の健康を促すと同時に、脳の活動を活発にする機会を増やし、認知症の発症を遅延させることです。
コグニサイズのポイントは課題が上手くなることではなく、脳へのちょうどいい負荷をかけることで脳の活動を活発にすることです。
そのため創意工夫によって課題の内容を変えていくこと、また一緒にコグニサイズを取り組む仲間と間違えても笑いながら、試行錯誤して楽しんでいくことが大事なんですね。
→ 認知症予防に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら
【関連記事】
続きを読む うつ病性仮性認知症対策|前頭葉の血流を増やす方法は有酸素運動(散歩など)+知的刺激(川柳など)を行う「コグニサイズ」|たけしの家庭の医学