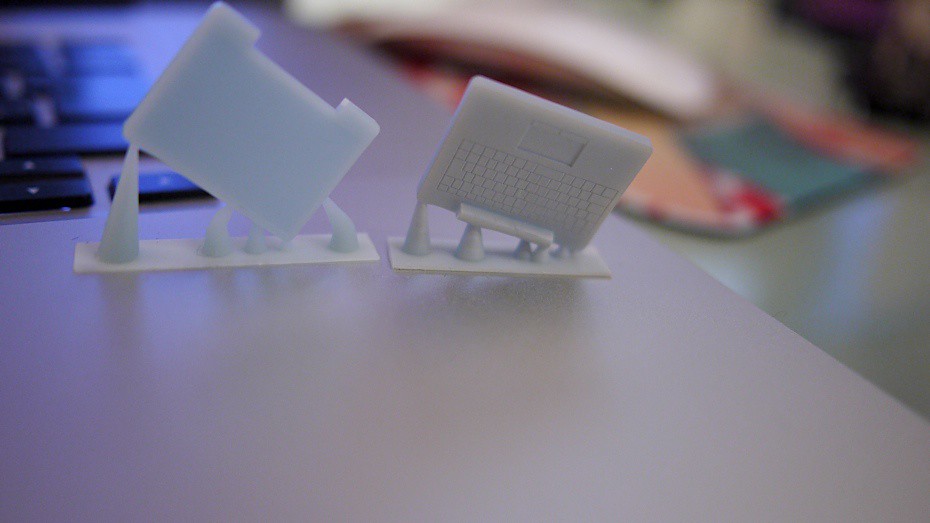by Werner Schütz(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 花粉症の症状 > 花粉症で7割が女子力低下?|「マスク美人」になるチャンス!
花粉症で7割が仕事効率低下 – 重症者の約3割「トイレでサボった」経験あり
(2014/3/6、マイナビニュース)
68.0%の女性が花粉シーズンは女子力が低下すると回答している。
<中略>
3割強の男性も、花粉症の女性は女子力が低下していると回答している。
花粉症のシーズンは女性の約7割が女子力が低下すると回答しているそうです。
その理由は何でしょうか?
その理由としては、「肌が荒れたり、赤くなったりするので化粧のノリが悪い」(63.9%)、「マスクで顔が隠れるので、化粧に気合いが入らない」(49.6%)などが挙げられた。
肌が荒れたり、赤くなったりして化粧ノリが悪いという理由やマスクで顔が隠れるので化粧に気合いが入らないそうです。
ただ、マスクを着けていることをポジティブに捉えてみてはどうでしょうか?
「マスク美人」という言葉があるように、マスクを着けている人はキレイに見えることが多いようです。
【関連記事】
見た目の第一印象を決める上で重要な顔のパーツは「目」によれば、見た目の第一印象を決める上で重要な顔のパーツは「目」が91%だったそうで、マスクを着けることにより、よりその効果が高まるのではないでしょうか?
また、花粉症によってちょっと目もウルウルしていますし、目に注目が集まることは間違いありません。
花粉症でマスクを着けることをポジティブに捉えてみてはいかがですか?
→ 花粉症の症状(目・鼻・のど) について詳しくはこちら
→ 花粉症対策 について詳しくはこちら
→ 目がかゆい|目のかゆみの原因・対策・対処法 について詳しくはこちら
P.S.
ロングヘア&つけまつげは花粉症によくない!によれば、つけまつげにも付くことがあるので、できればナチュラルメイクにした方が良さそうです。
【目の花粉症の症状 関連記事】
- 花粉症による目のかゆみ対策・対処法
- どうして目に異物(花粉など)が入ると、目がかゆくなるのか?
- どうして花粉症になると、まぶたが腫れるのか?その2つの原因|花粉症の症状
- どうして花粉症になると、涙が出る(涙の量が増える)のか?|花粉症の症状
- なぜ花粉症で「目が痛い」という症状が出るの?|花粉症による目の痛み対策
- 実際に感じている花粉症の症状第1位は「目のかゆみ」
- 花粉症の症状:目のかゆみ・充血 洗いすぎは逆効果
【のどの花粉症の症状 関連記事】
- なぜ花粉症になると「咳(せき)」が出るの?その原因|花粉症の症状
- 花粉症患者の約8割が実感するのどの異常の理由とは
- 花粉症の人で「口の中がピリピリしびれる」は要注意!野菜や果物でアレルギー反応が起きる!?
【鼻の花粉症の症状 関連記事】
- どうして花粉症になると「鼻づまり」になるの?その原因|花粉症の症状
- どうして花粉症になると鼻水が出るの?その原因|花粉症の症状
- どうして花粉症になると「くしゃみ」が出るの?その原因|花粉症の症状
- 正しい鼻のかみ方5つのポイント-副鼻腔炎や中耳炎に気をつけよう
【肌の花粉症の症状 関連記事】
【花粉症 関連記事】