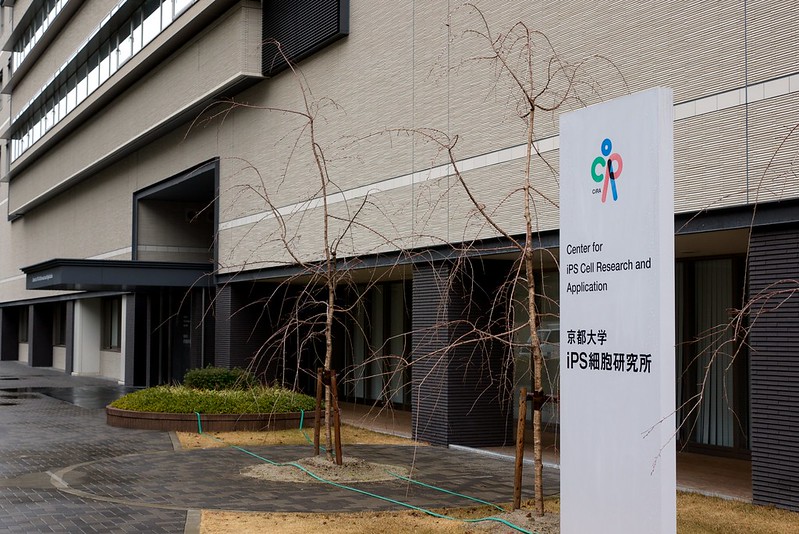by Joey(画像:Creative Commons)
炭水化物は飽和脂肪より健康に悪い? 研究
(2014/11/24、AFP)
心臓病など多岐にわたる健康上の問題に関連するとして長きにわたり悪者扱いされてきた飽和脂肪だが、摂取量を2倍~3倍近くにしても、その血中濃度は上昇しないことを明らかにしたとする研究論文が、21日の米オンライン科学誌プロスワン(PLOS ONE)で発表された。
飽和脂肪酸の摂取量を2倍から3倍にしても、血中濃度は上昇しないことが明らかになったそうです。
一方、炭水化物については、糖尿病と心臓病のリスク増に関連がある脂肪酸の血中濃度上昇に関係していることが、同じ研究で示された。
炭水化物が脂肪酸の血中濃度上昇に関係しているそうです。
飽和脂肪酸悪玉論の真相とは?|飽和脂肪酸は心臓疾患の原因にはならない?によれば、昔との食生活の違いの一つとして、飽和脂肪酸の摂取量が減ったものの、炭水化物の摂取量が増えているそうです。
炭水化物の摂り過ぎは、肥満や糖尿病の原因になり、さらには心臓疾患になる可能性も高まります。
論文によると、炭水化物の少ない食事を与えると、体内の「パルミトレイン酸」と呼ばれる脂肪酸が低下したとされ、これは炭水化物の再導入で徐々に増加したという。パルミトレイン酸について研究チームは、「病気を促進する恐れがある、健康に有害な炭水化物の代謝」に関係するものとしている。
このパルミトレイン酸の増加は、炭水化物が体内で燃焼されずに脂肪に変換される割合が増加していることを示していると研究チームは指摘する。
つまり、先日の記事と今回の記事を総合すると、飽和脂肪酸の摂取が脂肪酸の血中濃度の上昇に関係しているのではなく、炭水化物の摂取が脂肪酸の血中濃度の上昇に関係していて、そのことが糖尿病や心臓病のリスク増に関係していると考えられます。
■まとめ
今回の記事をまとめてみます。
1.飽和脂肪と心臓病との関連性はない
2.炭水化物を摂取すると、脂肪酸のパルミトレイン酸が増加し、病気(糖尿病や心臓病)のリスクに関係していると考えられる。