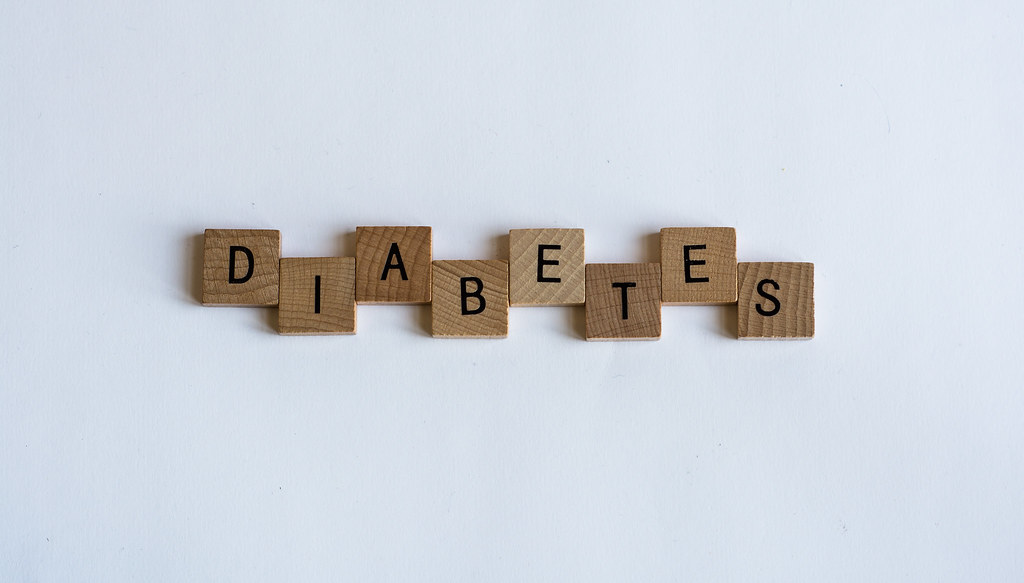英国バイオバンクの約6万人のデータを用いた研究によれば、睡眠時間よりも規則的な睡眠の方が健康と長寿にとって欠かせない要素で、規則的な睡眠のグループは、規則性の低いグループに比べて、全体の死亡リスクが20~48%、がんによる死亡リスクが16~39%、心血管疾患による死亡リスクが22~57%低下することがわかりました。
■研究のポイント
この研究は、睡眠の長さ(何時間寝るか)よりも、睡眠の規則性(毎日同じ時間に寝て起きること)が健康や長生きに与える影響が大きいことを示しています。
英国バイオバンクの約6万人のデータを用いて、加速度計(動きを記録するデバイス)で睡眠パターンを測定した結果、睡眠の規則性が低い人に比べて、規則的な睡眠パターンを持つ人は、全体の死亡リスクやがん、心血管疾患による死亡リスクが大幅に低いことがわかりました。
具体的には、規則的な睡眠のグループは、規則性の低いグループに比べて、全体の死亡リスクが20~48%、がんによる死亡リスクが16~39%、心血管疾患による死亡リスクが22~57%低下。
睡眠時間(短すぎる・長すぎる)も死亡リスクに関係しますが、睡眠の規則性が死亡リスクを予測する力は睡眠時間よりも強いことがわかりました。
■【仮説】睡眠の規則性が重要な理由
1)体内時計(概日リズム)の安定化
人間の体には、睡眠やホルモン分泌、体温調節などを管理する「体内時計」があります。
規則的な睡眠は、この体内時計を安定させ、体のさまざまな機能(代謝、免疫、ストレス応答など)が最適に働くようにします。
不規則な睡眠は体内時計を乱し、ホルモンバランスや免疫機能の低下を引き起こし、がんや心血管疾患のリスクを高める可能性があります。
【関連記事】
- 体内時計とダイエットの関係|エネルギー摂取量が減少しているのに肥満者数が増加している理由には「体内時計」が関係?|#たけしの家庭の医学
- 【明るい寝室に注意!】睡眠中に光にさらされた人は体内時計の混乱で概日リズム睡眠障害が起こりうつ病を引き起こす可能性がある!|奈良医科大学
2)不規則な睡眠は睡眠のタイミングがバラバラで十分な回復が得られない可能性
不規則な睡眠は、睡眠のタイミングや質がバラバラになり、十分な回復が得られないため、慢性的なストレスや炎症が増加し、長期的に死亡リスクを高める可能性があります。
3)規則的な睡眠をとる人は規則正しい生活習慣の人が多い傾向
規則的な睡眠をとる人は、食事や運動などの生活習慣も規則正しい傾向があります。
これにより、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが減り、結果的に死亡リスクが低下する可能性があります。
つまり、「規則性」こそが重要な要素と考えられます。
■まとめ
毎日同じ時間に寝て起きるという規則的な睡眠こそが健康リスクを減らす方法といえますので、健康的なルーティンを身につけましょう!
【参考リンク】
- Windred DP, Burns AC, Lane JM, Saxena R, Rutter MK, Cain SW, Phillips AJK. Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: A prospective cohort study. Sleep. 2024 Jan 11;47(1):zsad253. doi: 10.1093/sleep/zsad253. PMID: 37738616; PMCID: PMC10782501.