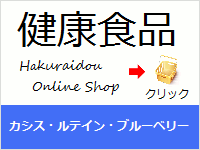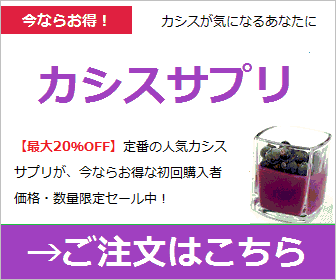by McLevn(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 目の病気 > スマホ老眼 > 10代、20代にも老眼が 眼の健康調査で判明
10代、20代にも老眼が 眼の健康調査で判明
(2010/6/4、とれまがニュース)
健康食品などの市場調査をしているヒューマによる視力矯正と眼の健康調査の結果、4629人から回答があり、老眼の人が10代(2.9%)や20代(0.5%)の中にも存在することが分かった。
記事によれば、若い10代、20代でも老眼の症状が出ている人がいるようです。
これはどういった原因があるのでしょうか。
テレビ、パソコン、携帯電話などを見続けているために起こっているかもしれません。
気になります。
それによると、過去1年以内で罹患した眼の病気や過去に手術した眼の病気についての問いで、21.9%の人がドライアイをあげ、特にソフトコンタクトレンズを使用している人では38.6%がドライアイであることが分かった。
使い捨てコンタクトレンズ(1日を除く)を使用している人も35.3%とドライアイになっている人が目立った。
過去1年以内に目の病気になったことがあるという問いについて、約2割の人がドライアイになっており、また、ソフトコンタクトレンズを使用している人の約4割がドライアイであることがわかったそうです。
ヒューマでは「コンタクトレンズを使用している人に眼の症状を訴える人が多く、目の乾燥・充血・疲れが目立った」としている。また「ハードコンタクトレンズを使用している人は、他のコンタクトレンズを使用している人に比べ、眼の充血を感じる割合が高いようだ」と報告している。
コンタクトレンズを使用している人に目の乾燥・目の充血・目の疲れといった症状が多いようです。
【追記(2016/7/6)】
2010年当時は携帯電話でしたが、2016年現在では若い10代、20代でも老眼の症状が現れることを「スマホ老眼」と呼ばれるようになっています。
→ スマホ老眼 について詳しくはこちら
■スマホ老眼対策
目を酷使すると、ピント調節を行う機能が低下し、また、ロドプシンの再合成がうまくいかなくなるため、目のかすみが起こります。
つまり、大事なことは、きちんと目を休めること。
そこで、目を休めるための目の疲れ解消法を紹介します。
 定期的に目を休める
定期的に目を休める
50分使ったら10分休憩を入れるなど長時間使わないようにする。
 遠くを見たり、目を動かして目の緊張を和らげる
遠くを見たり、目を動かして目の緊張を和らげる
 まばたきの回数を意識的に多くする。
まばたきの回数を意識的に多くする。
「20-20-20-20」という眼精疲労回復エクササイズは、20分おきに20フィート(約6メートル)離れたところを20秒間見つめながら、20回連続で瞬きをすると疲れ目に良いそうです。
→ 眼精疲労解消法 について詳しくはこちら
【関連記事】
 スマホと適度な距離をとる
スマホと適度な距離をとる
スマホとパソコンとで異なるのが「距離」です。
パソコンの場合、通常45センチ程度の間隔をあけて操作しますが、スマホの場合、近い場合では15センチ程度で使用している人もいるくらいです。
近くでモノを見続けるというのは、つまり、ピントを合わせ続けているということです。
スマホを見る際には、近くにピントを合わせるために毛様体筋の調節を行っているのですが、目を酷使することで、この毛様体筋に負担がかかっているからです。
また、スマホやパソコンが原因の「夕方老眼」の人が増加している!?によれば、スマホは強い光を発していて、目に入る光の光量を抑えるための虹彩筋にも負担がかかっているようです。
【関連記事】
 蒸しタオルで目のまわりを暖め血行をよくする
蒸しタオルで目のまわりを暖め血行をよくする
目の疲労回復には42度のシャワーで目の周囲を温めるとよい?によれば、42度のシャワーで眼の周囲を温めると、目の疲労回復に効果があるそうです。
 目の周囲をマッサージする。
目の周囲をマッサージする。
目の周りの皮膚は非常に薄く、刺激を与えすぎるといけないので、目のクママッサージを参考にしてみてください。
→ 目のクママッサージ について詳しくはこちら
 目のかすみは、疲れ目や加齢、病気など目の症状から起きます
目のかすみは、疲れ目や加齢、病気など目の症状から起きます
かすみ目を予防するためには、定期的に眼科で診てもらうことが重要です。
その際、疲れ目によるかすみ目だった場合には、目の栄養補給(カシス・ルテイン・ブルーベリー)と休息をとってください。
→ カシス(アントシアニン)の健康効果 について詳しくはこちら
→ ブルーベリー(アントシアニン)の健康効果 について詳しくはこちら
→ ルテインの健康効果 について詳しくはこちら
【関連記事】
【AD】
→カシスサプリ選びに悩むあなたに
→カシスサプリ通販専門店
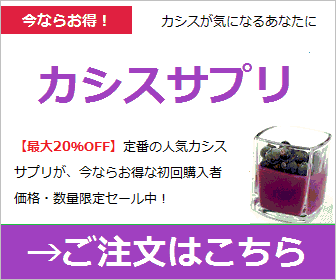
今なら最大15%引きのお得な初回購入者価格・まとめ買いセール特価で購入できます!
■緑内障とは|緑内障の症状・原因・眼圧・予防
■飛蚊症とは|飛蚊症の原因・症状・治し方・見え方
■加齢黄斑変性症とは|症状・原因・治療・サプリメント
■白内障とは|白内障の症状・原因・治療・予防
■ドライアイとは|ドライアイ(目が乾く)の症状・原因・治療
■眼精疲労の症状(頭痛)・原因・マッサージ・ツボ
■老眼とは|老眼の症状(初期症状)・予防・改善
■スマホ老眼の症状・原因・予防
■糖尿病網膜症の症状・治療・分類・予防
■VDT症候群とは|VDT症候群の症状・原因・対策
■網膜剥離とは|網膜剥離の症状・原因・見え方
■近視とは|強度近視・仮性近視
■結膜弛緩症とは|結膜弛緩症の症状・原因・治療
■斜視(隠れ斜視)
■眼瞼下垂(まぶたのたるみ)の症状・原因
■まぶたの痙攣の治し方|まぶたがピクピクする原因
■翼状片の症状・原因・予防
■瞼裂斑の症状・原因・予防・対策
■紫外線対策と目の病気(翼状片・瞼裂斑・白内障)
■コンタクトレンズと目の病気・正しい使用法・ケア
 目の症状
目の症状
■目の充血の原因・治し方|目が赤いのは目の病気のサイン?
■目の疲れを取る方法(ツボ・マッサージ)|目が疲れる原因
■目の痙攣の治し方・止め方|目がピクピクする原因
■目の下のクマを取る方法 原因と解消方法
■目がかゆい|目のかゆみの原因・対策・対処法
■目が痛い|目の痛みの原因となる目の病気と解消法
■目のかすみの症状・原因・対策|目がかすむ
■肩こり頭痛解消法|めまい・吐き気の原因は眼精疲労?
■目やにの原因となる目の病気|どんな色の目ヤニが出ている?
■光がまぶしい・目がまぶしい
■目がゴロゴロする|目の異物感の原因はゴミそれとも病気?