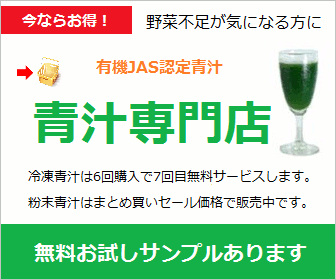> 健康・美容チェック > がん > 抗酸化作用 > アブラナ科野菜の摂取量が多いほど全死亡リスクが減少!なぜアブラナ科野菜摂取量が多いと死亡リスクが低下するの?
■アブラナ科野菜の摂取量が多いほど全死亡リスクが減少!
アブラナ科野菜と全死亡および疾患別死亡との関連について(国立がん研究センター)によれば、男性、女性ともにアブラナ科野菜の摂取量が多いほど全死亡リスクが減少し、また男性でがん、女性で心疾患、脳血管疾患、外因による死亡リスクも減少していることがわかりました。
ちなみに、男性ではブロッコリー、たくあん摂取量が一番多いグループで、女性では大根、ブロッコリー摂取量が一番多いグループで死亡リスクの減少が見られました。
■なぜアブラナ科野菜摂取量が多いと死亡リスクが低下するの?
なぜアブラナ科野菜摂取量が多いと死亡リスクが低下しているのでしょうか?
クレソンに含まれるイソチオシアネートの抗酸化作用でがん予防|みんなの家庭の医学によれば、アブラナ科の野菜には抗酸化作用を持つ「イソチオシアネート(Isothiocyanate)」という栄養素が含まれているそうです。
イソチオシアネートが体内に入ると、抗酸化物質が大量に作られ始め、抗酸化物質が、全身の細胞内にある有害な活性酸素を無毒化してくれることにより、がんの発生を抑制してくれると考えられるそうです。
国際がん研究機関(IARC)によれば、ブロッコリー・キャベツ・クレソンなどアブラナ科の野菜ががんリスクを減少させると発表されているそうです。
【関連記事】
アブラナ科野菜と全死亡および疾患別死亡との関連について(国立がん研究センター)でもアブラナ科野菜に多く含まれるイソチオシアネートや抗酸化性ビタミンの持つ抗炎症および抗酸化作用が死亡リスクの低下に寄与している可能性を指摘しています。
→ 抗酸化食品|抗酸化作用とは・抗酸化物質 について詳しくはこちら
野菜や果物を積極的にとって病気を予防しましょう!
■アブラナ科の野菜とは?
アブラナ科の野菜には青汁で有名なケール、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、カリフラワー、クレソン、大根、白菜、小松菜、水菜、チンゲン菜、菜の花などが含まれます。
→ ケールの効果・効能 について詳しくはこちら
<PR>
【最大15%OFF】有機国産ケール100%の青汁が今ならオトクな価格でご提供しています。
【関連記事】
続きを読む アブラナ科野菜の摂取量が多いほど全死亡リスクが減少!なぜアブラナ科野菜摂取量が多いと死亡リスクが低下するの?