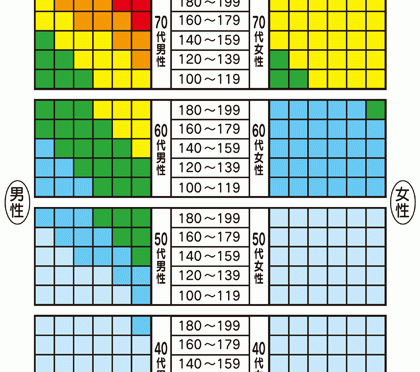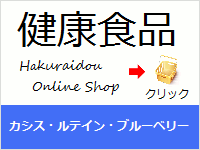> 健康・美容チェック > コレステロール > 本当に血管が若返る!コレステロール調節術|ためしてガッテン(NHK)
2011年1月19日放送のためしてガッテンでは、「本当に血管が若返る!コレステロール調節術」が取り上げられました。
【目次】
■本当に血管が若返る!コレステロール調節術
●動脈硬化は、血管の内側にプラーク(コブのような膨らみ)ができる状態になりますが、これまでの常識では、プラークを「大きくならないようにする」ことはできても、「小さくする」ことはできないと考えられてきました。しかし、最新の研究ではそれが変わってきていているそうです。
●細胞膜の材料がコレステロール → コレステロールがないと生きていけない
細胞から古いコレステロールを回収して肝臓へ捨てに行くもの。
回収トラック(アポA-1)と積み荷のコレステロールをあわせて“善玉コレステロール”と呼ぶ。
肝臓から細胞へと新しいコレステロールを配達するもの。
この、配達トラックと積み荷のコレステロールをあわせて“悪玉コレステロール”と呼ぶ
→ コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事 について詳しくはこちら
→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら
●善玉コレステロールで動脈硬化改善
食生活のバランスが崩れたりして、配達トラックが血液中に増え過ぎると、血管の壁の中にコレステロールが入り込んでしまいます。
すると、白血球の一種であるマクロファージがやってきてコレステロールを食べ、掃除しようとします。
しかし、マクロファージにはコレステロールを分解する力がありません。
食べ過ぎたマクロファージは死んでしまい、どんどん血管の壁の中にたまっていきます。
こうしてできるのがプラークなのです。
配達トラックは増えすぎると動脈効果を起こしてしまうので、“悪玉”と呼ばれているのです。
一方、回収トラックは、細胞から余分なコレステロールを回収する役割なので“善玉”と呼ばれます。
でも、これまではプラークを小さくする程の力はないと考えられていました。
ところが最近では、それができるということが分かってきたのです。
回収トラックは、いったん進んでしまった動脈硬化を改善してくれる、まさに“善玉”コレステロールだったのです。
善玉コレステロールがマクロファージの中からコレステロールを引き出すということが新たに分かったそうです。
→ HDLコレステロールを増やす方法と善玉コレステロール吸う力をアップする方法 について詳しくはこちら
→ 「レムナント」と「Non-HDLコレステロール」とは?基準値・対策|#ガッテン について詳しくはこちら
●コレステロールの危険度は男女差がある
実は、動脈硬化の進行は男女で大きな差があるのです。
女性ホルモンには、“悪玉コレステロール”値を下げる作用をはじめ、血管を保護する様々な効果があります。
そのため、40代までの間、女性の血管は男性よりはるかに若く保たれています。
女性ホルモンの値が下がってくる 50才前後になると“悪玉コレステロール”値が急上昇して、男性より高くなることも多いですが、動脈硬化はすぐには進みません。
女性ホルモンには、悪玉コレステロールを下げる効果や血管を保護する効果などがあり、男性に比べると女性の血管は若く保たれるそうです。
●糖尿病・高血圧・喫煙など他の危険因子があると、危険度が急上昇するため、男性より危険になる場合もある。
●コレステロールが低い人の中には、肝臓病(肝臓の病気)・がんでコレステロール値が下がってしまった人が含まれる。病気が原因で死亡率が高くなる。
※これ以外にも要因があるとする研究もあるそうです。
●自己判断で薬をやめるのは危険なので、危険因子を調べた上で、医師と相談するようにしたほうが良いそうです。
●コレステロールは栄養の一つ。高齢者は低栄養に注意。
【関連記事】
- お年寄りは低栄養に注意|低栄養になると、免疫の低下、筋肉の減少、骨が弱くなることで、感染症や骨折の恐れが高くなる
- 低栄養の原因はアルブミン不足|ためしてガッテン(NHK) 4月28日
- 肉好きシニアが増えている!?|肉で低栄養が予防できる!?
●なにもしないのにコレステロールが下がったら、病気の可能性も。
●「コレステロールが気になる人は肉より魚を食べたほうが良い」は○。
魚にはEPAが含まれており血管を保護する・中性脂肪を下げるといった動脈硬化予防の効果があるといわれている。
●「コレステロールが気になる人はいかやたこは食べないほうが良い」は×。
いかやたこには、悪玉コレステロールを下げるタウリンが含まれており、それほど気にする必要はないそうです。
●「オリーブオイルをたくさんとると動脈硬化を防げる」は×。
カロリーの摂り過ぎは動脈硬化に悪影響。
●「たまごはコレステロールが多い」は○。
コレステロール摂取の目標1日あたり300mg以下。たまご一個あたり250mg。ただ健康な人は気にする必要はないそうです。
○コレステロールの吸収率は人によって違う。
○一日あたりのコレステロール
日本人の食事摂取基準(厚生労働省)では男性750mg、女性600mg(上限)となっています
●善玉コレステロールを増やすには?
善玉を増やすには「有酸素運動」が有効です。
ランニング以外の運動でも大丈夫。
1日に歩く歩数が多ければ多いほど、善玉の値も高くなることが分かっています。
善玉コレステロールを増やすには、運動が有効。(特に有酸素運動)
○運動には悪玉コレステロールを直接下げる効果はない
○運動で善玉コレステロールが増えた場合総コレステロールが増えてもOK
「運動しているのにコレステロールが下がらない」とお悩みの方も、ガッカリすることはありません。
悪玉が下がらなくても、善玉が増えれば回収する力が上がるので、動脈硬化を改善する方向に向かうと考えられています。
運動をして悪玉コレステロールを低下させる効果はないものの、善玉コレステロールを増やせば、動脈硬化の改善につながると考えられるそうです。
→ HDLコレステロールを増やす方法と善玉コレステロール吸う力をアップする方法 について詳しくはこちら
→ 【ガッテン】善玉コレステロールの吸う力をアップする方法!EPAを含む青魚(サバ缶)!ナッツ&緑茶!ウォーキング!|11月28日 について詳しくはこちら
→ 血管年齢を若くする方法|血管年齢を下げるために効果的な食べ物・運動 について詳しくはこちら