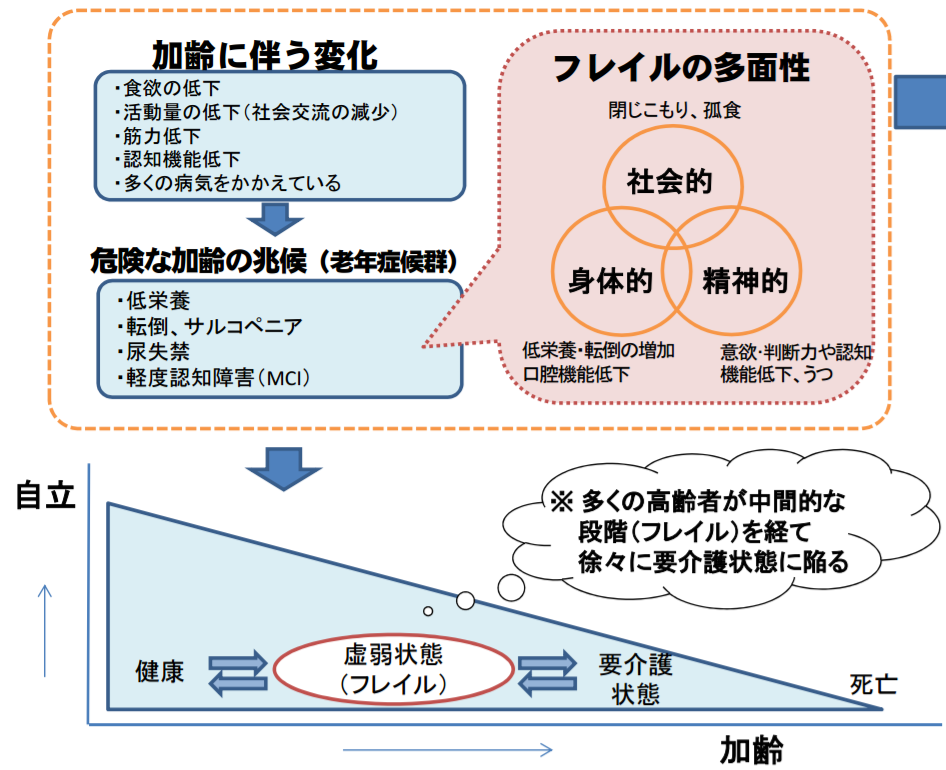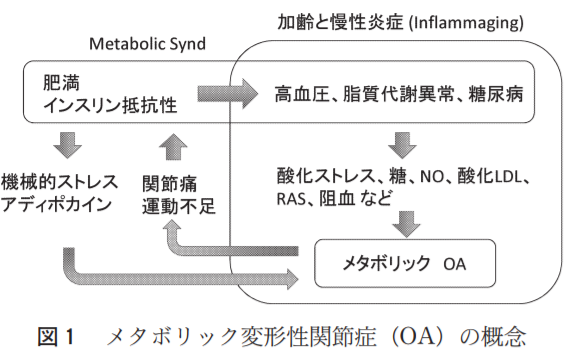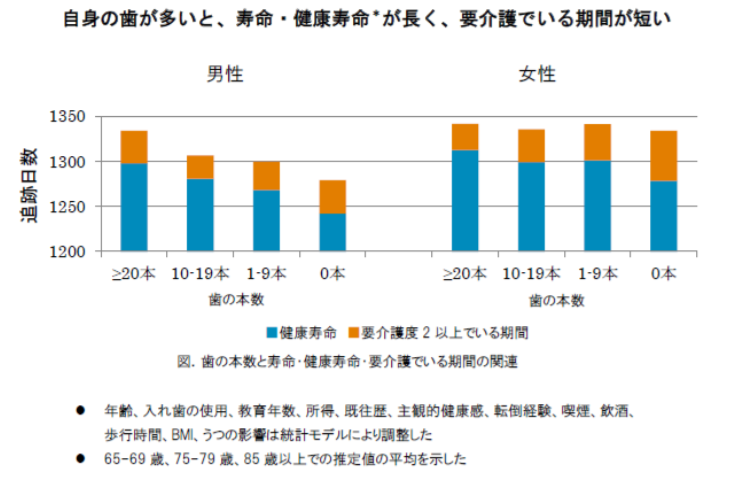> 健康・美容チェック > 認知症 > 一日に歩く時間が長い人ほど認知症になりにくい!40代・50代は認知症予防のためにも運動する時間を増やそう!|東北大
【目次】
■一日に歩く時間が長い人ほど認知症になりにくい|東北大
【認知症予防に長時間歩行 研究】https://t.co/h4IrFteRvj
1日に歩く時間が長い人ほど、認知症になりにくいとの研究結果を、東北大の研究グループが発表。認知症を予防するため、高齢者に歩く時間を増やすように呼びかける意義は大きいという。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2018年12月10日
「長く歩く人、認知症になりにくい」東北大の研究グループが発表(2018/12/10、読売新聞)に紹介されている東北大の遠又靖丈講師の研究グループの研究によれば、一日に歩く時間が長い人ほど認知症になりにくく、仮に「30分未満」「30分~1時間」のグループが歩行時間を増やして、一段階上のグループに移ると、認知症になる割合が低く抑えられることが分かったそうです。
■運動と認知症(認知機能)の関係
by Mike Baird(画像:Creative Commons)
認知症の予防につながる9つのリスク要因|中年期の聴力低下・中等教育の未修了・喫煙・うつ・運動不足・社会的孤立・高血圧・肥満・2型糖尿病によれば、認知症のリスク要因の一つに運動不足が挙げられています。
中年期の運動によって脳の萎縮や認知機能の低下を予防できる!?によれば、米ボストン大学などの研究チームによるランニングマシンで運動してもらうテストによれば、運動成績が悪かった人は脳が萎縮していることがわかったそうです。
軽い運動でも脳の認知機能は向上する!?によれば、筑波大学体育系の征矢英昭教授らの研究で、ジョギングに相当する運動を短時間行うと脳の中の判断力や注意力を支配する部分の活動が活発になることがわかっており、またウォーキング程度の軽い運動を短時間行なっても脳の認知機能が高まることがわかったそうです。
【関連記事】
有酸素運動をすると頭も体もスマートになる?によれば、運動の結果、脳の最大酸素摂取量が上がり、被験者たちの認知能力に大幅な改善が見られたそうです。
うつ病性仮性認知症対策|前頭葉の血流を増やす方法は有酸素運動(散歩など)+知的刺激(川柳など)を行う「コグニサイズ」|たけしの家庭の医学で紹介した国立長寿医療研究センターでは、頭を使いながら有酸素運動すること、例えば、暗算やクイズなどを解きながら速足で歩いたりすることを勧めているそうです。
このことを「コグニション」(認知)と「エクササイズ」(運動)を組み合わせ「コグニサイズ」と呼んでいるそうです。
週1回90分の運動プログラムを10か月間参加したグループでは、認知機能や言語機能が維持されており、また脳の特定部位の萎縮傾向がなかったそうです。
■中年期以降の歩行時間が継続して多いグループでのみ認知症発生リスクが低い
遠又靖丈講師らの研究によれば、中年期以降の歩行時間が継続して多いグループでのみ認知症発生リスクが低く、また、高齢期になってからの認知症を予防するためにも、中年期から高い水準の身体活動量を維持することの重要性が示唆されています。
【参考リンク】
- 遠又靖丈・張姝・杉山賢明 中年期・高齢期の身体活動量変化が認知症発生に寄与するインパクトの解明―中年期・高齢期の身体活動で日本人の認知症発生の何%が減少しうるか 第 32 回若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書 2015 年度 pp.41~44(2017.4)
認知症を予防するためにも、40代・50代の方はぜひ今のうちから運動に取り組んでいきましょう!
→ 認知症予防に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら
【関連記事】