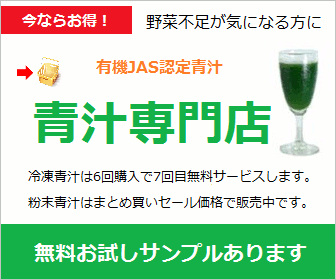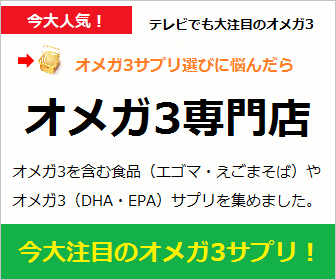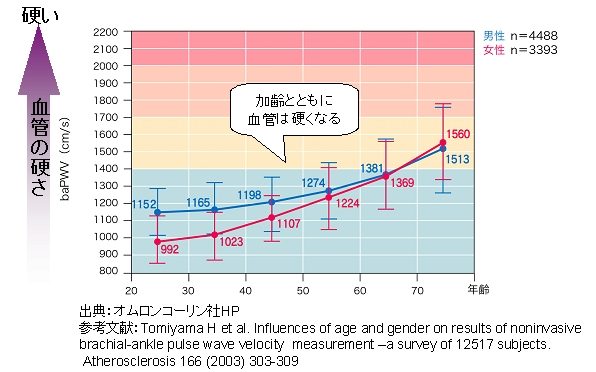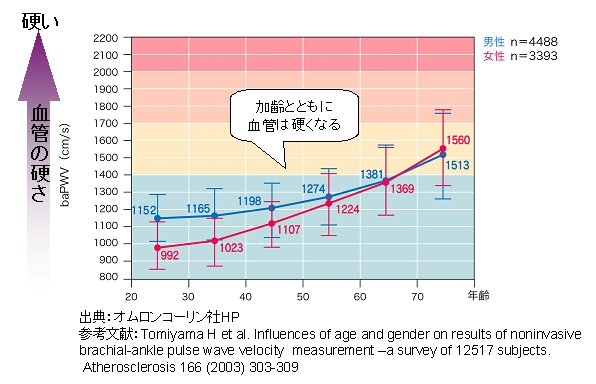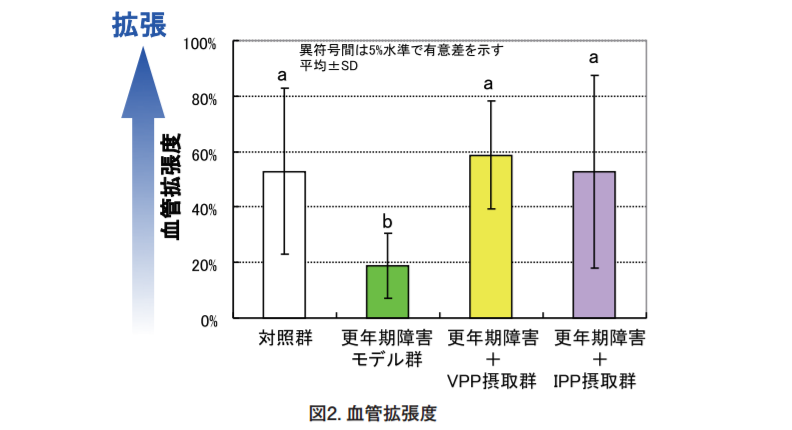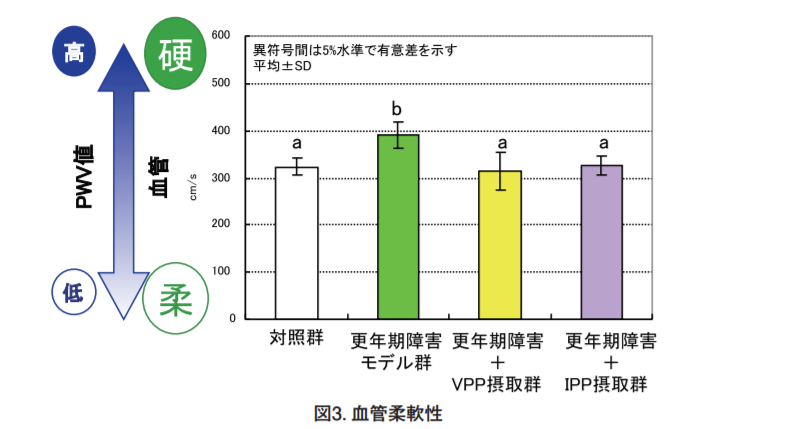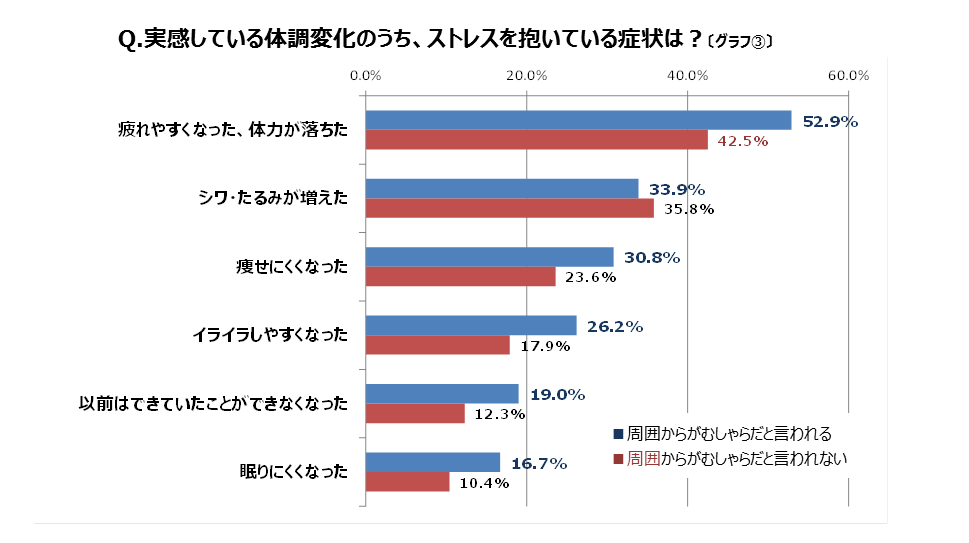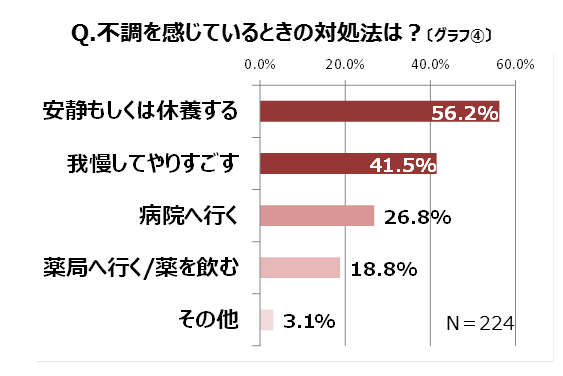> 健康・美容チェック > 突然の急な嘔吐(おうと)の原因となる病気・症状とは?
吐き気(嘔気)と嘔吐の違いは、吐き気(嘔気)は胃の内容物を吐き出したいという感覚・症状であり、嘔吐は脳の嘔吐中枢が刺激されて胃の中の内容物が逆流して吐き出される症状をいいます。
今回は、突然の嘔吐が前兆となる病気をまとめてみます。
【目次】
- 心筋梗塞による嘔吐
- 酒の飲み過ぎによる嘔吐
- くも膜下出血による嘔吐
- 胃潰瘍による嘔吐
- 急性すい炎による嘔吐
- 腎結石による嘔吐
- 更年期障害による嘔吐
- 熱中症による嘔吐
- 急性胃腸炎(感染性胃腸炎)による嘔吐
- 急性胃炎による嘔吐
- メニエール病による嘔吐
- 腸閉塞による嘔吐

■心筋梗塞の症状・原因・前兆・予防
■吐き気・嘔吐|なぜ心筋梗塞になると吐き気の症状が出るのか|心筋梗塞の症状
心筋梗塞の症状・前兆には「吐き気」があります。
なぜ、心筋梗塞になると「吐き気」の症状が出るのでしょうか?
心臓の下壁の心筋梗塞(心臓の下の部分の筋肉が壊死する心筋梗塞)が起きると、迷走神経が刺激を受けます。
迷走神経は、ほとんどの内臓にある知覚神経で心拍数や胃腸の動きに関わっています。
そこで、心筋梗塞によって、迷走神経が刺激されると、吐き気・嘔吐の症状が現れます。
■心筋梗塞を予防する方法
 食事・食生活の改善・バランスのとれた食事に
食事・食生活の改善・バランスのとれた食事に
動脈硬化の予防には食事・食生活の改善は欠かせません。抗酸化食品に注目が集まっています。
バランスのとれた食事でミネラル・ビタミン補給しましょう。
また、食事の量にも気をつけましょう。
→ 抗酸化食品 について詳しくはこちら。
 食物繊維で脳卒中や心筋梗塞のリスク減
食物繊維で脳卒中や心筋梗塞のリスク減
45歳以上の男女約8万7千人を約10年間、追跡調査を行い、食物繊維の摂取が多いグループは、そうでないグループに比べて、脳卒中や心筋梗塞などの循環器病の発症リスクが低かったそうです。
水溶性の食物繊維よりも不溶性食物繊維のほうが脳卒中のリスクを下げる効果が高かったそうです。
ただ、心筋梗塞を防ぐカギは悪玉善玉比(悪玉コレステロールと善玉コレステロールの比率)|みんなの家庭の医学 2月9日によれば、心筋梗塞を予防するには悪玉善玉比を改善することが重要であり、善玉コレステロールを増やす方法として、水溶性食物繊維を摂取することがおススメされていました。
→ 食物繊維の多い食品 について詳しくはこちら。
【参考記事】
- 食物繊維で脳卒中や心筋梗塞のリスク減 厚労省研究(2011年8月12日)
 ダイエットをして、肥満を解消する
ダイエットをして、肥満を解消する
肥満は動脈硬化の原因の一つだと考えられている。
 オメガ3の多い食事を心がける
オメガ3の多い食事を心がける
オメガ3脂肪酸の多い食事(青魚、えごま油、シソ油、亜麻仁油、くるみ、緑黄色野菜、豆類などの食品)を積極的にとる。
→ オメガ3脂肪酸 について詳しくはこちら。
 EPAを含む青魚を食べる
EPAを含む青魚を食べる
EPAの8つの美容&健康効果によれば、青魚に含まれるEPAを摂取することで、中性脂肪値が著しく低下するといわれています。
→ EPA について詳しくはこちら。
 脂身の多い肉など動物性脂肪の食べ過ぎに注意する
脂身の多い肉など動物性脂肪の食べ過ぎに注意する
 ストレスを解消する
ストレスを解消する
ストレスは血圧にも影響を与える。自分にあったストレスを解消するリラックス方法を見つけましょう。
 規則正しい睡眠で休息をとる
規則正しい睡眠で休息をとる
 塩分の取りすぎに気をつける
塩分の取りすぎに気をつける
塩分の摂りすぎは血圧を上昇させる。
 運動
運動
【参考記事】
 血糖値コントロール
血糖値コントロール
なぜHBA1Cの値が高いと心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるのか?によれば、HbA1cが高いと動脈硬化が進み、心筋梗塞などの危険を高めると考えられるので、血糖値をコントロールし、動脈硬化を進まないようにしましょう。
 お酒(アルコール)の飲みすぎに気をつける
お酒(アルコール)の飲みすぎに気をつける
 タバコを控える
タバコを控える
喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進させるので禁煙をする。
 体重・血圧を測り、自己管理に心がける
体重・血圧を測り、自己管理に心がける
肥満や血圧の高めな人は、体重計と血圧計を用意して、体重そして血圧の自己管理を心がけることも大切です。
ちょっとした食事などの生活習慣の改善が動脈硬化の予防に役立ちます。
 定期的な検査
定期的な検査
健診では、血圧、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロールの値などを検査し、動脈硬化の進行度を診断します。
定期的な検査の中で、かかりつけの医師と良い関係を築き、生活・食事指導を受けましょう。
■酒を飲み過ぎて嘔吐するのは、体が緊急事態のサイン
川崎医療福祉大学・医療技術学部の古川直裕教授の解説によれば、酒を飲み過ぎて嘔吐するのは、“体が緊急事態にひんしている”というサインなのだそうです。
■酒を飲み過ぎて嘔吐するメカニズム
酒を大量に飲み、血中のアセトアルデヒドの濃度が閾値(いきち)を超えると、延髄の最後野に存在する『化学感受引き金帯』という場所に信号が入ります。続いて、口腔(こうくう)咽頭反射や味覚、腹部臓器感覚に関与する孤束核(こそくかく)を通じ、嘔吐中枢へ信号が送られることで嘔吐が起こると考えられています。
■くも膜下出血の症状・特徴とは?どんな症状が起きるの?
くも膜下出血の症状の特徴は次の通り。
- 脳の表面に出血が起こり、致死率が高い
- 突然の激しい頭痛
- 吐き気・嘔吐
- 意識障害(意識の混濁)
- 両手両足の運動障害(麻痺)
■くも膜下出血を予防する方法
くも膜下出血の前兆・前駆症状・症状・原因とはによれば、くも膜下出血とは、脳を覆うくも膜と軟膜のすき間に出血を起こす病気で、多くは脳の動脈にできた瘤(こぶ)、いわゆる動脈瘤(りゅう)が破裂して起こります。
しかし、くも膜下出血の原因となる動脈瘤がなぜ出来るのか、いつ破裂しやすいかはわかっておらず、予防が難しいのだそうです。
くも膜下出血を起こさないようにするには、次のことに気を付けた方が良いそうです。
- 喫煙や大量の飲酒を避ける
- 高血圧にならないようにする
- 脳ドック
→ 脳卒中の症状・前兆・原因・予防 について詳しくはこちら
【くも膜下出血関連記事】
- 紅白初出場!星野源さんが乗り越えた「くも膜下出血」とは?
- KEIKO、くも膜下出血で手術
- 台風が近づくとくも膜下出血・ぜんそく発作が起こりやすい?|ホンマでっかTV 8月31日
- 巨人・木村拓也コーチ、くも膜下出血で倒れる
■胃潰瘍の症状(痛み)・原因・予防・食事
胃潰瘍とは、不摂生やピロリ菌の影響で保護膜が壊され、胃酸によって、胃の壁が浸食されえぐられているような状態で、痛みや出血を起こす胃の病気です。
- 胃が痛い(さしこむように痛い)
- 食後の胃痛(食べ物が潰瘍を刺激することで痛みがある)
- 胸やけ・呑酸(どんさん:すっぱい液体が口まで込み上げてくる)
- おなかが張る(胃酸の分泌が低くなることで、腸の動きが鈍くなったり、ガスが増えたりする)
- げっぷ
- 吐き気・嘔吐がする
- 食欲がない(食べ物が胃に残っているため)
■胃潰瘍の原因
胃潰瘍の原因は、胃酸の消化作用によって、自分の粘膜が攻撃されるために起こります。
通常は、胃から分泌される胃酸と胃酸から胃の壁を守る粘液の分泌のバランスがとれています。
しかし、胃粘膜を守る働きと胃粘膜を攻撃する力のバランスが崩れ、攻撃側が優位になった状態になると、胃潰瘍が起こるのです。
胃の粘膜におけるバランスが崩れる原因としては、いくつか挙げられます。
●ストレス
胃などの内臓の働きは自律神経によって調節されていますが、ストレスによって自律神経の働きが乱れると、粘膜の血流が悪くなり、粘膜が傷つきやすくなって潰瘍を生じます。
【関連記事】
●アルコール
胃や食道、腸など消化管のがんにはアルコールがリスク要因であるともいわれています。
【関連記事】
●喫煙
喫煙は、胃酸の分泌を多くし、またニコチンが粘膜の血流を妨げることで、胃粘膜の攻撃と防御のバランスが崩れます。
●非ステロイド消炎鎮痛薬(NSAID)
非ステロイド系の消炎鎮痛剤の服用は、胃の粘膜を保護するプロスタグランジンを作る力を低下させることで、防御役の粘液の出を悪くしてしまいます。
●ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)
胃潰瘍のほとんどでピロリ菌が発見されています。
胃炎や胃潰瘍を起こす原因として注目されたのが、ピロリ菌で、抗生物質を使って除菌すると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の再発が抑えられます。
■胃潰瘍の治療
内視鏡検査で確実な診断が行われます。
ピロリ菌感染が確かめられた場合は、再発防止の除菌治療が有効だと考えられています。
詳しくは医師の指導に従ってください。
■急性すい炎の症状・原因・食事
急性すい炎の症状としては、次のような症状が現れます。
- 上腹部の痛み(みぞおちから左上腹部あたりで、背中側まで痛くなることがある)
- 吐き気・嘔吐(おうと)
- 発熱
■膵炎の原因
膵炎の原因としては、胆石症やアルコールの飲み過ぎ、高脂肪・高カロリー食などがほとんどの原因と言われています。
胆石症は、胆石(脂肪の消化を促進する胆汁成分が固まってできる)が、胆嚢(胆のう)や胆管の中にできる病気で、胆管とすい管は十二指腸乳頭部という共通の出口をもっており、この乳頭部に胆石がつまると、すい臓にすい液がたまり、胆汁がすい管に逆流し、すい液が活性化されてすい炎が起こります。
アルコールの過剰摂取がどのようにしてすい炎を引き起こしているのかその仕組みはまだわかっていないそうですが、アルコールの影響がさまざまなことを引き起こすことで、膵炎を起こしていると考えられます。
それは、高脂肪・高カロリー食によって中性脂肪が増えると、すい臓に負担がかかり、すい炎を引き起こす原因になると考えられるからです。
お酒の飲み過ぎや不規則な生活習慣、高脂肪・高カロリー食、喫煙といった生活習慣に見覚えのある方は注意したほうがよいようです。
■膵炎の予防
1.お酒の飲み過ぎをやめる
2.高脂肪・高カロリー食→低脂肪・低カロリー食に
3.良質のタンパク質・ビタミン・ミネラルを摂取する
■腎結石の症状・原因・痛み・食事
腎臓結石の症状は、次のような症状があります。
- 突然、脇腹が激しく差し込むような痛み
- 血尿(目で見えない潜血のこともあります)
- 嘔吐
- 下腹部や大腿部の痛み
【関連記事】
■腎臓結石の原因
腎結石の一般的な原因は、水分補給状態を保てないことです。
夏の暑さと湿気は過度の発汗と脱水症状を引き起こすとともに、腎結石のリスクが高まると考えられます。
■腎臓結石の予防
 水分補給
水分補給
1.5~2リットルを目標に水分をたくさんとるようにする。
特に、夏の暑い日に汗をたくさんかくような時には、尿の出や色(あまり濃い尿とならないように)を気にしながら十分に水分をとるようにしましょう。
 動物性たんぱく質の摂り過ぎに注意する
動物性たんぱく質の摂り過ぎに注意する
動物性タンパク質の取りすぎによって、尿中のカルシウム排泄量を増やすために結石ができやすくなります。
また、尿酸の元であるプリン体を多量に含むレバーなどを摂り過ぎると、高尿酸血症となり、痛風の原因となると同時に尿酸結石の原因となります。
 シュウ酸塩を含む食べ物を避ける
シュウ酸塩を含む食べ物を避ける
腎結石ができやすい人は、シュウ酸塩を高濃度に含むほうれん草やチョコレート、ナッツなどを避けたほうがよいようです。
また、シュウ酸塩の吸収を抑えるため、次のことに気を付けましょう。
- 塩分を控えめにする
- 肉の摂取量を減らす
- 1日に何杯か水を飲む
 レモン(クエン酸)
レモン(クエン酸)
アイスティーは40歳以上の男性の腎結石リスクを高める?によれば、40歳以上の男性が腎結石のリスクを低減するには、アイスティーをやめてレモネードを飲む方が良いそうです。
その理由としては、
レモンには腎結石の成長を阻害するクエン酸が高濃度に含まれている。
からなのだそうです。
クエン酸がなぜ結石予防につながるのでしょうか?
尿酸は尿の中に含まれる酸で、体が健康な状態にあれば尿として体外に排出されるのですが、酸性になってくると完全に排出されず、体内に蓄積されてしまうのです。この尿酸の蓄積は痛風の原因となりますし、尿酸が固まって尿路結石をもたらす危険も高まります。
クエン酸には、身体をアルカリ性に保持する働きがあることによって、結石の成長を阻害してくれるようです。
【関連記事】
■更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状
更年期になり、エストロゲンが減少することによって、ホルモンバランスが崩れると、自律神経が乱れてしまいます。
胃腸は副交感神経が働いてリラックスしているときに働くのですが、自律神経が乱れてしまい、交感神経が優位に働き続けてしまうと、食欲不振(食欲がなくなる)や胃腸の不調、吐き気、嘔吐の症状が現れてしまいます。
【関連記事】
■更年期障害の食事・更年期を乗り切る方法
- 食生活の見直しをする
- ビタミン・ミネラルなどバランスの取れた食事で栄養を十分に摂る。
亜鉛は、ホルモンバランスを整える働きがある。
女性の場合は、亜鉛が不足すると女性ホルモンの働きが悪くなったり、月経異常を引き起こしてしまう可能性がある。
特に更年期ともなれば、亜鉛不足がホルモンバランスをさらに乱れさせて症状を悪化させてしまうことにもありえる。
→ 亜鉛の多い食品 について詳しくはこちら - 軽いウォーキングなどの適度な運動
- ご自身にあったリラックス方法
- 家族との会話をする機会を増やす
- 更年期障害のツボ
更年期障害のツボ:三陰交(さんいんこう)|たけしの本当は怖い家庭の医学 - 相性の合う医師・病院を見つけておく
■熱中症の症状・対策・予防
1度(熱失神・熱けいれん、現場での応急処置で対応できる軽症)
めまい、失神、筋肉痛、こむら返り、大量の発汗
2度(熱疲労、病院搬送が必要な中等症)
頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐(おうと)、倦怠(けんたい)感、虚脱感
→ なぜ熱中症になると、「熱疲労(めまい・頭痛・吐き気・嘔吐)」の症状を起こすのか? について詳しくはこちら
3度(熱射病、入院して集中治療が必要な重症)
意識障害、けいれん、手足の運動障害、体に触ると熱いぐらいの高体温
■熱中症対策(応急処置)
それでは、熱中症になったら、どうすればよいのでしょうか?
(1)涼しい場所に移し、衣服をゆるめてリラックスさせる
建物が近くにない場合には日陰で休ませましょう。
建物が近くにあればエアコンの効いた部屋で休ませましょう。
(2)首筋、脇の下、脚の付け根を(冷たいペットボトルなどを使って)冷やす
脈拍のとれる位置は血管が皮膚に近いため、そこを冷やすと、冷却された血液が全身を巡ることで、クールダウンします。
(3)顔が赤いときは頭を高く、青白ければ足を高くして寝かせる
(4)意識があり、嘔吐がなければ水分補給させる
水分だけでなく塩分などの電解質も失われていると考えられますので、水に塩分などの電解質と糖とがバランスよく配合された経口補水液を利用しましょう。
(5)皮膚が熱ければ、風を送ったり熱い部分にぬれタオルを当てる
(6)皮膚が冷たければぬれタオルをしぼり、冷たい部分をマッサージ
(7)意識がなかったり、急に体温が上がったらすぐ救急車を呼ぶ
【関連記事】
- なぜ熱中症になると、「熱失神(めまい・立ちくらみ・失神)」という症状を起こしてしまうのか?|熱中症の症状
- なぜ熱中症になると、「熱けいれん(筋肉痛・手足がつる・こむら返り・筋肉の痙攣・大量の汗)」という症状を起こしてしまうのか?
- なぜ熱中症になると、「熱疲労(めまい・頭痛・吐き気・嘔吐)」の症状を起こすのか?
- なぜ熱射病になると、体温が高い・意識障害・手足の運動障害・けいれん・おかしな言動や行動という症状を起こすのか?|熱中症の症状
- 熱中症は脱水状態や睡眠不足、腸内環境の悪化などにより体温調節機能が働かなくなることが原因で起きる
- 熱中症予防のためにも、「暑さ指数(WBGT)」(環境省)をチェックしよう!
- 熱中症で死亡した人の9割が屋内|65歳以上の高齢者やエアコン不使用のケースが多い
- 熱中症対策|経口補水液の作り方・インターバル速歩・牛乳|世界一受けたい授業 7月8日
- 異常に喉が渇くのは実は病気のサインかも!?のどの渇きの原因とは?
- なぜ水だけ飲んでも熱中症の予防にならないのか!?
■急性胃腸炎(感染性胃腸炎)の症状・原因・対策
急性胃腸炎とは、発症するまで前兆もなく、胃腸に急性の炎症が起こり、突然の嘔吐や下痢といった症状を伴う病気のこと。
急性胃腸炎の原因のほとんどが感染性胃腸炎であり、その多くがウイルス性(ロタウイルスやノロウイルスなど)です。
- 嘔吐
- 下痢
- 腹痛(おなかが痛い)
急性胃腸炎になると、発熱、下痢、嘔吐などの症状によって体の水分がなくなってしまい、場合によっては脱水症状を招くため、経口補水液による水分補給をしましょう。
●脱水のサイン
脱水のサインは以下の通りです。
- 手先の皮膚がかさかさする
- 口の中が粘る
- やる気や食欲の低下によるだるさ
- めまいや立ちくらみ、ふらっとする
■急性胃炎の症状・原因・食事
- 急激に激しい胃痛
- 吐き気
- 嘔吐(おうと:胃の中のものを吐いてもどすこと)
- 胸やけ
- 貧血
●原因
- 強い精神的ストレス
- アルコールの摂取
- 暴飲暴食
【関連記事】
●対策
安静にし、できるだけ水分などをとり、医師の指導に従ってください。
■メニエール病
回転性のめまいは、30分位から数時間続きます。
多くは、めまいに、吐き気、嘔吐、冷や汗、顔面が蒼白くなる、脈が速くなるなどの症状を伴います。
また、めまいと一緒に難聴や耳の塞がった感じ、あるいは耳鳴りなどの耳の症状が現れます。
【関連記事】
■腸閉塞
初期症状としては、下腹部を中心にお腹が張る腹部膨満感や腹痛、吐き気・嘔吐、冷や汗などで、顔面が蒼白になったり、発熱を伴うこともあります。
【関連記事】
■まとめ
突然の嘔吐は身体から出ている“体が緊急事態にひんしている”というサインです。
嘔吐の原因がはっきりわかっていない場合にはしっかりと病院で診てもらいましょう。
「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」