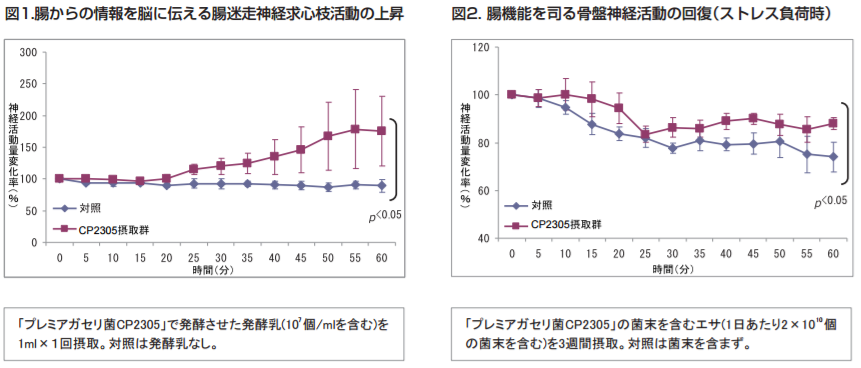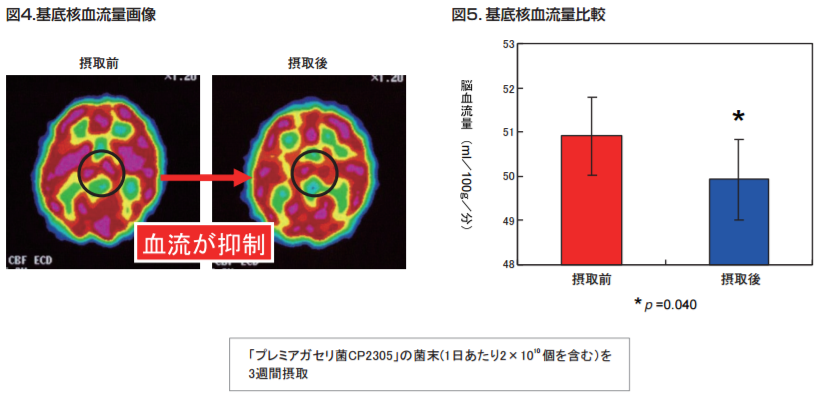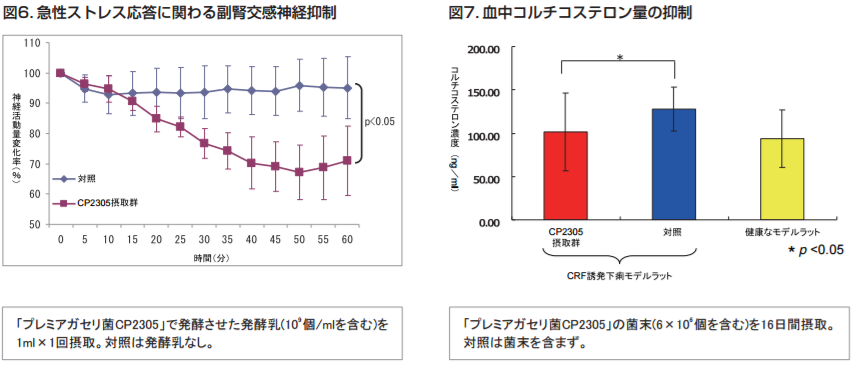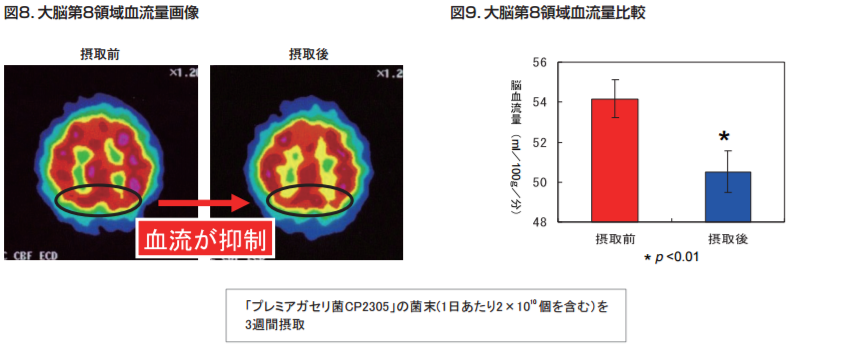> 健康・美容チェック > 胃腸の病気 > IBS(過敏性腸症候群) > 大学生の2割が過敏性腸症候群(IBS)の症状に悩んでいる|長崎大学
■大学生の2割がIBS(過敏性腸症候群)の症状に悩んでいる|長崎大学
by NEC Corporation of America(画像:Creative Commons)
(2015/6/25、読売新聞)
長崎大学教育学部の田山淳・准教授らは国内8大学と共同研究を行い、大学生の2割以上がIBSの症状に悩んでおり、症状がない学生に比べて学校生活にリスクを抱える人が1.6倍、就職への不安を持つ人が2.2倍多いことが分かったと発表した。
2013年5~12月に、長崎大をはじめ国内8大学に通う18~25歳の大学生1,663人(男性61%、平均年齢19歳)を対象に、IBS(Irritable bowel syndrome)の診断基準に当てはまるかどうかをアンケート調査したところによれば、大学生の2割以上がIBSの症状に悩んでいるそうで、IBSの症状がある人は症状がない人に比べて学校生活や就職に不安を持つ人が多いそうです。
■過敏性腸症候群(IBS)とは?
下痢や便秘やそれに伴う腹痛や腹部不快感が、長期に繰り返す過敏性腸症候群(IBS)だが、近年はIBSと診断される人が若い女性を中心に増えているという。
IBSは、大腸や小腸に原因となる異常が見られないが、腹痛などの腹部症状に下痢や便秘といった便通異常を伴う疾患です。
過敏性腸症候群(IBS)は、症状のタイプによって「下痢型」「便秘型」「混合型(便秘と下痢を繰り返す)」の3つのタイプに分類されます。
下痢系の過敏性腸症候群、男性の1割近くによれば、国内の20-79歳の男性のうち、下痢系の過敏性腸症候群(IBS)にかかっている人が1割近くいることが、島根大医学部第二内科の木下芳一教授の調べで分かっています。
「お腹虚弱体質」なエンジニアがIOT駆使してオフィスのトイレ空き状況をスマホでリアルタイムに確認できるシステムを開発でも紹介しましたが、自分自身はおなかが虚弱体質だと思っていても、実は正式には過敏性腸症候群(IBS)という体に異常がないものの、ストレスなどが原因となって腹痛などの腹部症状に便秘や下痢といった便通の異常を伴う病気である可能性もあります。
記事によれば、近年では、若い女性を中心にIBSと診断される人が増えているそうです。
■IBSの症状
おなかの張りや気持ち悪さ、おなかが鳴るといった症状があり、排便によって症状が軽くなることがあるが、急にトイレに行きたくなるため、症状がひどい場合は学校や会社に行けなくなるなど、生活の質(QOL)を低下させてしまう。
腸と脳には密接な関係があり、脳がストレスを感じると腸に伝わり、下痢などの症状を起こします。
【主な症状】
- 通勤や通学中、突然トイレに駆け込む
- 会議や試験前にお腹が痛くなる
- 旅行中に腹痛が起こる
【関連記事】
■IBSの原因
ストレスが主な原因と考えられている。
IBSは、大腸や小腸に原因となる異常がないため、ストレスが主な原因と考えられています。
IBSには、その他の原因もあるようです。
(2015/9/22、日刊ゲンダイ)
IBSの原因で見落とされやすいのが、「大腸の形の異常による通過障害」だ。日本人の8割は大腸の一部がねじれていたり、あるべき位置から離れて骨盤内に落ちていたりして、便がスムーズに通過しにくい。胆汁による過剰反応やコーヒーの飲み過ぎ、お酒の飲み過ぎが下痢を引き起こしていることもある。腸の炎症やがんでも便秘や下痢になることがあるので、続くようなら念のため医療機関を受診したほうがいい。
国立病院機構久里浜医療センター・内視鏡検診センターの水上健部長によれば、IBSの原因はストレスだけではなく、大腸の一部がねじれていることや胆汁による過剰反応、コーヒーの飲み過ぎ、お酒の飲み過ぎ、腸の炎症などが原因となることもあるそうです。
(2011/2/18、日経ウーマンオンライン)
腸管がねじれて、もつれたような形態異常を抱えていた。
<中略>
「こういう腸の人は、硬い便が少量出たあとに大量の下痢や軟便が出ることが多い。ねじれた部分に便が詰まって栓になり、下痢便をためてしまうのだろう」(水上医師)。
腸管がねじれた形態異常型のIBSの人は、ねじれた部分に便が詰まって栓になり、下痢便をためていることで、便秘と下痢を繰り返していると考えられるそうです。
腸の中に良い菌を増やす方法&便秘対策!腸に良いお風呂の入り方|林修の今でしょ!講座 3月10日によれば、腸の左の肋骨の下の部分がねじれやすいと紹介していましたが、この部分が関係しているのかもしれません。
アンケートで、形態異常型の人たちは発症前、特にストレスを抱えていないこともわかった。「結婚や引っ越しがきっかけで運動機会が減り、発症するケースが多い。ある程度体を動かしていれば、問題なく排泄(はいせつ)できていたのだろう」と水上医師。
形態異常型の人はストレスが原因ではなく、環境の変化によって、運動する機会が減るなどして、発症することがあるようです。
このように様々な原因が考えられるので、便秘や下痢が続く場合には、医療機関で診てもらった方が良いようです。
■IBSの基準
IBS診断基準(RomeⅢ)
過去3カ月間、月に3日以上にわたって腹痛や腹部不快感(痛みとは表現されない不快な感覚)が繰り返し起こり、次の項目の2つ以上がある
1.排便によって症状が軽減する
2.発症時に排便頻度の変化がある
3.発症時に便形状(外観)の変化がある
■IBSの治療
■治療薬
下痢型IBS治療薬「イリボー」、混合型IBS治療薬「コロネル」、便秘型IBS治療薬「リナクロチド」など
【参考リンク】
- IBS治療薬イリボーが女性患者にも適応拡大(2015/5/13、nikkei BPnet)
- 【アステラス製薬】便秘型IBS治療薬「リナクロチド」導入(2009/11/11、薬事日報)
■運動
運動をすることによって、腸のねじれがなくなり、改善することが考えられます。
■まとめ
過敏性腸症候群(IBS)は体に異常がないものの、ストレスなどが原因となって腹痛などの腹部症状に便秘や下痢といった便通の異常を伴う病気です。
→ 過敏性腸症候群(IBS)の症状・原因・チェック・治し方 について詳しくはこちら