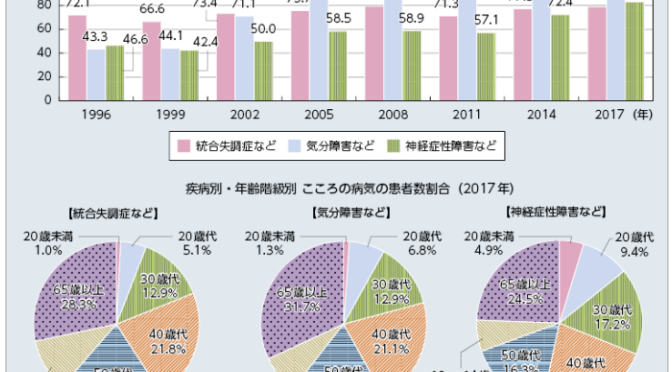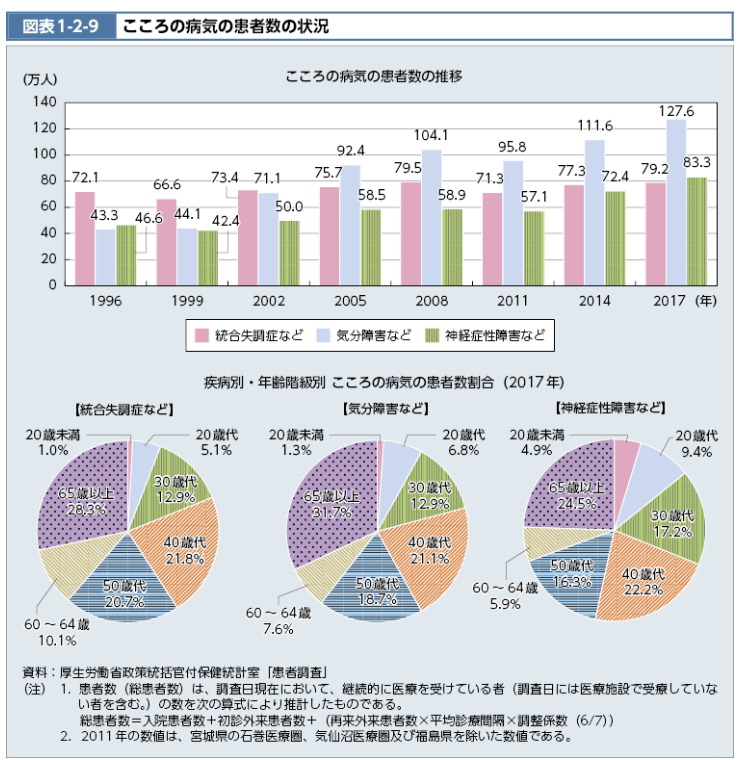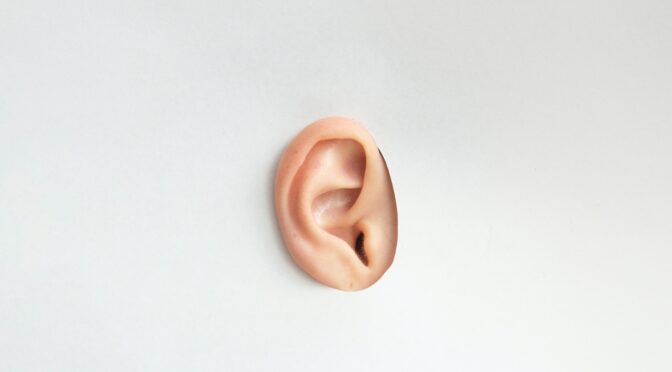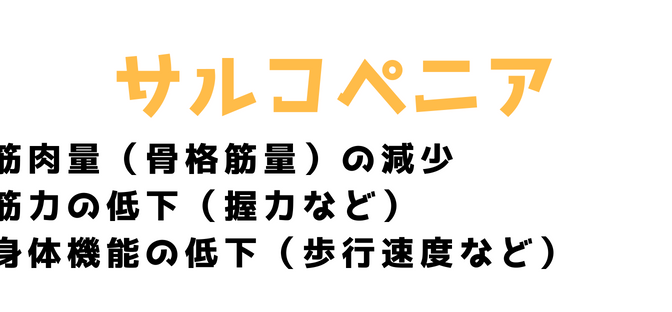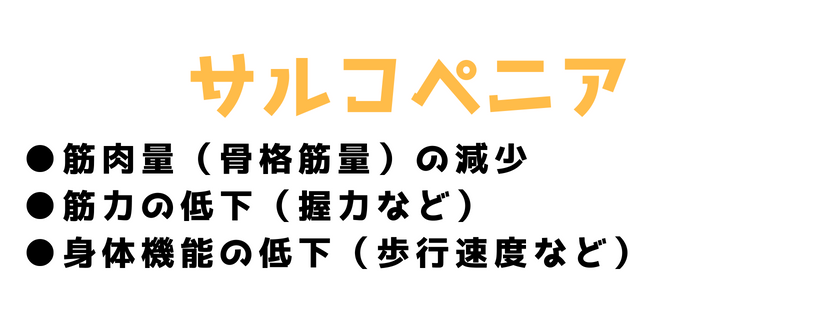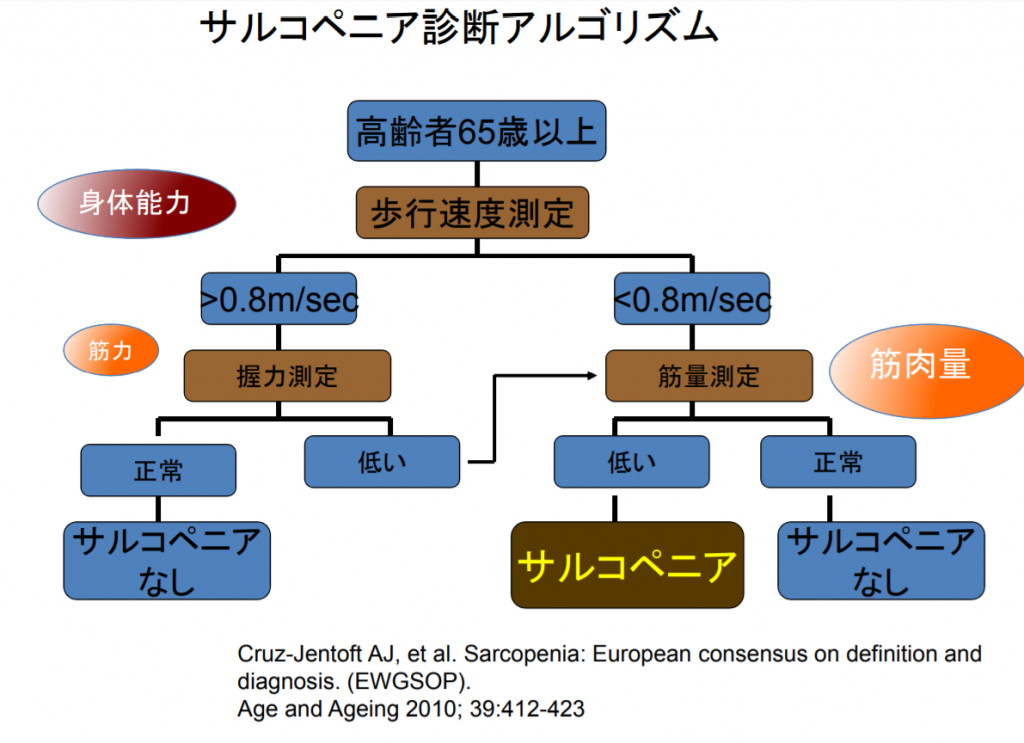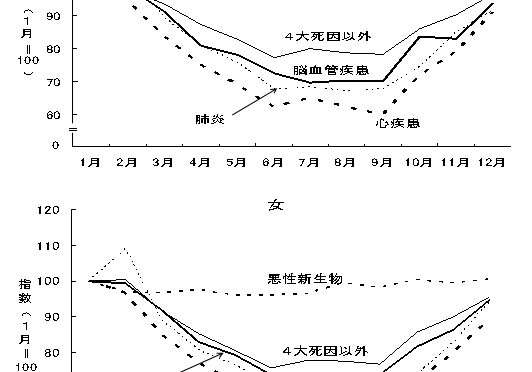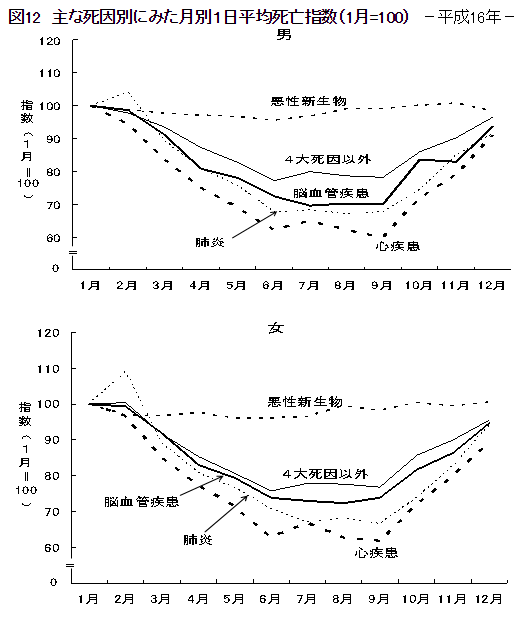Threadsを見ていると、更年期を「KNK」という秘密組織で、コードネームで呼び合う遊びが流行ってました。
→ 更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状 について詳しくはこちら
近年有名人の方が更年期障害に対してオープンに話されるようになって、少しずつ更年期への向き合い方が変わっているように感じます。
これから更年期を迎えるプレ更年期の人もいれば、現在更年期真っただ中の人、更年期が終わりどのように向き合ってきたかを伝える側になっている人などその状況はさまざまです。
【関連記事】
- 有森也実さんの更年期症状と更年期対策「ホットフラッシュ、朝起きられない、気分の落ち込み、動悸、めまい、頭痛、リンパの腫れ、顔面神経痛」
- 渡辺満里奈さんが更年期障害の症状を告白!【モーニングショー】/渡辺満里奈さん、野宮真貴さん、松本孝美さんが更年期障害について語る【ボクらの時代】
- 望月理恵さん、45歳ごろから更年期障害の症状に悩まされていたことを告白!血液検査で「女性ホルモン80歳」と診断
- 40歳を迎える藤本美貴さん、更年期に怯えていると告白!「やっぱホルモンには勝てないと思うんだよね」
- 大久保佳代子さんは更年期障害を告白!最近怖いのが尿漏れ
- 上原さくらさんが更年期障害かどうかわからない症状に悩まされていることを告白/肩こり・腰痛・疲れやすい・冷え性・寝付けない
- 君島十和子さんが行なう3つの更年期対策|人間ドック・体を冷やさない・女性ホルモンを食事で補う
- #高橋真梨子 さんの病気は重度の更年期障害だった|47歳の頃、めまい、手足のしびれなどの体調不良に
- #松本伊代 さんが更年期障害を告白 「のぼせやイライラ、落ち込む症状が現れている」|#バイキング #その原因Xにあり
- 加賀まりこさんは50代の頃更年期障害の症状に悩まされていた!
- 高畑淳子さん、「白い巨塔」撮影時には更年期障害の症状(ホットフラッシュ)に悩まされた!【ぽかぽか】
- かとうれいこさんは更年期障害をどう乗り越えたか?キーワードはアクティブレスト!
- 磯野貴理子さんはどのようにして更年期障害と向き合っていったの?
- 有森裕子さんが更年期障害を告白「ホットフラッシュ(大汗)」「イライラ」「気持ちの落ち込み」
- 飯島直子さんが更年期障害を告白
- フリーアナウンサーの勝恵子さんはHRT(エッチアールティー)とエクオールと運動で更年期症状を改善
- ともさかりえさんが更年期障害を告白「去年の夏から謎の火照りに悩まされている」
- 吉瀬美智子さんの更年期症状(ホットフラッシュや不眠)と更年期対策
- RIKACOさんが更年期障害の症状やその対処法を告白
- 葉月里緒奈さんが更年期障害をインスタで告白「ホットフラッシュ、頭痛、不眠が続くと日中ボーっとしてしまう」
- #南野陽子 さん、45歳ごろに更年期障害の症状(気分が重い、頭痛)を経験
- 大神いずみさん(51歳)、更年期症状と初期糖尿病を乗り越え、体重10.1キロ減量に成功!
- 君島十和子さんは閉経後に朝起きると理由もないのにドキドキして不安感に襲われるといった更年期症状が現れた!更年期症状の緩和・改善への取り組みとは?
また更年期・閉経前後で病気のリスクが高くなることもわかってきています。
【関連記事】
- 【NHKスペシャル】「#みんなの更年期」まとめ
- 閉経が早い女性の特徴とは?
- 初経から閉経までの期間が長くなると、肺がんの発生率が2倍以上高い!
- 閉経が早い女性は認知機能の低下が進む可能性!女性ホルモンの欠如が認知症リスクに関わっている!?
- 閉経後の女性は入浴でのヒートショックに注意!
- 閉経前・後ともに肥満になると乳がんリスクが高くなる!
- 閉経の遅い女性と初経の早い女性は、甲状腺がんのリスクが高い!
- 閉経年齢が45歳未満と比較して、閉経年齢が55歳以上のグループでは、子宮体がんのリスクは2.8倍!
- 飲酒はがんの原因なのか?|肝臓がん・大腸がん・食道がん・乳癌(閉経後)・口腔がんのリスクが高くなる
- 閉経期高血圧とは?予防する方法|閉経女性が塩分をため込みやすくなる原因とは!?
- なぜ閉経以降女性ホルモン(エストロゲン)が減少すると、高コレステロール血症の女性が急増するの?
- お酒飲むほど乳がん高リスク|閉経後の女性が1週間に日本酒換算で7合以上飲むと、発症率は全く飲まない人の1.74倍
- 【モーニングショー】閉経後の女性でLDLコレステロールの数値が上がったら、どのように食事に気を付けたらいいの?
- 隠れメタボ対策|なぜ隠れメタボになるのか?なりやすい生活習慣|隠れメタボは閉経後の女性に多い|#あさイチ #nhk
- 中年期と高年期では健康的な食習慣が違う!3食均等にたんぱく質を摂取したほうが筋肉はつきやすい/閉経後、更年期以降は血中脂質が増えていく
- 筋肉を鍛えるとLDLコレステロールが下がる!|筋トレが肥満の閉経後女性のコレステロールを下げる治療法になる可能性【論文・エビデンス】
- 体脂肪・内臓脂肪面積・動脈硬化…エクオールに生活習慣病リスク低減の可能性 50代・60代の閉経期女性の味方!
- 【更年期と女性の心臓血管の健康】女性の心血管疾患予防は閉経前後から始めるべき!
- 夫・パートナーに自分の更年期障害の話や相談をしたことがあるのは31.6%!女性の更年期障害について男性の理解度は2割強だった!
- 更年期症状を改善するホルモン補充療法を実施した医師は48%!理由は知識不足や経験不足!
- 【あさイチ】尿もれやニオイが気になる人に!正しい拭き方と排尿の仕方|簡略更年期指数(SMI)チェックの方法|女性ホルモンの治療(ホルモン補充療法・低用量ピル・漢方薬)のやり方
- 更年期世代の女性は糖質を摂りすぎている!?糖質依存度チェック
オープンな場で少しずつ情報が供給されることによって、更年期障害との良い向き合い方ができるようになるといいですね。
【補足】
■更年期障害の症状
- 更年期と生理|生理周期・生理不順(月経不順)・不正出血
- 不正出血|なぜ更年期になると不正出血が起こるの?|更年期障害の症状
- 更年期の生理周期(月経周期)は短い?長い?どう変化していくの?
- 更年期うつの症状・対策|イライラや不安はホルモンバランスの乱れが原因かも!?
- 胸の痛み(乳房の痛み・動悸)|更年期の症状
- 「頭痛・頭が重い」といった症状が起きる原因|更年期の症状
- めまい・ふらつき・耳鳴りの原因|更年期の症状
- 更年期(更年期障害)の多汗・発汗(顔から汗が止まらない)の原因・対処法
- ホットフラッシュ(顔のほてり・のぼせ)|更年期の症状
- 更年期の眠気の原因|なぜ夜寝ているのに昼間も眠いのか?|更年期障害の症状
- 不眠(眠れない)の原因・対策|更年期の症状
- 吐き気・嘔吐・食欲不振(消化器系の症状)|更年期の症状
- 手足のしびれ|更年期の症状
- 冷えのぼせの症状・原因・改善・対策・やってはいけないこと
- むくみ|なぜ更年期になるとむくむのか?|更年期(更年期障害)の症状
- 体がだるい(倦怠感)・疲れやすい|更年期(更年期障害)の症状
- 女性の抜け毛の原因|なぜ髪の毛が抜けてしまうのか?
- 物忘れがひどくなる(記憶力の低下)|更年期障害の症状
- 頻尿・尿もれ|何度もトイレに行きたくなる原因|女性の更年期障害の症状
- 抜け毛・薄毛|女性の更年期(更年期障害)の症状
- 口の渇きの原因|なぜ口の中が渇くのか?|更年期(更年期障害)の症状
- 喉の渇きの原因|なぜ更年期になると、のどが渇くのか?|更年期障害の症状
- 女性が更年期に太る3つの原因|更年期に太りやすい女性は生活習慣病に注意!
- 更年期高血圧とは!?|女性の高血圧は40代以降、急増する
■更年期障害の食事・更年期を乗り切る方法
●食生活の見直しをする
●ビタミン・ミネラルなどバランスの取れた食事で栄養を十分に摂る。
亜鉛は、ホルモンバランスを整える働きがある。
女性の場合は、亜鉛が不足すると女性ホルモンの働きが悪くなったり、月経異常を引き起こしてしまう可能性がある。
特に更年期ともなれば、亜鉛不足がホルモンバランスをさらに乱れさせて症状を悪化させてしまうことにもありえる。
→ 亜鉛の多い食品 について詳しくはこちら
【AD】
→健やかに過ごしたい40代・50代の女性に亜鉛サプリ!まとめ買いで最大18%OFF!
●軽いウォーキングなどの適度な運動
寝る前に毎日10分間、ヨガを取り入れたストレッチを3週間行うことで、更年期女性の「更年期症状」と「抑うつ」を改善することがわかったそうです。
→ 寝る前のストレッチ&ヨガは、女性の「更年期症状」と「抑うつ」を改善する効果がある!おすすめのやり方 について詳しくはこちら
●ご自身にあったリラックス方法
更年期障害の症状を和らげたいと考えている方は、呼吸をゆっくりしたり、音楽を聴いてみてはいかがでしょうか?
→ 更年期障害の症状の顔のほてり(紅潮)は音楽を聴くと改善する! について詳しくはこちら
●家族との会話をする機会を増やす
●更年期障害のツボ
→ 更年期障害のツボ:三陰交(さんいんこう)の位置・押し方|たけしの本当は怖い家庭の医学 について詳しくはこちら
●相性の合う医師・病院を見つけておく
●エクオール
大豆イソフラボンは、更年期障害の原因といわれる「エストロゲン」と構造が似ているため、体内に入ると、エストロゲンと同じような働きをするといわれています。
大豆イソフラボンは大豆製品などから摂れます。
ただ、最近の研究によれば、大豆イソフラボンの健康効果の恩恵を受けやすい人とそうでない人がいることが明らかになったそうです。
その違いは、エクオールを作り出すためのエクオール産生菌という腸内細菌を持っているかどうかです。
腸内細菌によって大豆イソフラボンに含まれるダイゼインという成分をエクオールに変えることで、ダイゼインのままと比べ、よりエストロゲンに似た働きをすると言われています。
更年期症状の軽い人はエクオールの量が多いそうで、更年期症状の重い人のグループに、エクオールをつくれる人が少なかったそうです。
更年期のホットフラッシュ(ほてり)や首や肩のこりを改善する効果が確認されているそうです。
エクオールの産出能力をチェックするには、「尿中エクオール検査」や「ソイチェック」といった簡単な尿検査で調べることができるそうです。
→ エクオール(EQUOL サプリ)が更年期(更年期障害)症状の軽減に役立つ について詳しくはこちら
【関連記事】
■更年期障害関連ワード